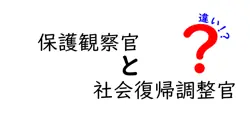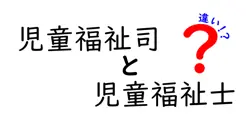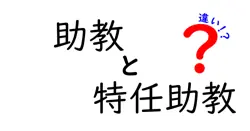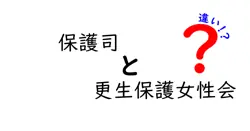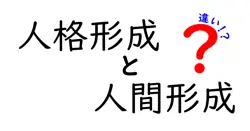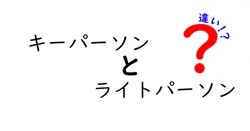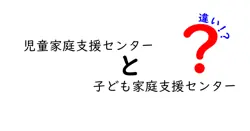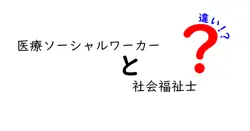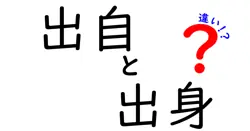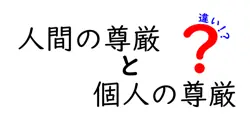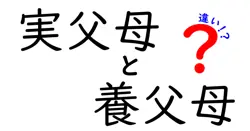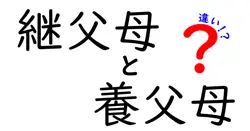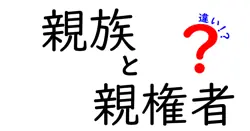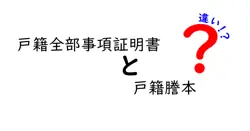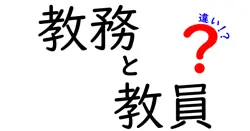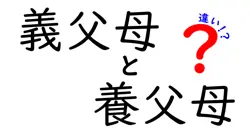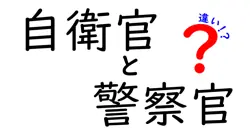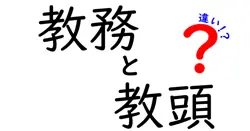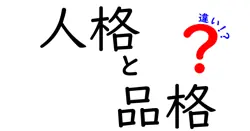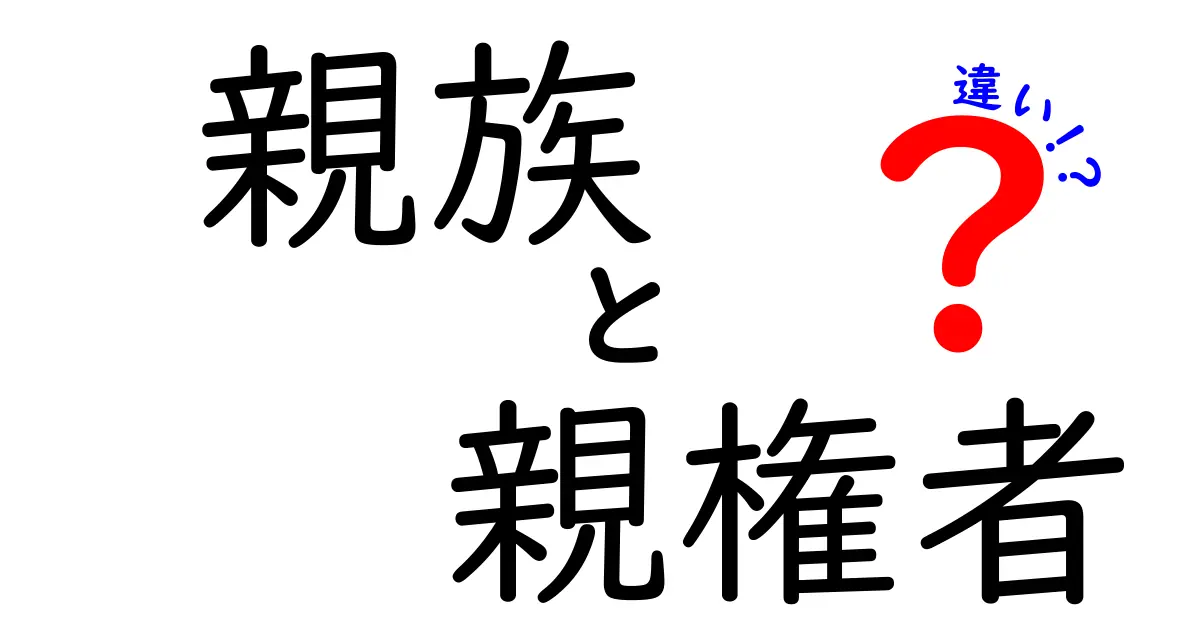

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに: 親族と親権者の違いを理解する理由
近年、家庭の出来事やニュースで「親族」「親権者」「後見」などの言葉を見かける機会が増えました。これらの言葉は似ているようで、意味と使い方がぜんぜん違います。正しく区別できると、子どもや家族の将来設計、学校・自治体の手続きがスムーズになります。本記事では、親族と親権者の基本的な違いを、日常生活の場面に落とし込んで分かりやすく解説します。
難しい法律用語を避け、例え話や身近な事例を用いて説明します。本文を読んだ後には、具体的に誰が何を決める権限を持っているかをイメージできるようになるでしょう。
親族とはどこまでを指すのか?
「親族」という言葉は、血縁関係や婚姻関係で結ばれた人々をまとめて指します。法的な権利義務を必ず伴うわけではないことが多い点がポイントです。日常生活では、父母・兄弟姉妹・いとこ・義理の親族などを含む広い意味で使われます。学校の行事の案内やお祝いごとで「親族の集まり」という表現を見かけますが、それは“近い身内”というニュアンスで、必ずしも法的代理権の有無を示すものではありません。
この区別を押さえておくと、役所の手続きやトラブルの際に誰がどの権限を持つのかを混同しにくくなります。
親権者とは何を持つ人のことか?
「親権者」とは、未成年の子どもについて、法的な代理人として教育や財産の管理を行う権利と義務を持つ人のことです。通常は両親のうちの誰か一方、もしくは二人がその役割を担います。親権には監護権と財産管理権が含まれ、日常の学校選びや医療の同意、銀行口座の管理まで影響します。ただし、家庭の事情によっては裁判所が後見人を選ぶケースもあり、そうした場合は「親権者」以外の人が法的代理人になります。親権者の判断は子どもの最善の利益を第一に考えるべきです。
この点を理解しておくと、もしものときにどの人が子どもを守るのかが明確になります。
現実のケースでの違いと注意点
実生活では、親族と親権者の関係は必ずしも一致しません。離婚後の養育権の争い、両親が異なる地域に住んでいる場合、誰が親権者になるかで学校の提出物や医療の同意などが変わってくることがあります。祖父母が日常的な世話を担当していても、財産の管理権や教育方針の決定権は親権者がもつのが基本です。成年に達した時には親権者の権利は終了しますが、成年後見制度が必要になるケースもあります。現実のケースを想定して、家族間の話し合いと法的手続きを整えておくことが安心につながります。
なお、地域の制度や学校のルールによって対応が異なるため、困ったときは自治体の窓口や学校の相談窓口に相談しましょう。
表で見る違いの要点
この表は親族と親権者の違いを視覚的に整理して理解を深めるためのものです。実際の手続きでは、ケースごとに専門家の判断が必要になることが多いので、表の情報を出発点にして、具体的な状況を一つずつ確認していくと良いでしょう。親族の範囲は家庭の事情や地域の慣習によっても多少異なることがあり、血縁の近さが近いほど権利の話題が混乱しやすい点に注意してください。例えば、離婚や養育費の場面では、親族と親権者の役割が分かれて現れるケースが多いです。日常の決定と法的な代理権の差をしっかり認識しておくことが大切です。
<table>この表を手元に置いておくと、ニュースや学校の連絡、家庭裁判所の説明資料を読んだときにも頭の中の整理が進みます。実務では、子どもの最善の利益を第一に考える基準が重要で、親族であっても必ずしも同じ権利を持つわけではありません。現実の場面で迷ったら、まずは家庭内での話し合いと、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
友だち同士の雑談風に、親族と親権者の違いを深堀りしてみると、同じ“身近な人”という言葉でも意味がだいぶ変わることが分かります。例えば、私の家では親族はおじさんおばさんの総称で、いとこも顔を合わせれば話が進みやすい存在。ただし、親権者は別の枠で、未成年の決定を責任を持って行う人のこと。親戚と法的な権利者の違いを、実生活の迷いごとにどう対処するか、ん? こうやって会話をしながら整理していくのが一番理解が深まります。