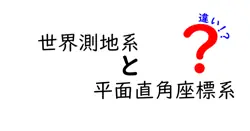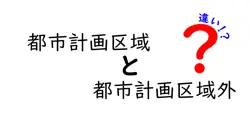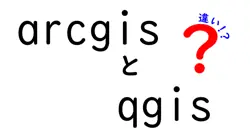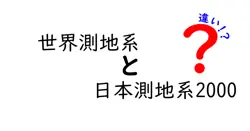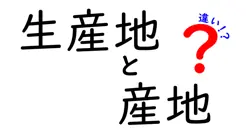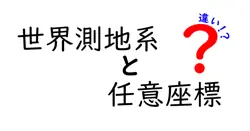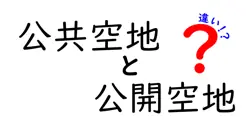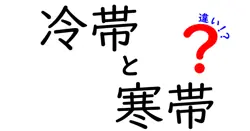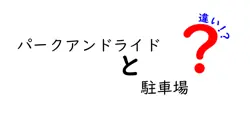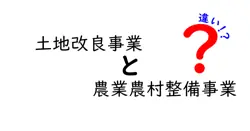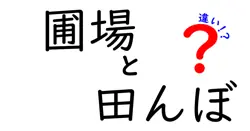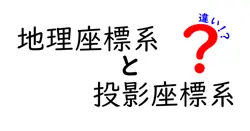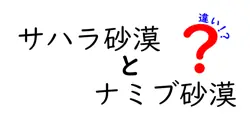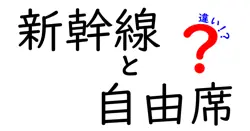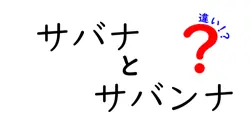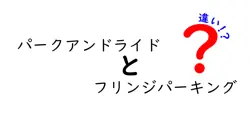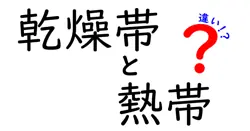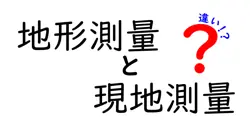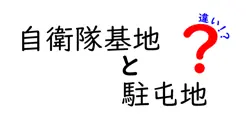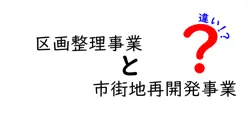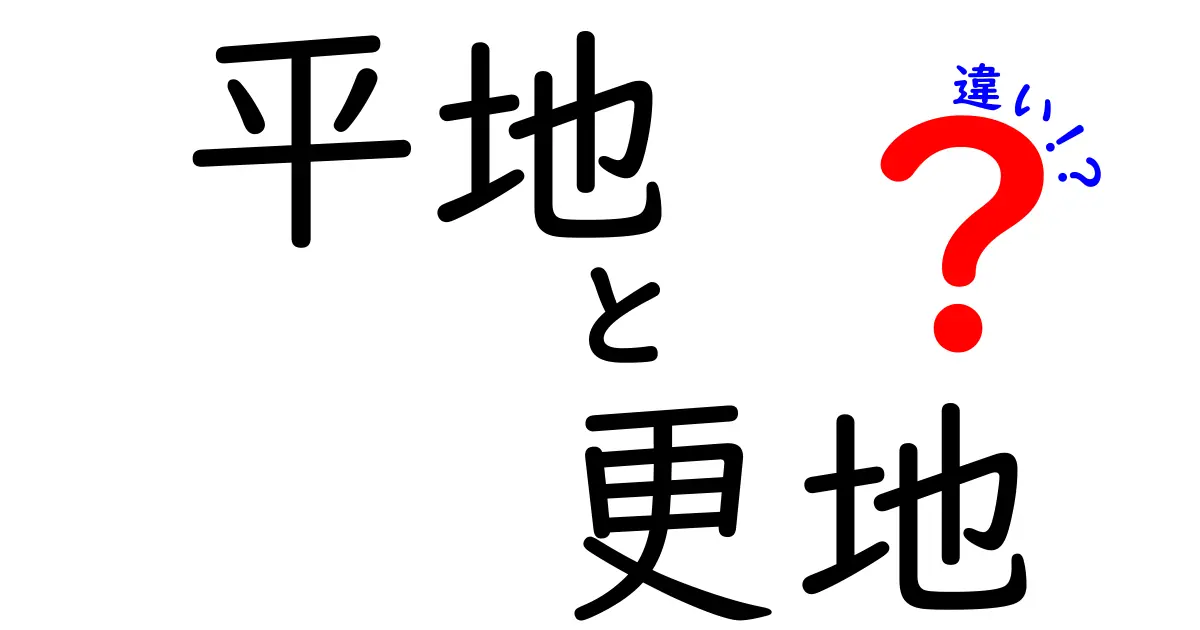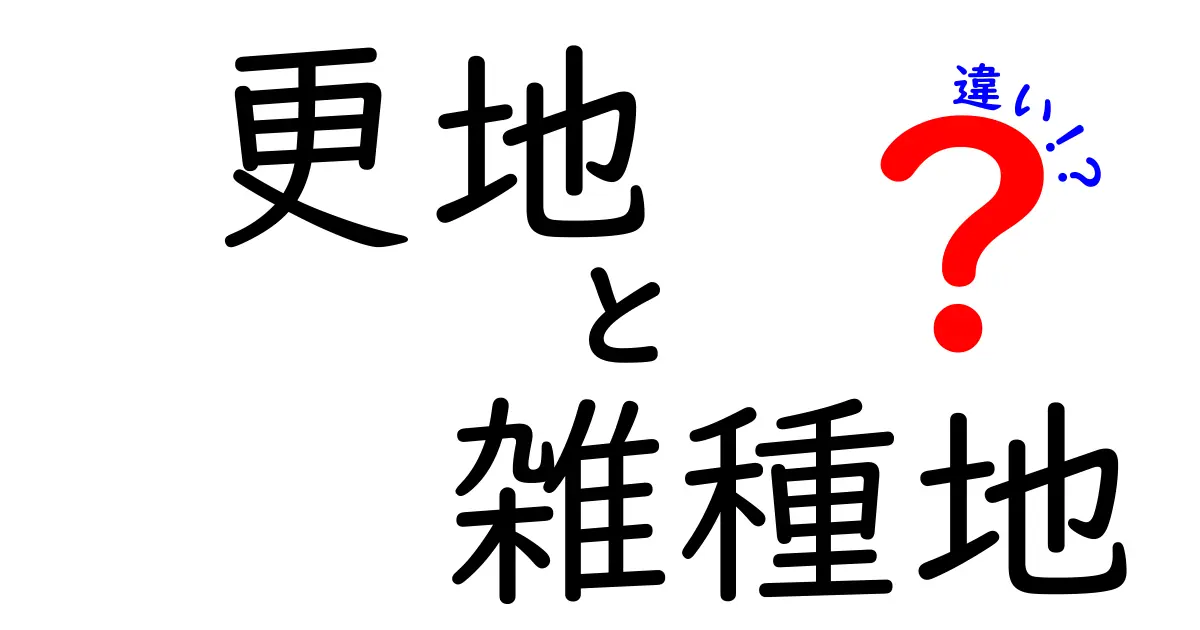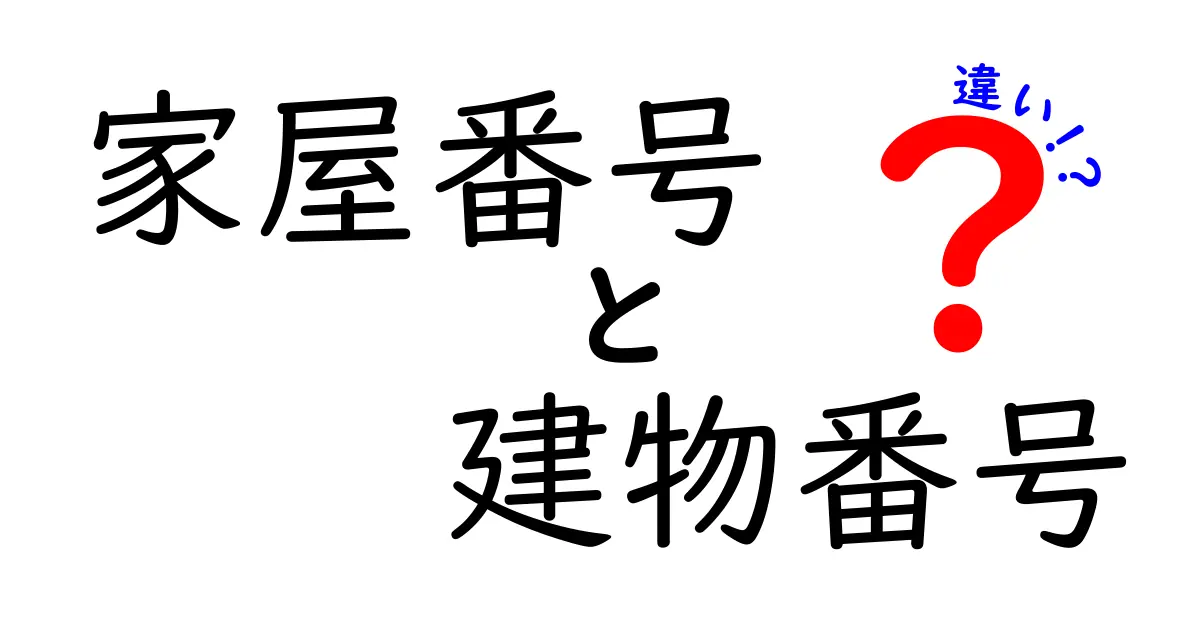

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
家屋番号と建物番号の違いを徹底解説!誰も知らない実務のポイント
日本の住所制度には複数の番号の呼び方があり、混乱を招くことがあります。その中でも特に混同されやすいのが家屋番号と建物番号です。この記事では、両者の意味と使い分けを中学生にもわかるように丁寧に解説します。まず、家屋番号は“その敷地(地番)に建つ家屋を特定する番号”です。敷地の中に複数の家屋がある場合、それぞれに異なる家屋番号が割り振られることがあります。これに対して、建物番号は“建物そのものを識別する番号”で、特に一つの敷地に複数の建物があるときに役立ちます。例えばマンションの棟ごとに建物番号が付くことがあり、郵便物の宛先や行政手続きで建物を正確に指すための手掛かりになります。
歴史的には、昔は地番と家屋番号が主な組み合わせでした。これに対して現在では住居表示の導入により建物番号が使われる場面が増え、同じ地域内でも建物ごとの識別がしやすくなりました。家屋番号は土地の区画を基準にした番号で、地番とセットで登記情報に現れることが多いです。建物番号は建物の構造を示す番号として機能し、特に新しく建てられた建物や複数棟の集まる施設では重要な要素となります。これらの違いを理解すると、郵便物の配達ミスや行政申請の入力ミスを減らせます。
実務での使い分けのポイントとしては、まずどの情報源を参照するかを確認することが大切です。登記簿謄本や土地台帳には地番・家屋番号の表記が出ることがありますが、現場の住所表記としては建物番号が中心になるケースが多いです。また、新しい物件や複数の建物がある場合には、建物番号を優先して使い、必要に応じて家屋番号と併記する形にすると混同を避けられます。最終的には、郵便局や役所の提出書類の指示に従うことが最も確実です。
この違いを日常生活で意識する場面としては、住所を入力する場面、荷物を送るとき、住民票を取るときなどが挙げられます。家屋番号と建物番号のどちらが記載されているかに気をつけ、誤って入力すると別の建物に届く可能性があります。特に都市部では、建物番号をもとに建物を特定するケースが多く、部屋番号(号)との組み合わせで正確な宛先を作ることが求められます。最後に、役所の窓口や不動産業者の担当者に確認する癖をつけると、将来のトラブルを未然に防げます。
表で見る違いと使い分けの要点
以下の表は、実務でよく遭遇する場面を想定して作成した要点です。見出しとしては500文字以上の本文を補足する形にしていますので、読みやすく整理されています。
表の構造を読み解くことで、どの場面でどの番号を参照すべきかが一層明確になります。
ねえ、建物番号って何だか地味だけど実は大事な話なんだ。街を歩いていて、同じ敷地に複数の建物がある場合、どの建物へ荷物を届けるかを決める手掛かりになるのが建物番号なんだよ。家屋番号は敷地内の個別の家を指す番号で、地番とセットで使われることが多い。一方、建物番号は建物自体を識別する番号として現代の住所表示の中心になっている。複数の建物がある区域では、建物番号を使って正確に建物を特定することが重要で、必要に応じて家屋番号を併記して混乱を避けるのが実務のコツさ。僕が郵便物を受け取るときに、建物番号が違うと別の建物に届いちゃう経験をしたことがあるんだ。だから、引っ越しや転入のときには、まず建物番号が何かを確認しておくと安心だよ。
前の記事: « 根保証と限定根保証の違いを徹底解説|リスクを抑える選び方と注意点