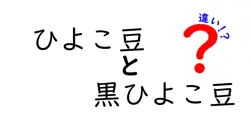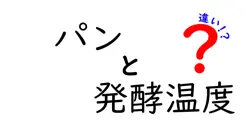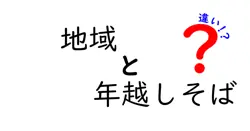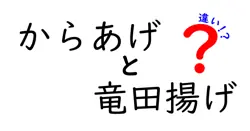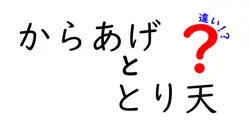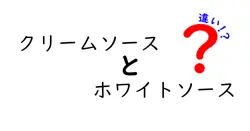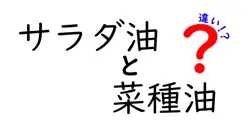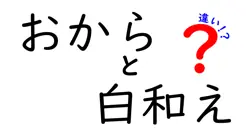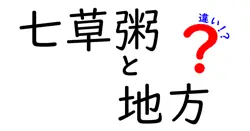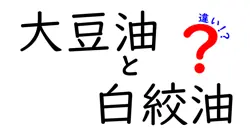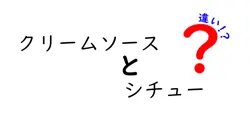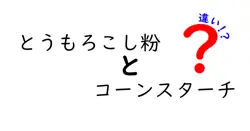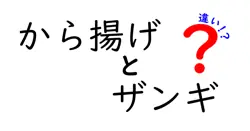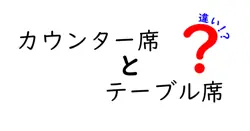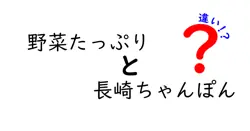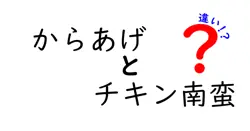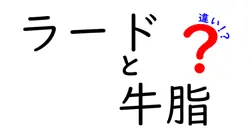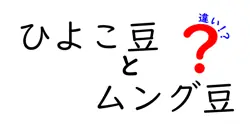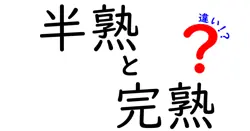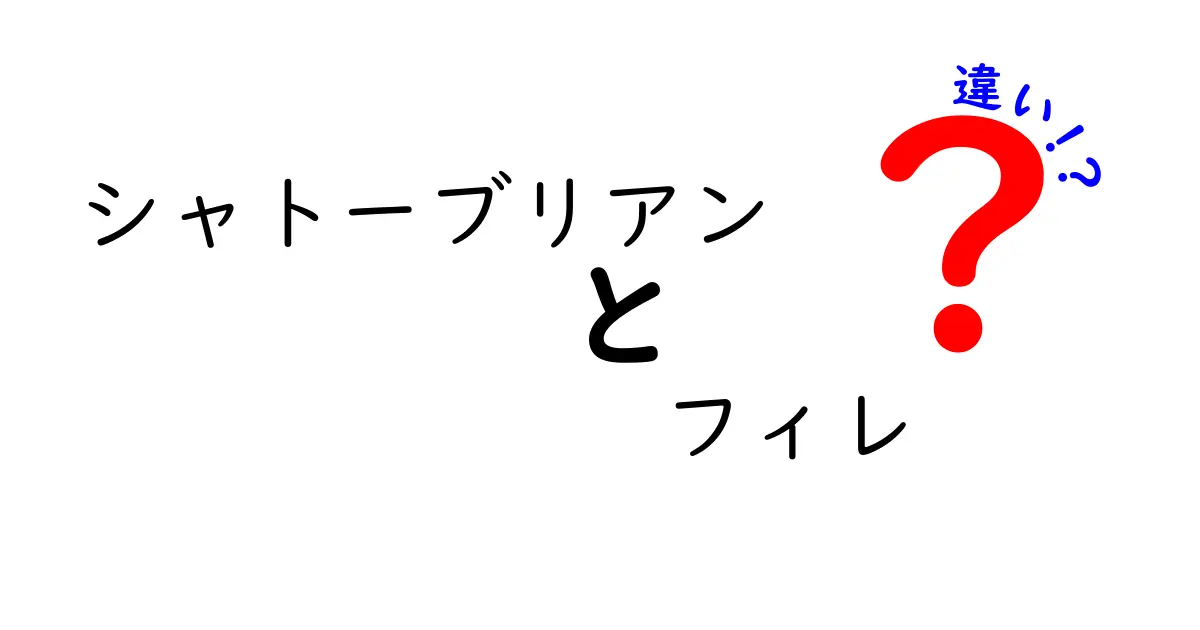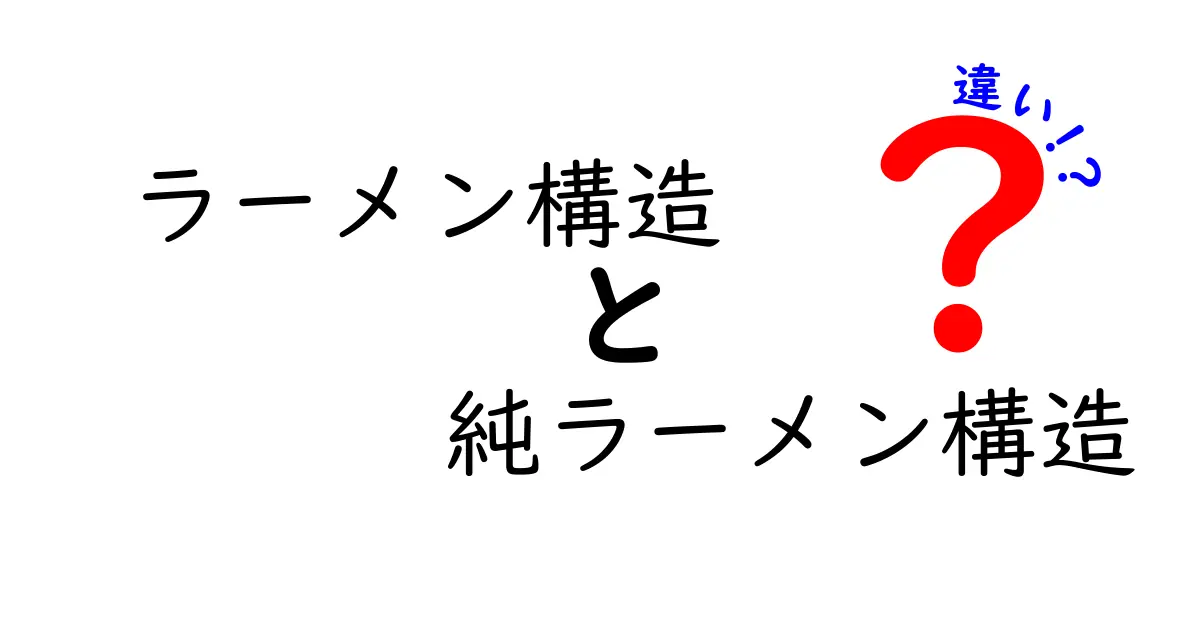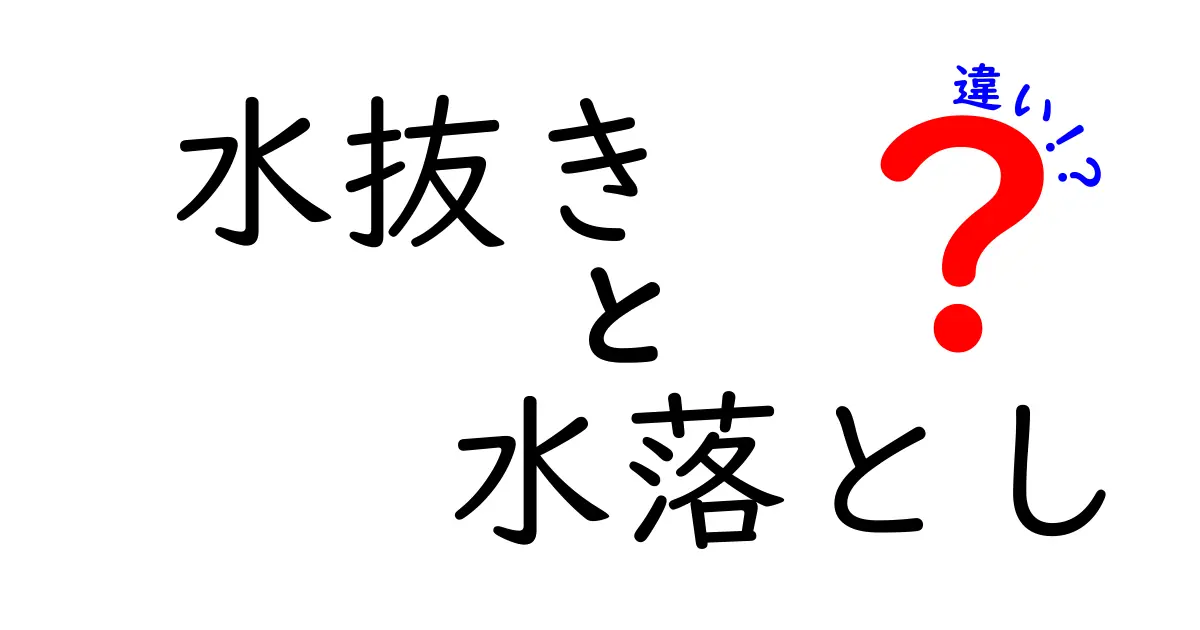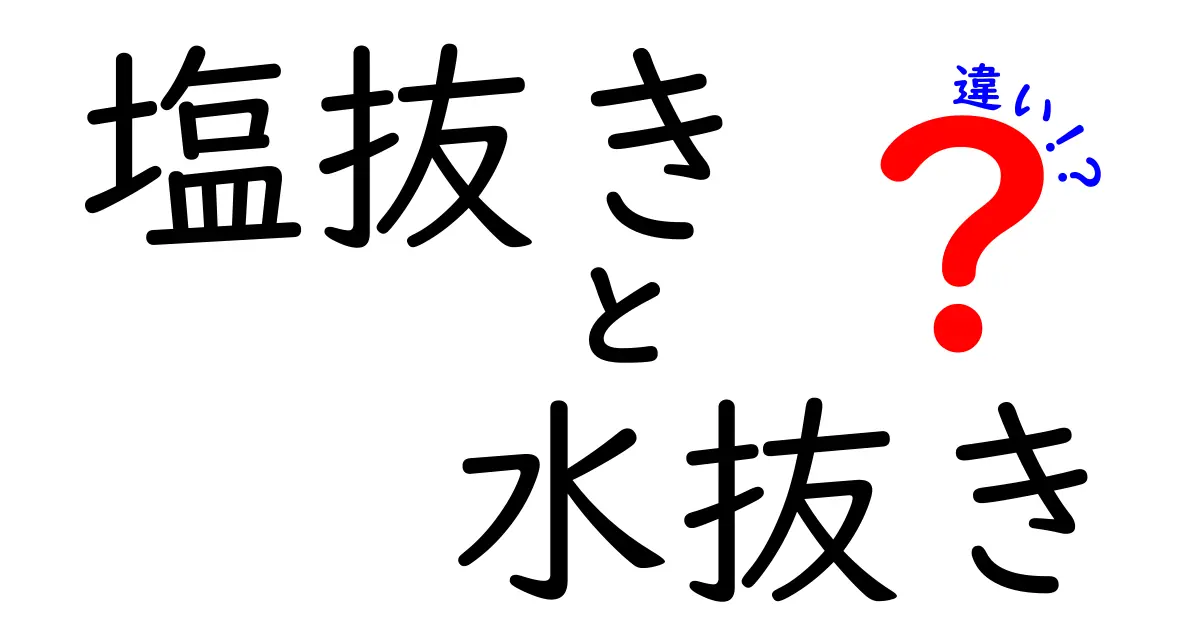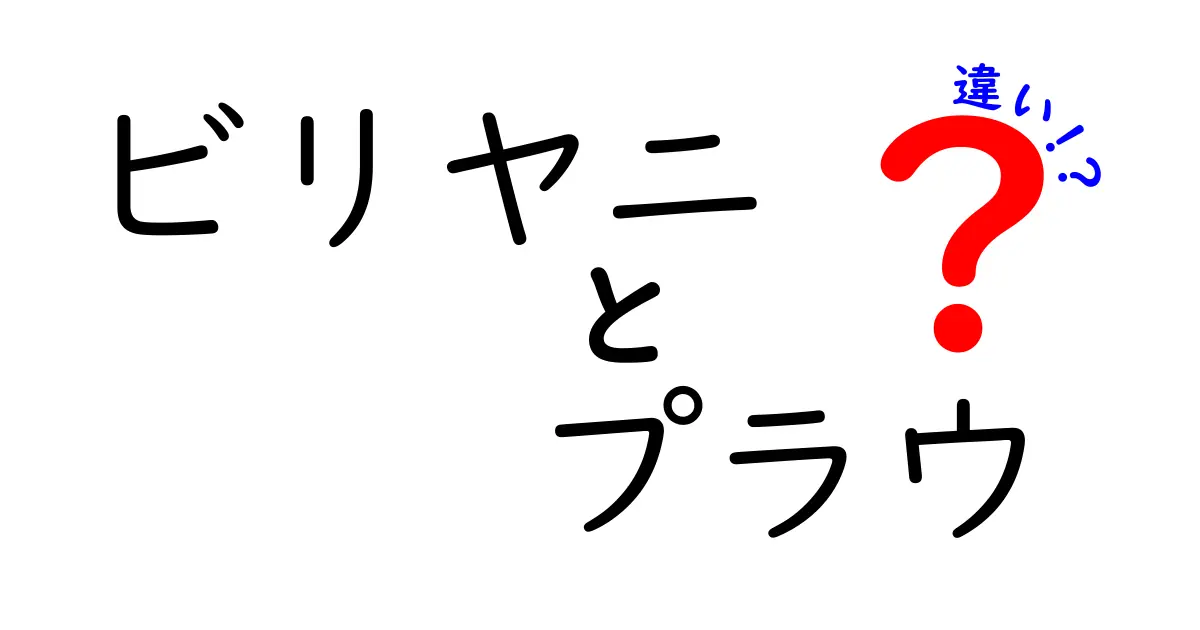

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
ビリヤニとプラウの違いを徹底解説
ビリヤニとプラウはどちらも米料理の王道ですが、作り方や米の扱い、香りのつけ方、味の深さの出し方が大きく異なります。
この違いを理解すると、レシピ選びが楽になり、食卓での会話も盛り上がります。
ビリヤニは層状に米と肉を重ねて、香り豊かな油脂とスパイスをふんだんに使うことで「華やかさ」を生む料理です。
プラウは米と肉を一体に煮込むスタイルが基本で、出汁の旨味と米の柔らかさを前面に出します。
香りの違いは大きなポイントです。ビリヤニはカルダモン、クローブ、シナモン、サフランなどの強い香りを多用します。油脂もギーやバターを使い、香りが口に広がる前に鼻に抜けるように設計します。プラウでは香りを控えめにして出汁の風味を活かすことが多く、素材の旨味をじっくり引き出す調理が中心になります。
この香りの差は食卓での第一印象を決め、イベントや特別な日の献立として人気が高いのはビリヤニのほうです。
米の扱いも大きな違いです。ビリヤニでは長粒種の aged basmati を用い、米を半分ほど下茹でしてから層状に重ねてダム炊きします。水分と熱をじっくり閉じ込め、米一粒一粒に香りと油脂が絡むのが特徴です。プラウでは通常、米を多少水に浸してから煮るか、出汁と一緒に煮て米粒をやさしくほぐします。結果として、プラウは米の食感がややしっかりしていて、肉のジューシーさと出汁の風味がまとまりやすいです。
香りと米の違い・仕上がりのコツ
香りの強さは香辛料と油脂の量、加熱の仕方に大きく左右されます。ビリヤニでは香りを最大化するために玉ねぎを長く炒めて甘さを出し、スパイスを全体に均一に絡めます。カルダモンやクローブ、サフランなどのスパイスを適切な順序で投入することが肝心です。これにより、蓋を開けた瞬間の香りが食欲を刺激します。対してプラウは出汁のコクと米の素朴な香りを前面に出すため、香りづけを控えめにし、米と肉の旨味のバランスを整えることを重視します。
仕上がりの食感ではビリヤニがふんわりとした層状で、口に入れた瞬間の香りが長く続くのに対し、プラウは米がしっかりと立つ一体感のある食感になりやすいです。
実生活での使い分けのヒント
日常の献立で選ぶ目安として、お祝いごとや特別な日にはビリヤニの華やかさを、普段の食卓や家族の夜ご飯にはプラウのやさしい味わいを選ぶとよいでしょう。料理の練習として始めるなら、まずはプラウから挑戦してみて、慣れてきたらビリヤニの層作りや香りづけを少しずつ追加していくと成功しやすいです。自宅のキッチンでこの2つの違いを体感することで、料理の幅がぐんと広がります。
友達と台所に立つときの会話のように言えば、ビリヤニは華やかなドラマの主役級、プラウは落ち着いた日常のヒーローです。ビリヤニは層を作って香りを閉じ込めるダム炊きの技が命で、油とスパイスの調和が味に深みを与えます。一方プラウは出汁と米を一体化させる煮込み方が基本で、素材の旨味が穏やかに広がるのが魅力です。どちらも美味しいのですが、香りと食感の好みで選ぶと食卓がもっと楽しくなります。
前の記事: « 刈払機 山林用 違いを徹底解説|山林用と一般品の違いと選び方