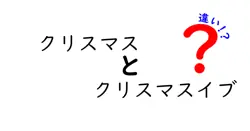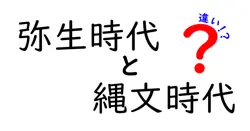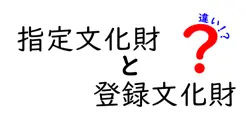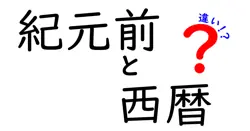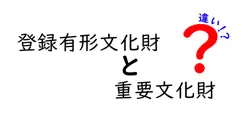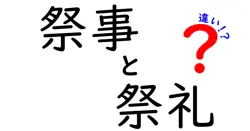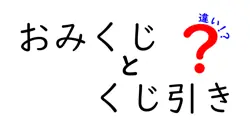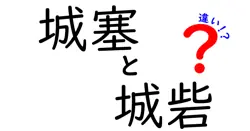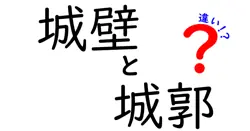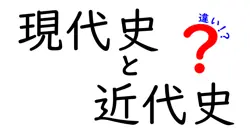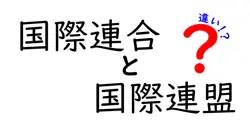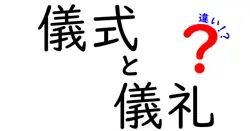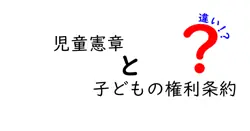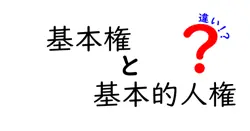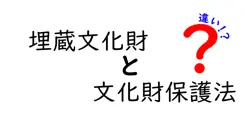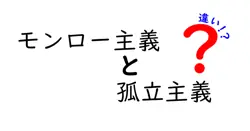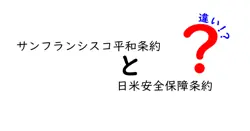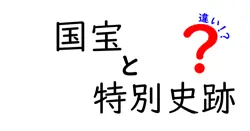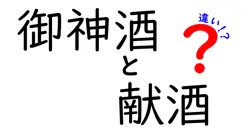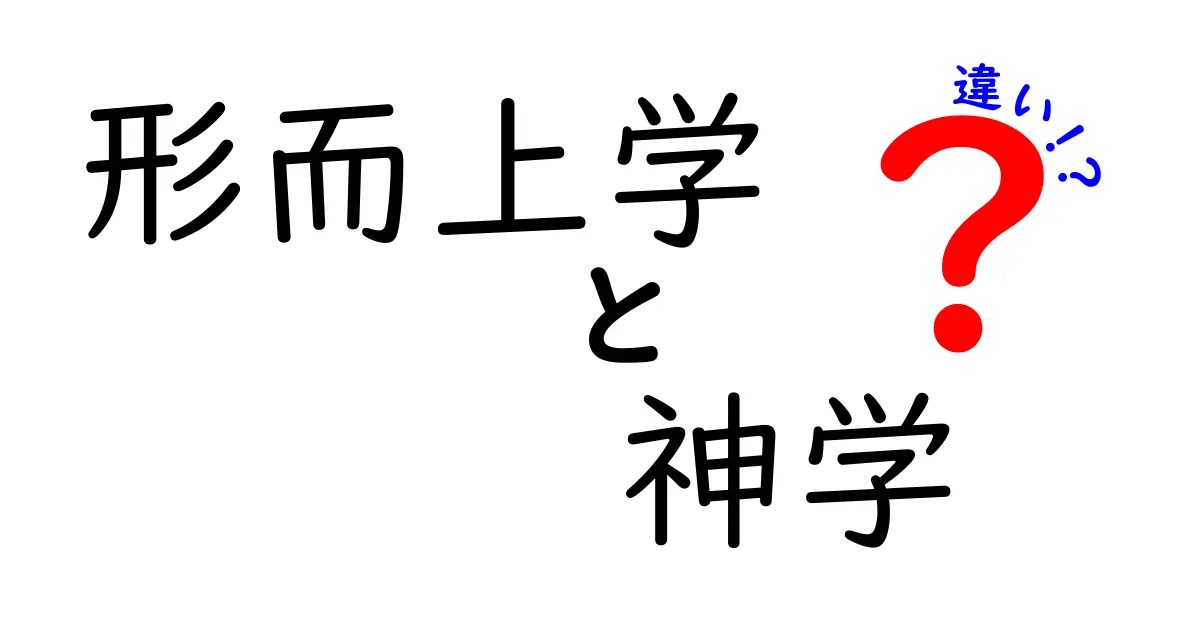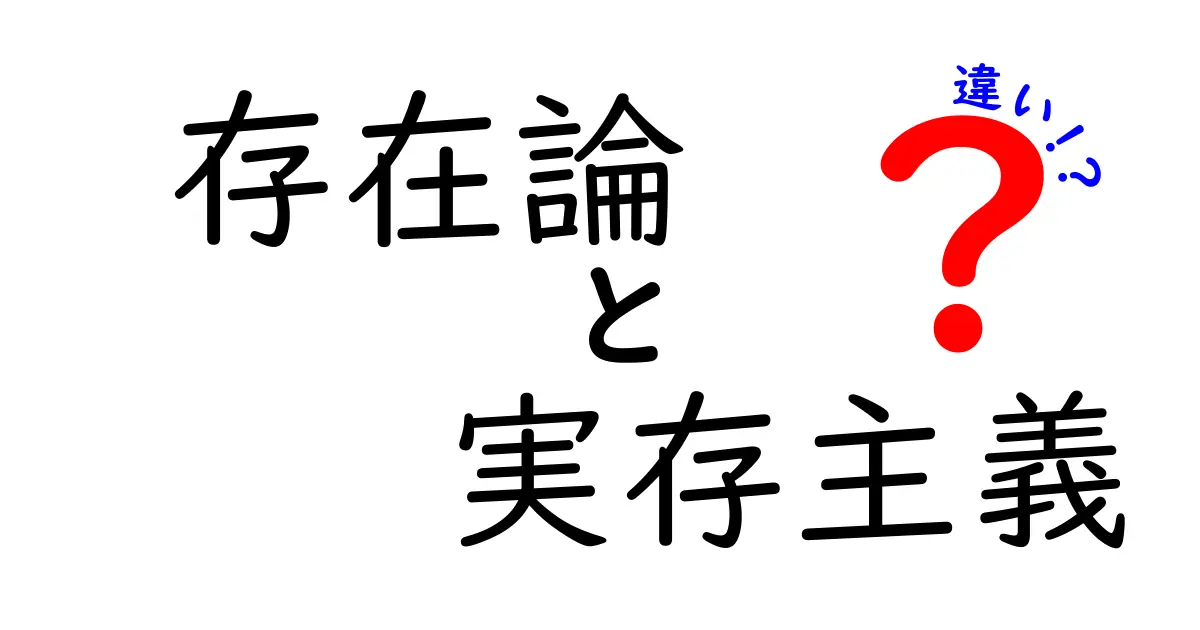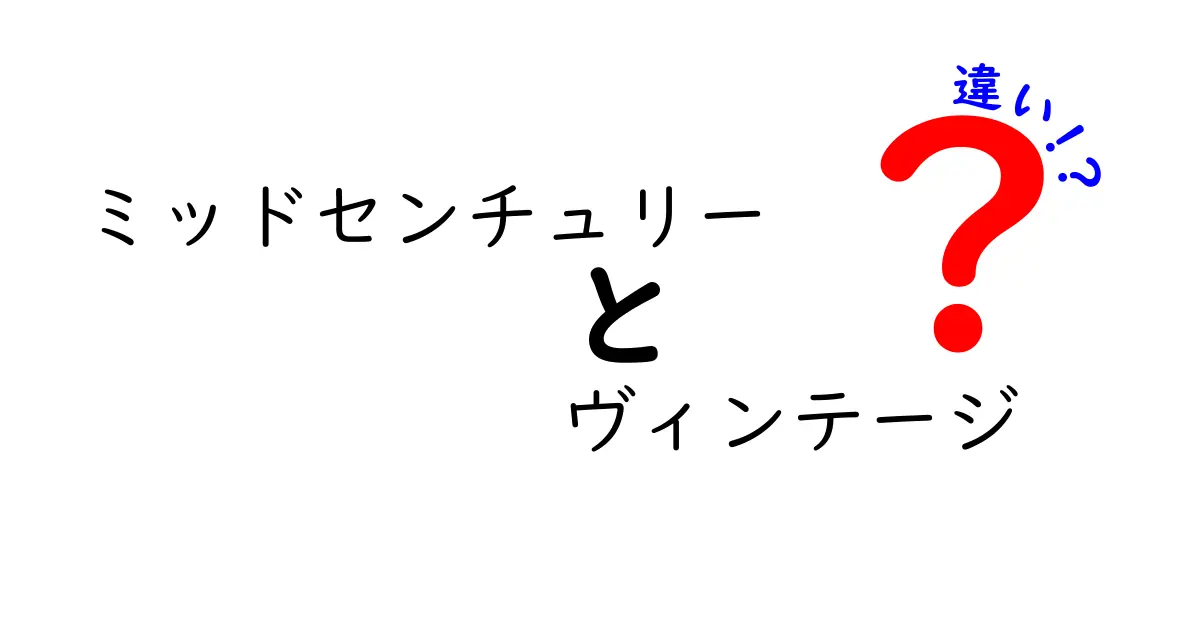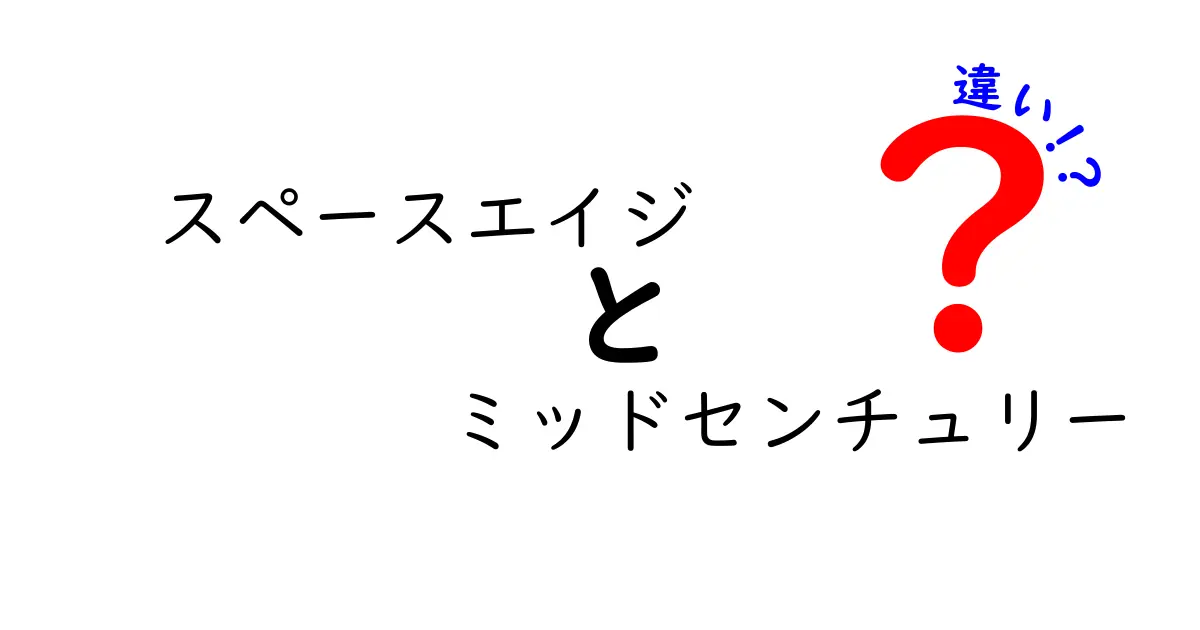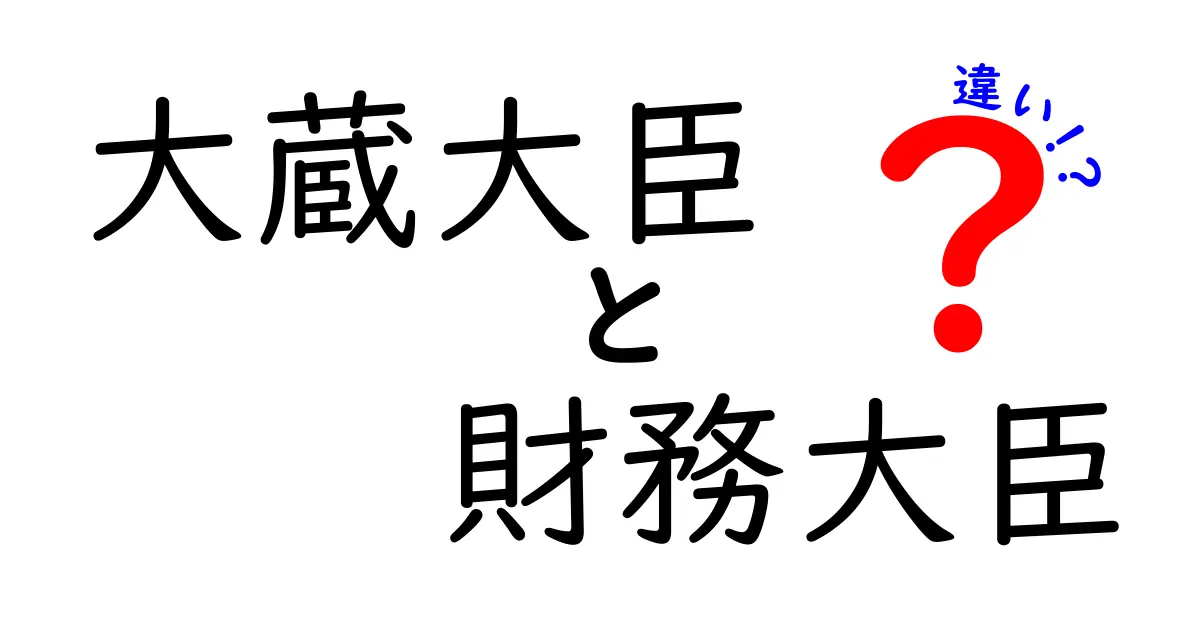

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:大蔵大臣と財務大臣の基本的な違い
この2つの名称は、見た目には似ているけれど指す意味や時代背景が大きく異なります。まず大切なのは、どの時代のどの組織を指しているかという点です。戦前・戦中の日本では大蔵省という政府機関が財政を統括し、その長として大蔵大臣が就任していました。この時代の経済政策は、戦争財政や復興資金の確保、貨幣供給の安定化など、国家全体の資金運用を直接左右する重大な職務でした。制度上は内閣の一員であり、時には財政と外交・軍事の調整役を兼任することもあり、権限は現在よりも分かりにくく、複雑な政治状況の中で動く場面が多くありました。
1949年の行政改革以降、財政の運用は財務省という新しい組織に移され、呼称も財務大臣となりました。名前の変化は、単なる語の違いではなく、組織再編による責任の明確化と透明性の向上を意味します。現在の財務大臣は、税制・予算・公債などの政策決定に関する最前線に立ち、閣僚として内閣全体の財政方針を整合させ、国会での予算審議に対して説明責任を果たします。歴史的な背景を知ると、どうして同じ「財政のトップ」なのに役割の呼び名が変わったのかが理解しやすくなります。
ただし、歴史の中で大蔵大臣という語が完全に消えたわけではなく、教科書や報道、古い文献の中には今も登場します。そのため、文脈を読み分ける力が大人でも少し必要になります。この章では、名前の変遷だけでなく、実際の権限の範囲、政策との関係、時代ごとの政治的影響を掘り下げ、現代の財務大臣の立場をしっかりと理解できるようにします。
歴史的背景と現代の役割の違い
この節では、過去と現在の具体的な権限の差、担っていた責任の広さ、組織の機構的な変化に注目します。
昔の大蔵大臣は、内政と外交の財政面の多くを握り、時には閣僚間の調整だけでなく、財政国家的な計画まで直接関与しました。現在の財務大臣は、税制の改正案、予算編成、歳入確保、国債発行など、日々の財政運営を指揮する立場です。
この違いは、制度が変わったことで生まれた「用語の意味の変化」と、「組織の成果物の違い」の2つの面から理解すると分かりやすいです。
また、実務の違いとして、財務大臣は財務省の政策方針を閣議に提案し、国会での予算審議にも直接関与します。これは戦前・戦中に比べて行政の分担が細分化され、透明性と手続きの厳格化が進んだ結果です。
以下の要点は、名称の背景と実務の現代的意味を結ぶキーポイントです。財政の三大柱である税収、歳出、公債の扱い方を理解すると、ニュースで財務大臣が何を決めたのかが見えやすくなります。戦後の制度改革によって、これらは法令と予算の形で国の意思決定プロセスに組み込まれました。
このように、名前の変化を知ることは、現在の政治の見方を深める第一歩です。中学生にも分かる言葉でまとめると、大蔵大臣は歴史の用語、財務大臣は今の制度の中で国の財政を動かす役割、ということになります。
放課後、友だちとニュースの話題で盛り上がっていたとき、財務大臣の役割の話題になった。彼は国の財布の管理者みたいに言われるけれど、実際には「税を集め、予算を配分し、国の借金をどう返すか」を戦略的に決める人だと説明すると、友だちは驚いていた。財務大臣は政策を提案し、国会で説明責任を果たし、私たちの生活費や公共サービスの資金源に直接影響を与える。つまりニュースを読むときは、彼らが何を選んだのか、なぜそれが必要なのかを一緒に追うと、難しい専門用語も身近に感じられる、という雑談でした。
前の記事: « 財務大臣と金融大臣の違いを徹底解説|中学生にも分かる実務ガイド