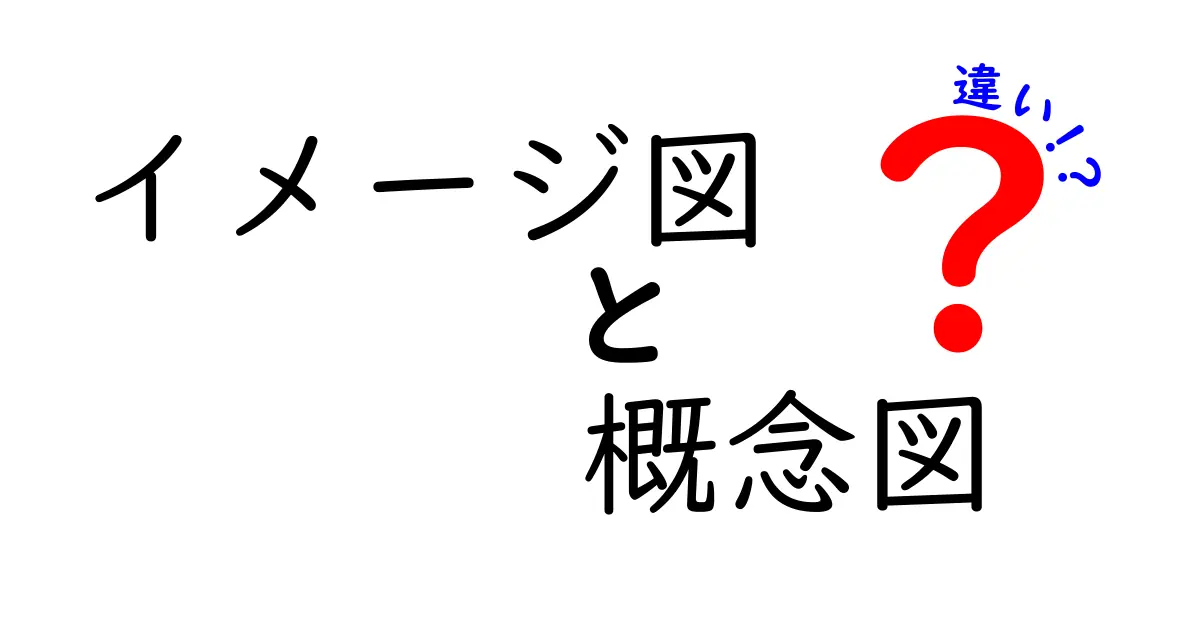

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
導入:イメージ図と概念図の違いを知る理由
私たちは日々、情報を頭の中で整理するときに「イメージ図」と「概念図」という二つの道具を使います。どちらも物事を整理するための図ですが、目的や描き方、伝え方が違います。ここを理解していれば、学校の授業ノートだけでなく、インターネットの記事や資料を読んだときに、何をどう伝えようとしているのかが見えやすくなります。
たとえば地図を思い浮かべてください。道順を覚えるときには白地図のイメージが浮かぶかもしれません。これがイメージ図の力です。一方で、ある仕組みを説明する場合には、関係性や階層を並べて描く概念図が役に立ちます。違いを実感すると、学習の効率が上がり、他人にも伝えやすくなります。
本記事では、イメージ図と概念図の特徴、使い分けのコツ、作成のステップを具体的な例を交えて丁寧に解説します。中学生のみなさんにも分かる言葉と身近な例を用いて、読み終わるころには「どちらをどこで使えばいいのか」が見えるようにします。
イメージ図とは何か
イメージ図は、物事の「見た目の印象」をもとに作られる図です。色や形、写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)の雰囲気、実際の場面を頭の中で描くような感覚で情報を伝えます。具体的には、あるテーマの全体像をひと目で感じ取れるように、色分けされたブロック、アイコン、写真のイラストを組み合わせて描くことが多いです。
たとえば「地球温暖化の影響」を説明するとき、海の色を青、陸の色を緑にして、気温の変化を矢印で示すといった感じです。ここで大事なのは、現象の“雰囲気”や“直感的なつながり”を重視することです。
その結果、受け手は話の全体像をざっくりと把握しやすく、話の流れを頭の中で追いやすくなります。ただしイメージ図は細かな定義や根拠を必ずしも示さないことがあるため、詳しい説明や数値が必要な場面では欠点にもなりえます。
概念図とは何か
概念図は、物事の成り立ちや関係性、階層構造を「つながり」で表す図です。中心となる概念を中央に置き、関連する概念を枝のように広げていくイメージで作ります。概念図の強さは、複雑な情報を整理して頭の中で“理由と結果”や“原因と効果”がどう結びつくかを見える化できる点にあります。
例えば「健康的な生活」の概念図を作ると、睡眠、食事、運動、ストレス管理といった要素がどのように影響しあうかを、一連の関係として示せます。
概念図を活用すると、学習の過程で新しい知識を既存の知識とつなげやすく、後から見直すときにも理解の軸がぶれません。
実生活での使い分けと作例
日常の学習でも、仕事でも、イメージ図と概念図の良さを組み合わせて使うと効果が上がります。まずは伝えたい“全体像”をイメージ図で表し、続いてその全体像を構成する要素の“関係性”を概念図で整理します。
以下の手順で作成すると、初心者でも分かりやすい図が作れます。
- 目的を明確にする:何を伝えたいのか、受け手は誰かを決める。
- 情報の階層を決める:大分類・中分類・小分類の順で並べる。
- 図の構成を決める:イメージ図は見た目の印象、概念図は関係性を重視する。
- 要素の表現を決める:色・形・アイコンを統一する。
ここからは具体的な作例です。以下の表は、教育現場でよく使われる「エネルギーの流れ」を題材に、イメージ図と概念図の違いを並べて示したものです。
見比べると、どの場面でどちらを優先すべきかが明確になります。
この表を見れば、作成時の意図を誰に伝えたいのかで選ぶ基準がはっきりします。
イメージ図は「とっさの理解」に強く、概念図は「深い理解の基盤」を作るのに適しています。
学校の授業や部活動の資料、プレゼンテーションの準備など、場面に合わせて組み合わせて使うのが効果的です。
また、図を作るときに心がけたいポイントとして、視覚的な一貫性を保つこと、情報の抜け漏れを防ぐチェックリストを持つこと、そして読み手の理解ペースを想定して段落を分けることがあります。これらを意識すれば、初心者でも数時間で実践可能な作例が作れます。
イメージ図と概念図の違いを深掘りする小ネタ: 友だちと課題の話をしていて、イメージ図は“見た目の印象”を先に伝える道具、概念図は“関係性”を整理する道具だと気づきました。実は作業の順番も大切で、最初にイメージ図で全体像を作ると、後から概念図で細部のつながりを埋めていくとスムーズです。この発見は、今後の学習計画やプレゼン資料作成にも役立ちます。
前の記事: « 仕様図と承認図の違いを徹底解説!図の役割を正しく使い分けるコツ





















