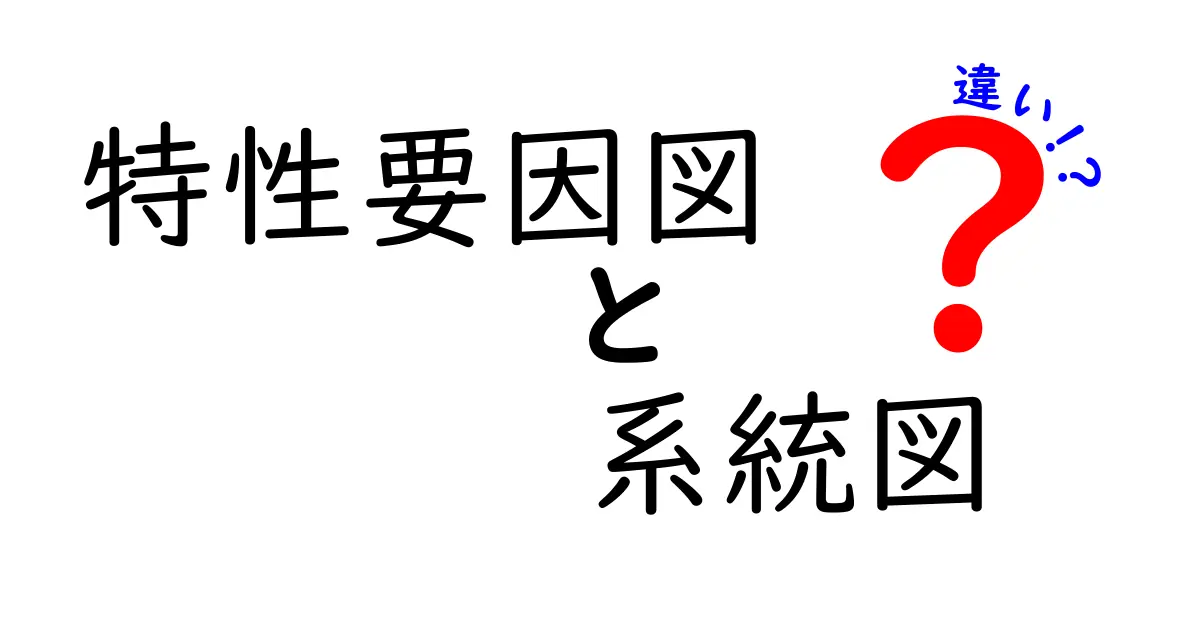

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
特性要因図と系統図の違いを徹底解説
特性要因図とは何か-原因と影響を整理する道具
特性要因図は問題の原因を整理していくための道具です。別名魚の骨図とも呼ばれ、頭に問題の主題があり、それを取り囲む原因を骨のような枝に見立てて整理します。品質管理や教育研究の場面で広く使われ、複雑な原因を視覚的に整理する力を育てます。図は水平の軸に主題を置き、そこから分岐する原因を「材料」「方法」「人/作業」「設備」などの大きなカテゴリに分け、さらに各カテゴリを細かな要因へと細分します。図を作ると、どの分野が原因として強く影響しているのか、またどう改善すればよいのかが見えやすくなります。ここで大事なのは情報を枝分かれさせすぎず、要点だけを拾うことです。
特性要因図の作成にはチームでのブレインストーミングが有効です。最初は主題を紙の左端に置き、次に大分類を右へ順に並べていきます。話し合いの中で「本当にそれが原因なのか」を検討するのは大切です。正確さよりも発想の幅を広げることが狙いであり、後半で現実的な要因へ絞り込む作業が残ります。実践では5W1Hを意識し、作業手順の順序、設備の状態、材料の品質といった具体的な要因まで掘り下げます。
特性要因図を使うときのコツは二つです。第一に主題と大分類をはっきり分けること。第二に全要因を羅列しただけで終わらせず、優先度と影響度を後で検討するためのメモを添えることです。図が大きくなりすぎると読み手が迷子になります。適度なスペースと分かりやすい名前を使い、関係を矢印で示すと理解が楽になります。最後に図を作った後は必ず現場で確認し、実際の変化とデータをもとに修正を繰り返しましょう。
<table>系統図とは何か-系統的な関係を示す図
系統図は物事の関係性を木のように分岐させて示す図です。ここでは因果関係ではなく、階層や分岐の順序、系統的なつながりを可視化します。生物の分類図や組織図、流れ図として日常にも使われ、情報の構造化に役立ちます。系統図の良さは「全体像を一目で把握できる」点です。どの要素が親要素か、どの要素が子要素かを見れば、全体の仕組みが頭に入ります。複雑な操作手順や製品の構成、プロジェクトの担当分担など、さまざまな場面で「どの要素がどの要素に繋がっているのか」を把握するのに適しています。
系統図を作るときには上位要素を左に置き、分岐する下位要素を右へと並べます。親子関係と依存関係を明確化することが目的で、ブレインストーミングで思いつきをどんどん書き出した後に、現実の階層構造に沿って整えます。人の役割や部門の責任範囲、ソフトウェアのモジュール構成など、抽象的な関係を具体的な形にするのが系統図の役割です。初めは簡単な二分木から始め、慣れてきたら三分岐、四分岐と拡張していくと読みやすくなります。
両方の図を比べると、目的が異なることがよく分かります。特性要因図は「原因を探す・解決策を決める」道具、系統図は「構造を把握する」道具です。現場ではこの二つを組み合わせて使います。問題の現象を特定して原因を並べ、それを構成する要素の階層を作成することで、全体像と個々の要因の両方を見える化できます。
違いを理解する実用的なポイント-使い分けのコツ
違いを押さえるときの要点は三つです。第一に目的の違いをはっきりさせること。原因を探して改善を目指すなら特性要因図、全体像を把握したいなら系統図を選ぶのが基本です。第二に図の表現方法が異なる点。魚の骨の形と木の形、どちらが適しているかを現場の読みやすさで判断します。第三に連携のしかた。現場のデータと経験を両方活用することで、図はより説得力を増します。実務では両方を使い分けることで問題解決のスピードと精度を高められます。
今日は特性要因図の話題を友だちと雑談風に深掘りします。特性要因図は問題の原因を整理する道具で、魚の骨の形に似ているから魚骨図とも呼ばれます。学校の実験や部活の改善活動で、何が問題を起こしているのかを見つけ出すのに役立つんです。私たちが初めにやるのは大きな主題を決めて、それを支える原因の枝を考える作業です。ここで大事なのは早く結論を出さず、思いつく理由をとにかく並べてみること。するとどれが本当に影響しているのか、だんだん絞られてきます。話しているとき、日本の学校でよくあるのは結果のせいにする癖ですが、特性要因図は原因に焦点を当て、誰がどんな作業を行ったかまで整理できる点が魅力です。ちなみに私が授業で試したとき、最初は10個以上の要因を書き出しました。後で優先度をつけると、実際に改善できる要因が3つ程度に絞り込めました。要因を一つ一つ検証するプロセスは退屈にも見えますが、図の力を借りれば誰でも現場の現象を「見える化」でき、仲間と協力して解決策を brainstorm する楽しさも味わえます。だからこそ、特性要因図は学習の現場にも部活動の改善にも強い味方になるのです。





















