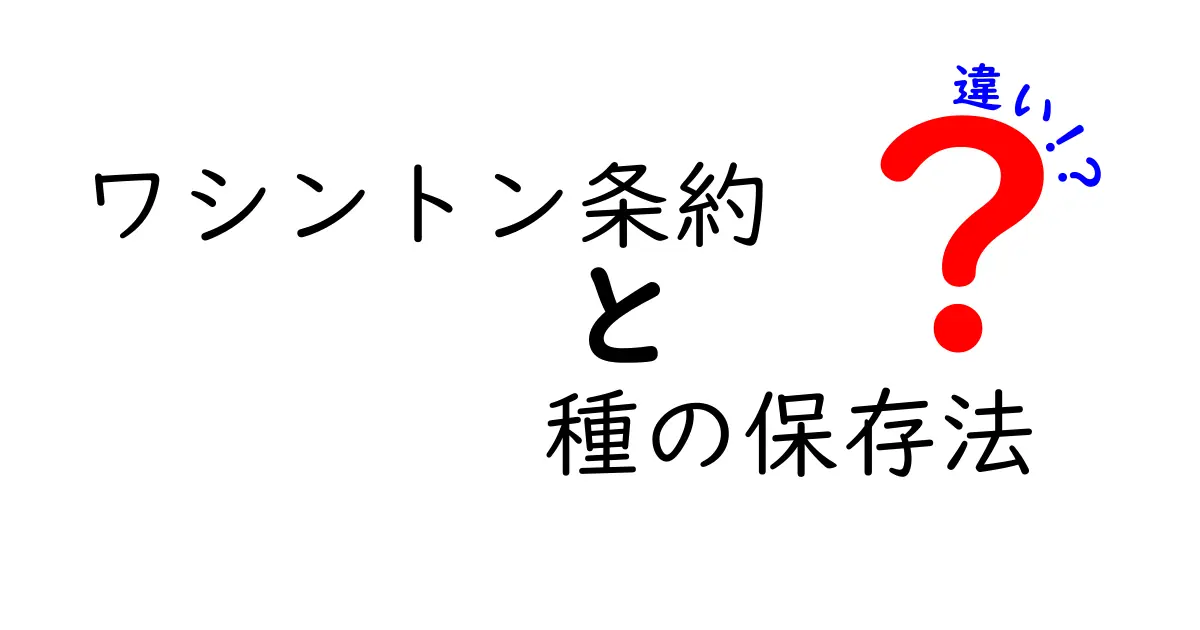

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに ワシントン条約と種の保存法の違いを理解する
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する国際協定のことです。正式名称は CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)で、1970年代以降、世界の生物多様性を守るために多くの国が参加しています。
この条約は「取引の規制」を中心に置いており、どの国がどの種を輸出・輸入できるかをルール化します。これに対して国内法である種の保存法は、日本国内での保護対象種の保護・管理・利用のルールを定め、国内での取引や展示、研究の際の手続きを細かく決めます。
つまり大きな違いは「どこで決まるか(国際か国内か)」と「対象の範囲が global か domestic か」という点です。ここを押さえれば、海外との取引が絡む場合と国内での研究・教育が絡む場合で、何を準備すればいいかが見えてきます。
さらに、二つの制度は相互補完的な関係にあります。CITES は絶滅の危機にある種を守るためのグローバルなフレームワークを提供しますが、具体的な適用は加盟各国の国内法に委ねられます。その結果、日本における輸出入や展示・販売のルールは、CITES の規定を受けつつ日本の種の保存法で規定されています。
このような重層的な仕組みを理解しておくと、海外の研究者と協力する際の手順や、国内での教育活動がスムーズに進むようになります。
ワシントン条約とは何か(CITESの概要と目的)
ワシントン条約は正式名称を CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)といい、絶滅のおそれがある野生動植物の国際取引を規制する国際的な協定です。
具体的には Appendices I II III に分かれており、Appendix I には絶滅の危機が進行している種、Appendix II には国際取引を注意深く管理すれば保護が可能な種、Appendix III には個別の国が保護を求める種が挙げられています。これにより輸出入には許可証が必要となり、違反した場合には罰則が科されます。条約の目的は「国際的な協力を通じて野生生物の取引による危機を減らす」ことです。
また、CITES はただの禁止リストではなく、現場での運用を柔軟に扱えるよう設計されており、研究・教育・保全活動の正当な目的には条件つきで認める場合があります。日本を含む多数の国がこの条約に加盟しており、国内法と整合させて実施しています。
この条約が現実の世界とどのようにつながっているかを理解するには、Appendix のリストの仕組み、許可の取得プロセス、国家間の情報共有の仕組みについて知ることが重要です。実務では、輸出入の許可を取り、どの種がどの程度の取引を許されるかを判断するためのデータベースや申請書の作成が不可欠です。これは科学研究や教育活動にも直接影響し、適切な手続きが行われていないと実験材料の入手が難しくなることもあります。さらに、違反した場合の罰則は国によって異なり、罰金や禁固、輸出入の停止などが科されることがあります。
<table>実務的な違いとよくある誤解
実務的には、条約は国際的な枠組み、国内法は実務のルールという点を押さえると理解が深まります。たとえば海外から日本へ種を持ち込む場合、CITES の許可と日本の種の保存法の両方の手続きが必要になることがあります。ここでよくある誤解は「CITESがすべてを禁止している」というイメージです。本当は「許可があれば合法的に取引が可能なケースもある」一方で、多くの種は輸出入自体が厳しく制限されています。もう一つの誤解として「国内法だけで完結する」と思われがちですが、実際には国際的な合意を国内法を通じて実装しているため、両方を理解する必要があります。さらに研究・教育目的での使用や展示、教育機関の展示物など、用途ごとに必要な手続きが異なる点にも注意が必要です。
このような違いを知っておくと、学校の授業や研究での資料集め、海外の自然史博物館とのやりとり、さらには旅行先での野生動物観察にも役立ちます。
ある日、友人とカフェでワシントン条約の話題になった。条約は“禁止”の印象が強い人もいるが、実際には輸出入には許可が必要で、正しい手続きさえ踏めば研究や教育のための使用が認められるケースもある。僕は友人に、条約は世界全体で野生動物を守るための道具であり、国内の法はそれを現場で動かす“現実のルール”だと説明した。国際協力と国内実務の両輪で動く仕組みを理解することが、私たちが安全に学び、自然を観察し、保全活動に参加する第一歩になる。





















