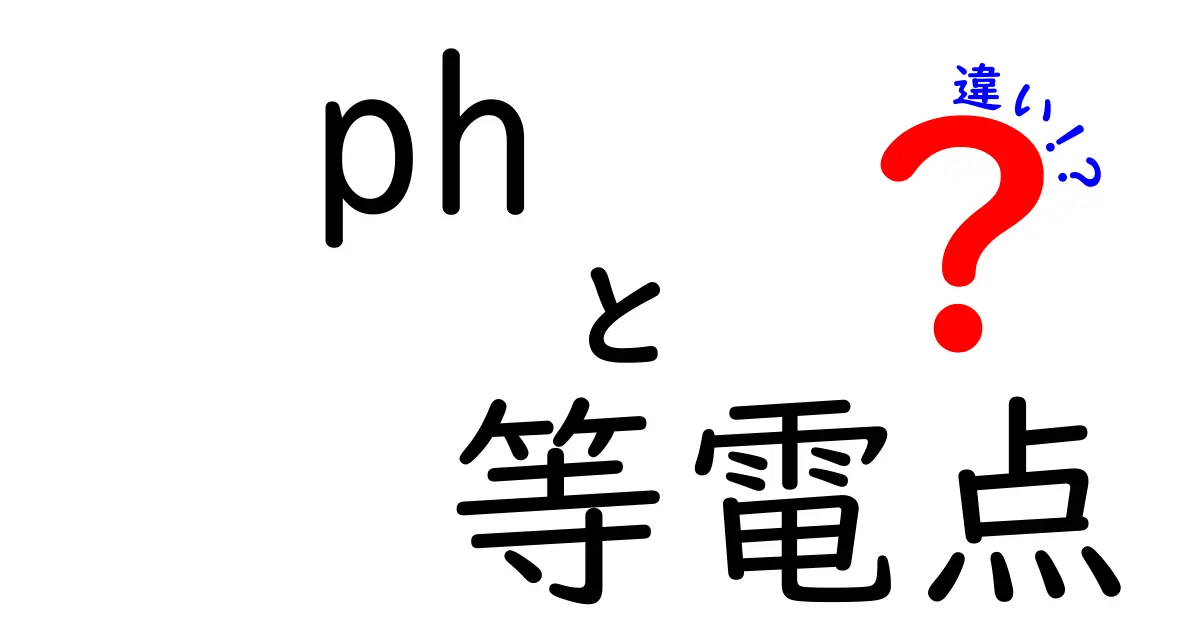

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに pHと等電点の基本を知ろう
pHとは水溶液の酸性度を表す数値です。水のように水素イオンが移動する世界では、0から14までのスケールで酸性とアルカリ性を区別します。0に近いほど強い酸性、14に近いほど強いアルカリ性、中性はおおむね7前後です。pHが小さくなるほど水素イオンが多くなり、味や匂い、色に変化が生まれます。pHは対数スケールなので、例え1単位変わるだけでも水素イオンの量は約10倍変わります。この感覚をつかむと、日常の料理や実験が楽しくなります。
一方等電点とは別の概念で、分子が荷電をもたずに中性の状態になるpHのことを指します。たとえばアミノ酸は酸性側と塩基性側の性質をもつ小さな分子で、pHが動くと正の電荷や負の電荷を帯びます。等電点では全体として荷電が0になるため、水に溶けにくくなることもあります。これを知っておくと、食品の加工やタンパク質の沈殿、薬の吸収の仕組みを理解しやすくなります。これらの違いを押さえることが、自然科学の学習や実験の第一歩です。
要点 pH は溶液の酸性度を示す指標、等電点は分子の荷電が0になる状態のpH、両方とも私たちの生活と密接に関わる重要な概念です。
pHと等電点の違いを具体例で理解する
ここでは身近な例を使って違いを整理します。pH は飲み物の酸性・アルカリ性を決め、味や保存性にも影響します。柑橘類の果汁はpHが低く、酸っぱく感じられますが、牛乳はpHが7近くで甘く感じることが多いです。対して等電点は分子そのものの性質に関係します。たとえばあるアミノ酸は体の中を通過する際に血液のpHと多くの条件が絡み、体内のタンパク質の形を決める大切な指標になります。体内の血液の通常のpHは約7.35〜7.45で、これが崩れると体の反応が乱れます。このように pH と等電点は別の現象を指していますが、溶液の挙動を理解するうえでどちらも不可欠です。次に、いくつかの身近な例で違いをさらに深掘りします。
表で整理すると、以下のような違いが頭に残りやすくなります。
このように pH と等電点は別の意味を持つ概念ですが、化学や生物の現象を読み解くためには両方を知っておくと理解が早くなります。次に、いくつかの身近な例で違いをさらに深掘りします。
実験室や厨房、学校の理科の授業では、pHメーターという器具で液体の酸性度を測定します。水道水はほぼ中性に近いpH 7ですが、柑橘類の果汁はpH が3〜4程度と低く、酸性が強いことがわかります。等電点は分子の荷電状態を決めるパラメータなので、同じ液体でも含まれるタンパク質の種類や温度によって変化します。例えばタンパク質が沈殿する条件はpH が等電点に近づくときが多いです。
身の回りの観察からヒントを探る
普段の生活の中にも pH と等電点のヒントは転がっています。発酵食品の塩分調整、野菜の漬物の色の変化、牛乳の酸化による風味の変化など、いずれも pH の変化が影響しています。一方で等電点を意識する場面としては、例えば自家製のタンパク質を含む食品を扱うときに、沈殿を起こさせたいときや、逆に溶かしたいときに pH を調整する技術が役立ちます。こうした考え方を、学習の中で実験デザインに取り入れると、科学の楽しさがぐっと深まります。
等電点という言葉を友だちと話すとき、私はこう説明します。等電点は分子が電荷をもたないちょうど良い pH の状態のこと。タンパク質は水の中で形を決める性質があり、pH が等電点に近づくと周りのイオンの影響で沈殿したり、溶け残ったりします。だから薬を体に吸収させたい時や、食品の沈殿を避けたい時には等電点を意識して pH を少し調整するのがコツです。学校の実験でも、等電点を起点に考えると、なぜ沈殿が生じるのか、なぜ溶けるのかが分かりやすくなります。
次の記事: l-ロイシンとロイシンの違いを徹底解説!知って得する摂取のコツ »





















