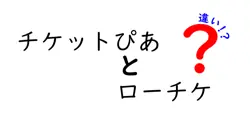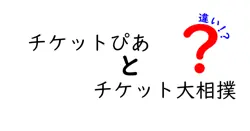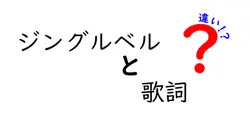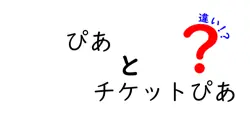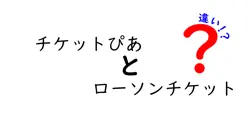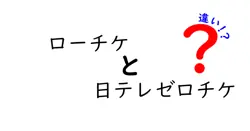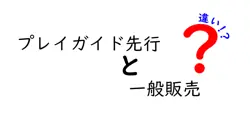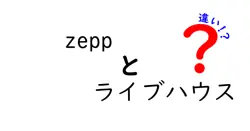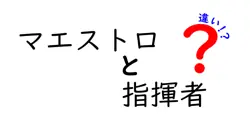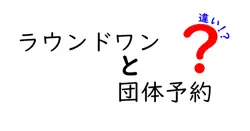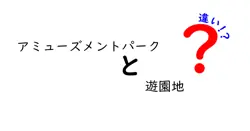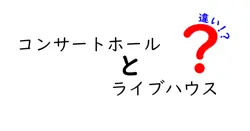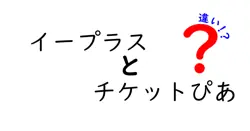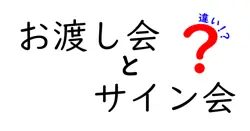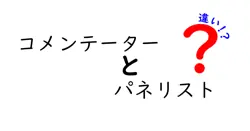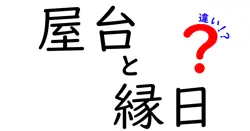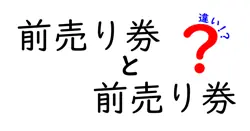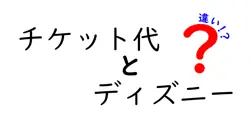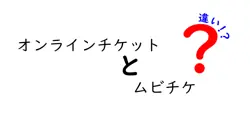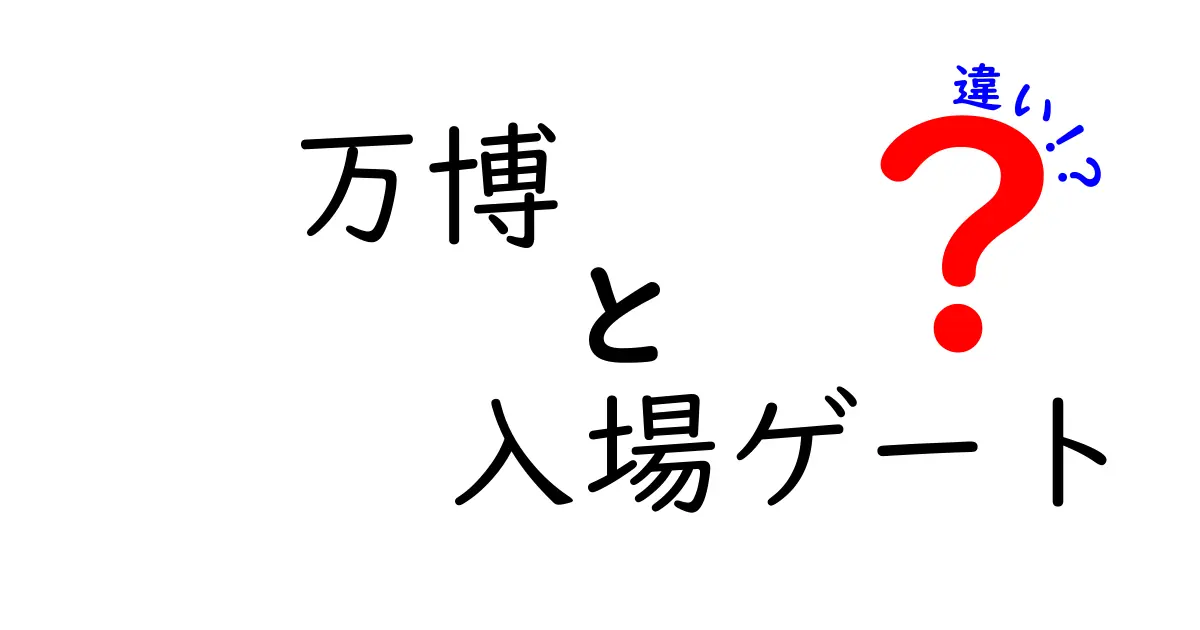

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
万博の入場ゲートの違いを知る完全ガイド
万博には、正門をはじめ北門・西門・東門・南門といった複数の入口が存在します。各ゲートには立地や動線の違いがあり、来場者の動き方に影響します。正門は会場の中心部に近づく入口で、初めて来る人にも分かりやすく案内板が多く設置されていますが、開場直後やパビリオンの新設イベントがある日には非常に長い列になることがあります。北門や西門は、特定のエリアへ直行するルートとして選ばれることが多く、展示エリアの端を目指すときに便利です。東門と南門は会場の端側に位置する場合があり、周囲の天気や日差しの影響を受けやすいことがあります。
また、セキュリティチェックの厳しさはほぼ同じですが、ゲートの混雑はその日の来場者数とイベントの配置によって左右されます。人が多いときは荷物検査や身分確認の時間が長くなることがあり、子ども連れや高齢の方が並ぶ場合は、少し時間に余裕を持つと安心です。ゲートを選ぶ際には、事前に公式サイトの地図や案内アプリで現在の混雑状況を確認するのが効果的です。場合によっては、チケットの受取場所や再入場の条件もゲートごとに異なることがあり、出入口の間違いが混乱を生まないよう前日までに確認しておくと良いです。
ゲート別の特徴と実用的な注意点
ゲートを選ぶときの基本は、訪問する日程と回るエリアの計画を先に作ることです。正門は案内板が豊富で初めての人にも優しい反面、時間帯によって列が長くなりやすいので、空きが出るタイミングを待つ余裕が必要です。北門は会場の北側へアクセスするルートとして便利で、午前中の混雑を避けたい場合に有利です。西門と東門は、特定のパビリオン群へ直行するのに適しています。南門は会場のイベント広場に近いことが多く、イベントの出入り口として使われることがあります。
実用のコツとしては、訪問前にアプリで待ち時間を確認し、空いているゲートを選ぶこと、天気が悪い日には日陰が多いゲートを選ぶこと、ベビー(関連記事:子育てはアマゾンに任せよ!アマゾンのらくらくベビーとは?その便利すぎる使い方)カーや車椅子を使う人がいる場合はバリアフリー設備のあるゲートを確認することが挙げられます。さらに、会場の動線を把握するための事前の地図確認と、入場後の移動ルートを決めた上で歩くペースを揃えると、混雑の中でも迷わず回れます。
実際の入場手順とゲート選びのコツ
入場の基本的な流れは、チケットをスマホ画面で提示するか紙のチケットを見せることから始まります。その後、セキュリティチェックを受けてゲートを通過します。ここで大切なのは、出入口を事前に絞っておくことです。目的地が決まっている場合は、そのエリアに最も近いゲートを選んだ方が移動距離を短く抑えられます。公式アプリを使うと現在の混雑状況やゲート周辺の案内板の位置が分かるので、待ち時間を減らすのに役立ちます。入場後は会場地図を使って効率的に回るルートを作ると、歩く距離と疲労が減ります。写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)スポットは混雑が激しくなる前後で混雑を避けるのがコツです。表の情報は、各ゲートの距離感や特徴をまとめたものなので、実際には出発前にチェックしておくのがおすすめです。
<table>友達と万博のゲートの話をしていた日、私はゲートをどう選ぶかがその日の体験を左右すると気づきました。正門の分かりやすさと混雑の長さ、北門のエリア直通の便利さ、西門や東門の特定エリア直行、南門のイベント寄りの動線など、それぞれの長所と短所を知ると、出発前に最適なゲートを選ぶ判断材料になります。私は計画を立てるとき、地図アプリの待ち時間表示と、家族構成に合わせたゲート選択をセットで考える癖を持つようにしました。ゲート選びは遊園地の入場口を選ぶ感覚に近く、適切なゲートを選ぶと歩く距離が減り、疲れも少なく、最後まで楽しく回ることができます。
前の記事: « 自己意識と自己概念の違いを徹底解説|自分を理解する第一歩
次の記事: ismsとPマークの違いを徹底解説|中学生にもわかる比較ガイド »