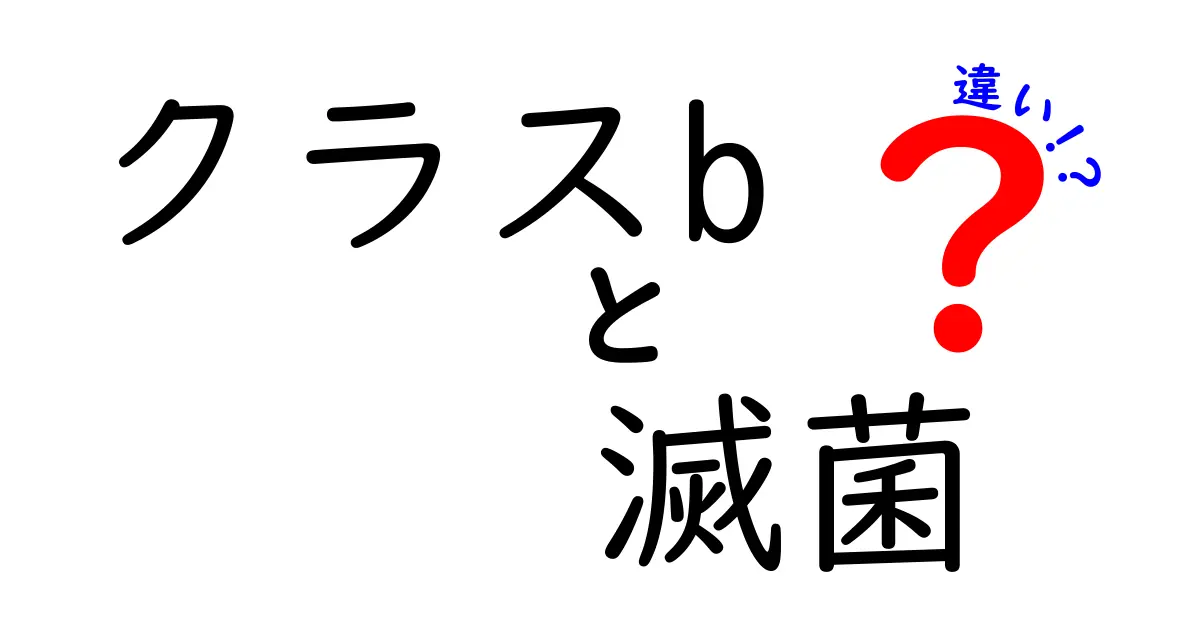

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
クラスB滅菌とは何か?基本の仕組みと目的
クラスB滅菌は、病院や歯科、研究機関で使われる滅菌サイクルのひとつです。滅菌とは、器具や材料に付着している微生物を完全に死滅させ、病原性をなくすことを意味します。
クラスBは、内部に空気が残っていると蒸気が奥まで届かず、滅菌が不十分になる可能性があるという考えのもと、特別な空気排除のプロセスを取り入れています。
この空気排除には動的エアリムーブと呼ばれる前処理が含まれ、機器の内部の空気を積極的に外へ出します。これに続いて蒸気が包摂的に器具全体へ浸透するよう、所定の温度と時間を維持します。最後には高温の蒸気を連続して循環させ、結露を防ぎつつ干燥を行います。
この一連の流れを適切に実施することで、包装材の中に入った複雑な形状の器具でも隅々まで滅菌でき、「滅菌済み」のラベルが付くことが多くなります。
少し専門的に言えば、クラスBはEN 13060やISO 17665に適合することを前提とする設計思想を持ち、前処理・蒸気・乾燥の三段階を連携させる点が特徴です。
このため、在宅や学校の実習では使わず、適切な教育と訓練を受けた施設で採用されることが多いのです。
クラスBの目的は、複雑な器具を含む「全体の滅菌を確実にする」ことにあり、陽性の信頼性を最大化することにあります。
クラスBの特徴と他の滅菌方式との違い
他の滅菌方式と比べると、クラスBにはいくつかの大きな特徴があります。
まずエアリムーブという概念が核心で、前処理の段階で機器内部の空気を積極的に除去します。これにより、内部の長尺の器具や内腔部まで蒸気が届きやすくなり、滅菌の信頼性が高まります。
次に、クラスBは通常、前真空・蒸気・乾燥を組み合わせたサイクルで動作します。これに対して、クラスNは比較的単純な蒸気充填による静的なサイクルで、空気が残りやすい領域の滅菌には適していません。
またクラスSは荷重の種類や大きさに一定の制限があり、短時間の滅菌サイクルを前提にしています。つまり、複雑な器具や大きな荷重、内部の空洞がある場合には、クラスBの方が適していると判断されるのが通常です。さらに、実務的には検証やバリデーション、Bowie-Dickテストの実施が求められ、毎回の点検が欠かせません。
実務での使い方と選び方のポイント
実務でクラスBを選ぶときには、荷物のタイプと量、器具の形状、包装状態を最初に考えます。まず内腔のある器具や長さのある器具を滅菌する場合、クラスBの前処理と乾燥の能力が有効です。次に、病院や診療所の運用時間と人員、コストのバランスを検討します。通常、クラスBは機材の導入費用と運用コストが高い分、滅菌の信頼性が高く、検証・教育を受けたスタッフが適切に運用することが前提です。
また、バリデーションは必要ですが、ここでは検証と適合性確認の手順を日々の運用の中で組み込むことが大切です。現場では、Bowie-Dickテストを日次で実施し、滅菌サイクルが規定の条件下で動作しているかを確認します。さらに、荷重の配置にも気を付けます。荷物は蒸気の流れを妨げないよう、互いに重ねず、空間を開けて配置します。これにより乾燥も均一になり、荷重の一部だけが過剰に乾燥してしまうことを防ぐことができます。
最後に、定期的なメンテナンスと点検、ログの保管を徹底することが、長期的な滅菌品質の安定につながります。
よくある質問と誤解
よくある質問と誤解を解くコツを簡潔にまとめておきます。
Q1: クラスBは全ての荷物に適用できますか?
A1: 内腔がある器具や長尺の器具でも対応しますが、特定の包装規格やサイズ制限があり、荷重の形状によってはクラスNやクラスSの適用が適切な場合もあります。
Q2: 使用コストは高いですか?
A2: 導入費用・運用費は高い傾向にありますが、滅菌品質の向上とトレーサビリティの確保を考慮すると長期的には費用対効果が高くなります。
Q3: 学ぶべきポイントは?
A3: Bowie-Dickテストの理解と日常の点検・記録の習慣化です。日々の運用で安定した滅菌を保つコツは、適正な荷重配置と適切な乾燥時間の管理にあります。
ある日の実験室で、友達とクラスB滅菌の現場の話をしていた。エア抜きの話題になると、彼は『空気が残っていると蒸気が中まで届かないんだよね?』とつぶやく。私は『そう、エア抜きは滅菌の命綱みたいなもの。前処理で空気を押し出しておくと、複雑な器具でも蒸気が均一に回る。だからBは難しい器具にも適しているんだ』と答えた。彼は『じゃあ、NやSとはどう違うの?』と聞き、私は簡単に説明した。Nは静的で、Sは荷重によって制限がある。つまり、内部構造が複雑な器具ほどBが有利になる場面が多い。こうして私たちは、滅菌の「仕組み」と「現場の現実」を結びつける学習が進んだ。
次の記事: 殺菌と滅菌の違いを中学生にもわかるように解説!どちらを使うべき? »





















