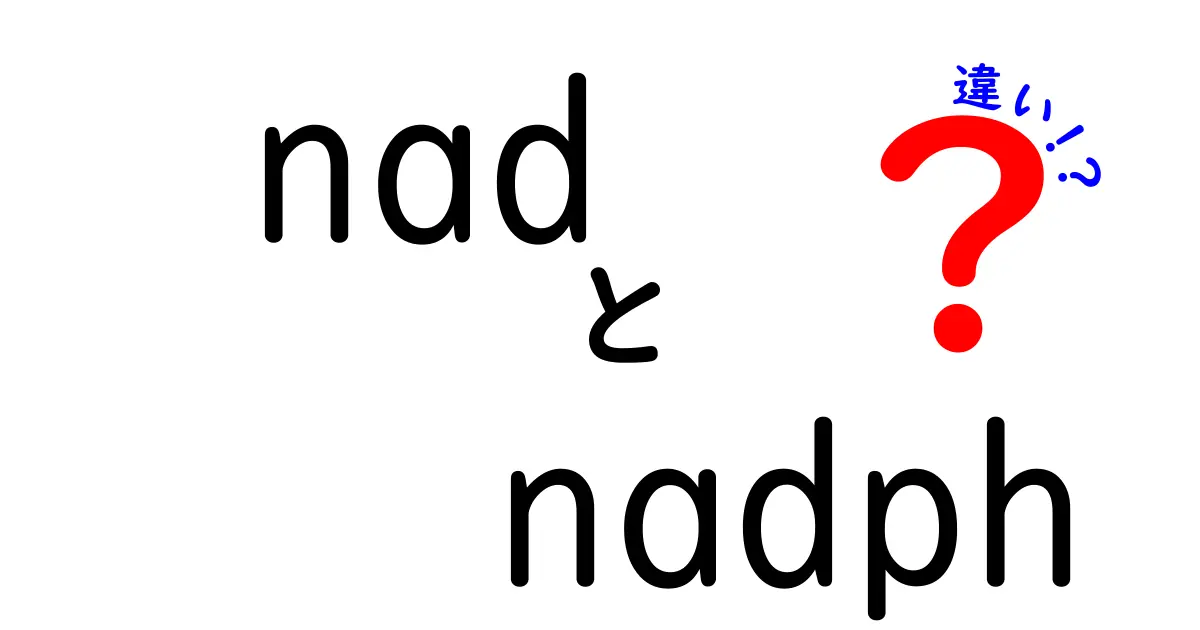

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
nadとnadphの違いを理解する基本ガイド
このガイドでは NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドの略)と NADPH の違いを、体の中の電子の流れという視点から、中学生にも理解しやすい言葉で解説します。まず基本のポイントは二つです。第一に NAD+ は酸化反応で電子を受け渡す“受け取り役”として働き、電子を受け取ると NADH に変わり、これが酸素を水へと変える過程へとつながり、最終的には ATP という形でエネルギーを生み出します。第二に NADP+ は NADPH をつくる“準備段階”として働き、NADPH が誕生すると、体の中で還元力を発揮して生体の合成反応を進めたり、抗酸化防御を支えたりします。これらは別々の経路で使われ、同じ「赤ox反応」を使う分子でも、使われ方が違います。つまり NAD+ 系は主にエネルギーを作り出す側、NADPH 系は生体を作ったり守ったりする側と覚えると理解が進みやすいでしょう。さらに重要なのは、これらが細胞の中で働く場所が必ずしも同じではないことです。NAD+ の形は主に細胞のミトコンドリアや細胞質に存在しますが、NADPH は脂質合成が行われる場所や抗酸化反応が起きる場所で活発に働くことが多いのです。こうした背景を知ると、なぜ同じように見える二つの分子が異なる役割を担うのかが分かってきます。最後に、授業の中で私たちがよく使う覚え方のコツをひとつ挙げるとすれば、NAD+ 系は“エネルギーの走者”、NADPH 系は“合成と守りの力”と覚えることです。これだけを押さえれば、以後の代謝の話にもスムーズにつながります。
NADとNADPの基本的な違い
ここでは NAD+ / NADH / NADP+ / NADPH の基本的な違いを整理します。まず NAD+ は酸化形、NADH は還元形、いずれも電子を運ぶ「赤ox反応の携帯役」です。NADP+ は NAD+ のリン酸化形で、NADPH を作る準備段階として働き、NADPH は還元力を強く持つ物質です。つまり、どこで使われるか、どの反応に関わるかで役割が分かれます。NAD+ 系は主にエネルギーを作り出す場面に関与し、糖や脂肪を分解して ATP を作る過程で電子を受け取り NADH に変わります。NADPH 系は脂質の合成、核酸の修復、抗酸化反応など、体を作ったり守ったりする反応で使われます。覚えるコツは「NAD+ 系=エネルギー生産」「NADPH 系=生合成と防御」という大枠に分けて考えることです。さらに臓器ごとの違いや、実際の反応パターンを知ると理解が深まります。
具体的な使い分けの例と表
代謝の現場での使い分けを具体的な例で説明します。まず解糖系とミトコンドリア内呼吸では NAD+ が受け取った電子を NADH に変え、最終的に酸素と結びつけて水と ATP を作ります。これが“エネルギーを作るライン”です。一方で脂肪酸の合成やコレステロールの生成、DNA の修復、グルタチオン還元などの反応には NADPH が必要です。これらは還元力を提供して、分子を“還元”することで化学的性質を変え、物質を作り直します。表を見れば、どの反応にどちらが使われるのかが一目で分かります。以下は超入門版の表です。なお、現実の生体ではこれらが同時に複雑に動くため、簡単なイメージとして覚えておくと良いでしょう。
<table>日常生活への影響と覚え方
NAD と NADPH の違いを知ることは、私たちが授業や実験で見かける“体の中の力の源泉”を理解する第一歩です。例えば運動中のエネルギー生成、健康的な食事の中でのビタミンB群の役割、体内の酸化ストレスへの対応など、NAD/NADPH は見えないところで活躍しています。覚え方のコツとしては、NAD+ 系を“エネルギーの走者”、NADPH 系を“合成と守りの力”と覚えると、機能の違いがつかみやすいです。中学生の皆さんが日常生活の中でこの言葉を見かける場面は、スポーツのエネルギー出力の話、栄養の話、化学の還元反応の話のいずれかです。私たちはこの2つの分子を同時に意識することで、体が「どうしてこの動作ができるのか」「どうしてこの反応が起こるのか」をより深く理解できるようになります。最後に、学校の授業ノートに NAD/NADPH の図を描いてみてください。矢印を使って NAD+ から NADH、NADP+ から NADPH、そしてそれぞれの反応の要点をメモしておくと、受験や実験のときにも役立ちます。
ねえ、NADって体の中の小さな電車の切符みたいなものだと思わない?NAD+ は電子を受け取って NADH になって、その電車はミトコンドリアの方へ走って ATP を運んでいくんだ。NADPH は別の路線で、脂肪を作るときの還元力や体を守る抗酸化の武器になる。だから NAD+ 系がエネルギーを作る走者、NADPH 系が体を作る際の力の源になるんだって。こう聞くと、体の中でどうしてこの二つが違う役割を果たしているかが分かってくると思う。友達にもそんな話をしてみると、きっと「へえ、そうなんだ」と驚くはずだよ。





















