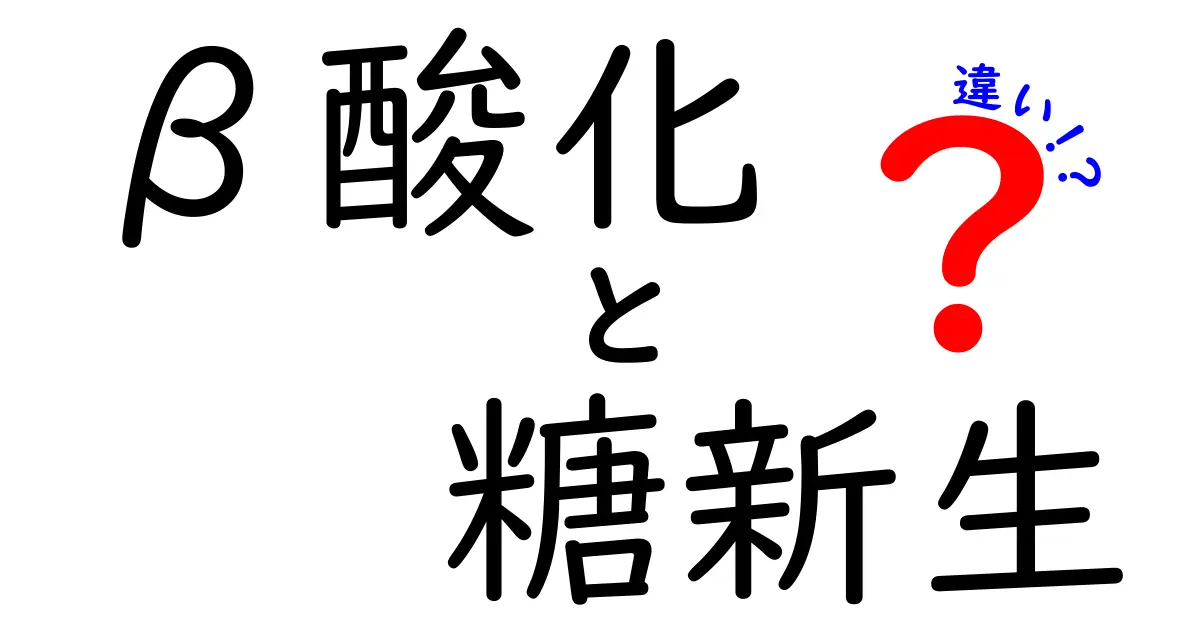

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
β酸化と糖新生の違いを理解するための基礎
長い時間の運動や空腹のとき、体は「エネルギー」をどう作っているのかを考えます。現代の私たちは普段パンやごはんなどの炭水化物を食べていますが、時にはそれだけでは足りません。そこで体は脂肪の中に隠れたエネルギーを取り出して使います。ここで登場するのがβ酸化と糖新生です。β酸化は脂肪酸を細胞の中で少しずつ切り分け、最終的にはアセチルCoAという小さな分子を作り出す作業です。この過程は主にミトコンドリアと呼ばれる細胞の中の工場で進み、最終的にクレブス回路へとつながる材料を作ります。脂肪から得られるエネルギーは糖質と比べて「長い間貯蔵され、長時間かけて燃える」特徴があります。だから、長く動くスポーツや断続的な運動のときにはとても大切です。
一方で糖新生は、糖質が十分にあるときにはあまり必要ありませんが、食事が足りないときや激しい運動をしているときには血糖値を保つために働きます。糖新生は肝臓や腎臓で行われ、乳酸やアミノ酸、グリセロールなどの材料から新しいグルコースを作ります。作られたグルコースは血液に放出され、体の各部位が必要とする糖を供給します。このようにβ酸化と糖新生は、体のエネルギー戦略の中で「脂肪を燃やす」「血糖をつくる」という2つの役割を担い、互いに状況に応じて使い分けるのです。
ここで覚えるべきポイントをいくつか挙げます。まず β酸化は脂肪を分解してエネルギーの元になるアセチルCoAを作る作業であり、場所は主に ミトコンドリアです。次に 糖新生は血糖を保つために新しいグルコースを作る作業で、材料には 乳酸・アミノ酸・グリセロール などが使われ、主に 肝臓 と 腎臓 で進みます。これらは私たちが眠っている間やご飯を食べていない時間でも、体が動けるようにサポートしてくれる重要な仕組みです。
- β酸化は脂肪をエネルギーへ変える作業
- 糖新生は不足時に血糖を作る作業
- 場所の違い:β酸化はミトコンドリア、糖新生は肝臓・腎臓
- 主な材料:脂肪酸、乳酸・アミノ酸・グリセロール
β酸化とは何か、糖新生とは何か、そしてどう違うのか
二つの仕組みを比較すると、体が「どうやってエネルギーを作るか」という戦い方が見えてきます。β酸化は脂肪酸を分解してエネルギーの元になるアセチルCoAを次々に作り出します。この過程で放出される電子は電子伝達系に運ばれ、ATP という形で私たちの筋肉や脳の働きを支えます。β酸化は主にミトコンドリアの内部で進み、脂肪酸が細いリンクを順番に外されていく様子をイメージすると分かりやすいです。反対に糖新生は血糖値を安定させるために新しいグルコースを作る作業です。材料は乳酸・アミノ酸・グリセロールなどで、肝臓と腎臓が主な現場になります。糖新生が活発になるのは、夜寝ているときや長時間の断食など、体が糖を節約したいときです。こうした時、脳に必要な糖を確保するため、体は糖新生を優先します。
特徴の違いを覚えるコツは、二つをセットで考えることです。β酸化は脂肪をエネルギーへ変える作業、糖新生は不足時に糖を作る作業、この二つの役割が同時に働く場面は少なくありません。さらに、場所の違いとしてはβ酸化はミトコンドリア、糖新生は肝臓と腎臓が主役です。こうして体の中の“時間軸”と“場所”を意識すると、難しい用語も自然に結びついていきます。中学生のみなさんは、実験のグラフを思い浮かべながらこの二つを見比べてみるといいでしょう。
友だちとの雑談風に話すとき、私はこう説明します。β酸化は脂肪を燃やすお仕事、つまり脂肪酸を一本ずつ切ってアセチルCoAに変える作業です。細胞の中のミトコンドリアで静かに進み、たくさんの小さな分子が集まるとクレブス回路へ行ってエネルギーATPを作ります。糖新生はその対角線のような役割で、糖質が不足したときに肝臓などで新しいグルコースを作り出します。二つは別の道だけど、空腹時にはどちらも体の命を守る大切な仕組みです。





















