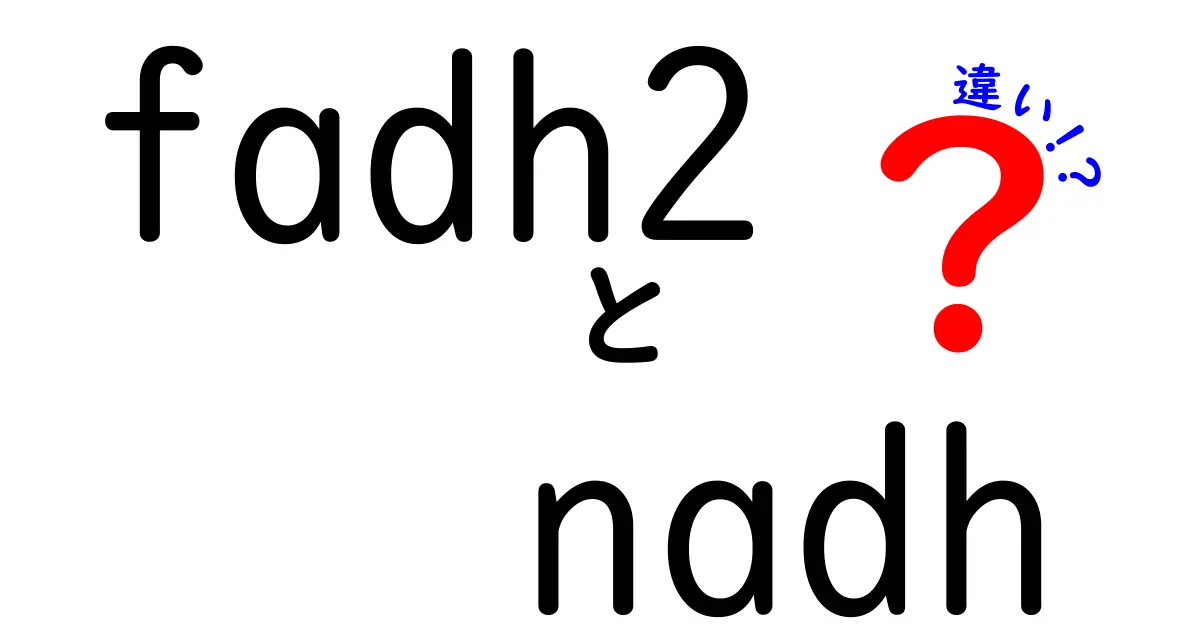

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:fadh2とnadhの基本を知ろう
FADH2とNADHは、体の中でエネルギーを作る過程で重要な分子です。どちらも「還元型の補酵素」と呼ばれ、電子を受け取って別の場所へ渡す役割を持っています。ここでの大事なポイントは、これらが「電子の運び手」であり、最終的にはATPというエネルギーの形に変換される点です。ATPは私たちの体を動かす原動力であり、呼吸、筋肉の収縮、細胞の修復など、さまざまな生命活動に使われています。では、なぜこの2つの分子が区別されるのでしょうか?その答えは主に「電子を受け取るタイミングと運ぶ距離」「電子を受け取る部位の違い」「発生するエネルギーの違い」にあります。これから具体的に見ていきましょう。
最初に覚えておきたいのは、NADHとFADH2は同じ「電子を運ぶ役目」を持つが、受け取る電子の性質や使われる場所によって役割が少し異なるということです。体内には解糖系、クエン酸回路、電子伝達系と呼ばれる一連の反応があり、NADHとFADH2はそれぞれの段階で電子を受け渡します。この過程で、私たちの体は水と二酸化炭素を作り出し、同時に大量のATPを作るのです。ここでは、中学生にも分かるように、実際にどんな場面で両者が活躍するのかを、日常の例えを使って丁寧に説明します。
さらに、NADHとFADH2の「数の多さ」も話題になります。私たちが運動をして筋肉を使えば、エネルギーを作る回路は活発に動き始めます。するとNADHが増え、電子伝達系を経由してATPが大量に生産されます。一方でFADH2はNADHよりも少し低いエネルギーを伝える性質があり、その結果、同じ時間で作れるATPの量にも差が出ます。このような差は、私たちが日常生活で感じる疲れの感じ方や、スポーツをしたときの体の動き方にも影響します。ここでは、NADHとFADH2の特性の違いが、身体の中でどのように結びついてエネルギーを作り出すのかを、具体的な例を交えて解説します。
電子伝達系での役割を比較する
NADHは一度に多くの電子を渡すことができ、その結果として電子伝達チェーンの第1複合体などを強く刺激します。これにより、プロトンのポテンシャル差が大きくなり、ATP合成の効率が高まる場面が出てきます。FADH2はNADHよりも少ないエネルギーを渡すことが多く、主に二次的なルートを支える役割を果たします。つまり、NADHが先頭を走って体のエネルギーを大きく引き出す場面が多い一方で、FADH2は補助的に働く場面が多いと覚えておくと理解が進みます。ここで重要なのは、この違いが「どの段階で作られるか」「どの酵素が関わるか」によって決まるという点です。
NADHは解糖系やクエン酸回路で主役を務め、電子伝達系では多数の電子を渡します。FADH2は脂肪酸分解など別の経路で生成され、NADHよりも少ないエネルギーを持って渡します。この差が、ATPの総生産量に影響するのです。表を使って簡単に比較してみましょう。
<table>表のとおり、NADHとFADH2には「どこで生まれ、どのくらいの力を持って電子を運ぶか」という違いがあります。これらの違いを理解すると、体のエネルギー作りの仕組みが見えてきます。視点を変えると、NADHとFADH2は別々の道を歩みつつも、最終的に同じ目的地であるATPの生成に貢献している点がとても面白いです。普段の生活の中で「疲れやすさ」や「筋肉の動き方」を感じるとき、もしかするとこの二つの補酵素の働き方の差が影響しているかもしれません。これを知ることで、体がどのようにエネルギーを作っているのかが身近に感じられるはずです。
この章のまとめとして、NADHとFADH2の違いは単なる用語の違いではなく、私たちの体がどの経路を使ってエネルギーを生み出すかを決定づける大切な要素だと覚えておきましょう。これを理解すると、スポーツのときの体の動き、休憩中の疲労感、さらには食事の影響まで、日常のあらゆる場面が少しずつ見えてきます。
ある日の理科室の雑談を思い浮かべてみて。友達がNADHとFADH2の話をしていて、私はふと「じゃあNADHってどんな場面で働くの?」と質問した。友達はニコニコしながら「解糖系とクエン酸回路の主役だよ。ここでたくさんの電子を受け取って、次の段階に渡すんだ」と答えた。すると別の友達が「でもFADH2は? NADHより少しエネルギーを渡す感じだよね」と続ける。私は「つまりNADHが先頭で大きな力を出す場面が多く、FADH2はそれを補助する役割を担うことが多いんだ」と理解する。話は続き、教科書には出てこないけれど身の回りの痕跡、例えば運動後の疲れ具合や体の温まり方にもこれらの調整が関係しているのかもしれない、という結論に至った。こうした会話を通じて、NADHとFADH2は別々の道を進みつつ、最終的にATPという体のエネルギーになる道に合流する、そんな日常の“科学の小さなドラマ”を感じ取れるのが楽しいんだ。>





















