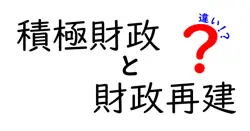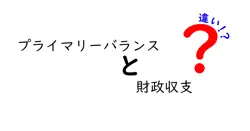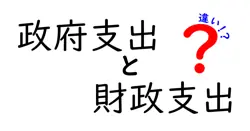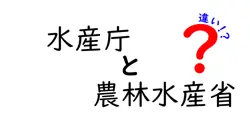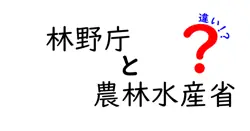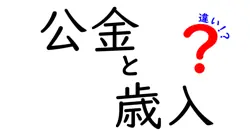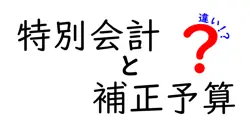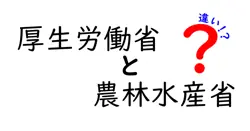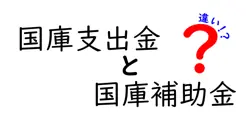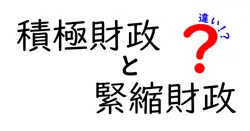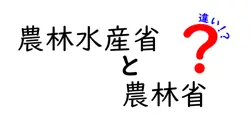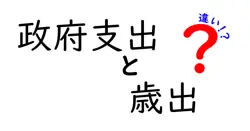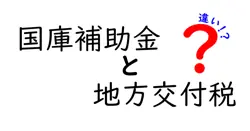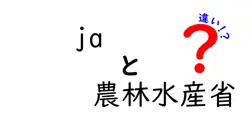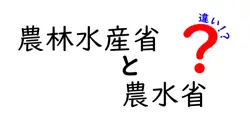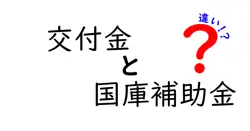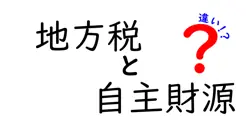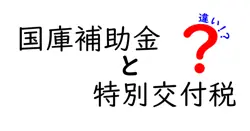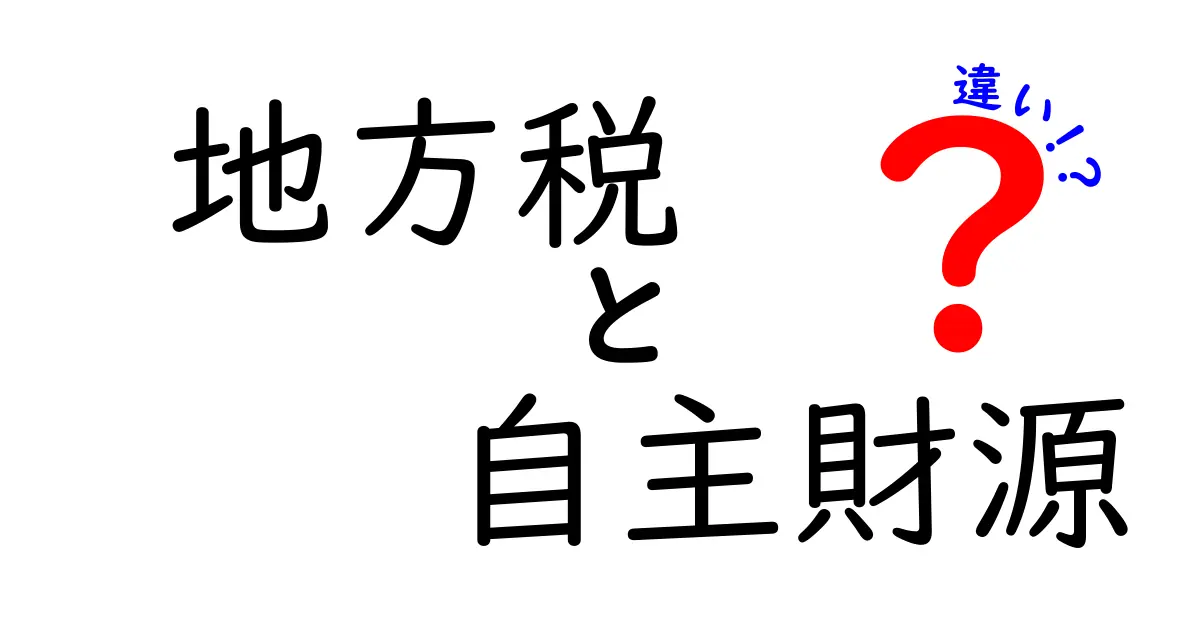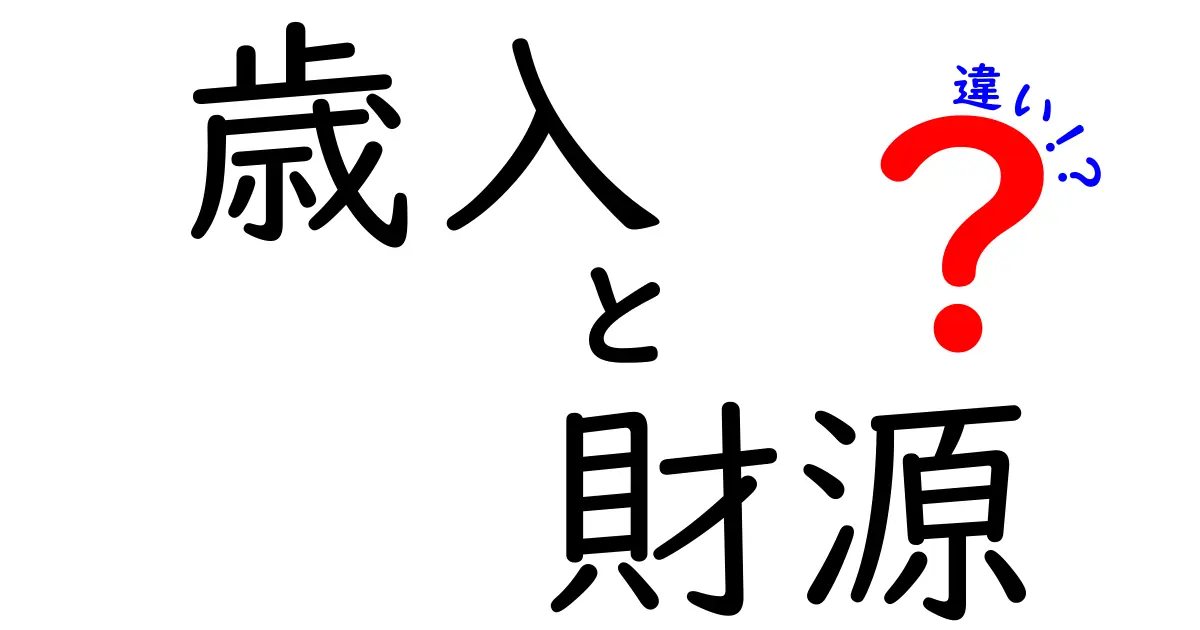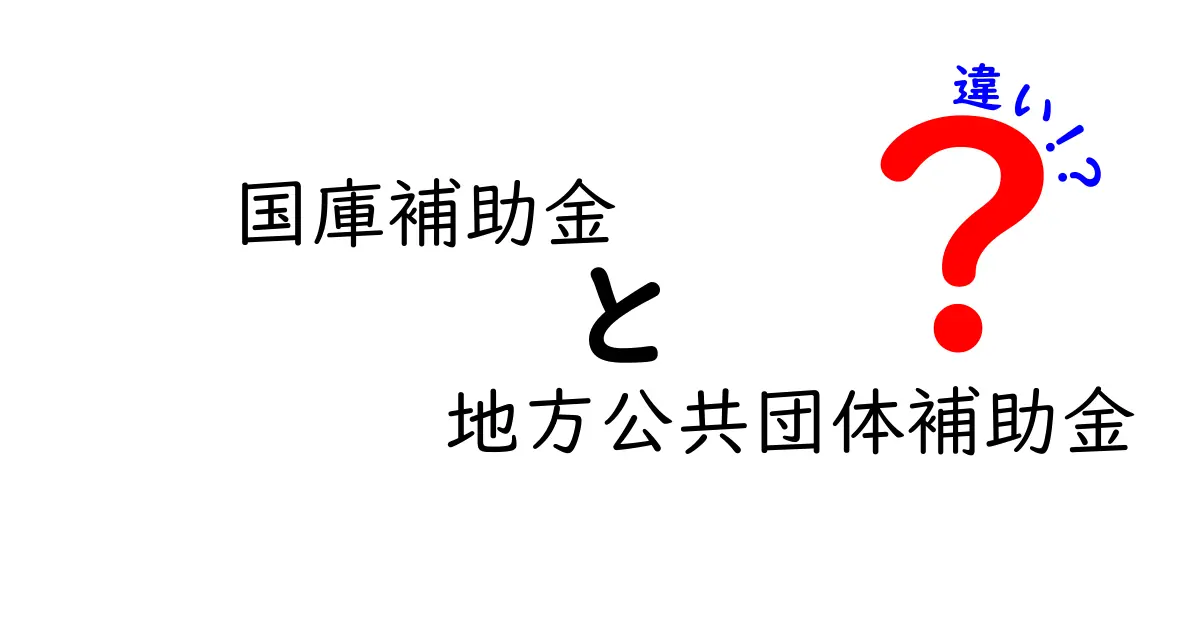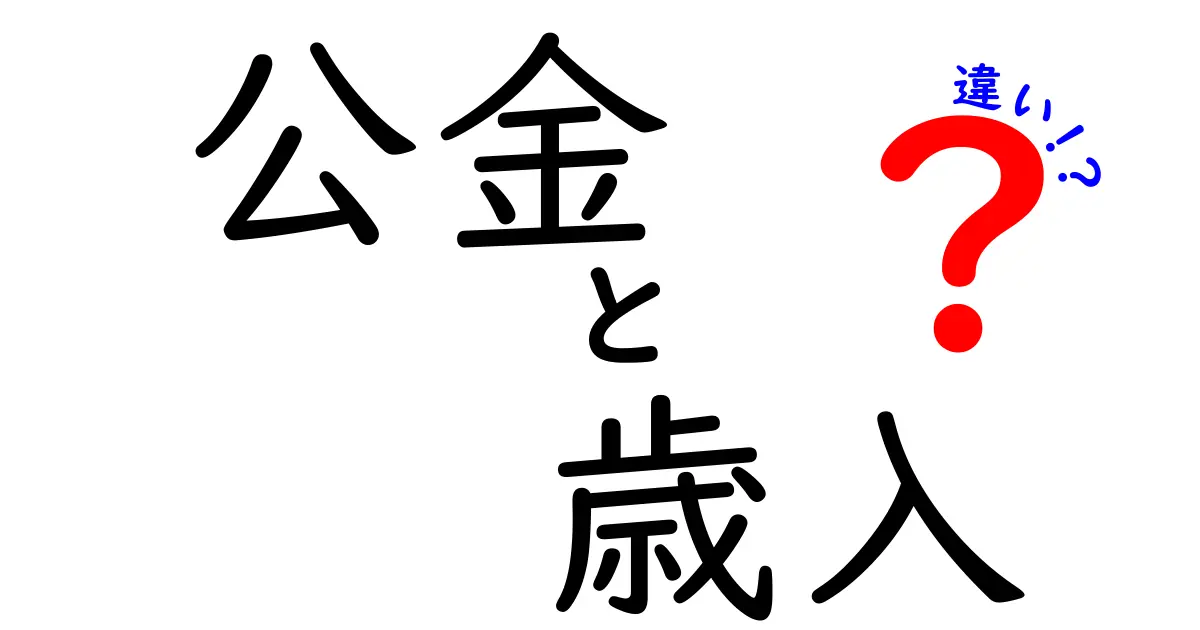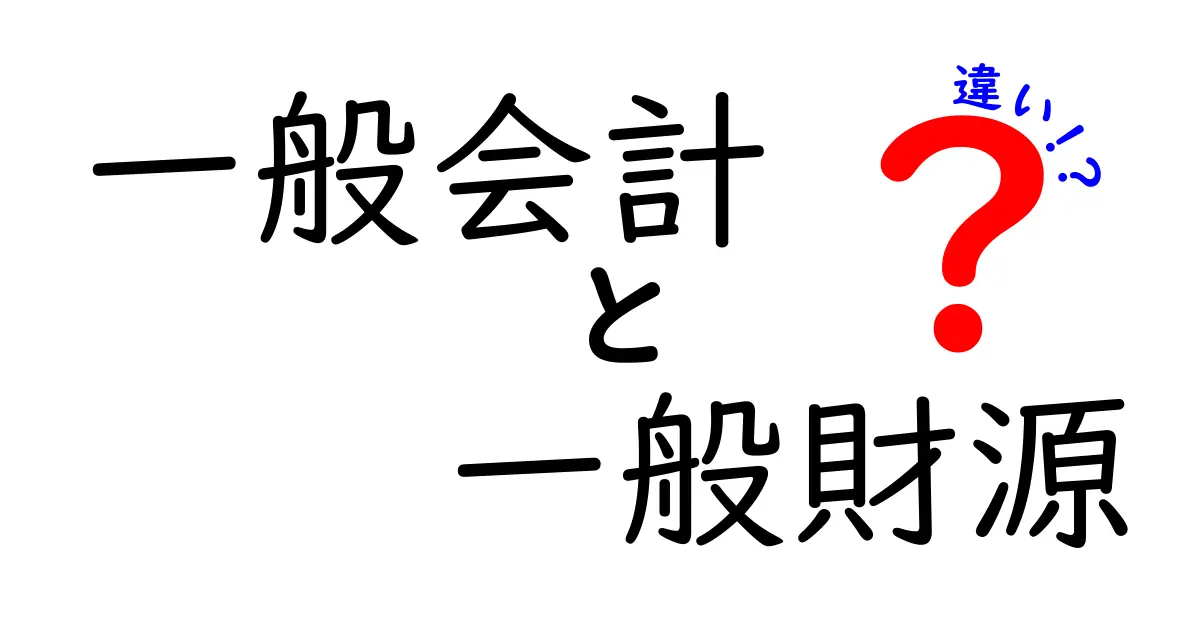

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:一般会計と一般財源の基本を押さえる
ここでは、一般会計と一般財源の違いを初心者にもわかるように丁寧に解説します。まず、一般会計とは、国や自治体の予算の中核をなす会計区分で、日々の行政サービスの支出を広くカバーする大枠の財政枠組みです。
これに対して、一般財源は財源の性質を表す用語であり、使い道の自由度が高い資金を指すことが多いです。
通常、一般財源には、自由に使える資金と、特定の目的に使うことが求められる資金が混ざっていることがあります。
そして、一般会計はこの財源をどう配分し、どの費目にどれだけの支出を割り当てるかを決める会計の枠組みそのものです。
つまり、一般会計と一般財源は表面的には別の概念ですが、実務では切っても切り離せない関係にあります。
ポイントとしては、(1)一般会計は予算編成の土台、(2)一般財源は使い道の自由度の度合いを示す財源のこと、という基本を押さえることです。
違いを整理する4つのポイント
この4つのポイントで違いを見える化します。
1. 目的と使い道 一般会計は行政サービス全体の予算枠であり、教育や道路整備など多くの費目を含みます。一般財源は資金の性質を示し、使い道が自由になる資金と使途が厳しく縛られる資金が混在していることがあります。
2. 財源の自由度 一般財源は使える範囲が広くても一定の制約はあります。一般会計はこうした財源を組み合わせて構成され、財源の性格に応じて新たな支出の優先順位が決まります。
3. 会計の統合と分離 一般会計は全体の会計の中心であり、他の会計区分と連携して予算を管理します。一般財源はこの中心の中で配分の司令塔の役割を果たしますが、別個の資金源としての性質を持つことがあります。
4. 実務上の取り扱い 実務では一般財源の使い道を超えて新規の支出を計画する際、一般会計の枠組みの中で改変が生じます。これらの調整は透明性と説明責任の観点から重要です。
財源と会計の区分の具体例
たとえば町をイメージしましょう。町の運転資金の大半を占める一般会計は、教育費や道路の整備費、公園の管理費など日常的に発生する支出を広くカバーします。これに対して一般財源として考えられるのは、地域振興の特定財源のように、使い道があらかじめ定められている資金のことです。一方で、一般財源には自由度が高い資金も含まれますが、使途が限定される場合が多く、更新費用や長期的プロジェクトには追加の承認が必要となるケースが多いです。こうした区分を理解しておくと、税金の使い道を説明するときや、誰がどの資金を使えるのかを説明するときに役立ちます。
自治体の予算で見る実例
例えばある自治体が新しい学校の建設を計画するとき、建設費の大半を一般会計の予算で賄うことが多いです。ここでの資金の性質は、使途が広く、複数の費目にまたがる作業を含みます。もしこの自治体が特定財源を使って建設を進める場合、財源の性格上、教育費用や施設の維持費用といったカテゴリに限定され、他の分野へ資金を転用することは難しくなります。実務ではこのような差を正しく理解し、適切な部門間の調整を行うことが求められます。
見やすい比較表
以下の表は一般会計と一般財源の違いを視覚的に比べるためのものです。項目ごとに意味や特徴を整理し、混同を避けるのに役立ちます。なお、現実の予算では自治体や国の制度ごとに表現や区分名が異なることがありますが、基本的な考え方は同じです。公的な文章では数字に加え根拠の説明も重要ですが、ここでは概念の比較に焦点を当てています。さらなる理解のためには、実際の予算資料を参照することをおすすめします。
<table>まとめとポイント
この解説の要点をまとめると、一般会計は日々の行政サービスの予算枠組みであり、一般財源は使途の自由度を含む資金の性質を示す概念だということです。違いを正しく理解することで、予算の組み方や財源の使い方を説明する際に混乱が生じにくくなります。中学生のあなたにもできるように噛み砕くと、こうなります。まずは財源の自由度の有無をチェックし、次にその資金がどの費目に使えるのかを確認します。最後に全体の予算のバランスと透明性を意識して、誰が何の目的で予算を動かしているのかを把握する。これらの視点がそろえば、一般会計と一般財源の違いはぐっと身近なものになります。
今日は一般会計と一般財源の違いを雑談風に深掘りします。町の公園を例にとると、一般会計は公園の運営全体の予算を見渡す枠組みです。ここには清掃スタッフの給料、花壇の維持、イベントの費用などが含まれます。一方で一般財源は資金の出どころの話で、自由に使えるお金が入っている場合もあれば、特定のプロジェクトだけに使えるお金が入っている場合もあります。資金の自由度が高いほど、使途を決める際の説明責任も増します。現場では、複数の財源を組み合わせて一つの事業を進めるときに、どの資金をどの費目に使うべきか、誰が決定するのか、そしてどんな報告が必要かという話題が自然と出てきます。こうした会話を通じて、難しい制度の話を現実の感覚に近づけていくのがコツです。最終的には、二つの概念は対立するものではなく、公共サービスを支える二つの側面として連携して動くという点を覚えておくとよいでしょう。