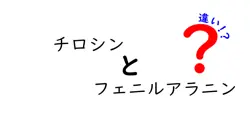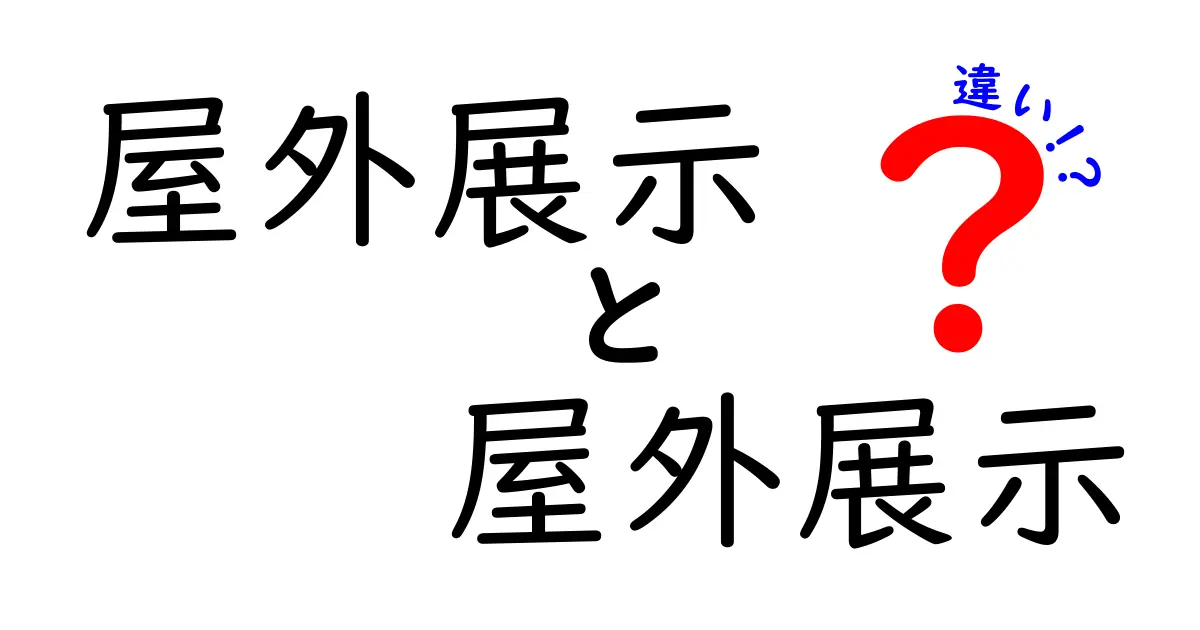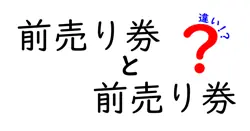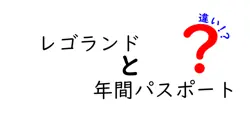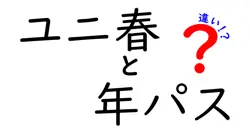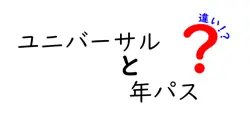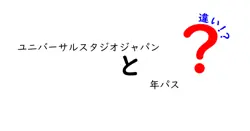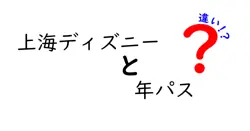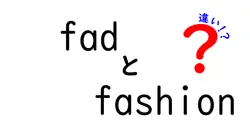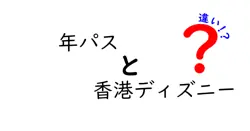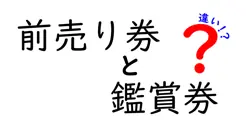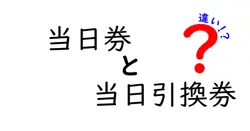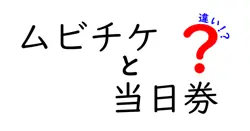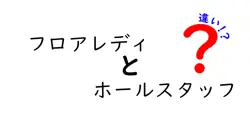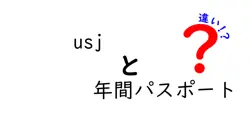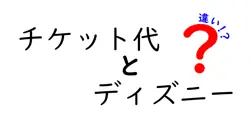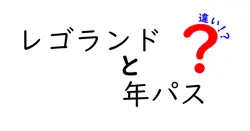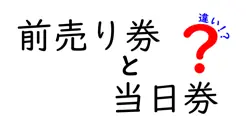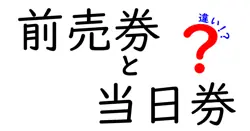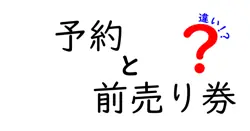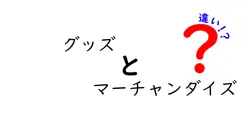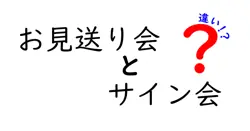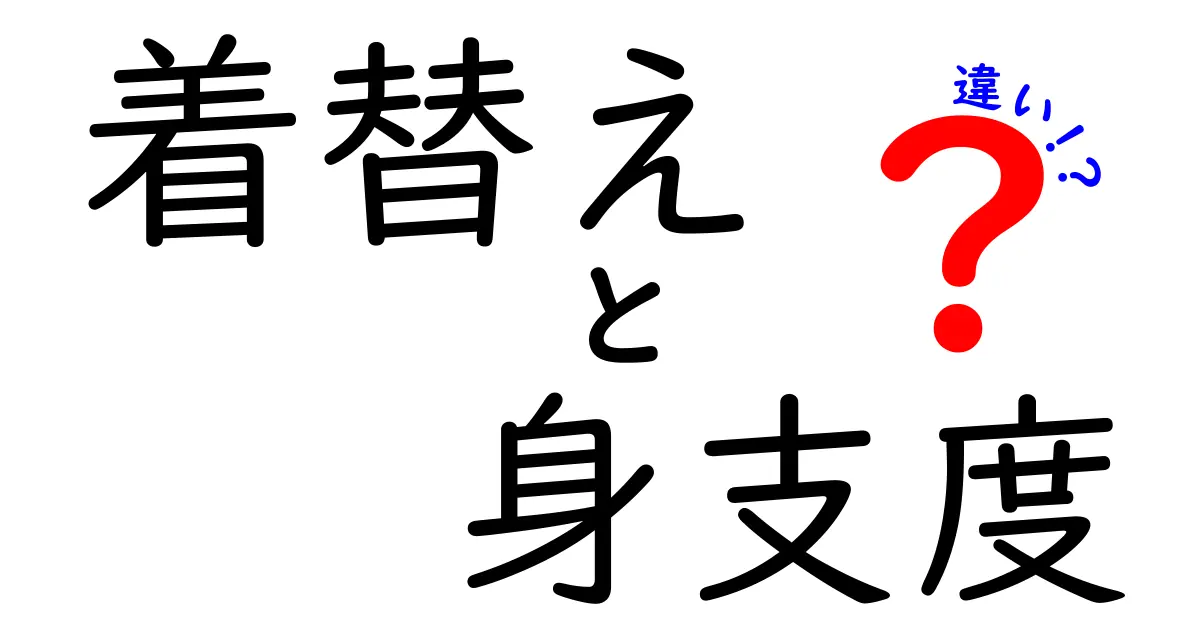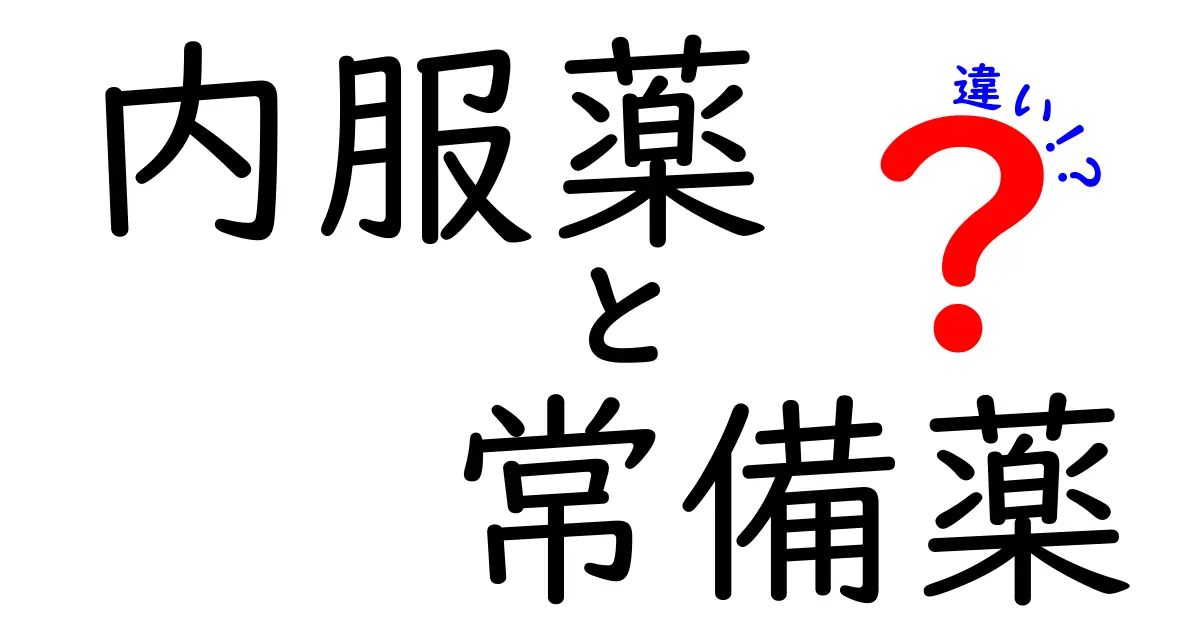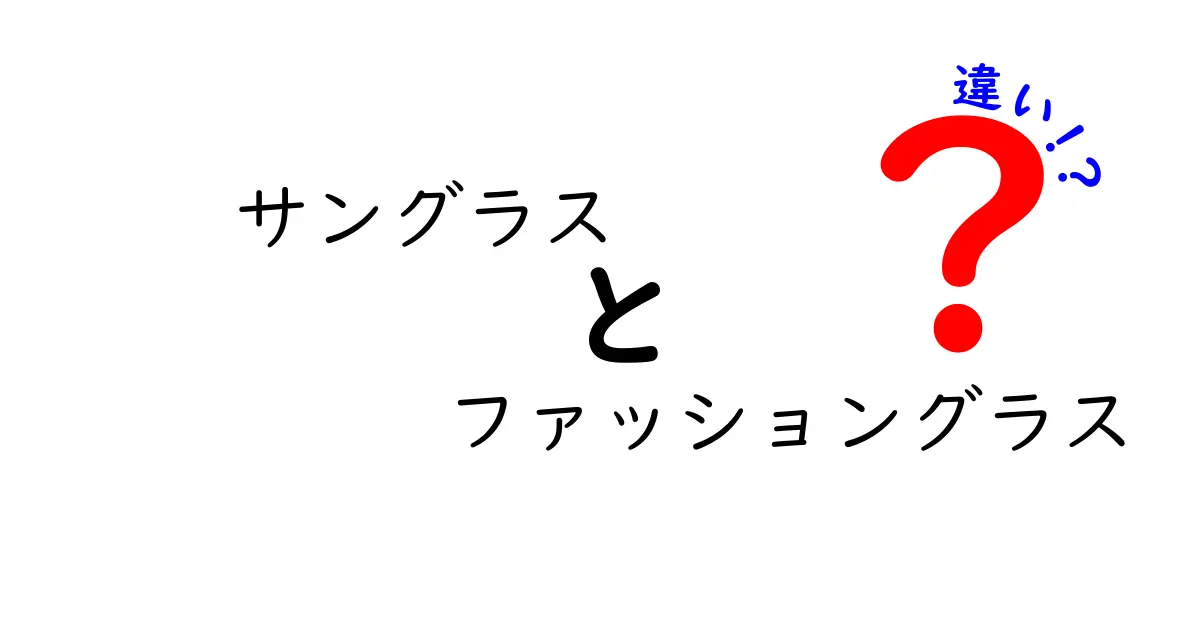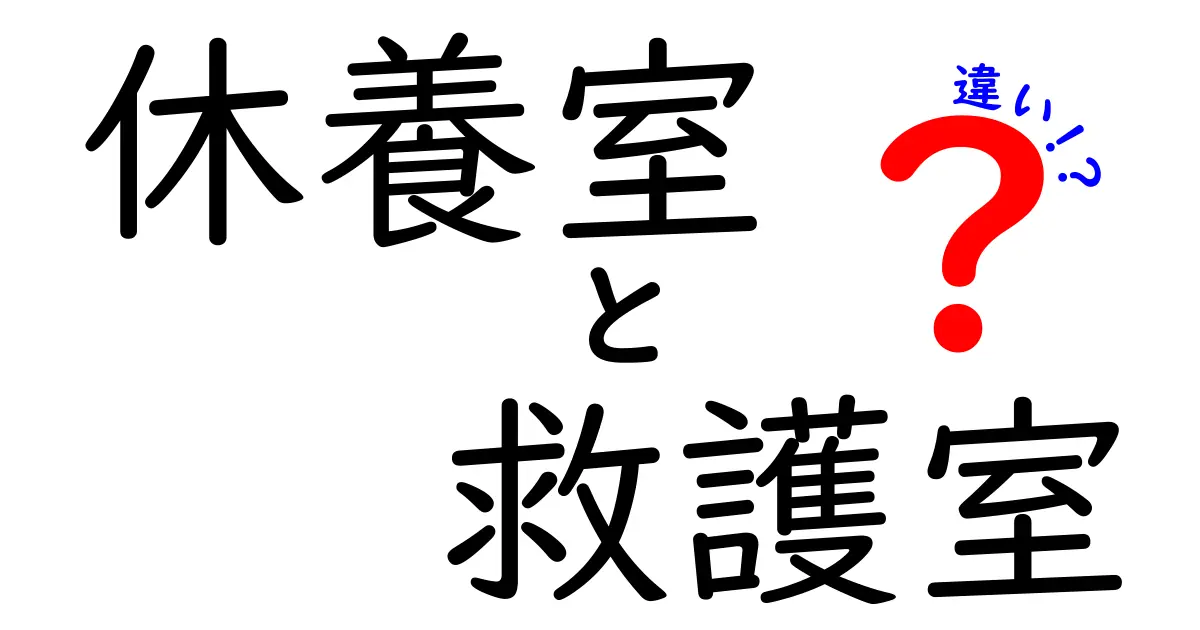

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
休養室と救護室の違いを知ろう
日常生活の中で、学校や企業の建物には似たような「休むための部屋」がいくつかあります。その中でも特に混同されやすいのが休養室と救護室です。名前だけを見ると同じように感じることもありますが、実際には目的・運用・設備・対応する人が大きく異なります。本記事では、両者の意味と役割を分かりやすく整理し、どんな場面でどちらを使うべきかを具体的な例を交えて解説します。中学生にも理解しやすい言葉づかいを心がけ、図表も交えて読みやすく作りました。
まずは基本の考え方を押さえましょう。
・休養室は主にリラックス・休憩を目的とした空間で、心身を整える場所です。
・救護室は体の痛みや怪我に対して応急処置を提供し、安静を確保する場です。これらの違いを理解することが、正しい対応の第一歩になります。
そもそも意味と役割
休養室と救護室の違いを正しく理解するためには、それぞれの言葉が指す役割をはっきりさせることが大切です。休養室は心身を回復させるための場で、静かな空間、座れる場所、軽い飲み物が設置されていることが多いです。痛みや体調不良があっても、すぐに医療的な処置が必要でない段階の「休憩」が目的で、心の安定を取り戻すことを重視します。一方、救護室は怪我や急な体調不良に対して初期対応を行い、必要に応じて医療機関へ連絡する窓口として機能します。ここには応急処置用の道具や酸素、消毒薬、包帯などが揃っており、医師や看護師、救急対応ができるスタッフが待機していることが一般的です。
このように目的が違う就業・教育現場の部屋であり、それぞれの場面で適切な対応が求められます。休養室は落ち着いた時間を過ごし心身を整えるため、救護室は急なトラブルに対して迅速に対応するための場所です。どちらを使うべきか迷ったときには、まずは怪我・痛みの有無と緊急性を判断することが大切です。
利用場面と場のイメージ
学校や職場、スポーツ施設など、さまざまな場所で休養室と救護室は異なる形で現れます。学校では、休養室は授業の合間の休憩室や部活動後のリフレッシュ地点として使われることが多いです。生徒が授業中に体調を崩した場合には、救護室で体温を測る、傷口を消毒する、安静の指示を仰ぐなど、応急処置を伴う対応が中心になります。職場では、長時間のデスクワークで集中力が切れたときの休養室、突然の腰痛や頭痛時の応急処置をとる救護室といった使い分けがあります。フィットネスクラブやスポーツ施設では、休養室で呼吸を整えたり水分補給をしたりする一方で、救護室は転倒・打撲・捻挫などのケガに対する初期対応をすばやく行います。
場のイメージとしては、休養室が「静かで心地よい空間」、救護室が「清潔で整理整頓された医療的な空間」という印象を持つと覚えやすいでしょう。常に状況に応じて、誰が・何を・どうするのかを意識することが、適切な使い分けのコツになります。
設備・対応の違い
休養室と救護室では、設置されている設備や担当者の役割も異なります。休養室にはソファや椅子、静音性の高い環境、飲み物や軽いスナック程度が置かれていることが多いです。ここでの目的は心身を落ち着け、疲労を回復させることなので、長時間の滞在を想定した快適性が重視されます。一方、救護室には消毒セット、包帯、絆創膏、消毒液、血圧計(関連記事:アマゾンの【血圧計】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)、酸素ボンベなど、医療的な応急処置に必要な道具が揃っています。常駐の看護師や救急救命士、あるいは学校の保健室の保健師など、医療に詳しいスタッフが対応するのが基本です。もちろん現場の状況によっては、救急車を呼ぶ判断をするケースもあります。下記の表は、基本的な違いを端的に示したものです。
<table>
実際の使い分けのコツ
日常の場面での使い分けをつかむコツは、まず「今この人に必要なのは休ませることか、応急処置か」を判断することです。体調が優れないときは休養室へ誘導して無理をさせず、痛みや怪我がある場合は救護室へ移動して適切な処置を受けさせます。学校や企業の規定にもよりますが、長期の沈黙や痛みが続く場合は医療機関への受診を促す、自己判断での安静の長さを過大に設定しない、この2点を意識すると混乱を避けられます。場所の違いだけでなく、対応するスタッフの役割の違いを理解しておくと、急なトラブルにも適切に対応できます。
まとめとよくある勘違い
休養室と救護室の違いは、目的と対応の性質に大きく現れます。休養室は心身の回復を促す静かな場所、救護室は怪我や急な体調不良に対して迅速な初期対応を行う場所です。学校や職場での混乱を避けるためにも、両者の役割を明確にしておくことが大切です。よくある勘違いとしては、「救護室は必ず病院と同じで大掛かりな処置をする場所だ」という誤解や、「休養室はただのリラックススペースだから特別な対応は不要」という認識です。現場の基本ルールを守りつつ、必要な場合は専門スタッフの判断を仰ぐことが最善の対応につながります。最後に、どの部屋を使うにしても、利用者の安全と安心を第一に考えることが最良の結論です。
救護室について友人と話していたときのこと。友だちは「救護室ってなんだか病院みたいで怖い」と言っていましたが、私はこう答えました。救護室は決して病院ではなく、急なトラブルを解決するための“最初の一歩を踏み出す部屋”だと。もし転んで痛いとき、頭がくらっとする時、まずは体を休めるための場所が休養室。そして、痛みが強い、出血がある、吐き気がする、そういうときには救護室へ行き適切な処置を受ける。大事なのは安心して話せる人が近くにいること。そんな場を作ることが学校や職場の安全につながるんだと実感しました。