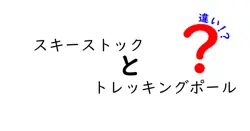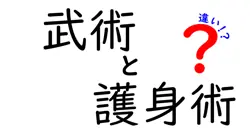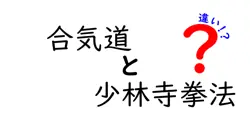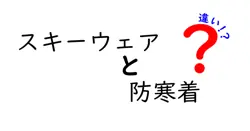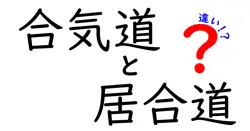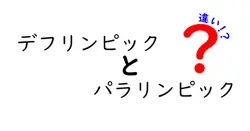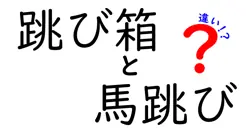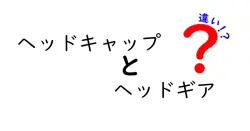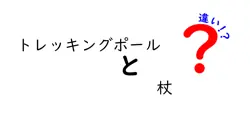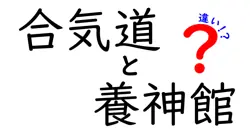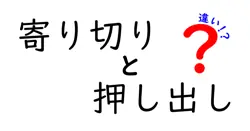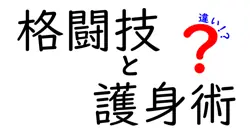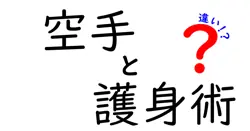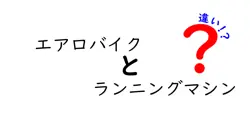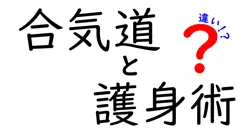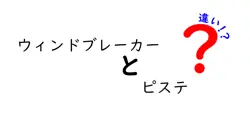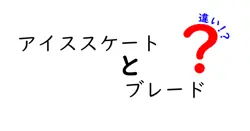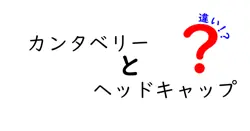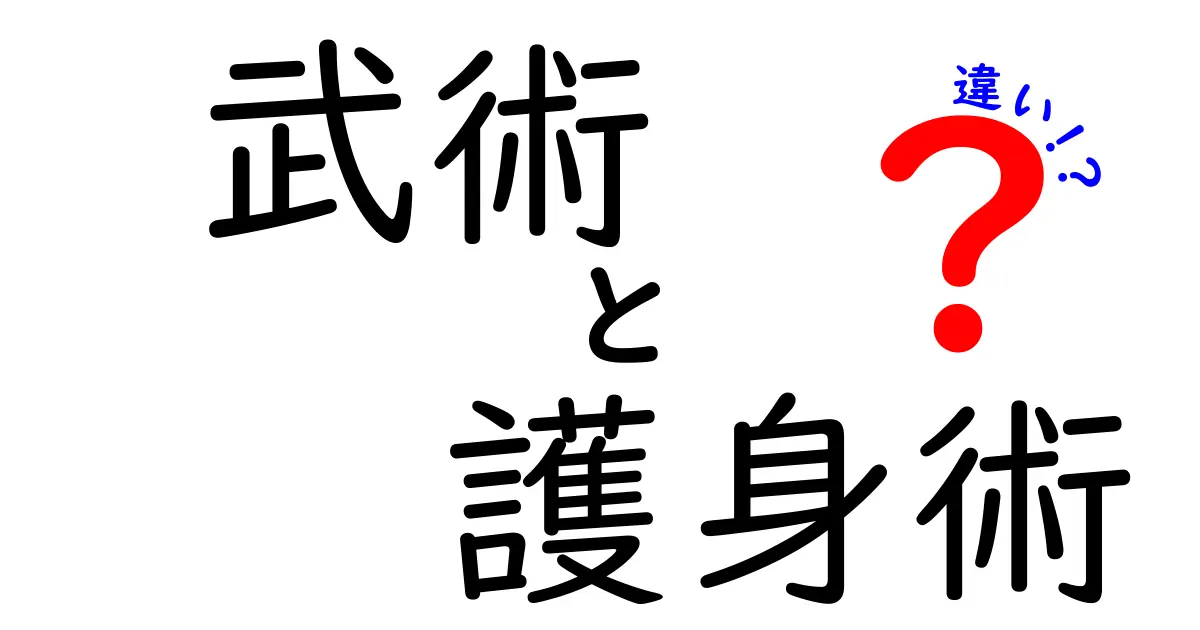

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
合気道と大東流合気柔術の違いを徹底解説|初心者にもわかる比較ガイド
まず初めに結論を先に伝えると、合気道と大東流合気柔術は“相手の力をどう扱うか”という点で共通していますが、稽古の目的と道場の方針、教える技の幅が異なります。合気道は現代の剣道・柔道・空手と同じく、対戦よりも心身の統合や安全の実践を重視する現代武道として発展しました。そのため「相手を傷つけずに動きを取り戻す」ことを最優先に、間合い・タイミング・呼吸といった内面的な要素が重視されます。大東流合気柔術は、古武道としての護身術の一部を現代に伝える流派の総称で、伝統的な技の体系と動作の美を保ちながら、実戦的な取り回しや崩し方にも重きが置かれます。両者の基本理念には敬意と安全性があり、学ぶ人の性格や目的に合わせて選択できる柔軟性があります。ここでは、起源・技法の捉え方・指導法・現代の実践形という四つの視点から、できるだけ分かりやすく整理します。
なお、道場選びをする際には「指導者の考え方」「カリキュラムの透明性」「安全対策の徹底」が重大な判断材料になります。
この章の目的は、違いを単なる名前の違いとしてではなく、実際に体感できる動作の根っこの部分の差として理解してもらうことです。
歴史と成り立ち
合気道は現代の道場で広く普及している武道として、創始者の植芝盛平によって20世紀前半に体系化されました。彼は武術の伝統的な鍛錬と新しい精神修養を結びつけ、対戦よりも相手を傷つけずに動きを取り戻すことを第一に置く哲学を打ち出しました。その結果、現代の多くの道場では、安全性・相手を傷つけない技の流れ・心身のバランスという三つの柱が教えの中心になります。大東流合気柔術は、江戸末期から明治期にかけて各流派が体育的要素と護身術を統合して作られた体系の総称です。支流の系統は、護身術としての実践性を重視する一方で、古流の名を守りつつ技の美と伝統を伝えることにも力を入れます。これらの歴史は、現代の道場での実践形を理解する手掛かりとなります。
現代においては、両者の歴史を同時に学ぶことで、技術の背後にある哲学・倫理・社会的背景を理解する視点が深まります。
技術と目的の違い
技術の出発点は同じ「相手の力を利用する」という考え方ですが、目的の解釈には差があります。合気道は“心身の調和と安全第一”を最優先に、動作の美と流れを追求します。教え方は段階的で、受け身・崩し・抑えの三つのステップを通じて、力の使い方を学びます。大東流合気柔術は、護身術としての現実的な制御と、身体の連動を重視します。力の方向転換や関節の操作など、体の使い方を具体的な技として積み上げ、実戦的な状況を想定した練習が多く取り入れられます。どちらも“安全性”と“技の原理理解”を共通の柱としますが、道場ごとにこのバランスの取り方は異なるため、体験稽古を通じて自分の感覚に合う方針を選ぶとよいでしょう。
技術的には、崩しと回転の使い方、呼吸法、体の中心の取り方など、基礎原理は共通しますが、現場での適用の仕方には差が生まれやすい点を覚えておくと混乱を避けられます。
技術と練習のポイント
合気道の練習は、相手の動きに合わせて自分の重心を移動させ、接触点を利用して回転や崩しを作ることが基本です。技名より原理の理解を優先し、受け身・崩し・抑えの三段階を順に練習します。大東流合気柔術では、もっと実戦的な切り返しと守りの技術が重視されることが多く、力の連携を体全体で感じ取りながら行います。基本動作を反復して体に覚えさせ、その後、さまざまな場面を想定した組手へと発展させます。両者を比べると、動作の美しさと機能性のバランスの取り方に違いが出やすいです。
初めての稽古では、指導者の安全指示を最優先に受け入れ、怪我を避ける姿勢を徹底してください。
また、正しい姿勢と呼吸の組み合わせを身につけることが、どんな技にも応用できる土台になります。
簡易比較表
<table>この表は入り口の目安に過ぎません。道場によって細かな技の名前や型の順序は異なりますが、いずれも「相手の力を利用しつつ自分の安全を守る」という根幹は変わりません。体験稽古で感覚を確かめ、質問を重ねることが、違いを理解する最短ルートです。
また、どちらを選ぶにしても、最初は正しい基本動作を身につけることが最優先です。
この点を忘れずに、楽しみながら学んでください。
友人と雑談していたときの話。『歴史』という言葉を改めて考えると、合気道と大東流合気柔術の歴史は、道具や城郭ではなく“人の動きの記録”として蓄積されてきたんだと分かります。歴史を追うと、技の名称よりも、どのように心と体の動きを結びつけて安全を保つかという原理が共通していることに気づきます。昔の師は相手の力を利用するコツを、現代の道場では安全な稽古として伝え続け、私たちはその伝統の上に自分の動きを積み上げていくのです。
次の記事: 反撃と迎撃の違いを徹底解説!いざというときに役立つ3つのポイント »