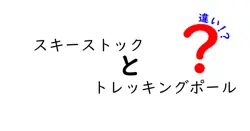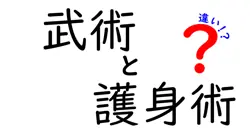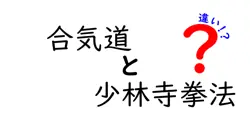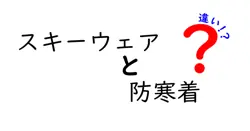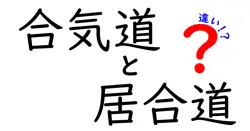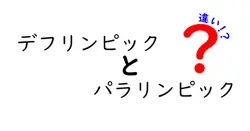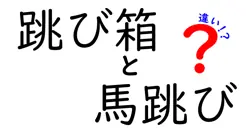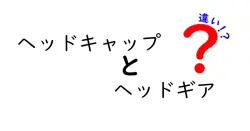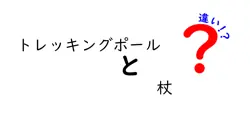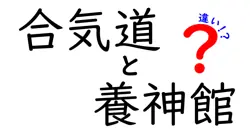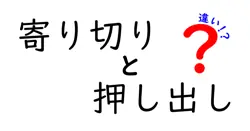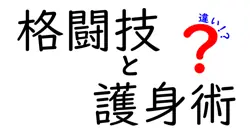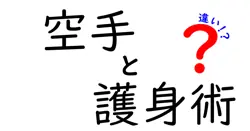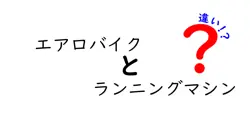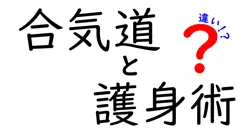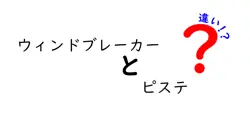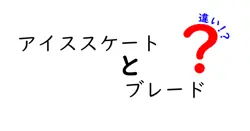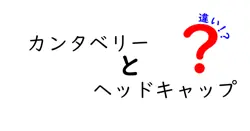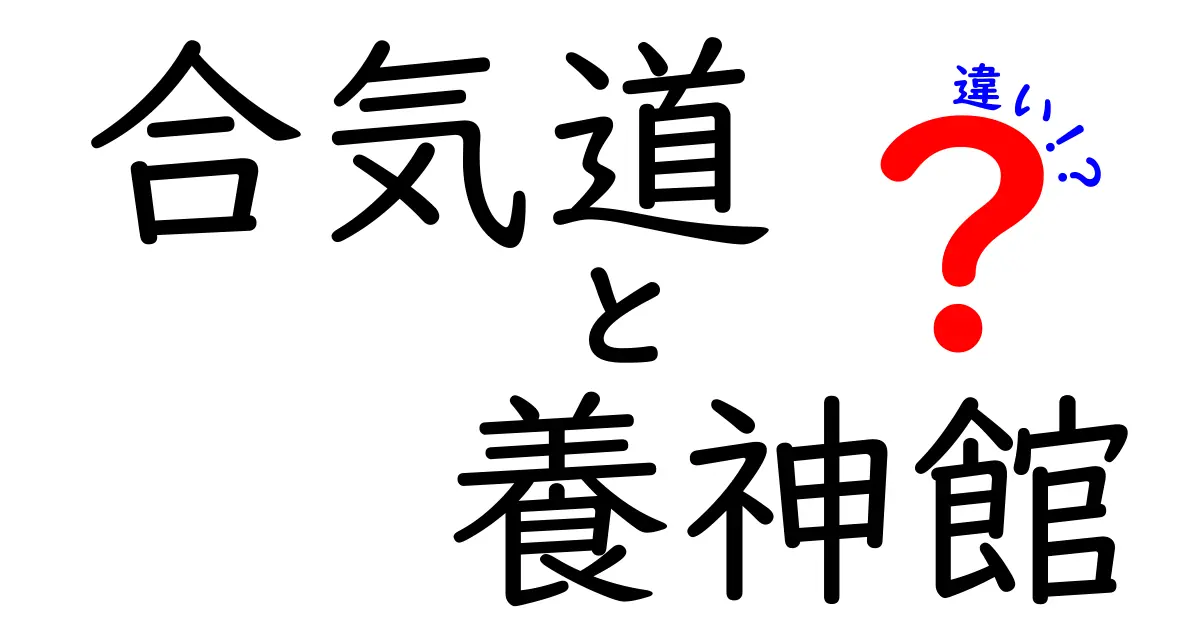

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
合気道と養神館の違いを理解するための入口となる長文の解説:養神館の成立背景、創始者の思想、技の性質、練習方針、指導方法、道場の運営スタイル、歴史的な経緯、現代の普及状況、そして「違い」という視点から見た学科的な整理を、初めて読む人にも分かるように丁寧に説明します。養神館は誰が創始したのか、どのような教育理念を掲げ、基本技(kihon)をどのように重視しているのか、流派間の差異はどこに現れるのかなど、具体的な点を多数挙げて比較します。さらに、映像での練習や演武の際の姿勢、呼吸と体の連動、競技的要素の有無、舞台裏の教室運営、初心者の導入の仕方と中級者へのステップアップ、海外の普及状況と国際的な組織の違いまで、総合的に一つの枠組みとして提示します。
この章では合気道そのものの意味や養神館の位置づけを、言葉の定義から実際の動作まで順序よく解説します。まず合気道という名称がどのように生まれ、何を目指す武術として世界に広まっていったのかを歴史的観点から整理します。次に養神館の成立過程を、創始者の教育哲学と道場の運営方針、初心者から上級者までを見据えた段階的な指導方法と具体的な練習メニューに落とします。
そのうえで技術の性質を分解し、力を使わず相手の動きを利用する原理、身体の重心移動、呼吸の連携といった基本要素がどのように異なる流派で扱われているかを実例とともに説明します。
さらに道場の雰囲気や礼法の違い、試合の有無、昇段審査の基準、国際普及の現状、海外道場での運営の工夫と課題など、日常の練習風景に直結する要素を具体的に比較します。最後に結論として、合気道という一つの文化がどのように分岐していったのか、養神館がどの位置を占めるのかを、読者が自分の興味や目的に合わせて選択できる手がかりとして提示します。
養神館と一般の合気道の技術的・組織的違いを分かりやすく整理するセクションとして
養神館の技術は基本技kihonを軸に構成され、安定した姿勢と体幹の使い方を重視します。相手の動きに対して自分の体をどう適合させるかという観点が強く、手首や膝の使い方、重心移動の順序、呼吸のタイミングを練習の中心に据えます。これに対して一般の合気道の流派では動きの柔軟性と創造性を重視する場合が多く、同じ局面でも複数の解法を使えるよう訓練します。結果として、道場ごとに練習メニューや段位認定の基準、演武の美学が異なることがよくあります。私たちが知っておくべきは、どの流派を選ぶかというよりも、目的に合った練習方針を見極める力を養うことです。
ここで大切なのは、技の“軽さ”と“正確さ”のバランスです。養神館では力を使わず相手の円運動を活かす感覚を磨く訓練が中心で、初心者のうちは特定の動作を何度も繰り返すことで体に染み込ませます。一方で流派によっては相手の動きを読み解く洞察力を養う課題が多く、技の応用範囲を広げる訓練が多く組まれます。
実践のヒントと道場選びの考え方
道場選びの際には、練習方針だけでなく雰囲気、指導者の経験、段位審査の公平性、怪我予防の取り組み、設備・環境の清潔さなどを確認します。養神館の道場は初心者にも段階的な指導を提供することが多く、基本技の反復と正確性を重視します。対して他流派の道場では応用技や実戦的な演武に比重を置くところもあり、やや自由度が高い場合があります。自分の目的が、技を安全に学びたいのか、技術の幅を広げたいのか、競技性を求めるのかで選択肢が変わるのです。
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
今日は部活帰りに友達と高校の柔道場の話をしていて、合気道の流派の違いについて盛り上がりました。友達は養神館について名前は知っているものの、どんな練習をするのか、どの点が他の流派と違うのかをよく知らず、ただ柔らかい動きだけだと思っていたようです。私は頭を使って説明しました。養神館はkihonという基本技をとても重視しており、毎回の稽古でこの基本動作を正確に積み重ね、体幹の安定と呼吸の連動を徹底させる練習が多いと伝えました。実際には、同じ技でも細かいフォームや体の使い方の違いが現場で大きな差になり、道場の雰囲気や指導者の解釈次第で学べるものが変わると話しました。私たちは後日、違いの整理ノートを作ることにして、見学や体験へ行く計画を立てました。
前の記事: « 自衛と防衛の違いとは?中学生にも分かるわかりやすい解説