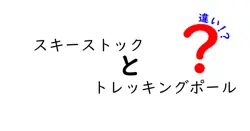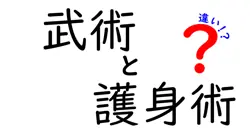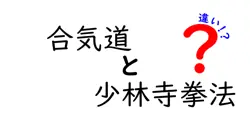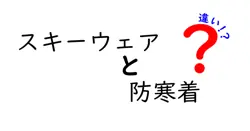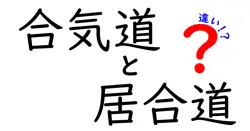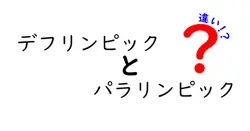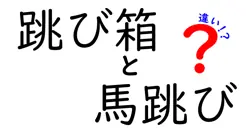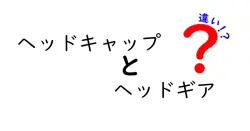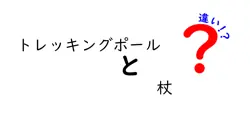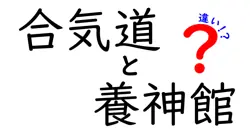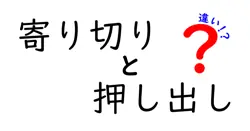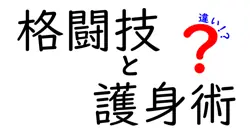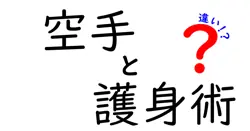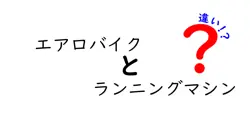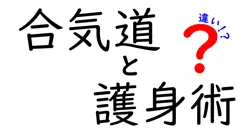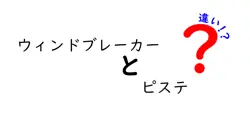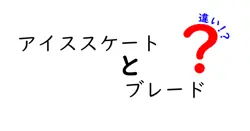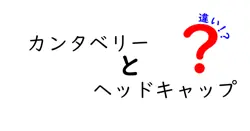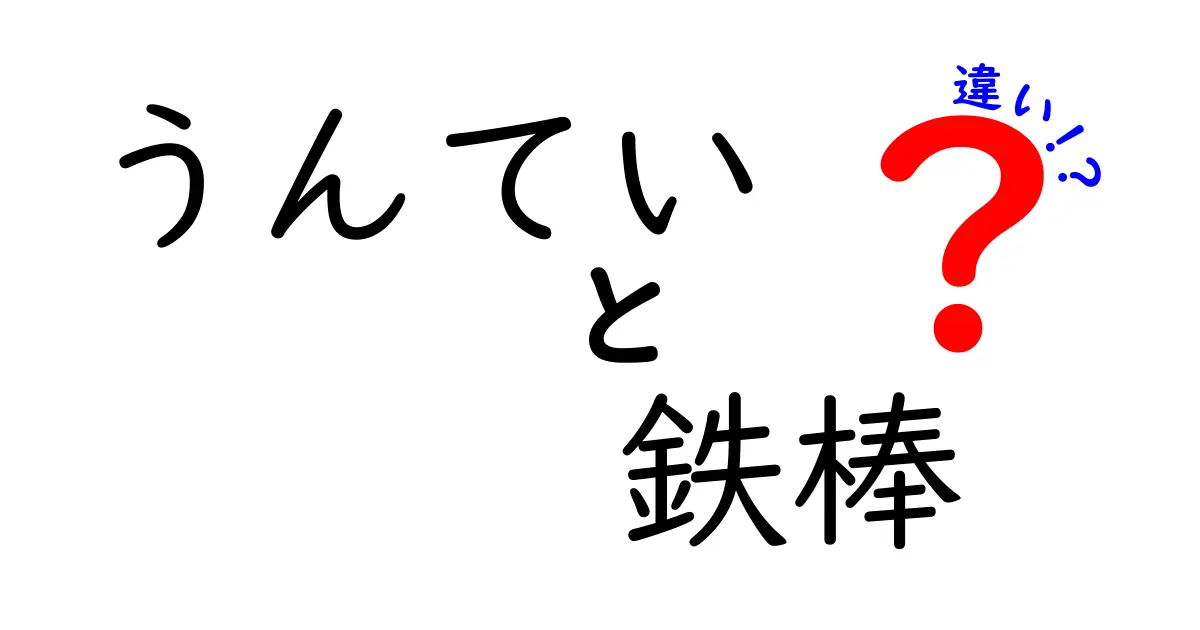

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
うんていと鉄棒の基本的な違いを把握しよう
うんていと鉄棒は、学校の体育や公園の遊具コーナーでよく見かける運動遊具です。
しかし、見た目が似ていても「何を目的に作られているのか」「どう体を使うのか」が大きく異なります。
本セクションでは、まずそれぞれの道具の定義を確認し、体の動かし方の違い、練習の目的、対象となる筋肉の動きについて、わかりやすい言葉で解説します。
中学生のみなさんが日頃の体育の授業や部活動で遭遇する場面を想定して、具体的な使い分けの考え方を紹介します。
形状と設置場所の違い
うんていは、複数の水平のバーが連なる長い構造物で、地面に固定された大きな遊具セットの一部として見られることが多いです。
遊具全体が横方向へと広がり、子どもたちはバーの間を手で握って渡っていきます。手と腕の力だけでなく、体幹の安定性やバランス感覚も同時に使います。
また、うんていの設置場所は校庭や playground 内の複合遊具エリアが一般的で、複数人が同時に動く場面が想定されます。
一方の鉄棒は、一本の垂直または低めに設置された棒を中心に構成され、シンプルな設計です。
鉄棒は技の練習用として切り出され、特定の高さに固定されるケースが多く、体育館の器具置き場や校庭の専用コーナーに設置されることが一般的です。
この違いは、遊ぶときの安全距離や移動の難易度、学習する動作の焦点にも影響します。
さらに詳しく見ると、うんていは複数のバーの間を移動する「連動動作」が中心になるため、グリップの握り方や体幹の支え方が、鉄棒で求められる力の使い方と異なってきます。鉄棒は一本の棒を軸にして回転やぶら下がりの技を追求することが多く、動作の正確さと力の分配が大切です。これらの違いを理解しておくと、子どもたちが自分に合ったトレーニングプランを組みやすくなります。
また、設置場所の環境要因(地面の硬さ、周囲の障害物、他の子どもとの距離)を踏まえた安全な使い方を考える際にも、この違いは重要な指標になります。
遊び方とトレーニングの違い
うんていの遊びは、友だちと協力して渡っていく「連携の練習」や「リズム感の獲得」を中心に行われます。
手と手を順番に移動させ、体を水平に保つためには腰をひねらず、肩甲骨を動かす感覚が大切です。
足は体を支える補助の役割を果たし、蹴り出すよりは細かな体の配置で次のバーへ移行する技術が身につきます。
この練習は、 coordination や全身の協調性、腹筋群の持久力を育てるのに適しています。
鉄棒は、より個人の力強さと技術の正確さを重視します。
ぶら下がる力、懸垂をする力、体を回す回転運動、技の完成度を高めるフォームの習得など、上半身の筋力と技術の組み合わせを練習します。
練習を重ねることで、筋力の偏りを避け、体の背面と腹部のバランスを整えることができます。
実際の授業や練習では、まず低い高さから段階的に難易度を上げるアプローチが効果的です。うんていは低いバーから始め、体幹の安定性を確認しつつ、徐々に手の距離感や体の幅を広げます。鉄棒は最初はぶら下がるだけの練習から始め、徐々に懸垂や踏ん張りの動作を取り入れていきます。それぞれの動作を分解して練習することで、関節や筋肉への負担を最小限に抑えつつ、成長期の子どもでも安全に上達していけるのです。
安全性とコツ
安全第一を前提に、準備体操と手のグリップの整え方を徹底します。
うんていでは、最初は低い位置のバーから始め、身体を安定させるコアの力を少しずつ高める練習をします。
正しい握り方は、手のひらと指の力の均等な使い方を学ぶことから始まり、長時間の練習で皮膚の擦り傷を防ぐ保護対策も必要です。
鉄棒では、握る手の幅を適切に設定し、肩をすくめず・腰を過度に反らさずに動く練習をします。
落下時の体の崩し方、地面への安全な着地方法、周囲の人への配慮といった実践的な安全知識を身につけることが大切です。
練習前後のストレッチ、適切な休憩、栄養補給、睡眠など、身体を回復させる生活習慣も忘れずに取り入れます。
うんていについての小ネタというか雑談風エッセイ。友だちと肩を並べて渡るとき、誰が“ここまでいけるか”を競い合う瞬間が、生徒同士の信頼関係を深めるきっかけになることがあります。つい速度を競しがちですが、実はスピードよりも手のひらの感覚と体幹の安定が重要です。力任せに引っ張るより、呼吸を整え、腰を安定させて移動する方が安全で長く続けられる――そんな小さな気づきが、スポーツだけでなく日常の動作の上達にも結びつくのです。うんていは、子どもたちが協力して新しい動きを覚える体験を通じて、コミュニケーション能力や集中力を育てる良い機会にもなります。最初は少し戸惑うかもしれませんが、仲間と一緒にゆっくり進むことで、達成感を感じやすくなります。こんな小さな成功体験の積み重ねが、後の学習意欲にもつながるのです。一方で、鉄棒の練習は、自分の力を確かめながら成長していく実感が強く、努力の成果を直に感じられる点が魅力です。ですから、うんていと鉄棒は「一人で完結する練習」と「仲間と楽しみながら伸ばす練習」という、対照的な側面を持ちつつ、相互補完的に子どもの体づくりをサポートしてくれる存在なのです。