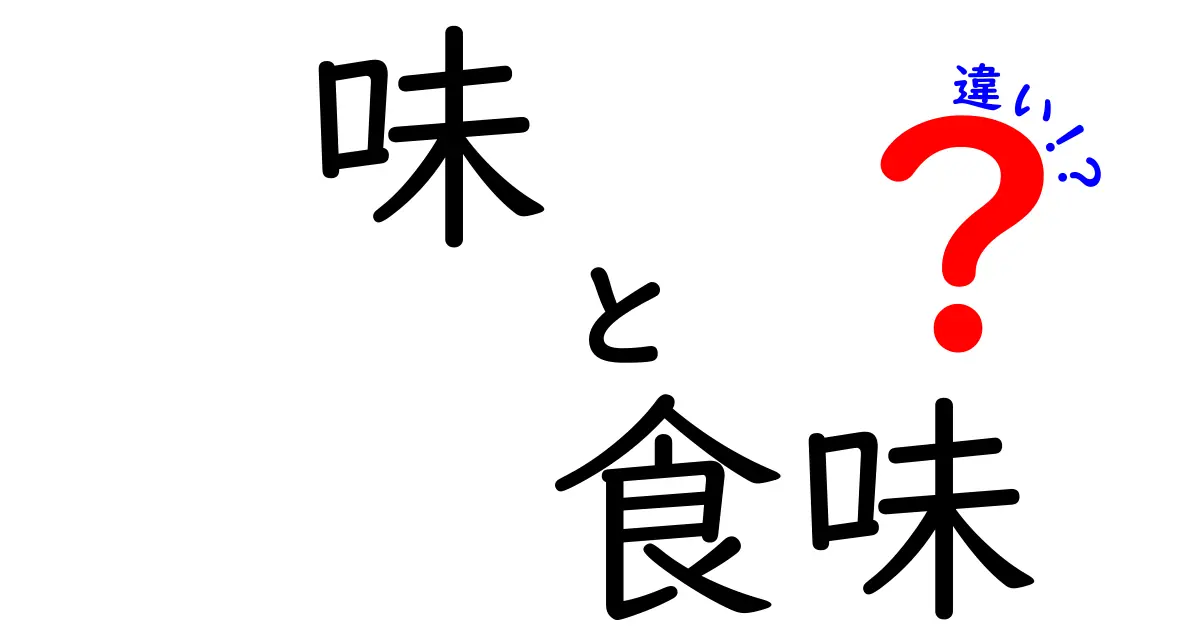

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
味と食味の基本を知ろう
味とは何かを説明する前に、まず日常の感覚に結びつけて考えましょう。味は舌の上で感じる基本的な感覚で、甘い・酸っぱい・塩辛い・苦い・うま味の5つが代表です。これらは舌の味蕾という小さな器官が化学物質を検知することで生まれ、食べ物を噛んで飲み込むとき脳に信号が伝わります。たとえばリンゴを噛むときには甘味が強く感じられ、レモンをかじると酸っぱさがピリッと舌を刺激します。
この「味」は、料理の中心となる要素の一つであり、食べ始めの第一印象を大きく左右します。これに対して食味はもっと広い概念です。食味には味だけでなく、香り・食感・温度・後味・舌触りなど、体験としての総合感覚が含まれます。香りは鼻の奥で感じる匂いのため、実際に口に入れた瞬間だけではなく、飲み込んだ後にも強く影響します。歯ごたえがカリカリしているか、滑らかで口の中でどう感じるか、温度が冷たいか温かいかも味の印象に影響します。
このように、味と食味は別物の要素が組み合わさって「おいしさ」を作り出す仕組みです。多くの人が最初に感じるのは味そのものですが、食味を豊かにする工夫を追加すると、同じ材料でも全く違う印象になります。以下の要素を押さえると、日常の料理で味と食味の違いを意識しやすくなります。
- 味は舌が感じる基本の感覚(甘・酸・塩・苦・うま味)
- 食味は香り・歯ごたえ・温度・後味などの総合印象
日常で感じる違いの具体例
身近な例を挙げてみましょう。リンゴは生でかじるとシャキッとした歯ごたえと甘酸の香りが強く、舌の上に残る甘味が心地よいです。これが味としての反応です。一方で同じリンゴを煮たり焼いたりすると、香りは少し弱まり、甘味の後味が長く続く食味の印象になります。香りが弱くなると、食べる人の気分も変化します。さらに温度が影響する例として、アイスクリームは冷たいことで甘味の感じ方が控えめになる一方、口の中で溶けると香りが広がり、食味の満足感が増すのです。
このような現象は、料理の設計にも活かせます。例えば煮物は香りを閉じ込めるために蓋をして蒸し煮にすると、食味が深まりやすくなります。反対に揚げ物は油の香りとカリッとした食感で食味が強くなり、味の印象が一気に変わります。
このように、味と食味は別物の要素であり、それぞれの役割を理解して組み合わせることが、おいしさを演出するコツです。さらに、日常の料理で工夫することで、香りの広がりや歯ごたえの変化を楽しめるようになります。
タケシ: 今日のテーマは『味と食味』だよ。ミユキ: うん、味は舌で感じる甘・酸・塩・苦・うま味のことだよね。タケシ: そう。でも食味は香りや歯ごたえ、温度、後味まで含む総合的な体験なんだ。ミユキ: なるほど。例えばアイスクリームを食べるとき、舌の味は甘いけれど、香りが広がるかどうかで実際の満足感が変わる。タケシ: だから同じ材料でも、準備の仕方で食味を変えられるんだね。





















