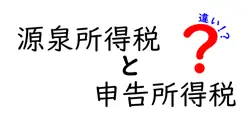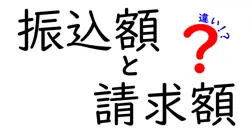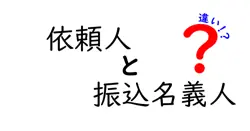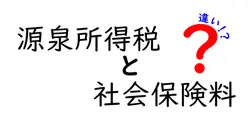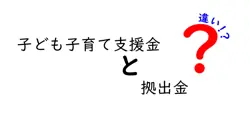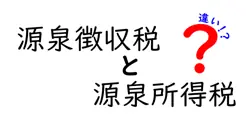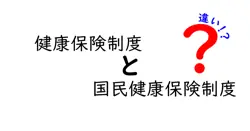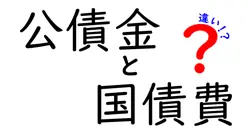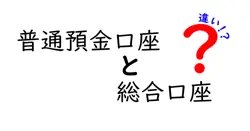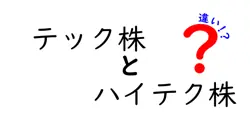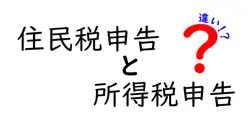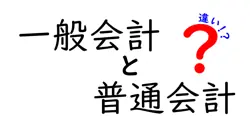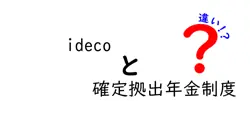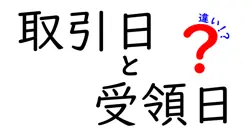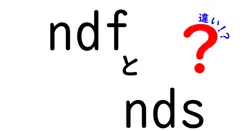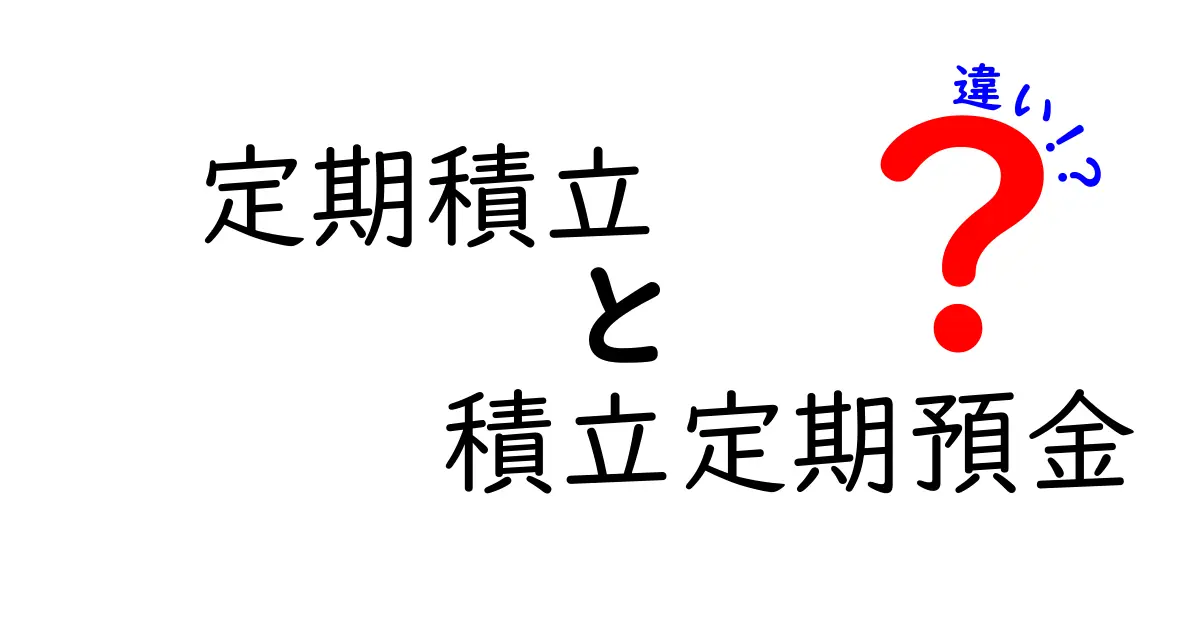

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
定期積立とは何か?基本を押さえる
定期積立とは、毎月決めた金額を自動的に銀行口座から引き落とし、一定の期間にわたって積み立てていく仕組みのことです。日常の家計管理としても取り入れやすく、教育資金や将来の大きな支出を計画的に用意するのにぴったりです。主なポイントは三つです。まず第一に「自動性」です。定期積立は事前に設定しておけば、毎月の作業を省略できます。第二に「期間の設定」です。期間を決めることで、将来の資金目標を具体化でき、途中での暴走買いを抑えやすくなります。第三に「金利の取り扱い」です。定期積立の中身が普通預金に振替えるか定期預金として運用されるかはプラン次第で、金利の動向も大きく影響します。ここで押さえておきたいのは、流動性の制限と金利リスクです。定期積立は、資金を一定期間、引き出しにくくする設計になっていることが多く、必要な時にすぐ現金化できるとは限りません。急な出費が増える月には、別の資金源を用意しておくのが安全です。また、金利は市場の動きや銀行の経営方針によって変動します。高い金利が魅力的に見える季節でも、途中解約時のデメリットを考えると、長期の計画と現実的なキャッシュフローをセットで考えることが大切です。定期積立を始める前には、銀行が提供する商品説明書を読んで、元本保証の有無や引き出しルール、自動継続の有無を確認しましょう。結局のところ、定期積立は「コツコツ貯める力」を高める道具です。自分の収支と目標に合わせて無理なく組むことが成功の鍵です。
積立定期預金とは何か?メリット・デメリット
積立定期預金は、毎月決まった額を積み立て、一定の期間が満了するまで預金を解約せずに運用する商品です。特徴としては、利率が期間の長さや商品ごとに設定され、満期時に元本と利息がセットで返ってくる点が挙げられます。魅力は、金利が安定している場合が多いことと、元本が保全されやすいことです。特に小さな額の積み立てでも、長期間の運用を前提にしているため、複利効果が働きやすく、総合的な利息が大きくなるケースがあります。一方でデメリットとしては、満期前の解約や中途の取引に対して違約金やペナルティが設定されていることが多く、急な資金需要には向かない点です。さらに、流動性の低さが挙げられます。預金は満期日まで動かせないため、突然資金が必要になってもすぐには現金化できません。こうした点を踏まえると、積立定期預金は「安全性を最優先しつつ、一定の資金を将来の大きな出費に備える貯蓄手段」として有効です。
ただし、金利の変動や手数料、口座条件は銀行ごとに異なるため、複数の商品を比較することが重要です。預金保険の対象となることは一般的ですが、最終的な元本の安全性は金融機関の信用力にも依存します。契約前には、満期日、再投資の有無、最低積立額、引き出し条件を具体的に確認しましょう。
両者を使い分ける実践ガイド
実務的には、自分の資金計画と生活設計を前提に判断します。まずは自分のライフイベントの時期を整理しましょう。教育資金の準備や将来の一括支出を見据える場合、積立定期預金のような「満期が約束された商品」が向きます。これに対して、日々の生活費の残高を増やしつつ、金利変動の影響を受けても柔軟に対応したい場合は、定期積立を中心に据え、必要に応じて一部を途中解約が比較的扱いやすい配分へ変更する選択肢を取るのが現実的です。実際には、口座の金利動向、手数料の有無、最低積立額、解約条件を比較して、自動積立機能を活用できるかどうかを確認します。表やグラフで比較すると、どのくらいの期間でどれくらいの利息になるかが見えやすくなります。次に、目標金額と期間を具体化します。例えば教育資金を子供が大学に入る前に一定額貯めると決めたら、毎月の積立額と満期までの月数を計算します。現実には、生活費の変動、臨時の出費、ボーナスの有無などが影響します。そのため、運用方針の見直しを年に一度は行い、金利の動向に合わせて積立額を調整する柔軟性が大切です。最後に、家族で話し合いをします。子どもの教育費、老後資金、旅行資金など、目的ごとに複数の口座を使い分けると、目標が見えやすく、挫折しにくくなります。実際の体感としては、貯蓄の進捗が見えるとモチベーションが上がり、自然と計画性が身についていきます。日常の習慣としての積立は、ちょっとした工夫で大きな効果を生む点が魅力です。
<table>- 自動積立で継続のモチベーションを保つ工夫をする
- 複数の商品を比較し、解約条件と手数料を必ずチェックする
- ライフイベントごとに口座を分けると目標が明確になる
友達とカフェで積立の話をしていたら、積立定期預金をどう使い分けるかで盛り上がったんだ。Aさんは「金利がいい方を選ぶべき?」と聞いてきた。私はこう答えた。積立定期預金は“満期が約束された貯蓄”だから安心感は高いけれど、途中でお金が必要になったときの柔軟性は低い。だから、教育費の準備みたいに長い目で使うお金には向いている。一方、Bさんは「毎月の自由度が欲しい」と言っていた。定期積立は自動で積み立ててくれる利便性が高く、生活費の調整をしつつ資金を育てられる良さがある。結局、僕らは“目的と期間”で使い分けるのが賢いと結論づけた。現実の生活では、急な出費の可能性と将来の計画を両立させるため、両方を併用するのが現実的だと感じた。積み立てを始めるときは、最初に目標額と期限をはっきり決めて、定期的に見直すのがコツだと思う。そんなふうに、金融商品は道具だと捉え、上手に使い分けることで、日々の貯蓄のモチベーションも上がるはずだよ。