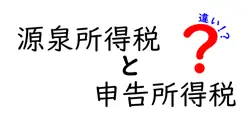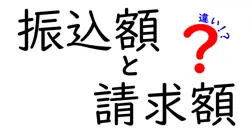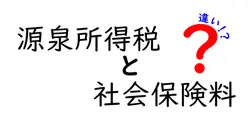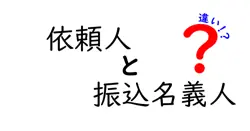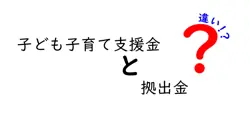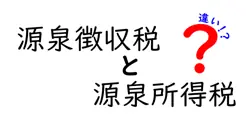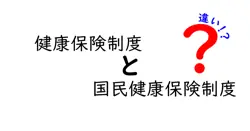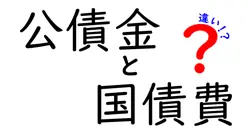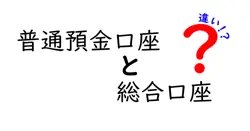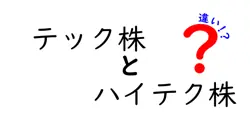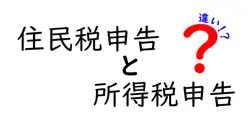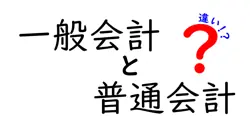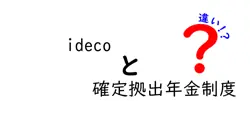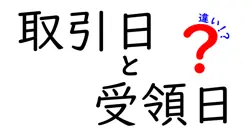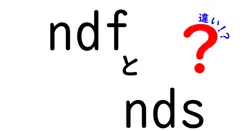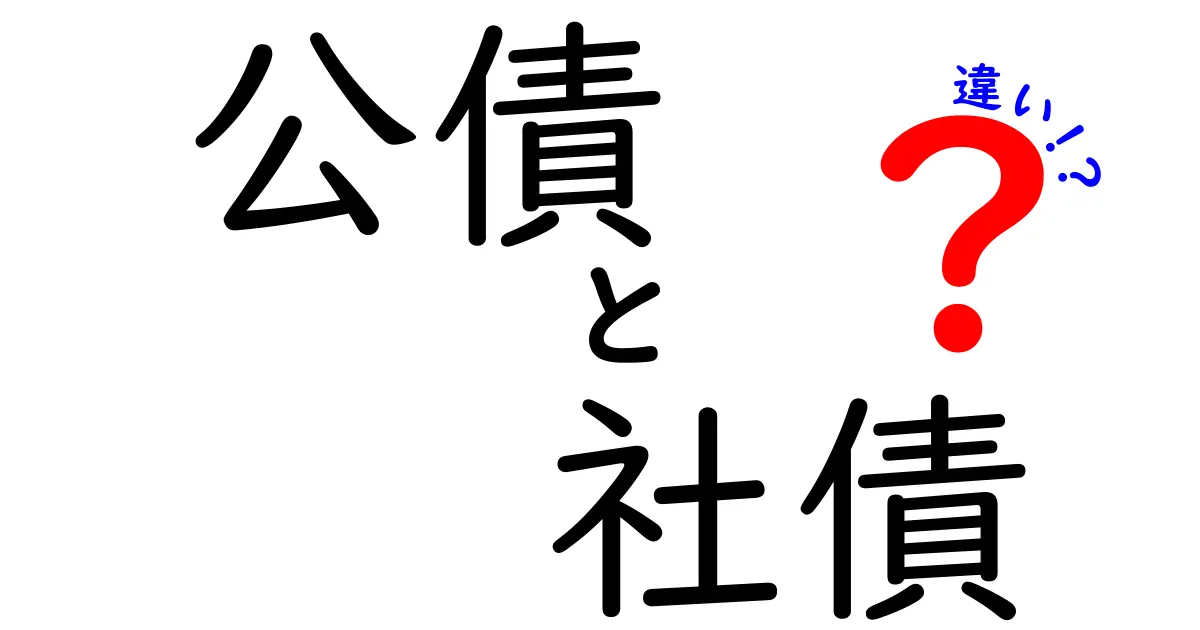

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
公債と社債の違いを徹底解説!初心者でもわかるポイントと具体例
公債と社債は、ニュースでよく耳にする言葉ですが、初めて聞く人にとっては「どこがどう違うのか」が分かりにくいものです。
ここでは「誰が発行しているのか」「リスクはどう違うのか」「利率はどう決まるのか」「用途は何か」など、基本から具体例まで、中学生でも理解できるように分かりやすく整理します。
まず大事な考え方は、発行する主体が公的機関か民間企業かという点と、信用の保証とリスクの関係、そして利回りの差です。公債は基本的に国家や地方自治体が発行するため、一般に信用度が高く、元本の安全性が比較的高いと考えられますが、リターンは社債より低めになることが多いです。一方、社債は企業が資金を調達するために発行します。企業の業績や信用状態によってリスクは大きく変わり、同じ期間の公債より利回りが高い場合が多いものの、倒産やデフォルトのリスクも伴います。
このような基本を押さえたうえで、実際にどのような場面で選ぶべきか、どう組み合わせて投資するべきかを見ていきましょう。
続いて公債と社債の特徴を一つずつ詳しく見ていきます。
公債の特徴と使われ方
公債は、政府や地方自治体が財政資金を調達するために発行します。
最もよく目にするのは国が出す国債で、元本が返ってくる保証が高いとされることが多いです。政府は国のインフラ整備や教育、社会保障など長期的な費用を賄うために資金を必要とします。その結果、国債は長期・中期・時には超長期のものが市場に出され、投資家は安定した利息を得ることを期待します。一般に公債はデフォルトのリスクが低いとされ、信用力が高い評価を得やすいのが特徴です。ただし、景気が悪化して税収が減ると、国の財政にも影響が出ます。そのころは金利が低めに設定されることが多く、買い手としては「安全性とリターンのバランス」をどう取るかが課題になります。
使い道としては、超長期の infrastructure projects、社会保障の財源確保、財政赤字の穴埋めなど、国家全体の安定を目的とした発行が中心です。投資の観点からは、年金資金や保険会社など、安定した運用を求める機関投資家が好んで購入します。
このように、公債は「信用の高さ」と「安定性」が魅力ですが、利回りは社債に比べて低いことが多い点を忘れずに。
また、自治体が出す地方債も地域の事業を支える重要な資金源で、発行条件は国債と似ていますが、地域ごとの経済状況に応じてリスクと利回りが変わることがあります。
社債の特徴と使われ方
社債は、企業が資金を調達するために発行します。企業の規模や信用力によってリスクと利回りが大きく変わる点が大きな特徴です。市場でよく見かけるのは「発行体の信用格付け」が公開されていて、格付けが高いほど安全性が高いと判断されます。格付けが低い企業は、利回りを高く設定して投資家を引きつける必要があります。これが「リスクとリターンのトレードオフ」です。社債は発行体の業績が好調なら高い利率を維持でき、財務状況が悪化すると価格が下がったり、途中で利払いが見直されたりすることもあります。投資家としては、格付けだけでなく企業の事業モデル、業界の競争状況、借入金の総額などを総合的に見て判断します。
社債は利息が比較的高いことが魅力ですが、債務不履行のリスクがあるため、分散投資が重要です。
また、社債には「転換社債」「無担保社債」「担保付き社債」など、さまざまなタイプがあり、それぞれに特徴とリスクが異なります。転換社債は株式へ転換できる可能性がある一方、株価の影響を強く受けやすいなど、投資家の戦略によって選択が分かれます。
利率・リスク・発行主体の比較
以下は、公債と社債の代表的な違いを要点だけでまとめた表です。
<table>
表の読み方の例としては、利回りだけでなく信用格付けや市場の需給も影響します。公債は「安定性」を、社債は「利回りの高さ」を重視する投資家に向いています。
投資戦略としては、リスクを分散するために公債と社債を組み合わせるのが一般的です。
また、発行体の格付けは常に変動するため、最新の情報をチェックする習慣をつけましょう。
具体的な例と表で理解を深める
ここでは数字の感覚をつかむための簡単な例を挙げます。公債は5年物と10年物が市場に出ており、現在の金利環境では5年物が年利1.0%前後、10年物が1.5%前後、というレンジになることが多いと理解しておくとよいです。一方、社債は同じく5年物・10年物があり、業績が安定している大企業なら年利2.0%前後、成長が期待できる中堅企業だと3%を超える場合があります。ここで大切なのは、リスクとリターンの関係を自分の目で見ることです。
株式と違い、債券は元本が戻ることを重視しますが、発行体の信用状態が悪化すると価格が下がることがあります。
この例を見て、どういう組み合わせが自分の目的に近いかを考えましょう。
最後に、自分の投資目的、期間、生活費の安定性を考慮して選択することが大切です。
公債について友達とカフェで話すときの雑談風の深掘りです。公債は政府が資金を調達するための約束の紙のようなもので、利回りは低めでも安全性が高い。対して社債は企業が資金を調達するための手段で、利回りは高めだがデフォルトのリスクもある。つまり、私たち投資家が「安全と利回り、どちらを取るか」という選択を迫られる場面が生まれる。僕がもし友だちなら、まずはリスクを分散することをおすすめする。公債と社債を組み合わせれば、安全性と収益性の両方をちょうどよく保てる。今の教育費や将来の旅行費用を見据え、現実的な目標に合わせて配分を変えるのが大切だ。