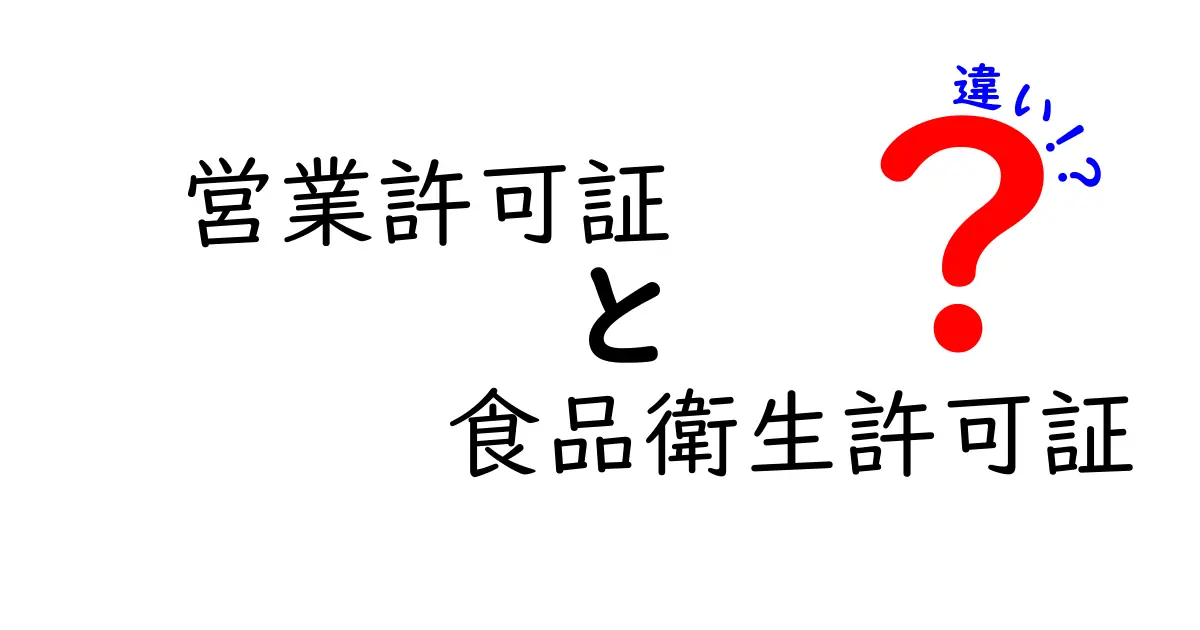

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:営業許可証と食品衛生許可証の基本を押さえよう
飲食店を開くときには必ず知っておきたい法律の仕組みがあります。営業許可証と食品衛生許可証は名前が似ていますが、役割や対象が異なります。
まず、営業許可証は店舗の場所や業態そのものが営業して良いかを判断する許可で、都道府県の行政機関が審査します。施設の衛生設備、排水、衛生管理体制、従業員の教育などが主な審査項目です。
一方、食品衛生許可証は食品を「製造・加工・販売・提供する過程」に関する衛生管理を審査するものです。食品を扱う工程の衛生管理マニュアル、温度管理、原材料の保管方法などの適切さを確認します。発行元は地域によって呼び方や運用が異なることがありますが、両方とも保健所や知事部局が関わる点は共通です。
この2つは別物ですが、実務上は両方が必要になるケースが多いため、混同せずに正しく理解することが大切です。
次の章から、それぞれの違いを詳しく見ていきます。具体的な用途がどう異なるのか、どんな場面で申請が必要になるのか、取得の流れや注意点を丁寧に解説します。読者のみなさんが開業前に困らないよう、実務で役立つポイントを優先して紹介します。
違いを整理:具体的な用途と取得条件・実務の違い
営業許可証と食品衛生許可証は、それぞれの対象と目的が異なります。
まず営業許可証は店舗そのものの「場所と業態」を基準に審査され、店舗の敷地、設備の配置、衛生管理体制、従業員の衛生教育がチェックされます。レストランやカフェ、惣菜店など、日常的に調理・提供を行う施設が対象です。発行元は都道府県知事または保健所で、店舗の開業許可を最優先に扱う制度と言えます。
対して食品衛生許可証は食品そのものの取り扱い過程に焦点を当て、製造・加工・販売・提供の工程での衛生管理を審査します。特に生鮮食品の加工や弁当・デリカテッセンの加工ライン、製造所などで必要となり、温度管理・衛生教育・原材料管理・清掃頻度などが審査項目に含まれます。発行元は同じく都道府県知事や保健所ですが、対象が「食品の取り扱い工程」になる点が大きな違いです。
実務上の典型的な組み合わせとしては、新規に店舗を開く場合、営業許可証の取得と同時に食品衛生許可証の対象区分の審査を受けることが多いです。これにより、店舗としての営業可否と食品の衛生管理が同時に確認されます。以下の表を使えば、両者の違いを一目で把握できます。
このように両者は“場所の許可”と“食品を扱う工程の衛生管理”という切り口の違いがあります。どの業態で何を扱うかを整理したうえで、必要な申請を漏れなく進めることが大切です。地域によっては細かな運用が異なることもあるため、実際には地元の保健所へ確認することを強くおすすめします。
次の章では、取得の実務的な流れと注意点を具体的に紹介します。
実務の流れと注意点:申請のステップとよくあるミス
申請の基本的な流れは概ね同じですが、地域の窓口によって手順や必要書類が異なる場合があります。まず現地の保健所に電話で相談し、現地のチェックリストを入手します。次に、施設の図面や設備の写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)、衛生教育の実施予定、厨房の設備清掃計画などを整えて提出します。審査には通常数週間かかることが多く、設備の小さな不備」が見つかると再申請を求められることもあります。
申請が受理されると検査員が現場を訪問し、衛生管理の実践を確認します。ここでのポイントは従業員の衛生教育が定期的に行われているか、温度管理が適切か、原材料の保管方法と清掃の徹底などの実務を、誰が見ても分かる形で整備しておくことです。
最終的な許可証の交付後も、定期的な衛生教育の実施や設備の点検を怠らないことが長期的な経営の安定につながります。よくある質問と答えをいくつか挙げておくと、改装後の再申請の有無や取得費用の目安など、現場の体感と法的要件のギャップを埋めるヒントになります。
したがって、開業を目指す人は事前の準備として「場所の種類と取り扱い食品の区分」をしっかり整理し、地域の窓口の案内に沿って手続きを進めることが重要です。
食品衛生許可証の話題って、友人とカフェの話をしているときにふと出てくる小ネタです。私が以前、友達と話していたとき、彼は厨房の衛生チェック表を見て呟きました。『味は良くても衛生がダメなら店は成り立たないんだね』と。実際、食品衛生許可証は単なる形式ではなく、温度管理や手袋の使用、清掃の頻度など現場の“日常”を正しく回すためのルールそのものです。私たちが普段口にする料理の裏側には、こうした衛生の工夫がたくさん潜んでいます。たとえば、野菜を洗う前の手洗い、冷蔵庫の温度設定、器具の分別洗浄など、目に見えないところで店の安全性が守られているのです。だからこそ、食品衛生許可証を持つことは安心して食事を楽しむための基本でもあります。現場での些細な配慮が、みんなの健康を支える大切な柱になるのです。





















