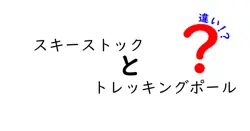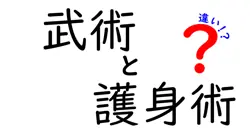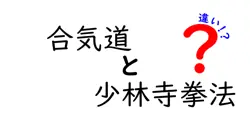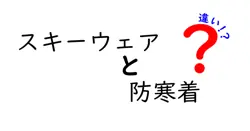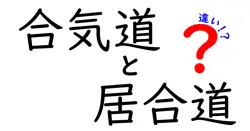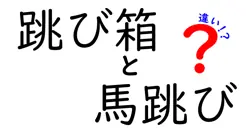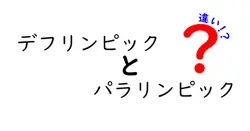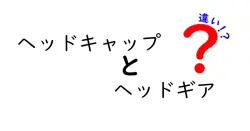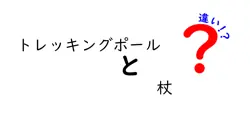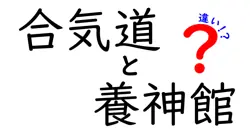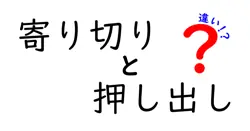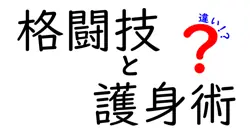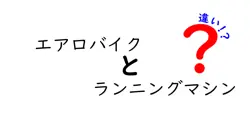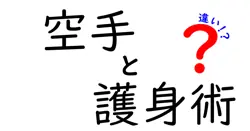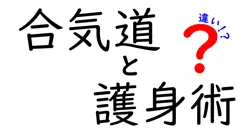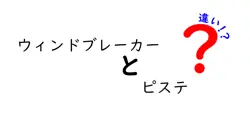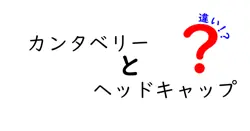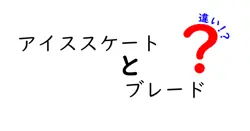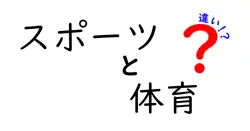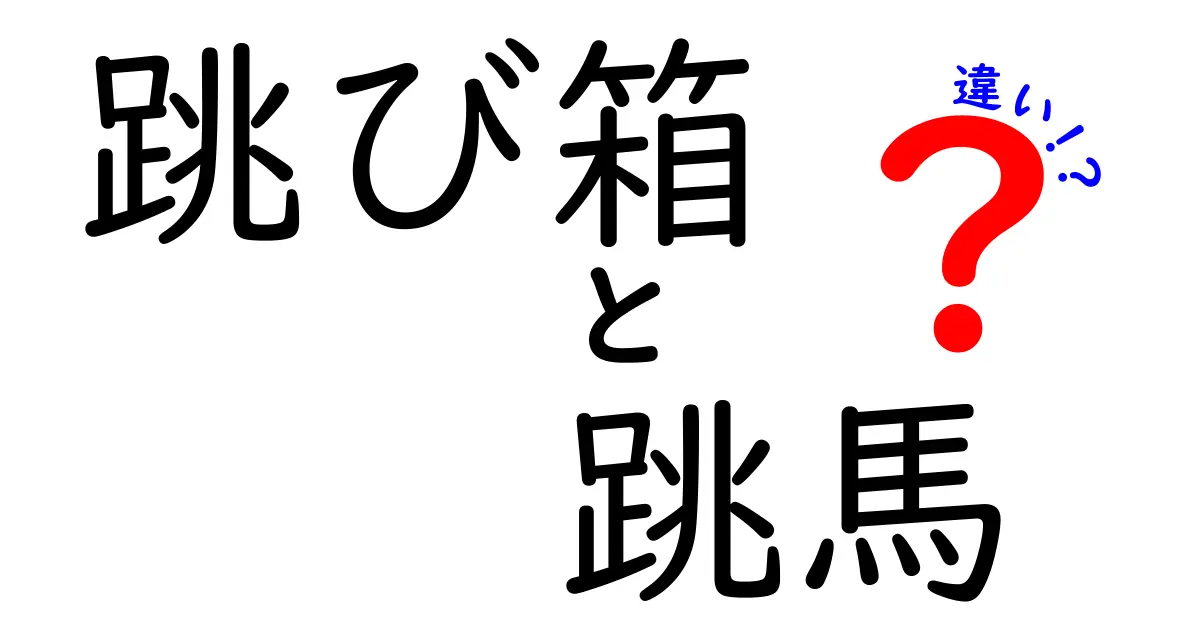

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
跳び箱と跳馬の違いを徹底解説!授業・競技・練習で困らない見分け方と練習のコツ
学校の体育でよく登場する跳び箱と跳馬。名前は似ていますが、目的と使い方がかなり違います。跳び箱は箱状の器具を使って“跳ぶ”動作を練習するもので、足元の安定性と着地の柔らかさを中心に鍛えます。箱の高さを段階的に変えることができ、低い段から始めて徐々に難易度を上げられるのが特徴です。
対して跳馬は鉄製の馬の形をした器具で、両手をバーのように地面につけて体を支えながら回転・蹴り上げ・止める技を練習します。両手の位置、体幹の安定、腕の力が特に重要で、跳び箱よりも高度なバランス感覚と連動性が求められます。
この違いを知っておくと、体育の時間に自分に合った練習を選ぶヒントになりますし、競技会や発表会で観察する際の視点も広がります。
また、練習の場面で必要となる安全対策も大きく異なります。跳び箱は床とマットの組み合わせで安全性を確保しやすく、段階的な高さ設定と柔らかい着地を意識します。跳馬は高さがあり、手首や肘、肩への負担を防ぐために補助具とマットを適切に配置することが大切です。これらのポイントを理解しておくことで、練習中の怪我リスクを減らし、効率的に技術を積み上げられます。
以下のポイントを押さえると、違いがさらにはっきりします。
1) 目的の違い:跳び箱は踏み切りの力と正確な着地を鍛えるのに適しており、跳馬は体幹と上半身の安定性を鍛える技術練習が中心です。
2) 器具の形:跳び箱は箱状の段階的な高さ、跳馬は馬の形をした水平のバーに近い形です。
3) 練習の順序:跳び箱は基本動作→応用動作、跳馬は基礎→高度な技へと段階的に進めます。
この順序を守ると、体の反応と動作の連携が自然に身についていきます。
道具の形と使い方の違い
跳び箱は箱状の器具が連結され、段階的に高さを変えられるのが特徴です。子どもは低い段から始め、距離感と着地の感覚をつかみやすい設計になっています。跳ぶ動作は「足をそろえて真っすぐ飛ぶ」基本形と、「蹴り上げて回転を取り入れる」難易度の高い形の2系統に分かれます。
跳馬は幅の狭い馬のような器具で、両手を地面につけて体を支えながら技を作り出します。手の位置や腕の角度、体幹の動きがダイレクトに結果に影響するため、基本動作の安定を最優先に練習します。高さは跳び箱よりも変化が大きくなることが多く、補助具とマットの活用が欠かせません。これらの違いを理解しておくと、授業やクラブでの練習計画を自分で考えやすくなります。
さらに、安全第一の観点で、跳び箱は床面の状態を整えること、跳馬は手首や肩の負担を減らす準備体操を徹底することが大切です。練習の前後には必ずウォーミングアップとクールダウンを行い、痛みを感じたら無理をせず指導者に相談しましょう。こうした基本を守ることで、体の動きの美しさと技の安定性が同時に高まり、体育の授業や部活練習がより楽しくなります。
友達と体育館で跳馬の話をしていたとき、意外にも跳馬の難しさは“高い場所に手をつくという単純さの裏にある細かなコツの積み重ね”だという話題になりました。跳び箱のように箱を越える爽快感だけではなく、跳馬では手の置き方、体幹の支え方、回転のタイミングなど、地味だけれど失敗の許されない要素が多いのです。だからこそ、初めは基本の姿勢と安定感をじっくり練習してから、徐々に難しい技へと移るのがコツだと感じました。設備や指導者のアドバイスを味方にして、一歩ずつ着実にレベルアップしていくのが楽しい発見でした。跳箱派の友達と情報を交換するうち、見方が広がり、体育の時間がますますおもしろくなる予感がします。こうした日常の小さな発見が、スポーツの楽しさを深めてくれるのだと実感しました。