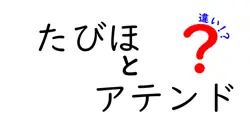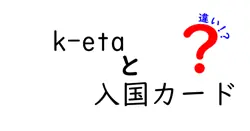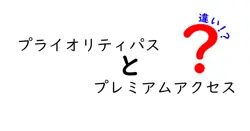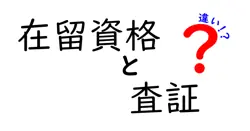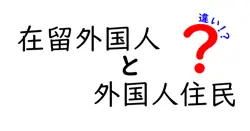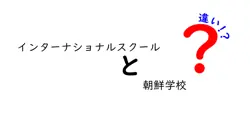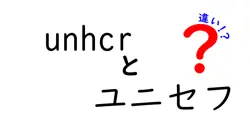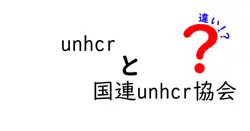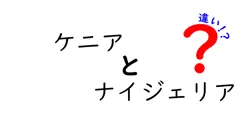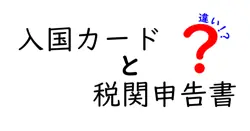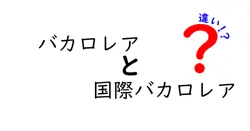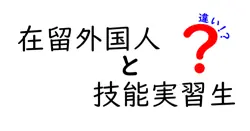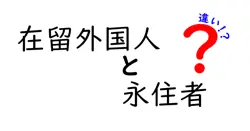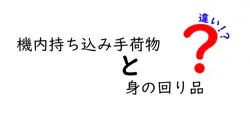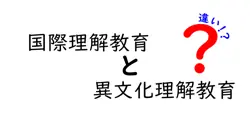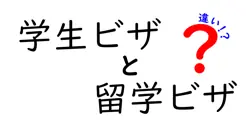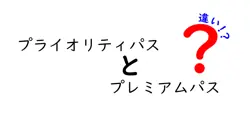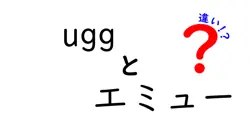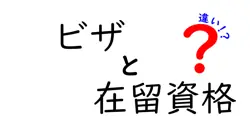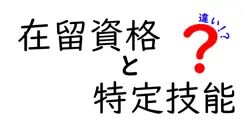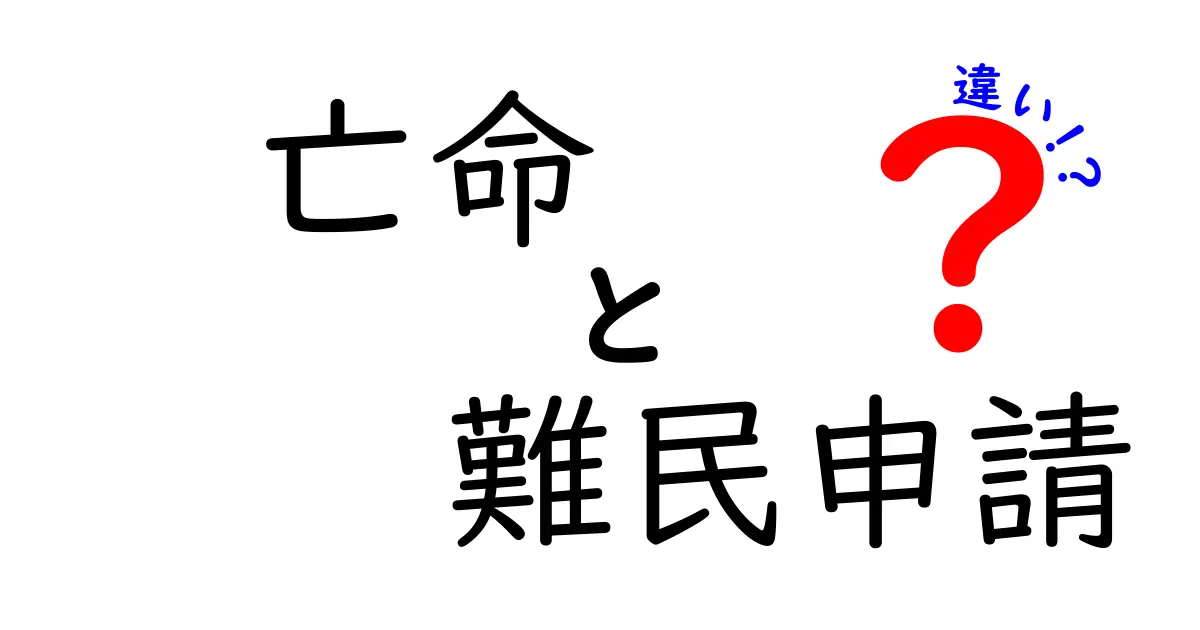

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:亡命と難民申請の違いを正しく理解する
近年、日本を含む世界各地で人々の移動が活発になっています。ニュースでよく耳にする「亡命」や「難民申請」という言葉も、実は意味が異なります。亡命は個人が自分の国の政権や社会体制からの迫害を逃れるために国外へ逃げ出すこと、そしてその人が自分を保護してくれる国へ受け入れてもらうことを指します。一方、難民申請はその人が「自分は難民だ」と認定されるよう、正式にその国の機関に認定を求める手続きのことです。申請には条件や手続き、審査の流れがあり、必ずしも認定されるとは限りません。
この二つは似ているようで、制度の仕組みや申請の場面が異なるため、混同しないことが大切です。以下では、基本的な意味から実務上の違い、手続きの流れ、注意点まで、分かりやすく解説します。
まず大切なのは、どちらも人の尊厳と安全を守るための国際的な仕組みであるという点です。亡命は迫害を避けるための「逃げる理由と逃げ場所の確保」の話、難民申請はその逃げた人が正式に「難民として保護を受ける権利があるか」を判断してもらう手続きの話です。ここを理解すると、ニュースで聞くケースの意味がずっと分かりやすくなります。
亡命と難民申請の基本的な意味と違いを整理する
まず、それぞれの言葉の意味をしっかり分けておくことが大事です。亡命は、個人の行為とその背景を指す名詞的な語です。難民申請は、政府や国境警察、移民当局などが実際に行う手続きの名称です。簡単に言えば、亡命は「逃避の行為」、難民申請は「保護を求める手続き」という二つの側面を持っています。
また、亡命をして国外へ出る人が全員すぐに難民として保護されるわけではありません。難民認定には審査があります。審査の結果、難民としての保護を受けられると判断されれば、在留資格や生活支援が提供されることがあります。一方、審査の結果が不認定なら、状況に応じて他の在留資格を探すか、国外退去を求められることもあります。
このように、亡命は「逃げる理由と場所の選択」、難民申請は「保護を正式に求める手続き」という違いを押さえると、実務的にも混乱を避けやすくなります。以下の段落では、具体的な違いをさらに詳しく、実務的な観点から説明します。
実務上の違いと流れ:申請と認定のステップを理解する
実務的には、まず亡命の意思と理由を整理して、国外へ出る前後の事情を確認します。次に、受け入れ国の難民申請窓口へ申請します。申請には、身分証明、出入国の記録、迫害の具体的事例、証拠となる資料などが必要になることが多いです。
難民申請の審査は、専門の審査官が個々のケースを検討します。審査には数か月から数年かかることもあり、結果として難民認定、不認定、補完的保護などの判断が下されます。補完的保護は、難民として認定されない場合でも一定の保護を受けられる制度を指します。ここで重要なのは、審査結果は個別ケースごとに異なるという点です。
また、申請中は生活費の支援や就労の可否など、現地の生活事情にも大きく影響します。申請国や地域によって制度が異なるため、正確な情報は現地の専門機関や弁護士、NPOなどに相談するのが安全です。
比較表で見る亡命と難民申請の違い
以下は、主要な違いをわかりやすく並べた表です。
この表は、実務の概要をつかむための目安として読んでください。正確な制度設計は国ごとに異なるため、具体的なケースでは専門機関の案内を優先してください。
実務での注意点とよくある質問
実務的な注意点としては、申請時期の遅延を避けること、必要書類を揃えること、真実性を保つことが挙げられます。虚偽の申請は後日撤回されるだけでなく、今後の保護の機会を失う原因にもなり得ます。
また、言語や文化の違いが審査の理解を難しくすることがあります。この場合、信頼できる通訳者や支援団体のサポートを受けると良いでしょう。よくある質問としては、「難民認定を受けられなかった場合の選択肢は?」「申請中の就労は認められるのか?」などがあります。これらは国ごとに制度が異なるため、現地の法律専門家に具体的なアドバイスを求めることが重要です。
まとめ:亡命と難民申請の違いを正しく理解して行動する
亡命と難民申請は似ているようで、意味と手続きの点で大きく異なります。亡命は逃げる行為と場所の選択、難民申請は保護を求める正式な手続きです。実際の流れでは、申請の準備、申請の提出、審査、結果に応じた対応というステップが続きます。子どもや家族を守るためにも、正確な情報を得て、安心して判断できるようにしましょう。最後に、制度は国によって変わるため、最新の公式情報を必ず確認してください。
ある日の放課後、友だちのミナとニュースを見ていた。ミナは難民申請のニュースを見て「難民になるってどういうこと?」とつぶやく。私は、亡命と難民申請の違いをもう少し分かりやすく伝えようと、紙に図を書き始めた。亡命は“逃げる理由と場所の選択”の話で、難民申請は“保護を求める手続き”の話だと説明した。図には、逃げる動機、出発・到着手続き、審査の流れ、認定の有無、支援の有無を矢印付きで描いた。ミナは「自分がもし外国で安全を求める立場だったら、何を信じて進むべきか考えるきっかけになった」と言ってくれた。私は、難しそうな制度も、しっかりした言葉の意味を知れば身近に感じられると気づいた。学校での話題にもできそうだ。