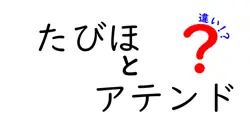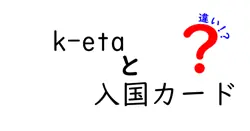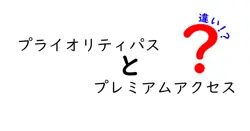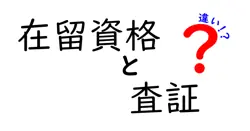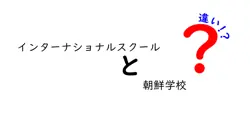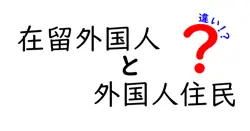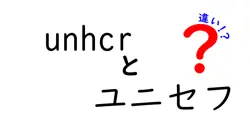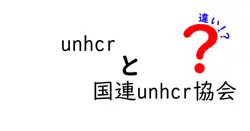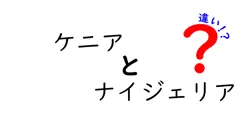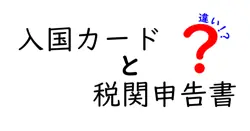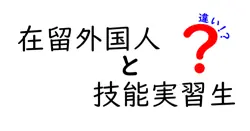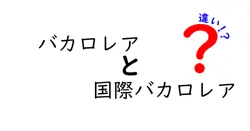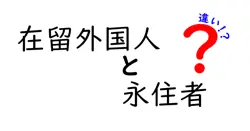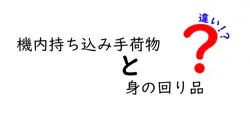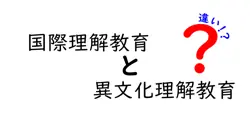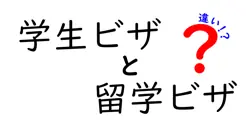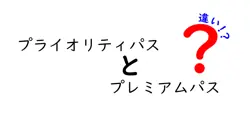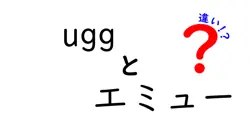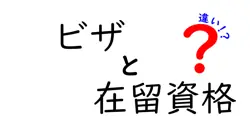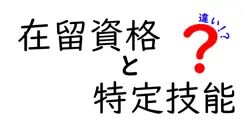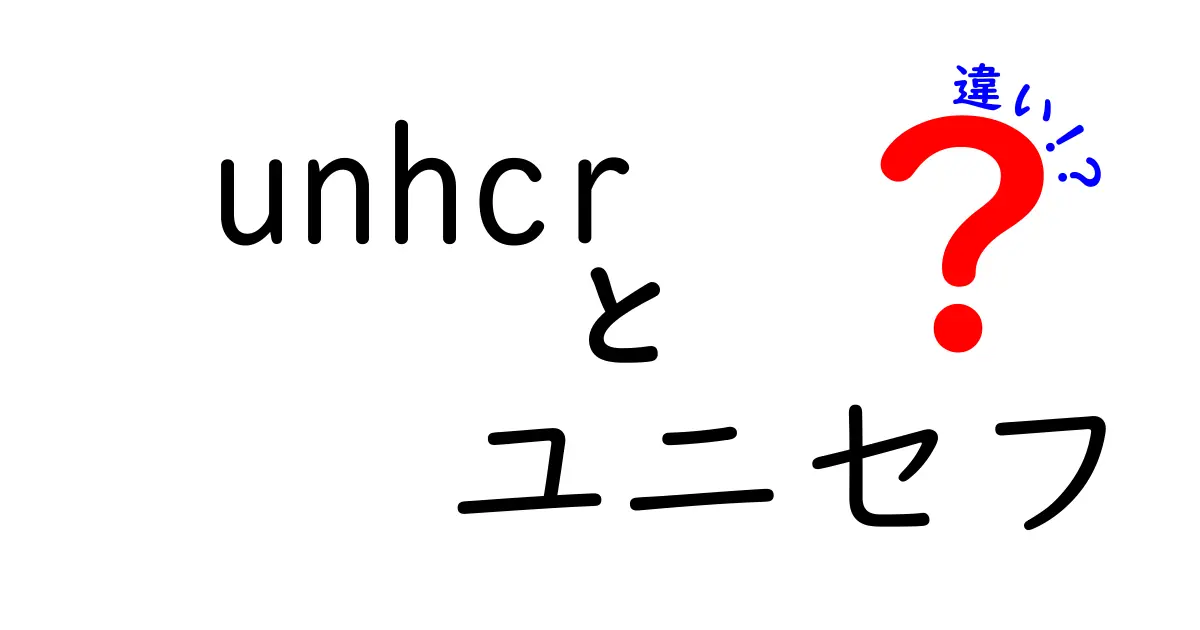

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
UNHCRとユニセフの違いを知ろう:基本のポイント
国際的な人道支援の世界にはさまざまな機関がありますが、その中でも UNHCR と UNICEF は特に有名です。この二つはよく混同されがちですが、役割や対象が根本的に異なります。
UNHCR は難民や迫害から逃れた人々の保護と安全の確保を第一にする機関です。彼らは難民の居場所を探し、危険から逃れる権利を守るための法的枠組みを作り、避難生活の支援を提供します。
一方で UNICEF は 子どもの権利と福祉 の促進を専門とする機関で、教育・予防接種・栄養改善・衛生設備の整備など、子どもの健やかな成長を長期的に支える活動を展開します。
この二つは紛争地域や災害現場で協力することが多いものの、対象と主な任務が異なるため、ニュースを読んだときに「誰が何を守ろうとしているのか」を分けて考えることが大切です。
要点まとめ:UNHCR は「難民の保護と庇護提供」が主な任務、UNICEF は「子どもの権利の実現と教育・健康の保障」が主な任務です。
1) 対象と使命の違い
UNHCR の本質は 難民と庇護を求める人々 の保護と安全の確保です。彼らは紛争や迫害の結果、故郷を離れざるを得なかった人々を救うための法的枠組み作りや避難の手続き支援を主な任務とします。難民だけでなく 無国籍者 や一時的な避難民も対象に含めることがあります。長期的には帰還や第三国移住の準備、生活再建の機会を見つけるサポートを提供します。UNICEF は すべての子ども の権利と幸福を守ることを第一に掲げ、教育、衛生、栄養、緊急支援のアクセスを確保します。
したがって「誰を救うのか」という根本的な視点が違うのです。
2) 活動の現場と資金源の違い
UNHCR は紛争地域や災害時の難民キャンプでの安全確保、避難体制の整備、帰還の計画づくりなどを現場の第一線で行います。資金は主に政府の拠出金や公的資金によるボランティア性の寄付と、民間の寄付が混ざる形で賄われます。UNICEF の場合は、子どもの教育・保健・栄養に直結するプログラムを現場で展開し、学校の建設・教員の訓練・ワクチン接種・栄養プログラム等を担います。資金源は政府からの拠出だけでなく、世界中の企業や個人からの寄付やパートナーシップも大きな比重を占めます。これらの違いは、実際の活動のスケール感や優先順位にも影響します。
3) 連携と成果の見え方
現場では UNHCR と UNICEF はしばしば協力しますが、それぞれの成果は異なる指標で測られます。UNHCR は 「避難生活の安全確保」「法的保護の提供」「durable solutions(恒久的解決)」 を中心に評価します。難民の数、難民キャンプの生活水準、第三国移住の進捗などが指標です。UNICEF は 「教育の普及」「ワクチン接種率」「栄養改善」「衛生設備の利用状況」 など、子どもの日常生活に直接影響する指標を重視します。現場での協力は、避難所の設営だけでなく、学校の再開、保健医療体制の強化、子どもの心のケアなど、人生の発展段階に合わせて連携します。
4) すぐに役立つポイントと日常への落とし込み
ニュースの向こう側の話と思わず、私たちにもできることを考えましょう。まずは 難民の人々の尊厳を尊重する言葉遣い を心がけ、必要なときは公式な情報源から正確な情報を得ることが大切です。次に 教育や衛生の重要性 について学び、信頼できる団体への寄付やボランティア情報を知ることも役立ちます。子どもを守る UNICEF の視点は、私たちの家庭や学校でも取り組める実践につながります。これらの動きを通じて、国や組織を超えた連携が生まれ、難民を取り巻く困難を少しずつ軽くする力になるのです。
今日は難民というキーワードを深掘りします。ニュースで難民と聞くと遠い世界の話に感じるかもしれませんが、実は私たちの身近にもつながる話です。UNHCR は難民の安全と保護の仕組みを作る支援、UNICEF は難民の子どもが学校へ行けるようにする支援をそれぞれ担います。この二つの動きが組み合わさると、難民の子どもが安心して学べる日が近づきます。私たちにできる小さな一歩は、正確な情報を学び、寄付やボランティア情報を知ること。難民の現場は遠い世界ではなく、私たちの選択一つで支援が広がる現場なのです。