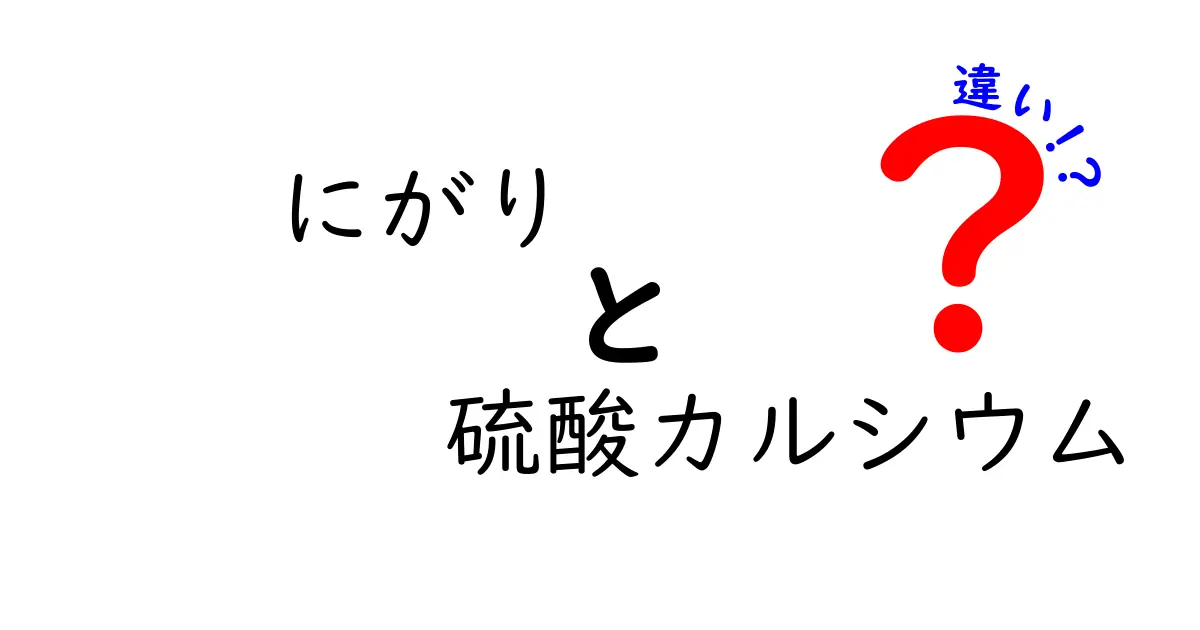

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
にがりと硫酸カルシウムの違いを理解する
まず押さえておきたいのは、にがりと硫酸カルシウムは“豆腐を固めるための塩のような役割”を持つものですが、成分がまったく異なる点です。にがりは海水から取れる塩化マグネウムを主成分とする水溶液で、MgCl2を中心にいくつかのミネラルを含んでいます。硫酸カルシウムは gypsum(石膏)として知られ、主成分はCaSO4です。
この基本的な成分の違いが、豆腐の固まり方や食感、風味に直接影響します。
次に大事なのは「なぜ二つの成分が使われるのか」という点です。にがりにはマグネシウムのほか微量のカルシウムなどが含まれており、豆腐の水分を適度に保ちつつ滑らかな口当たりを作ります。硫酸カルシウムはCa2+を多く供給するため、豆腐のネットワークをしっかり作りやすく、密度のある豆腐を作るのに向いています。これらは好みや用途、作り方の違いによって使い分けられます。
さらに、味の違いも無視できません。にがり由来の豆腐はわずかに風味が強く感じられることがあります。一方、硫酸カルシウムの豆腐は無味に近いと表現されることが多く、料理の味を邪魔しにくいという特徴があります。家庭では粉末状や液体状の凝固剤を手に入れやすく、使い方次第で食感を変えることができます。
このように、成分の違いと使い方のコツを知ると、目的に合った豆腐づくりがしやすくなります。
成分の正体と役割
この章では、にがりと硫酸カルシウムの成分の違いがどう豆腐に影響するかを詳しく見ていきます。にがりの主成分は MgCl2 で、海水由来のミネラルと結びついています。Mg2+ はたんぱく質の網目を柔らかく作る性質があり、豆腐を口の中でほどけるような滑らかな食感に導くことが多いです。さらに、水分の保持にも影響し、内部の孔の大きさが食感に影響します。
これに対して硫酸カルシウムは CaSO4 で、Ca2+ を多く提供します。Ca2+ はタンパク質同士を結びつける力が強く、豆腐のネットワークをしっかり形成します。その結果、密度が高く、切り分けやすい“しっかり系”の豆腐が作られやすくなります。
また、結晶構造の違いが水分保持にも影響します。にがりを使うと中心はしっとり、外側は少し弾力を感じることが多く、硫酸カルシウムを使うと外側がややしっかりして、中は密度の高いネットワークになる傾向があります。製造条件(凝固温度、溶液の濃度、豆の処理方法)次第で、同じ材料でも食感は大きく変わります。
こうした性質を理解することで、家庭の台所でもさまざまな豆腐を楽しめるのです。
日常生活での使い分けと注意点
家庭で豆腐を作るときは、どちらを使うかによって食感や仕上がりが変わります。滑らかな口当たりを好むならにがり寄りのレシピ、しっかりとした固さを出したい場合は硫酸カルシウム寄りのレシピを選ぶとよいでしょう。市販の凝固剤の表示を確認し、分量や水の温度を守ることが大切です。初めての場合は少量から試してみて、家族の好みの食感に近づけるのがコツです。
また、Ca2+の過剰摂取を避けたい場合は、使用量を調整したり、別の凝固剤と混ぜて使う方法もあります。安全性の点ではどちらも適切に扱えば問題ありませんが、保存状態には注意しましょう。
最後に、豆腐づくりは“科学と手作業の両立”です。温度管理、混ぜ方、凝固のタイミングを工夫することで、家庭のキッチンでも専門店に近い味わいを楽しむことができます。
koneta: にがりと硫酸カルシウムの話題を、友達どうしの会話風に深掘りしてみます。A「にがりって海の成分だよね。マグネシウムが多いんだって?」B「そう。マグネシウムは豆腐の網目をやさしく作るから、口の中でとろける感じになるんだよ。それに比べてCaSO4、石膏みたいなやつはカルシウムが多いから、ぐっと固めのネットワークを作るんだ。どっちがいいかは好みや料理次第。」A「ふむ。じゃあ、僕は滑らかな方が好きだからにがり寄りのレシピにしてみるよ。」B「了解。実験感覚で少しずつ量を変えて、自分だけの理想の豆腐を探すのが楽しいよね。」





















