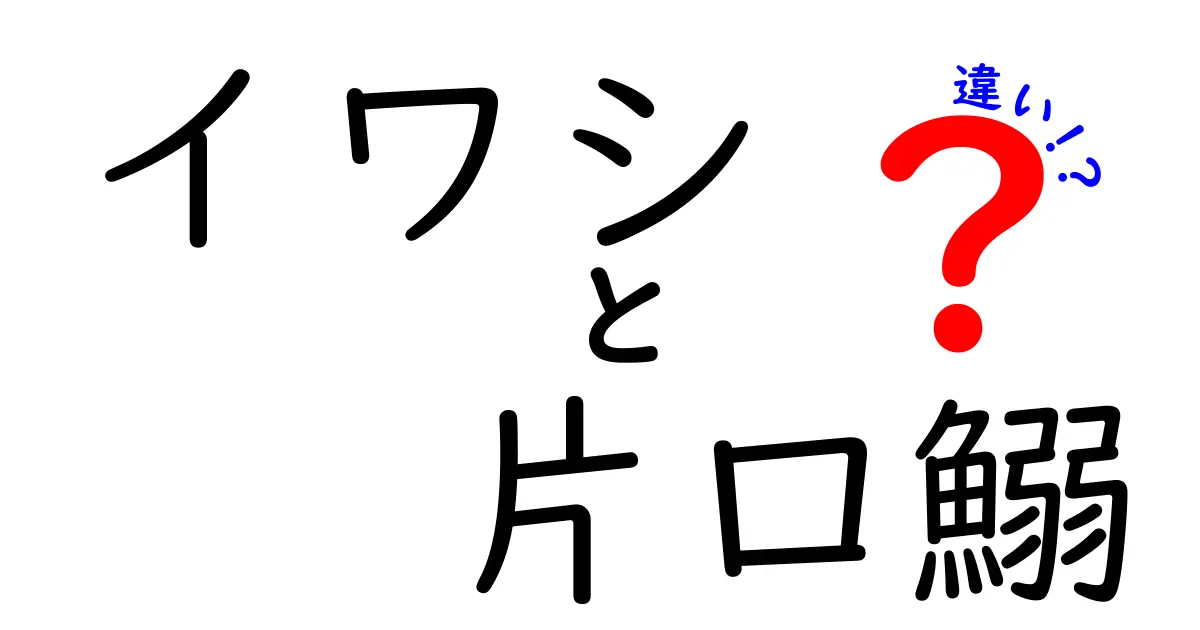

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
イワシと片口鰯の違いを理解する基本
ここでは「イワシ」と「片口鰯」という言葉の違いを、日常の料理や市場での呼称の面から解説します。
まず大切なのは、イワシは魚のグループを指す総称であり、日本語の家庭でもよく使われる一般名です。
一方で、片口鰯(読み方は「かたくちいわし」)は市場や料理現場で使われる、より具体的な呼称のひとつです。地域や漁法、流通の仕方によって、同じ魚を別の名前で呼ぶこともあります。つまり、「イワシ」=総称、「片口鰯」=特定の仲間または形・季節・用途で使われる名称という風に理解すると、混乱が少なくなります。以下の表を見れば、ざっくりとした違いがつかめます。
この表だけでも、どの語がどんな魚を指しているのかの基本が分かります。
とはいえ、現場では地域の言い方が大きく影響します。例えば市場で「片口鰯」と表示されていても、それが実際には「真いわし系の小さな魚」を指すことがあります。「呼び分けは地域と流通次第」と覚えると混乱を避けられます。さらに、旬の時期や漁法の違いによって同じ魚でも名前が変わることがあるのです。
料理の観点から見ると、使い分けは主に調理法と用途で決まることが多いです。
たとえば、塩干しや煮付け、佃煮などは片口鰯として扱われやすく、刺身や缶詰はイワシの名の下で売られることが多いです。これは味の濃さや骨の柔らかさ、脂の乗り方などの違いが関係します。
市場での呼名と料理の実例
現場での呼称の違いは、味や使い方にも影響します。以下の視点で見ると、何を買えばよいかが見えてきます。
・味の印象:イワシと片口鰯では脂ののり方が微妙に違うことがあり、焼き物や煮付けの仕上がりにも影響します。
・調理法の適正:塩干しや佃煮、煮付けには片口鰯が選ばれることが多く、刺身・缶詰・揚げ物にはイワシの名で販売されることが多いです。
・地域差:同じ魚でも地域ごとに名前が異なるケースがあり、同じレシピでも名称の表記が変わることがあります。
・季節と価格:漁獲状況により、同じ魚でも価格が変動しますので、予算や旬を考えて選ぶとよいです。
- 生のまま刺身で食べるなら、名称表記を確認してから購入する。
- 干物や塩焼きには、脂の量や骨の硬さを考慮して選ぶ。
- 煮付けや佃煮には、身離れの良さと火の入りやすさをチェックする。
このように、呼称の違いに加え「用途・調理法・地域差・季節感」が絡むと、選び方が格段に分かりやすくなります。
正しい理解と現場の実例を結びつけることが、失敗の少ない買い物と美味しい料理への近道です。
友人と海辺を歩いていたある日のこと。「片口鰯って、どう違うの?」と尋ねられたので、私は市場の呼称と料理の現場の話を交えて説明しました。イワシは魚の総称で、複数の種類を指す一方、片口鰯は市場や料理現場で使われる“固有名に近い呼び名”の一つと伝えました。地域や季節で意味が揺らぐこともあるため、結局は現場の流通と用途で判断するのが実践的だと伝えました。その日の帰り道、同じ魚が別の名前で呼ばれる場面をいくつも見つけ、私たちはやさしい言葉の成り立ちをめぐる雑談を楽しみました。日常の観察こそ、言葉と食の理解を深める最高の教材だと実感した瞬間でした。
この話を通して「イワシ=総称」「片口鰯=特定の呼称」という基本を押さえつつ、現場の実例を思い浮かべる練習をしてほしいと思います。地元の市場や家庭料理のレシピ帳を手に取って、同じ魚がどんな場面でどう呼ばれているかを探してみてください。名前の違いが、味わい方のヒントになることも多いのです。
次の記事: かつおとろかつおの違いを徹底解説!見分け方と美味しい食べ方 »





















