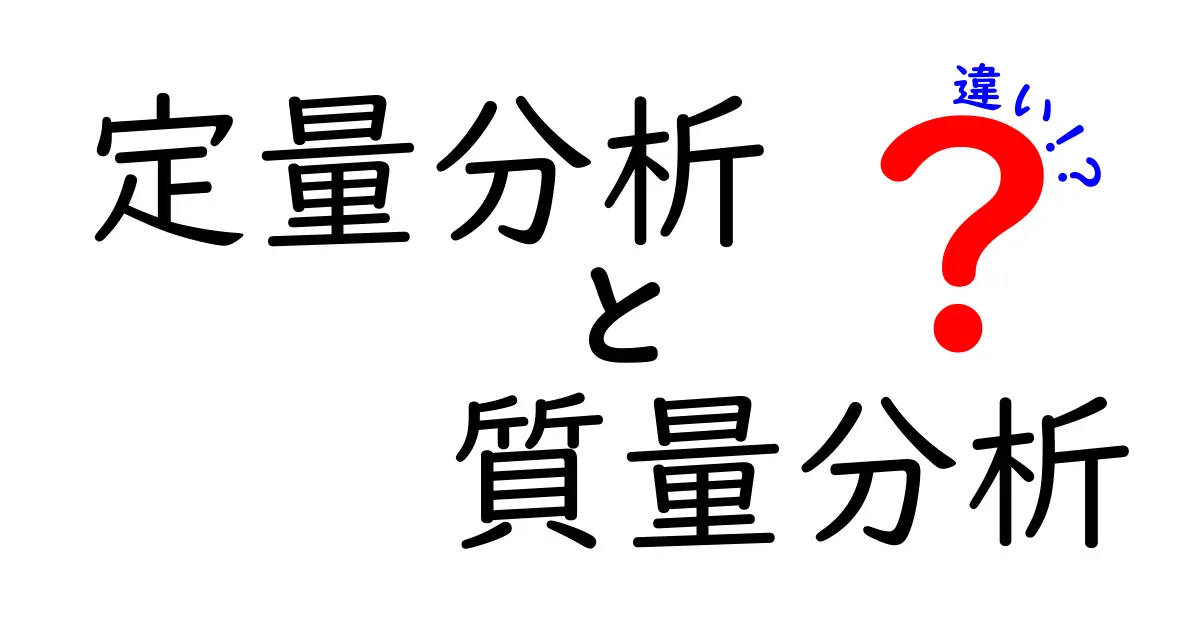

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
定量分析と質量分析の違いを徹底解説:基礎から使い分けまで
この二つの分析は、科学の世界で最も基本的な考え方を学ぶ入口です。定量分析と質量分析、どちらも"何かを測る・調べる"という点で重要ですが、実際には知りたい情報が違います。
この記事では中学生にも分かりやすい言葉で、それぞれの意味・目的・実務での使い分けを丁寧に解説します。
まずは両者の基本から押さえ、次に身近な例で差を見せ、最後に実践的な選び方をまとめます。
読み進めるうちに、同じ“分析”という言葉でも、何を知りたいかによって道具や方法が変わる理由が理解できるはずです。
定量分析は、“量を正確に測る”ことを目的とします。
果物ジュースの糖分濃度を測る、野菜の水分量を決める、薬の濃度を確かめるといった場面で使われます。
このときは、標準と呼ばれる基準と比較して、どれくらいの量があるかを数値で表します。
結果は通常、濃度・含有量・割合といった形で報告され、誰が測っても同じ数値になることが求められます。
この性質を「再現性が高い」といいます。
質量分析は、“物質の質量と構造を読み解く”ことを目的とします。
試料をイオン化して、重さの比(質量と荷電の関係、m/z)を測定することで、未知の物質が何なのかを推定します。
分子量を知る手掛かりになり、同じ分子でも異なる構造の可能性を見分けたり、化合物の同定に強い力を発揮します。
実験室では薬の安全性評価や食品の成分解析、環境分析など、さまざまな場面で活躍します。
なお、質量分析は定量的な結果を得ることも可能ですが、その場合は別の手法と組み合わせることが多いです。
この二つの分析は、目的が違うだけでなく、必要なデータの性質も異なります。
定量分析は「数量そのもの」を知るためのツール、質量分析は「物質そのものを同定・特徴づけるためのツール」です。
現場の研究者は、知りたいことに合わせて、どちらを使うか、あるいは両方を組み合わせて使うかを決めます。
学習のコツは、まず具体的な目的を決め、それぞれの手法がどんな情報を返してくれるのかを一つずつ紐づけて覚えることです。
定量分析とは何か?基本の意味と目的
定量分析は、その名の通り「量を測る」ことに特化した分析です。目的は量を数値で表し、比較・評価・決定に使えるようにすることです。
たとえば食品の糖分、飲料の塩分、環境中の特定成分の濃度など、さまざまな場面で用いられます。
測定には、標準物質という基準を準備し、それに対する対象の信号を読み取って量を決定する方法が一般的です。
結果は濃度、質量分率、含有量などの形で表現され、再現性と正確性が評価の要となります。
このため、機器の校正・標準曲線の作成・データの処理方法が特に重要なポイントです。
さらに、計測の過程では「どの機器を使うか」「どんな前処理を行うか」といった工程設計が、データの正確さを大きく左右します。
中学生の身近な例としては、家庭での糖度計を使った果物の甘さの比較と、研究室での高精度な濃度測定の間には、用いる道具と手順の違いがあると考えると理解しやすいです。
定量分析は、数値としての答えを厳密につくる力が魅力です。
質量分析とは何か?基本の意味と目的
質量分析は、物質の「質量」と「構造」を解き明かす強力な道具です。未知の化合物を同定したり、分子量を推定したりする場面で欠かせません。
代表的な流れとしては、試料をイオン化してから、質量分析計にかけ、生成したイオンの質量対荷電比を測定します。
結果として得られるスペクトラムには、どの分子がどんな質量をもつのか、どんな分解パターンが起こるのか、という情報が並びます。
この情報から、分子式の推定・構造の推測・未知物の特定が可能になります。
質量分析は機器の発達とともに進化しており、複雑な混合物の中から個々の成分を分離して同定する力を持っています。
また、LC-MS(液相色純と質量分析の組み合わせ)などの手法を使えば、同時に定量情報を得ることもできます。
未知のサンプルに対して、まず「何が入っているのか」を把握し、そのうえで必要な場合に量的測定を行う、という順序で進められるのが特徴です。
両者の違いを具体的に比較する表と要点
以下の表は、定量分析と質量分析の主要な違いを要点だけでも見やすく並べたものです。
ポイントごとに強調したい点を太字で示しています。
この表からも分かるように、定量分析は「量を、数値で」求めることに長けており、質量分析は「何者かを特定するための特徴を掴む」ことに向いています。
同じ実験でも、何を知りたいかによって使う道具が変わる点が最大の違いです。
実務での使い分けのコツと学習のコツ
実務では、最初に“何を知りたいのか”をはっきりさせることが大切です。
もし目的が「物質の量を正確に知ること」なら、定量分析を軸に計画を立てます。その際には標準曲線の作成、校正、測定の再現性の検証といった工程を忘れずに。
一方で「未知の物質を特定したい・分子量を知りたい」という場合には、質量分析を中心に据え、必要に応じて前処理や分離法(LCなど)を組み合わせます。
実務で重要なのは、分析の目的を明確にしたうえで、適切な機器・手法・データ処理を選ぶ判断力です。
この判断力は、授業・課題・部活動の研究計画の中で、少しずつ鍛えられていきます。
今日はこのテーマを雑談風に深掘りします。学校の実験室で友だちと話している感覚で、定量分析と質量分析の違いを一緒に探ります。まずは“何を知りたいか”を最初に決めることが大切だよ、という話から始めましょう。私たちは普段、数字を見て判断しますが、科学の現場では数字だけでなく背後の情報も大事。定量分析は“どれくらいあるか”を、質量分析は“何があるか”を教えてくれる道具です。時々、二つの方法を組み合わせると、より正確で深い理解が得られます。この雑談を通じて、迷ったときの判断材料が少し増えるといいなと思います。今後の学習や実験で、ぜひこの考え方を思い出してみてください。
次の記事: 試液と試薬の違いを徹底解説|用途別の使い分けと実務のコツ »





















