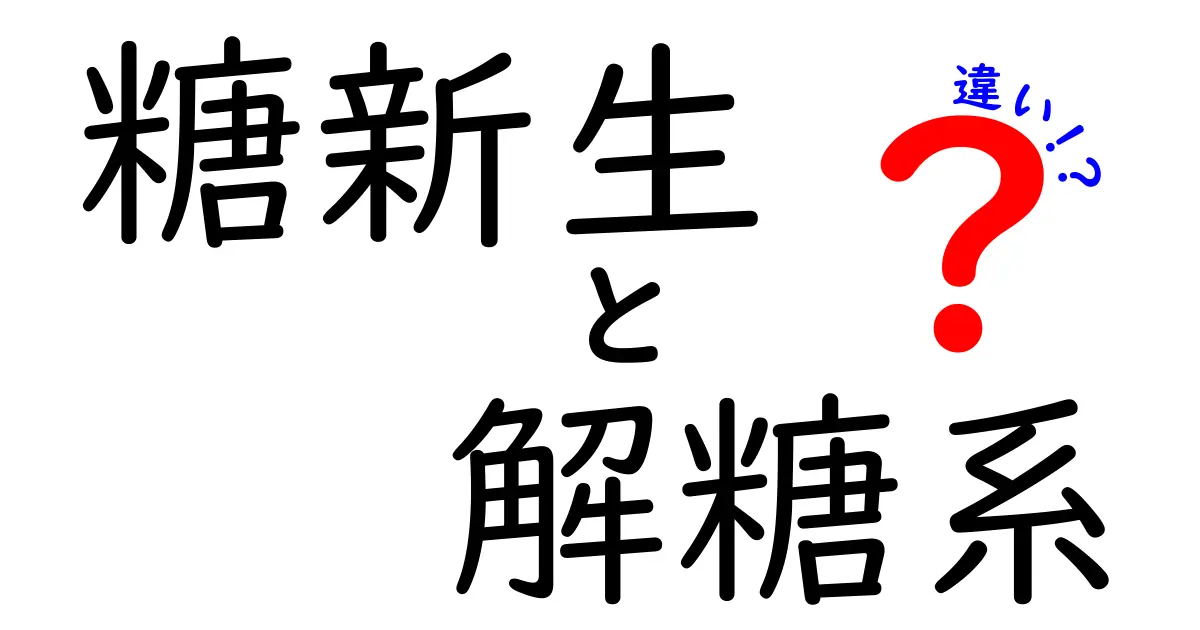

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
糖新生と解糖系の違いを理解するための基本
糖新生(gluconeogenesis)と解糖系(glycolysis)は、私たちの体がエネルギーを作り出すときに出会う「二つの道」です。大きな違いは、何を作るかとどの方向に進むかです。解糖系は糖を分解してATPを作る経路であり、細胞のほとんどの場所で起こります。結果として、ピルビン酸や乳酸ができ、少ない酸素でも進む(嫌気的)ことが特徴です。一方、糖新生は逆に「糖を作る」道で、主に肝臓や腎臓で起こります。体が空腹のときや、運動後の回復期に、グルコースを血中に供給する役割を担います。糖新生は多段階の反応から成り、いくつかの段階で解糖系と同じ中間体を使いますが、エネルギーの支出が大きいのが特徴です。例えば、グリセロールや乳酸、アミノ酸の一部を材料にして糖を作ることができます。糖新生と解糖系は、体の「燃料計画」を調整するチームのような関係で、常にバランスを取りながら動いています。普段は私たちが食べ物を摂ると解糖系が活発になり、空腹時には糖新生が働く—この切替えが、血糖値を安定させ、私たちの活動を支えています。ここまでの話で、“解糖系はエネルギーを作る道”、“糖新生はエネルギーを補充する道”という点が、頭の中に整理できるはずです。今後は、実際の反応の場所や、どんな酵素が動くかを見ていきましょう。
また、糖新生と解糖系の違いは、日常生活の話題にもつながります。例えば、長距離を走るときにはエネルギー源の切り替えが起こり、食事内容が血糖値に影響します。私たちの体はこの二つを使い分けて、動き続けられるように設計されているのです。
体の中での働き方とエネルギーの流れ
解糖系は、細胞の細胞質で起こり、糖を2つのピルビン酸に分解します。ここでATPを2分子とNADHが生まれ、酸素が不足していても一部は進行します。反対に糖新生は肝臓の細胞質とミトコンドリアの一部をまたがる複雑な経路で、ピルビン酸をグルコースへ変換します。これは眠っているときや断食中に特に必要となり、脂肪酸の分解産物や乳酸などの材料を使います。糖新生を促す主なホルモンはグルカゴンとアドレナリン、抑制するのはインスリンです。こうして血糖値を安定させ、脳や筋肉に必要な糖を供給します。解糖系と糖新生の相互作用を理解するには、エネルギーの流れと物質の流れを別々に考えるのがポイントです。解糖系はATPの供給を最優先に、糖新生は血糖の維持を最優先に働く、そんな二つの大きな目的を持つ道なのです。以下の表で、両者の違いを簡潔に並べてみましょう。
この違いを意識すると、運動前後の食事選びや、風邪をひいたときの体の反応にも納得がいくようになります。
まとめとして、糖新生は血糖値を維持するための長期戦略、解糖系は即座にエネルギーを取り出す短期戦略という風に覚えると、体の働きを理解しやすくなります。両方の道が並行して働くことで、私たちは食事や運動、休息のサイクルの中で安定したエネルギーを保っているのです。
この話題を日常の雑談に落とし込むと、糖新生と解糖系の違いがぐっと身近に感じられます。私は友だちと『解糖系は即席の攻撃、糖新生は長距離の作戦』みたいな例え話をしてみました。解糖系は糖を分解して手早くATPを作る道で、酸素があるときもないときも動くのが特徴。対して糖新生は断食中など血糖値を守るときに働く“資源の再利用”の道。乳酸が筋肉でたまり始めると、回復にも時間がかかる話題は雑談としても盛り上がります。こうした日常の比喩を使えば、教科書の難解な公式よりも、体がどうして今このように動くのかを直感的に理解できるはずです。次の授業で友だちとこの違いについて話すと、みんなの理解も深まるはずです。





















