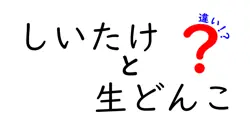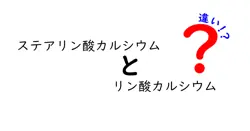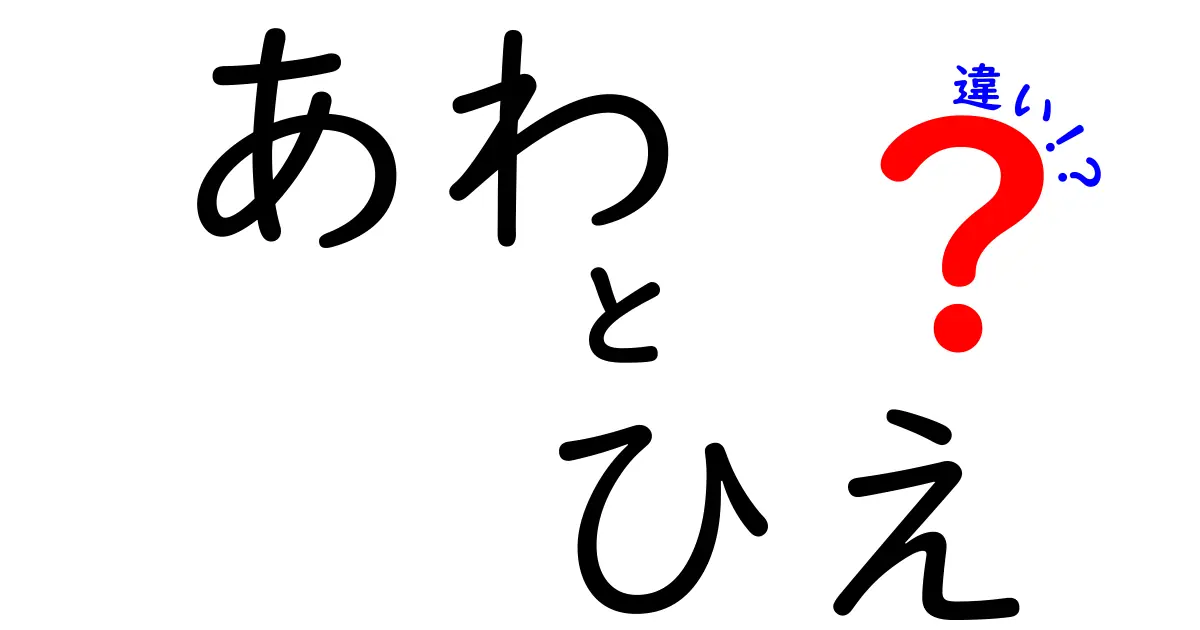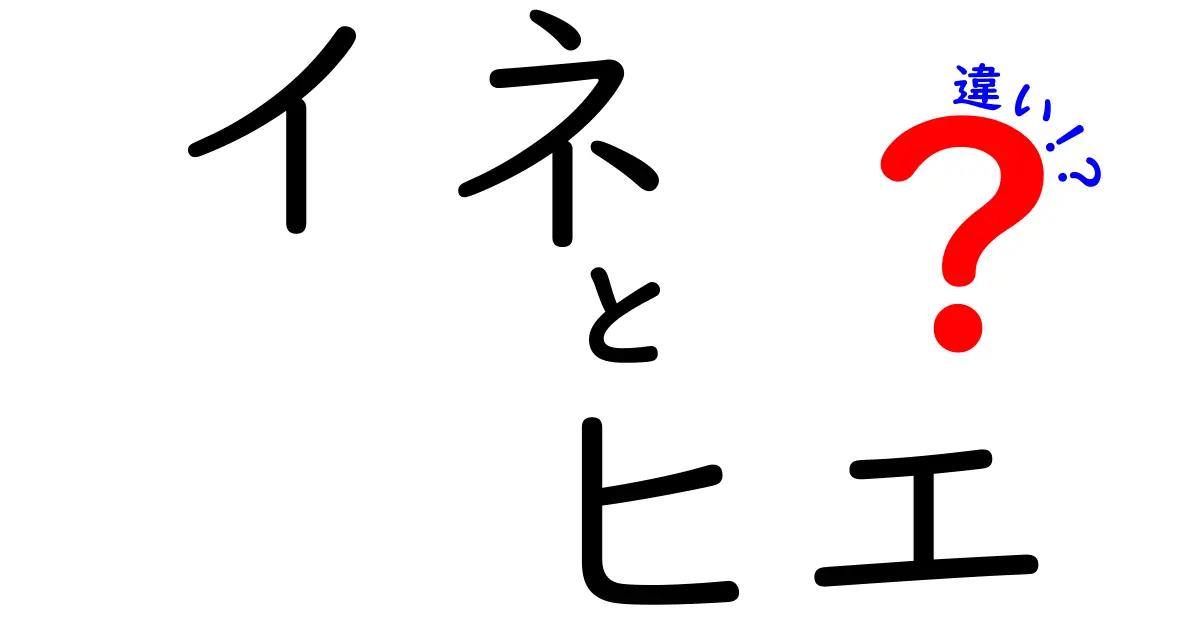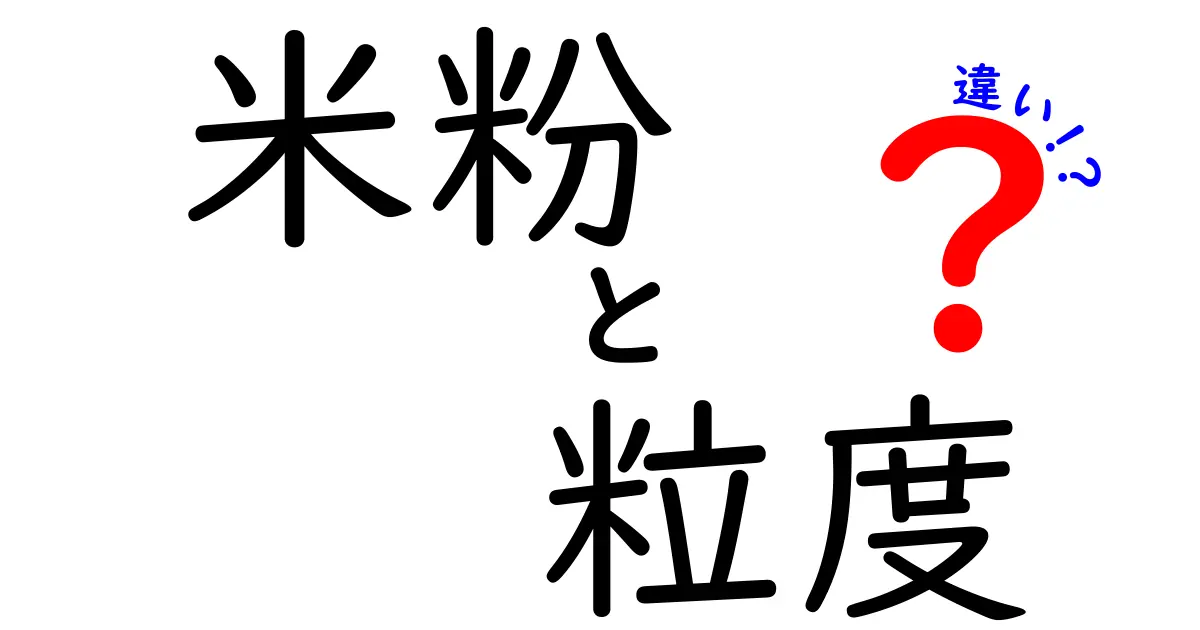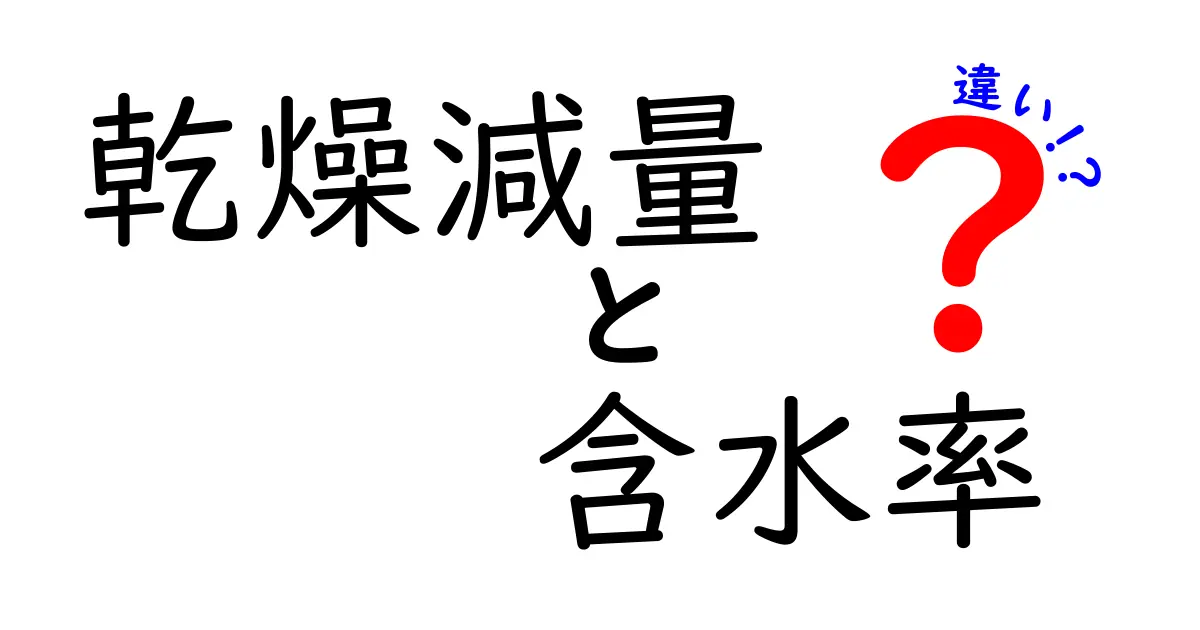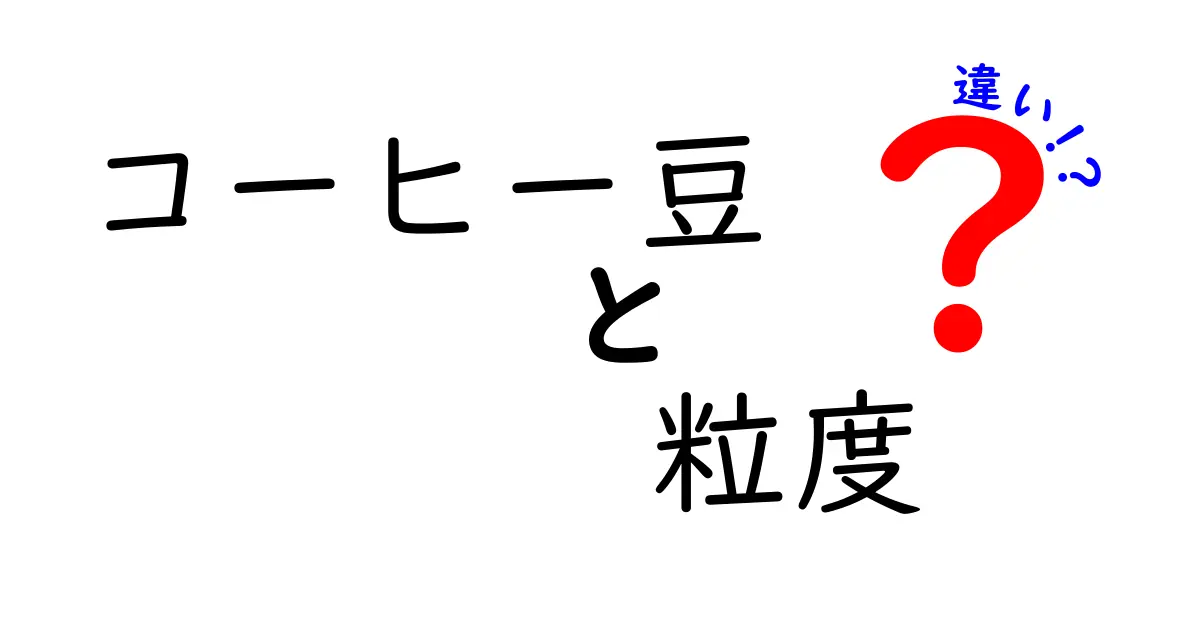

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
コーヒー豆の粒度と味のつながり:まずは基礎から
コーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)を淹れるとき、粉の大きさを意味する粒度は味を決める大きな要素です。 粒度は抽出の時間と溶け出す成分の量を直接左右します。挽いた粉は水と接触して成分を溶かしますが、粉が細かいほど水は粉の中を通りやすく、香りの成分も溶け出しやすいです。これが味の“濃さ”や“香りの立ち方”に大きく影響します。一方、粒度が均一でないと、粉の一部だけが先に抽出され、別の部分は後から抽出されるため、口に含んだときの風味がムラになってしまいます。
家庭用の挽き機は、粒度を微妙に変えることで抽出時間を調整できます。例えば、朝の忙しい時間には粗い挽きで短時間の抽出を狙い、時間に余裕があるときは細かい挽きで香りを引き出す…そんな使い分けが可能です。
粒度を決めるときは、使う器具、焙煎度、そして好みをセットで考えると失敗が減ります。焙煎が浅い豆は酸味が強く出やすく、細かい粒度だと苦味が出やすい傾向があります。逆に深煎りはコクが深くなりやすく、同じ粒度でも味が変わることがあります。
この基本を押さえておくと、初期の味作りが楽になります。抽出時間の目安を知ると、粒度を微調整するだけで味の方向性を変えられるからです。例えば、ドリップ式では中挽きが安定感を出しやすく、粗すぎると水の抜けが悪くなって薄く感じ、細すぎると濃厚で渋味が強くなることがあります。フレンチプレスは粗めの粒度が水の通りを穏やかにし、適度なボディ感を保ちやすいです。
味の表現は個人差がありますが、粒度と抽出条件の関係を理解しておくと、好みの味に近づける道筋が見えやすくなります。
また、新鮮な豆を使うこと、同じ豆でも焙煎度が変わると味が変わること、そして水の温度(90〜96℃程度が基本)も合わせて考えると、より再現性の高い抽出が可能になります。
粒度の基本と抽出の関係
粒度の違いは、コーヒーの味の根幹に関わる要素です。 粒が細いほど、粉の表面積が増え、水との接触時間が短くても成分が多く溶け出します。これを“抽出量”と呼び、適切な抽出量を保つことが美味しさの鍵です。 過抽出は苦味と渋味を強くし、不足抽出は酸味と薄さを目立たせます。抽出を安定させるには、挽き方だけでなく、水温、接触時間、粉の均一性も重要です。均一でない粉は、同じ抽出条件でも味がムラになります。したがって、家で美味しく淹れるコツは、粉を均一に挽くこと、抽出工程を一定に保つこと、そして新鮮さを保つことです。
粒度の範囲を知るには、代表的な三つの粒度を覚えると良いです。粗目は主にフレンチプレス、粗く砕けば水を通す余地が大きく、風味は重くなりがちですが、ボディ感が増します。中挽きはドリップやペーパーフルターで安定して味を出せる標準的な粒度。細挽きはエスプレッソなど短時間で高濃度を作るときに使われます。
どう選ぶ?淹れ方別の粒度ガイド
淹れ方別の粒度ガイドを知ると、すぐ実践に活かせます。
- フレンチプレス:粗挽きが基本。水抜けを良くすることで、オイル成分を過剰に引き出さず、クリアでマイルドな口当たりを狙います。
- ペーパードリップ/ハンドドリップ:中挽きが標準。抽出ムラを減らし、香りとコクのバランスを取りやすい。抽出時間は2〜4分程度を目安に。
- エスプレッソ:細挽き。高圧で短時間に抽出するため、苦味とコクを凝縮します。過剰な細挽きは圧力詰まりを起こしやすいので注意。
- コールドブリュー:粗挽き。長時間水に浸すため、粗さが必要。口当たりが滑らかで甘みが出やすいです。
実践編:家での粒度の測定と調整
家庭で粒度を測定・調整する実践は、味の再現性を高めるうえでとても大切です。まず、使用する挽き機が均一な粒度を作れるかを確認します。次に、同じ豆で粒度を変え、抽出時間を一定に保って味を比較します。最初は“粗さの変更のみ”に留め、他の条件は常に同じにします。水温は90〜96℃、水量は抽出量から換算して適切な比率を保ちます。新鮮な豆を使い、焙煎後2週間程度が目安です。豆の保存は涼しく暗所、密閉容器が基本です。これを守ると、粒度を変えたときの味の変化が分かりやすくなります。
実践のポイントは、記録を取ることです。挽き目を変えた日付、抽出時間、湯温、抽出後の香り・苦味・酸味・甘味の印象をノートに残します。これを繰り返すことで“自分の好みの粒度と抽出条件の組み合わせ”を見つけやすくなります。
器具別の推奨粒度と注意点
器具ごとに推奨粒度は変わります。
- フレンチプレス:粗挽き寄りの幅を試してみましょう。粉が水に沈む時間を長めに取り、オイル分を含んだ濃厚さを出します。
- ドリップ/ペーパーフィルター:中挽きが安定します。均一性を意識して挽くと、香りとコクのバランスを崩しにくくなります。
- エスプレッソ:細挽きが基本。圧力が高いため、粒度の揺れに敏感です。挽きすぎには注意。
- コールドブリュー:粗挽きが推奨。長時間浸すため、過度な粉の細かさは逆効果になります。
味の変化を体感する練習法
味の変化を体感するには、同じ豆・同じ水温・同じ水量で、挽き目だけを変える練習が効果的です。まず、粗挽きと中挽きを用意し、2杯ずつ同じ器具で抽出します。次に、香り、口当たり、余韻をノートに書き留め、香りの強さや苦味の出方を比較します。最後に、味の変化を自分の好みに合わせて微調整します。練習を繰り返すほど、微妙な差でも的確に捉えられるようになり、家での味作りが楽しくなります。
この練習のコツは、記録をとることと、同じ条件をできるだけ長く保つことです。道具の買い替えや豆の変化に対して、どの粒度でどう味が変わるのかを把握しておくと、次回以降の調整がスムーズになります。
友達とカフェで待っているとき、粒度の話題で盛り上がった。私が“粒度が違うとコーヒーの印象がこんなに変わるんだよ”と伝えると、友達は半信半疑だった。そこで私は自分の手元にあった同じ豆を使い、粗挽きと中挽きで同じ抽出時間を保って2杯を淹れてみせた。香りは粗挽きの方がふんわり、口に含むと軽やかなボディ。中挽きは香りが立ち、コクと酸味のバランスが整っている。友達はその違いに驚き、粒度を変えるだけでこんなにも味が変わるのかと感心していた。日常のコーヒーにも“遊び心”を取り入れると、毎日の一杯が新しい発見になるんだと実感した。粒度は難しく考えすぎず、まずは手元の器具と豆で実験することが大切だと感じた。
次の記事: アンモニアと硫黄の違いを徹底解説!中学生にもわかる基本と身近な例 »