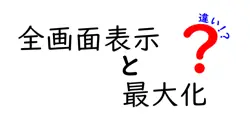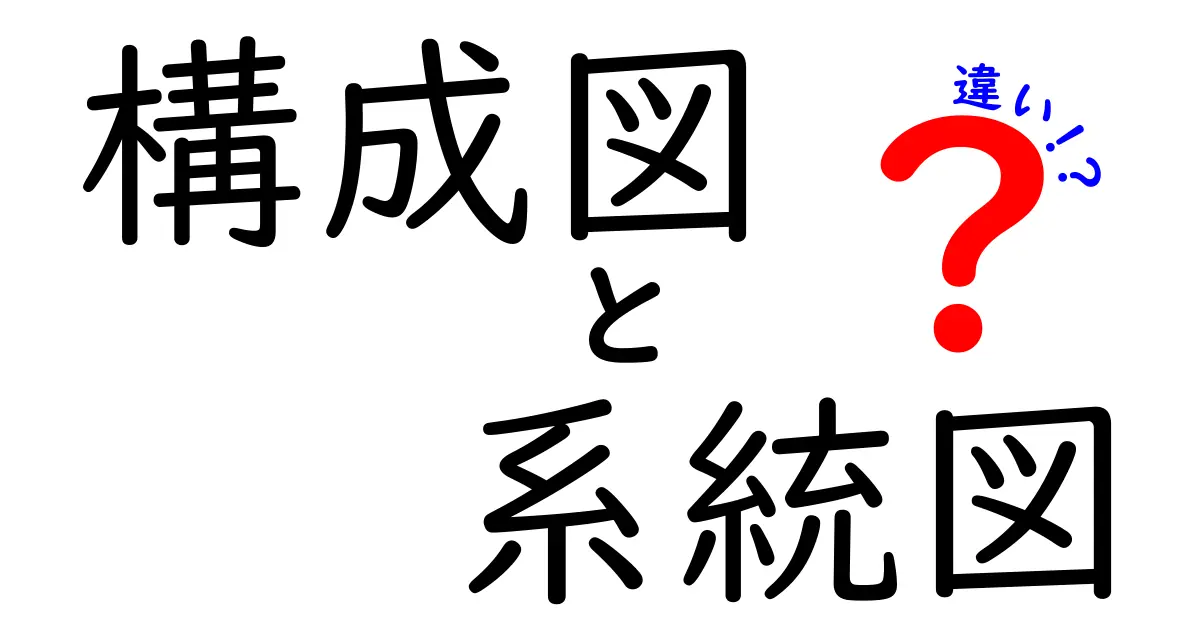

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
構成図と系統図の違いを徹底解説!クリックしたくなるポイントを徹底比較
このキーワードで記事を開いた全ての人へ、まずは結論をお伝えします。構成図と系統図は役割が違い、目的が異なる図です。構成図はシステムの部品とそれぞれの役割・接続を一枚の地図として見せるもので、動く仕組みを理解するためのツールです。系統図は要素をグループ化し、どの要素がどの階層や系統に属するかを示す分類の地図です。これだけ知っていれば、資料作成時に「どちらを描くべきか」がすぐに判断できます。
例えばウェブアプリの設計を考えるとき、構成図はサーバーやAPI、データベース、フロントエンドの関係性を見える化します。系統図は同じ機能を持つ部品をまとめ、技術カテゴリや製品ラインの関係を整理します。
このように違いを理解すると、会議での説明がスムーズになり、読み手に伝わる情報の質が格段に上がります。
構成図の特徴と使い方
構成図の特徴は、部品同士のつながりを「どの部品が何を担うのか」「どの機能がどの部品に依存しているのか」を視覚的に表す点です。図中のブロックは通常、機能名と役割を短いキャプションで示します。矢印はデータの流れ、依存関係、呼び出し順序を表現します。実務での使い方としては、要件定義の段階で全体像を共有するための入口として描くことが多く、設計書・テスト計画・運用マニュアルと連携します。
作成時のコツは「抽象度のコントロール」と「色分けの統一」です。たとえばデータベースは青、外部サービスは緑、処理はオレンジといった具合に色を決め、読み手が迷わないようにします。図を過度に細かくしすぎると、逆に全体像が見えなくなるので、適切な粒度を保つことが重要です。
系統図の特徴と使い方
系統図は、対象を階層的に並べて「属するカテゴリー」と「その下位のサブカテゴリー」を視覚化します。木のような分岐が多いほど直感的に理解でき、どの要素がどの系統に属するのかを一目で判断できます。ITの現場では機能の分類、ライブラリの依存関係、製品ラインの関係整理などに活用します。図の作成時には上位カテゴリを大きく配置し、下位カテゴリを段階的に分けると読みやすくなります。
系統図は変化の追跡にも強く、将来の変更が全体のどこに影響を及ぼすかを予測する力を養います。実務では、新規機能の追加時に「この機能はどの系統の部品と連携するのか」を検討する際に特に有用です。
違いのまとめと実務での使い分け
結論として、構成図と系統図は同じように見える図でも「伝えたい情報の性質」が異なります。構成図は現状の仕組みを俯瞰する地図、系統図は要素の分類・関係性を整理する地図です。使い分けの判断基準は、読者が知りたい情報が「動作の連携・依存関係」か「分類と所属・系統関係」かによります。実務では、初期設計には構成図を使って全体像を示し、設計の後半で系統図を使って部品のグルーピングを整えるのが現実的な流れです。
また、両図の統一感を出すコツとして、図の枠組み・カラーリング・文字サイズを揃えることが挙げられます。こうすることで、読む人は違う図を見ても「同じ世界観の図だ」と認識しやすくなります。
最後に、学習のコツとして、身近な題材で実践してみると理解が深まります。学校のイベント運営、部活動の連絡網、クラスの関係性といった題材から、構成図と系統図の両方を作ってみると、二つの図の視点の違いが体感できます。
友達とこの話をしていて、構成図と系統図は“同じ道具箱の別の道具”みたいな関係だなと感じました。構成図は機械の内側をのぞくような設計図で、部品どうしの関係を矢印で追います。系統図は家系図のように、どのグループに属するかを並べ、似た性質のものを集める感覚です。実生活でも、例えば学校の部活動を想像すると、部員が科目や役割という系統で分類され、どの部品がどの機能を持つかを整理するのが系統図、部の連携の動きを見るのが構成図です。多くの人は“何を伝えたいか”を迷いがちですが、それぞれの図が果たす目的を意識すると作り方が変わります。もし最近、資料を作る機会があれば、最初に両図を紙にざっくり書いてから、細かい説明を付け足すと理解が深まります。私が学んだコツは「適切な粒度と一貫した表現を決めること」です。これだけで、説明が格段に分かりやすくなるはずです。