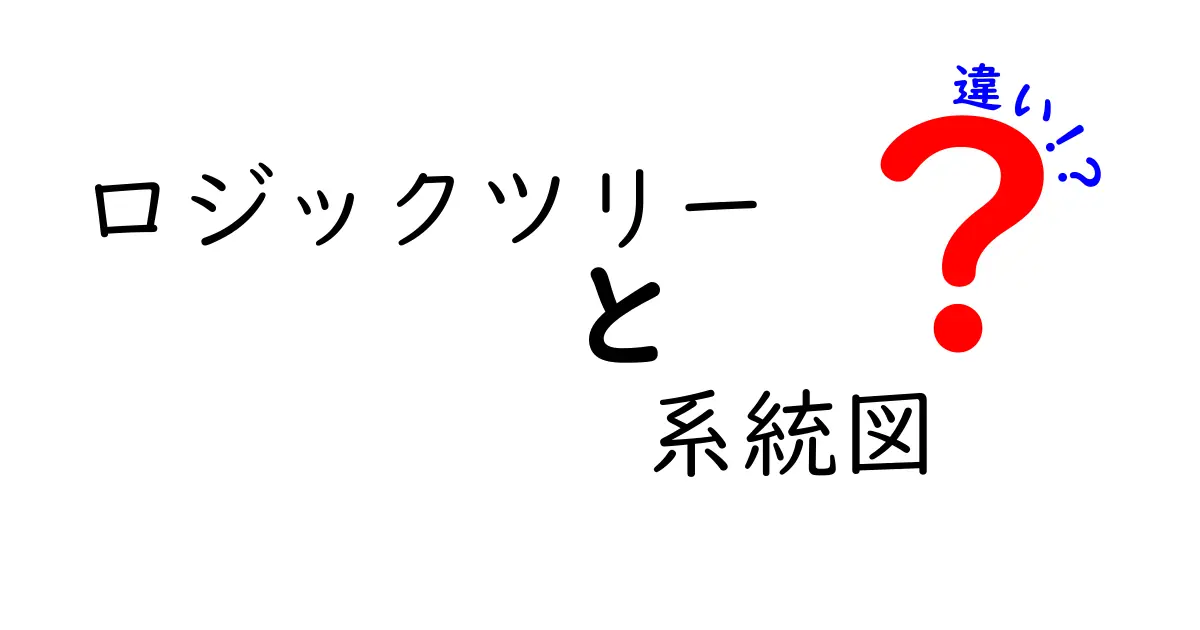

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
ロジックツリーと系統図の違いを徹底解説!用途別の使い分けと実践ポイント
このページでは「ロジックツリー」と「系統図」の違いを、中学生にも分かる言葉で分かりやすく解説します。
両者は似ているようで役割が異なり、活用場面や作り方も変わります。ロジックツリーは「原因と結果を階層的に分解する思考の道具」であり、系統図は「要素どうしの関係性を系統的につなげる地図」です。
この違いを押さえると、課題解決の最短ルートが見えるようになります。
このページを読むときのポイントは次の3つです。
・役割の違いを理解すること
・作り方のコツと実践のポイント
・実務での使い分けを知ること
1. ロジックツリーとは何か
ロジックツリーは、ある課題の原因や要素を大きな枝に分け、さらに細かく分解していく図です。
「なぜ?」と問をつなぎながら、問題の本質に迫るのが得意です。思考の道筋が見えるので、結論へと至る道のりが明確になります。たとえば「学力向上の理由」を探る場合、第一レベルは学習時間や睡眠、食事といった大きな要因、第二レベルは具体的な科目や学習法、第三レベルは1日のスケジュールなどと細分します。
この順序は階層的で、右へ行くほど細かくなり、左上の根本的な原因に戻れるのが特徴です。
ロジックツリーの実用例としては、問題解決の前に「何が本当に問題なのか」を明確にする作業です。原因と影響の因果関係を可視化するため、会議での議論を整理するのにも向いています。図の作成手順は、まず大きな問題を1本の幹として描き、次に主要な原因を枝分かれさせ、さらに細分していくという流れです。
ツリー形式は、話が飛躍せず、説明の順序を追いやすい点が強みです。
2. 系統図とは何か
系統図は、物事の関係性を「系統性」という観点で整理した図です。
木の枝のように、上位のカテゴリから下位の要素へとつながりを描きます。これは主に「どの要素がどの要素と関係しているか」を把握したいときに有効です。系統図の強みは、複数の要素が互いに影響し合う場面で、整理された全体像を一目で確認できる点です。たとえば動物分類の系統図や、製品ラインの関連部門を示す系統図など、関係を視覚的に捉えるのに役立ちます。
系統図を作るときのコツは、まず大きなカテゴリを決めてから、各カテゴリの中で関係性を示す要素を選ぶことです。横断的なつながりを色分けで表すと、どの要素が他の要素にどのように影響するかが一目で分かります。会議資料として用いる場合、系統図は「全体像の見取り図」として重宝します。
ただし、系統図は細かな因果関係を追うのには向かないことがあるので、ロジックツリーと組み合わせて使うと効果的です。
3. 実務での使い分けと作成のコツ
実務では、問題の性質に応じてロジックツリーと系統図を使い分けます。
大きな原因を「因果関係の流れ」として追いたい場合はロジックツリーが適しており、関係性を俯瞻的に捉えるには系統図が効果的です。作成のコツとしては、まず目的を明確にすること、次に主要な要素を抽出して階層を作ること、最後に不要な要素を削ることです。
また、図の見た目をすっきりさせることも大事で、色分けや矢印の方向、ラベルの統一感が理解を助けます。
このような配慮をすれば、同僚や上司に説明する際にも伝わりやすくなります。
- 表現の基本はシンプルさ
- 色分けで要素の性質を区別する
- 全体像と詳細の両方を示す
このように、ロジックツリーと系統図は似て非なるツールです。
適材適所で使い分けることで、問題の核に早く到達し、説明の説得力を高められます。
最後に覚えておきたいのは、どちらを使うかは「何を伝えたいか」で決めるという点です。伝えたい内容の性質に合わせて選択しましょう。
ロジックツリーの話題を深掘りする小ネタ。ねえ、家計の“原因と結果”を考えるとき、ロジックツリーは実は家計の地図みたいなものかもしれない。月々いくら使って何が生まれるのかを、木の幹から分岐する形で整理していくと、無駄遣いの原因がすぐ見つかる。友だちに「なんでそんなに買うの?」と問われても、ツリーの枝を辿れば“本当に必要なもの”と“衝動買い”の違いが自然と分かる。つまり、ロジックツリーは思考の整理整頓ツールであり、会話をうまく進めるための道具でもあるのだ。
前の記事: « 先行研究と既往研究の違いを徹底解説!中学生にもわかる簡単ガイド





















