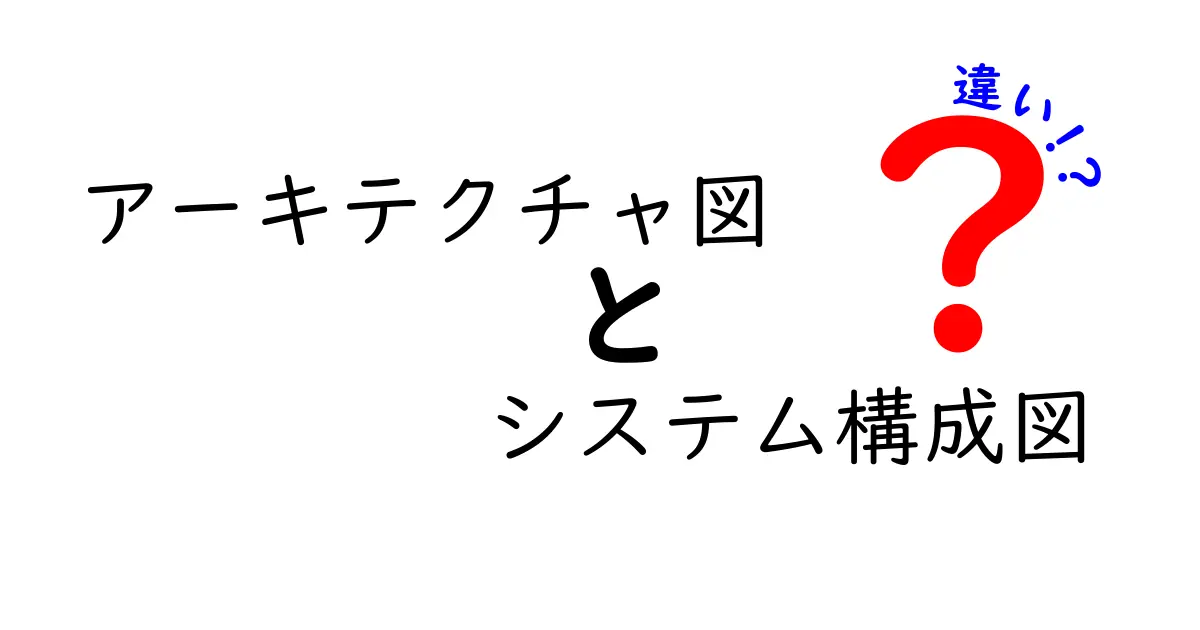

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:アーキテクチャ図とシステム構成図の基本を押さえよう
ここではまず両者の基本的な定義を押さえます。アーキテクチャ図とは、ソフトウェアやシステムの大まかな構造を示す図です。大きな部品の役割や、部品同士の関係性、データの流れを高レベルで示します。対してシステム構成図は、実装に近いレベルで「どの部品がどこに配置されているか」「どのサーバー・サービスが実際に動作しているか」を具体的に表します。ホスト名やネットワーク境界、デプロイ先の構成など、現場の開発・運用で直接使える情報が多いのが特徴です。
この2つは別物ではなく、同じプロジェクトを説明する際に補完的に使われます。アーキテクチャ図を作って全体像を共有し、システム構成図を作って詳しい実装を伝えると、関係者全員が理解を揃えやすいです。
<table>違いを理解するポイント
この節では、両者の違いを「抽象度」「対象読者」「目的」「表現の粒度」などの観点から整理します。抽象度はアーキテクチャ図が高いレイヤーで全体像を描くのに対し、システム構成図は現場の実装に近い細かな情報まで落とします。
「誰が読むのか」を意識することも大切で、経営層やアーキテクトには大局の理解を促す図が求められ、開発・運用チームには実装の根拠を示す図が必要になります。
さらに、目的を明確にすることで図の形が決まります。新規開発の方針を共有するならアーキテクチャ図、現在の構成を検討・変更するならシステム構成図が適します。
最後に、更新頻度と分かりやすさも重要です。アーキテクチャ図は長期的な設計変更が少ない場合でも読み直されますが、システム構成図はデプロイやサーバー構成が変わるたびに素早く更新されます。
- 抽象度の違い
- 対象読者の違い
- 目的と表現の粒度
- 更新頻度と運用
実務での使い分けと注意点
実際のプロジェクトでの使い分け例と注意点を紹介します。新規開発の設計段階では、アーキテクチャ図を最初に描くのが定石です。これにより、技術の選択肢やデータの流れ、外部システムとの連携が関係者に伝わりやすくなります。
その後、実装・運用フェーズに進むと、システム構成図の更新頻度が高くなります。サーバーの追加・削除、ネットワークの分離、ミドルウェアのバージョン変更などの情報を正確に反映させることが重要です。
注意点としては、図の過度な詳細化を避けること。過剰な情報は読みにくさを生み、決定を遅らせます。代わりに、主要な関係性とリソースの配置を分かりやすく保つ工夫が必要です。
- 図の更新責任者を決める
- 読者を想定して文字情報と図の説明を併記する
- 図のレベルを段階的に揃える(例:高レベル→中レベル→低レベルの順で補足資料を用意)
友達とカフェで雑談している設定で、アーキテクチャ図とシステム構成図の違いを深掘りします。Aさんは大きな部品の役割とデータの流れを全体像として描くのがアーキテクチャ図だと説明します。Bさんは実装に近い情報を示すのがシステム構成図だと返し、2つの図を使い分けることでプロジェクトの意思決定が早まると結論づけます。深掘りしていくと、どちらも相手を補完する道具だと気づくはずです。





















