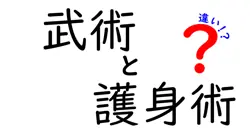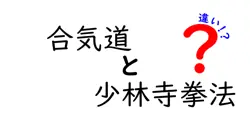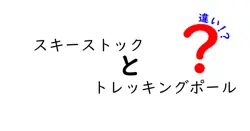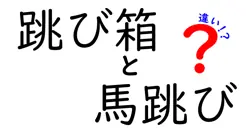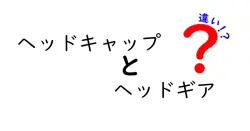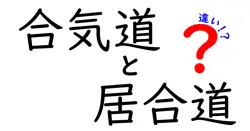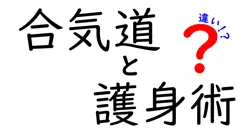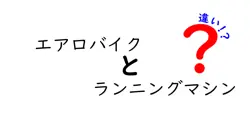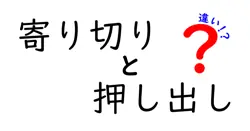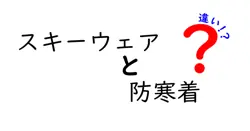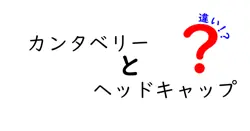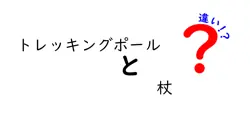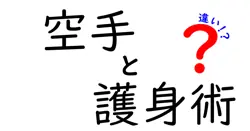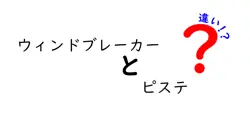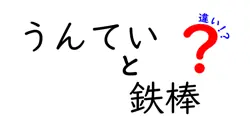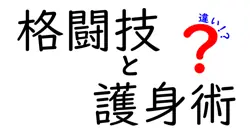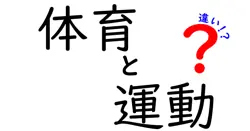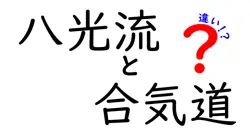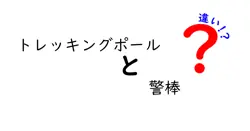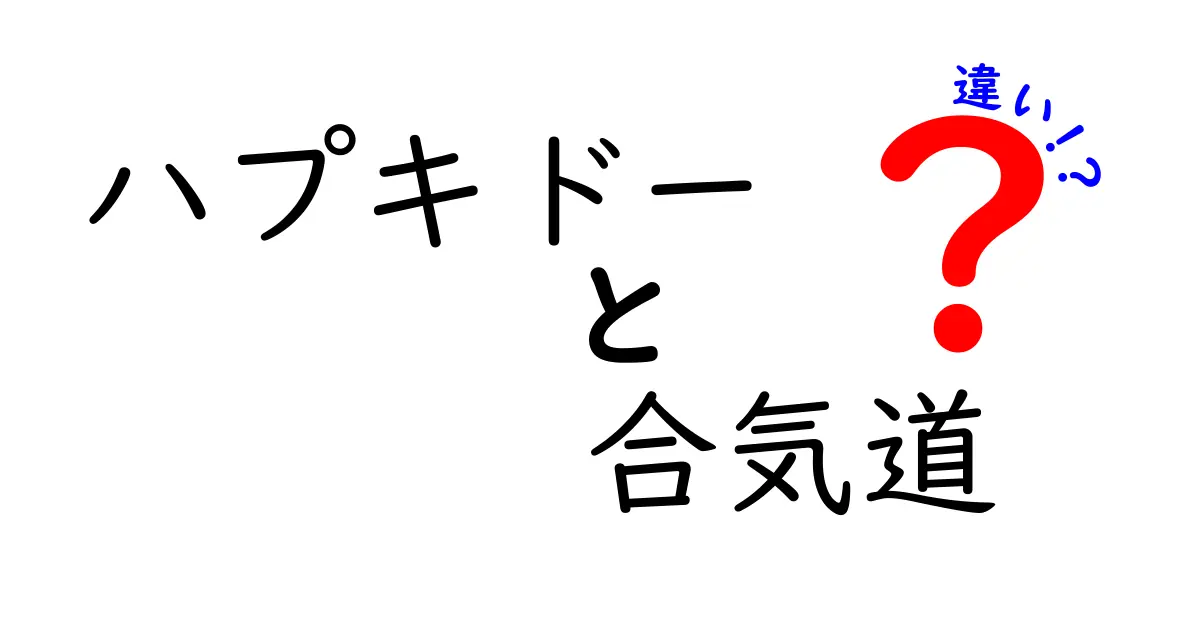

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
ハプキドーと合気道の違いを知ろう
ハプキドーと合気道は、どちらも相手の力を利用して自分を守る武道として知られています。しかし、発生した国や目的、技の性質は大きく異なります。この記事では、見た目が似ているように思える二つの武術の違いを、歴史・技術・稽古の方法・哲学という観点から中学生にも分かるように丁寧に解説します。はじめに結論を伝えると、ハプキドーは動きの幅が広く実戦寄りの技術が多いのに対し、合気道は力の方向を変える「調和」の考え方を中心に据え、相手の力を受け流すことを重視します。もちろん、それぞれの流派や指導者によって表現は変わりますが、共通点としては「相手を傷つけずに制圧する」という理念が根底にあります。以下の説明を読んでいけば、どの瞬間に違いが生まれるのか、具体的な技の例を通じて理解できるでしょう。
また、習得の難易度や安全性、日常生活での活用方法にも差がある点を触れていきます。
歴史と背景
合気道は日本の武術研究者・植芝盛平によって体系化され、20世紀初頭に誕生しました。彼は自然体の動きと調和を重視する「氣の流れ」を技術の軸に掲げ、力の方向を変えることで相手を崩す思想を深く追求しました。結果として、合気道は対人関係の優雅さと非暴力の理念を強調する武道として世界に広まりました。
一方、ハプキドーは朝鮮半島で20世紀中頃に発展した武道で、複数の技術を統合して実戦的な護身術を目指しました。創始者としてはチ・ヨンフル、ジ・ハンジェらが挙げられ、時代と流派の発展とともに技の幅が広がりました。手技だけでなく、関節技・投げ技・絞り技・護身術の組手・武器術を取り入れる流れが強く、学校や警察・自衛の現場での技術が重視されるようになりました。
技術の特徴と動作
ハプキドーの技は、関節技・絞技・投げ技・崩しの組み合わせが多様で、打撃技の要素も併せ持ちます。体幹の安定と足さばき、相手の力の方向を利用する「崩し」が基本です。武器術にも幅があり、木製の棒やサイなどの道具を使う稽古が盛んで、日常の防衛場面を想定した動作が多く練習されます。加えて、複数の技を連続させる連携の練習が重視され、実戦的な対応力を養います。対して合気道は、主に相手の力を受け流し、動きの軸を使って組み手を崩す技術が特徴です。足さばきよりも体の回転と重心移動を活かすことに重点を置き、関節技の極意を練習します。投げ技と固め技は、相手の動きを利用して安全に制することを第一に設計されています。
また、武器を扱う訓練も多く、長柄の杖や木刀を用いた稽古を通じてバランス感覚や反応速度を鍛えます。
このように、ハプキドーは技の数と選択の幅が広く、日常の護身を想定した実戦志向が強いのに対し、合気道は"調和"と"受け流し"を核にした哲学的な技術体系が特徴です。
稽古の目的と稽古法の違い
稽古の目的は、体力向上・技術習得・自己防衛意識・心の鍛錬などです。ハプキドーでは受け身の動作、崩しの連携、実戦に近い場面を想定した練習が多く、踏み込み・快速な手足の動作・反応速度を鍛えます。演武での安全を最優先に、相手との距離感を見極める訓練が中心です。合気道は、呼吸法・身のこなし・心の安定を重視した稽古が多く、技を美しく、相手と自身のエネルギーを合わせることを目指します。型の練習(形)や地稽古を通して、調和の美学を体で覚えることが多いです。
先生方は安全を守るため、初段~初級の段階では模擬的な動作から始め、徐々に力学の原理を理解させていきます。
哲学と精神性の違い
二つの武道の背後には、異なる哲学が存在します。合気道は「他者との調和を目指す」ことを最も大切にします。衝突を避け、敵の力を自分の動作に取り込み、最終的に相手を安全に去らせるという理念が練習の中心です。
一方、ハプキドーは「自分の身を守り、相手の攻撃を止める」ことを重視します。実戦性と機能性を前に出し、さまざまな状況での有効性を追求します。安全性を重んじつつも、力の制御・反応速度・判断力など、自己防衛に直結する精神性を育てる点が特徴です。
どちらも相手を傷つけない考え方を共有しますが、現場での目標設定とアプローチには明確な違いがあります。
日常生活への応用とまとめ
日常生活での応用としては、相手の力を受け流す動作や、重心移動を使った姿勢づくりなどが挙げられます。合気道の練習は、学校の体育の延長線上での体づくりや、ストレスの軽減・集中力の向上にも役立ちます。ハプキドーは、危険を感じたときの身のこなしや、距離感の取り方、複数の技を組み合わせる直感的な判断力を養うのに適しています。どちらも、暴力を避け、相手と自分の安全を第一に考える点で現代社会に役立つ知恵を提供します。結論としては、両者は“似ているようで異なる”武道であり、目的と学習の深さ、取り入れる技術の幅が大きく異なるということです。
ねえ、ハプキドーと合気道の違いを友達と話していたら、技の種類だけでなく考え方の違いが大きいことに気づいたんだ。合気道は相手の力を受け流す“調和”を第一にしているから、技をかける前の呼吸や体の動きがとても大事。対してハプキドーは複数の技を組み合わせて、 situation に応じて最大の効果を狙う実戦志向が強い。例えば、道場での練習でも相手の手首を崩す技だけでなく、距離を詰める動作、足を使うステップ、武器の扱い方など幅広い体験をします。僕が初めてハプキドーの見学をしたとき、技の連携の速さに驚いたけれど、同時に相手の力を受けながら自分の重心をどう置くか、呼吸をどう整えるかがとても大切だと感じました。
前の記事: « 反撃と迎撃の違いを徹底解説!いざというときに役立つ3つのポイント