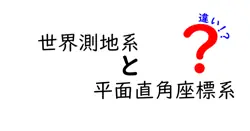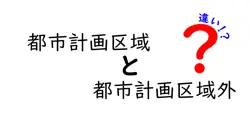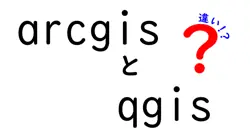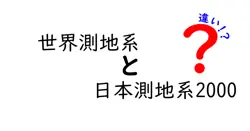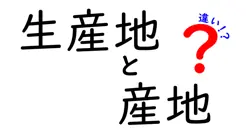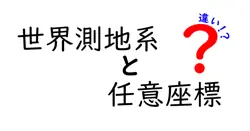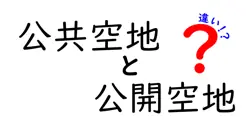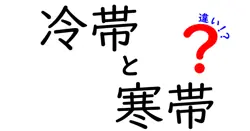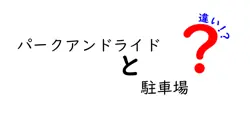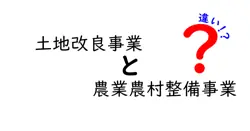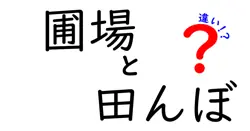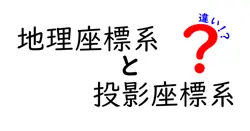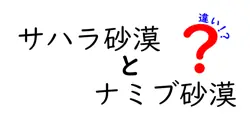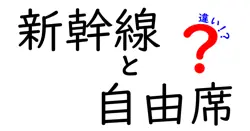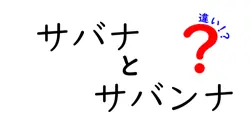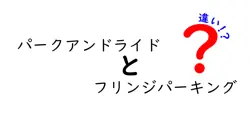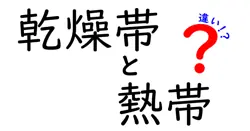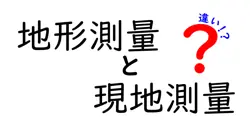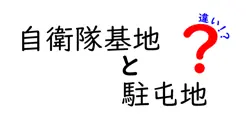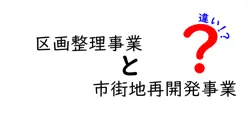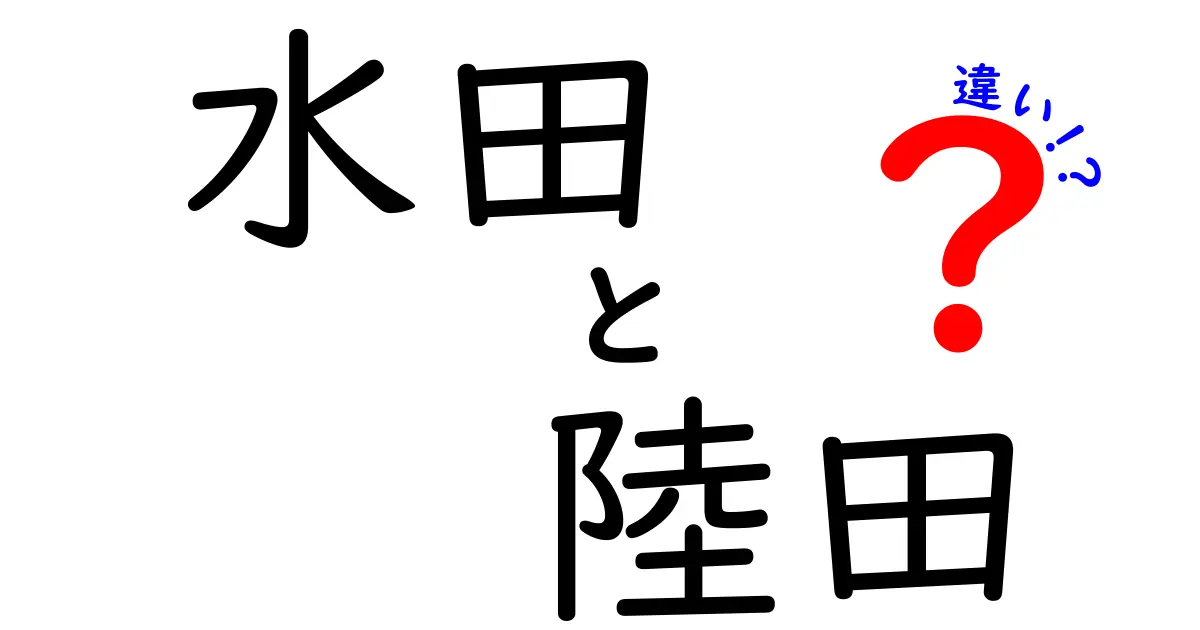

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
水田と陸田の基本的な違い
水田と陸田は、同じ農業の地面でも水の管理の仕方が大きく違います。水田は田んぼの水を一定量保つように設計されており、田植えの前に水を張り、収穫まで水位を調整します。これにより 水田は雑草を抑えやすく、作物の根が安定して成長する環境を作ります。反対に陸田(うるちだ)は水を張らず、乾燥した状態で作物を育てます。
水田は“田んぼの中に水がある状態”を前提に作られる農地であり、稲作に適した柔らかな粘土質の土壌や水はけの良さが重要です。陸田は畑作を前提とする土づくりが中心で、作物ごとに適した水分量や排水性を管理します。
この違いは作業の順番にも影響します。水田では田植え・藁・水管理・代かき・除草といった連携した工程があり、所得の確保にも影響します。陸田では畝立て・畑作の道具・乾燥させる季節の作業・肥料の与え方が大きく異なります。
要するに、水田は水を使って作物を育てる特殊な田んぼ、陸田は水をあまり使わず地表の水分を管理する畑地と覚えておくとわかりやすいです。
両者の共通点としては、いずれも農業の基本であり、適切な水・肥料・日照・土壌管理を組み合わせて作物を育てる点です。
生活や地域の気候によって、どちらを使うかが決まります。水が豊富な地域は水田が多く、乾燥・寒冷・過湿を避けられる地域では陸田が選ばれやすいという特徴があります。
水田と陸田が生まれた背景と歴史
水田と陸田が日本の農業で普及する背景には、気候・地形・人々の生活様式が深く関係しています。稲作は東南アジアや中国沿岸部で古くから行われており、湿地を水で満たす方法は自然の水資源を有効活用する知恵から生まれました。水田の発展には灌漑用水路の整備や田んぼの区画管理、共同作業の仕組みが欠かせません。
日本の平地は比較的水が豊富で、夏には洪水を抑え、冬には水を保持する技術が求められました。水田の仕組みは、灌漑・排水・田植え・代かきといった作業が季節ごとに繰り返され、地域ごとに工夫が重ねられてきました。
一方、陸田は農業の多様化とともに広まった形で、米以外の作物を育てる場として発展してきました。水を張らない、あるいは少なく張る作物は、土壌や気候、輸送手段の発展とともに選択肢として定着しました。
この歴史的な背景を知ると、水田と陸田の違いが「地形・気候・社会的なニーズの組み合わせから生まれた工夫の結果」だと分かります。現代でも地域ごとに、どちらを主に使うべきかはその地域の水資源・作物・市場の変化によって決まります。
現代の日本での使い分けと利点・欠点
現代では、地域の農業事情が変化しており、水田と陸田の使い分け方にも変化がみられます。水田は灌漑施設が充実している地域で依然として重要な作物生産地であり、特に稲作が盛んな地域では収穫量と品質の安定を目指して水管理を高度化しています。逆に降水量が少ない地域や、冬春の低温期に作物を育てる場合、陸田の活用が増えることがあります。
水田の利点は、雑草抑制・病害虫の管理・栽培期の重量安定性などが挙げられます。欠点は、灌漑・排水・田んぼ保全の維持コストがかかること、地形の制約で作付けが限定されることです。陸田の利点は、作物の選択の自由度が高く、排水性を調整することで病害のリスクを減らせる点です。欠点は、乾燥しすぎると土壌が硬くなり、作物の成長が妨げられることがある点や、水資源の確保が難しい地域では生産コストが上がることです。
地域の気候・水資源・市場のニーズに合わせて、水田と陸田の組み合わせ方を工夫することで、安定した収穫と作業の効率化を図ります。
現代の日本では、灌漑技術・ビッグデータを活用した水管理・省力化機械の導入など、技術進化によって水田の生産性を高める取り組みが進んでいます。これにより、ただ水を張るだけでなく、天候や水資源の変化に対応できる柔軟性が生まれています。
水田を歩くとき、田んぼの水が光を反射してキラキラしているのを思い出します。今日は友達と裏山の水田の近くを歩きながら、なんでこんなに水が多い場所で米が育つのかを雑談風に深掘りしてみましょう。水田は単に水を張るだけの場所ではなく、水の入れ替え・排水・田んぼの形・微生物の力など、見えない工夫がたくさん詰まっています。雨が少ない年には水の管理が難しくなり、逆に雨が多すぎると田んぼが水没して作物が痛む…そんな現場の苦労や喜びを、学生の皆さんにも伝えたいです。水田と陸田の違いも、生活の知恵として感じられるはず。