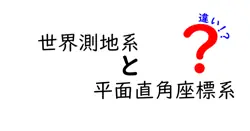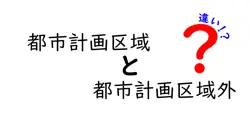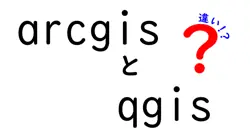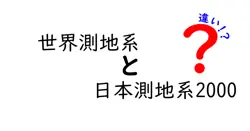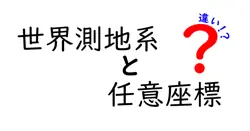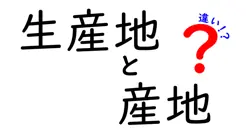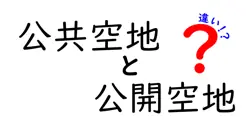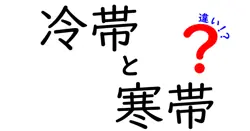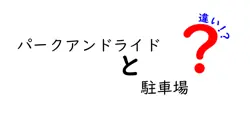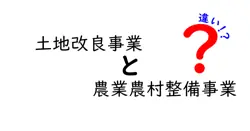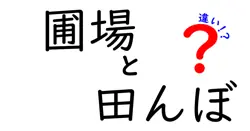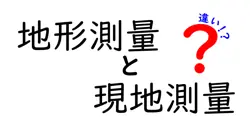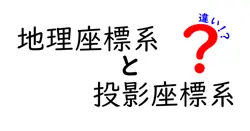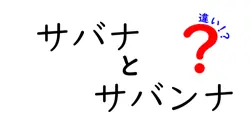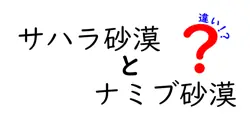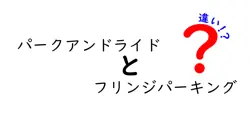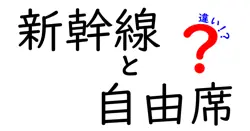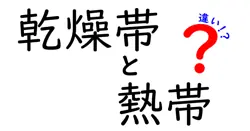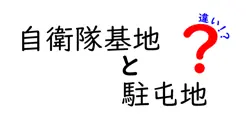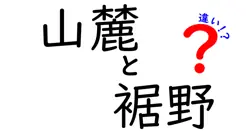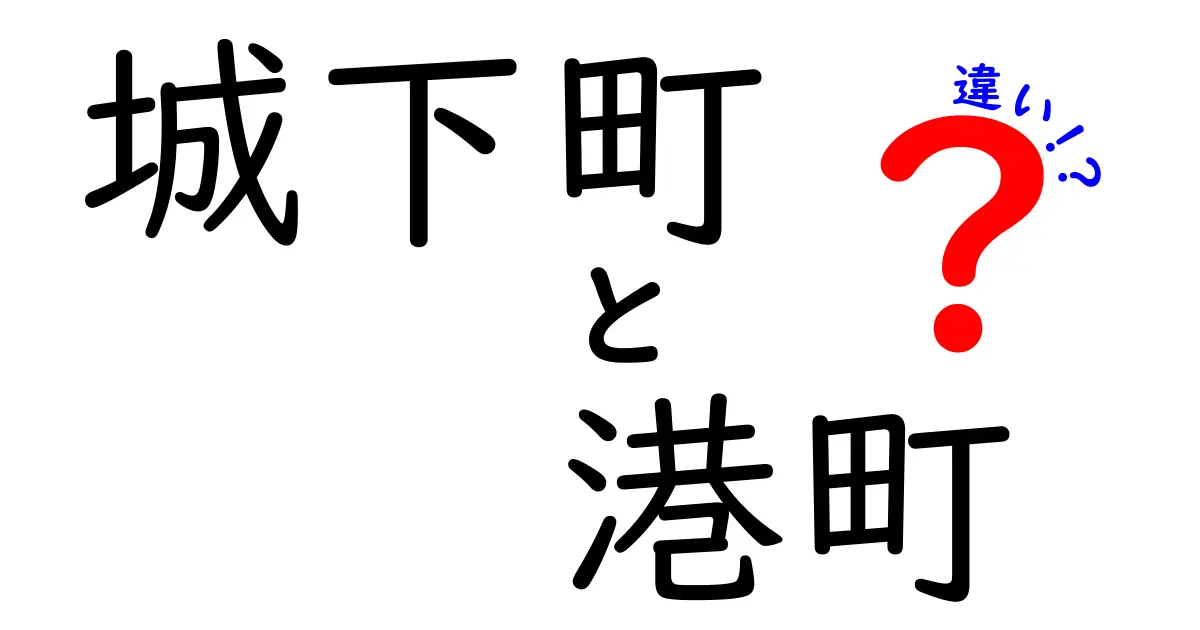

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
城下町と港町の違いを理解するための基礎
城下町と港町の違いを理解するためには、地理的な位置と歴史的な背景を同時に見ることがとても役に立ちます。城下町は多くの地域で、戦国時代から江戸時代にかけて城を中心に形成され、城の防御機能を基盤に都市が組み立てられました。城を守る堀や石垣が周囲を囲み、城の周りには行政機関や商人が集まり、町人の文化が花開く仕組みになります。城下町の道路は直線的な計画と曲がりくねった路地が混ざり、暮らしのリズムは、朝の市が始まるとともに動き出し、昼には商店街が活気づき、夜には照明と人の動きが街を生き生きとさせます。
このような配置は、軍事と政治の中心が城にあることを前提にしており、町の人々も「城下町の秩序」を大切にする傾向が強かったのです。
一方、港町は海と結びつくことで性格を大きく変えます。港には桟橋、倉庫、港市場、船乗りの宿が並び、輸送の動脈として機能しました。海を越えた交易品が港町に流れ込み、人々の顔ぶれも多様になります。漁師、船員、商人、技術者、時には外国人居留者が混ざり合い、日常の会話には異なる言語の言葉や異文化の影響が混じることも珍しくありません。港町は経済の血管が海に直接つながっているため、波のリズムと貨物の動きに街の生活が左右されやすいのです。
港町の建物は倉庫や商店が長く横に連なる形が多く、進入路や港に面した通りは人と車・荷物の動きで一日中にぎわいます。
| 特徴 | 城下町 | 港町 |
|---|---|---|
| 地理的中心 | 城の周辺 | 港湾部 |
| 経済の中心 | 城下町の商業・手工業 | 貿易・物流・漁業 |
| 建築の特徴 | 城郭・武家屋敷・商人町 | 倉庫・長い商店街・桟橋 |
| 生活リズム | 城の行事・朝市 | 船の荷役・港湾作業 |
違いを深掘りする視点
この両者の違いは、地理的要因と歴史的機能の結びつきによって生まれます。城下町は治安と秩序を保つための行政機能と商業機能が近接して発展し、街の形は城を取り囲むように規模を広げました。港町は海を通じて外部と結びつく力が強く、物流と情報の流れが街のテンポを決めます。歩くときの匂い、聞こえる声の種類、見える建物の特徴など、日常の体験にもこの違いが表れやすいのです。
城下町と港町を比較することで、日本の地方都市の多様性や、地域ごとの歴史の積み重ねをより身近に感じることができます。
港町の話題を一つ深掘りしてみると、港の匂いはただの香りではなく街のリズムそのものだと気づくんだ。朝早くの船の出入りが人の流れを作り、倉庫のシャッターが開く音が街の一日を始める合図になる。私は昔、夜明け前の港を歩いていたことがある。潮風が頬をなで、船の甲板に残る塗料の匂いと木の香りが混ざって、心の中に小さな物語が芽生えた。港町の人たちはこのリズムを生活のペースに組み込んでおり、混雑の時間帯を避ける知恵や、季節ごとに変わる港の荷役スケジュールを身につけている。そんなささやかな工夫こそ、港町の「生きた知恵」なのだ。
前の記事: « 城跡と遺跡の違いをわかりやすく解説!見分け方と歴史の謎を楽しむ