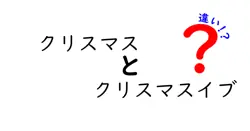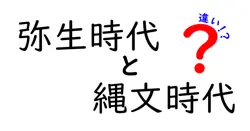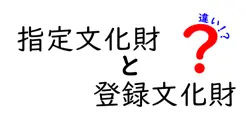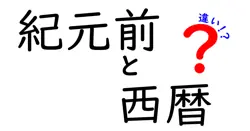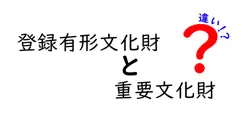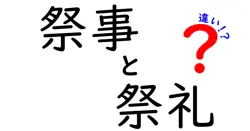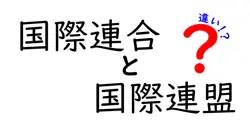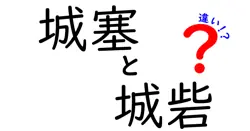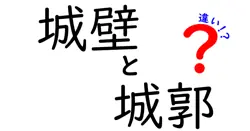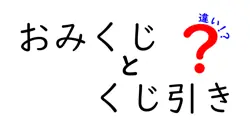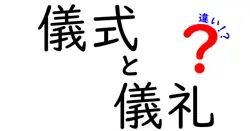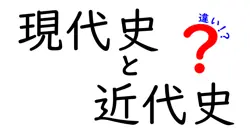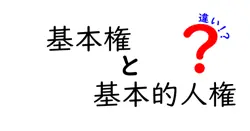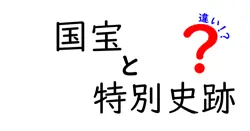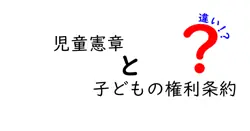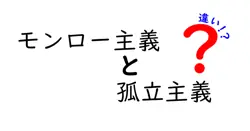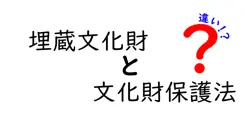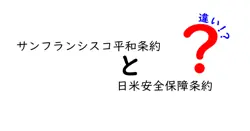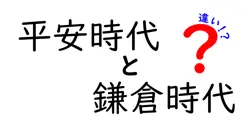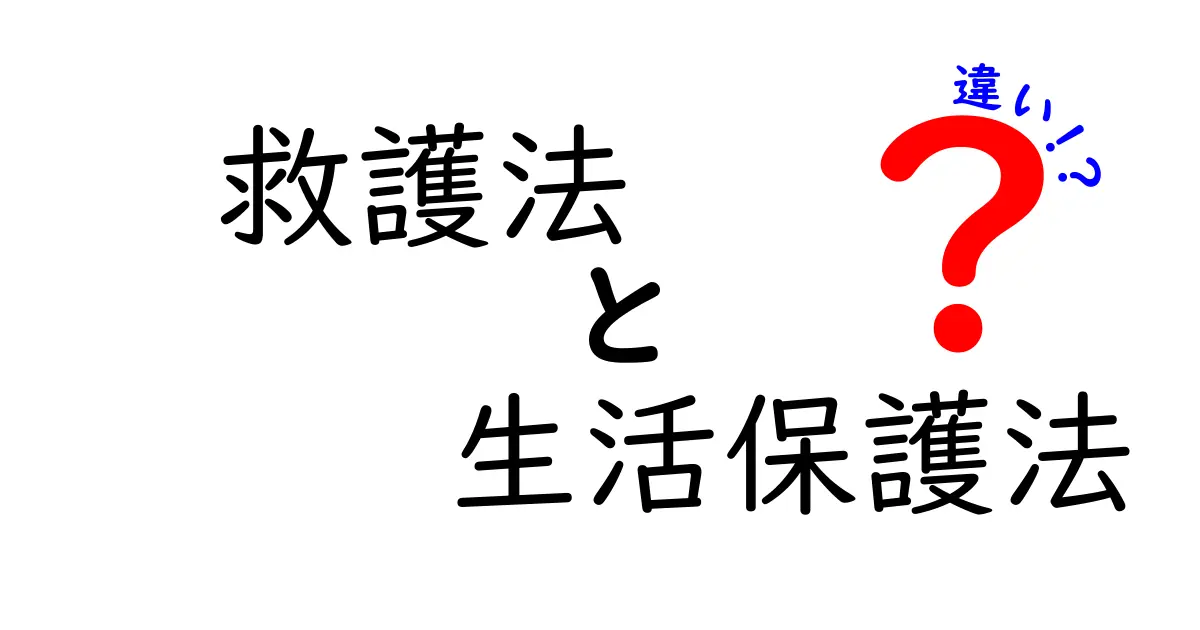

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
救護法と生活保護法の違いを、戦後の制度設計の歴史的背景・目的のニュアンスの違い・対象者の範囲・給付の種類とその運用基準・申請の手続きと審査の流れ・生活保護の自立支援の枠組み・社会的影響・行政と地域の役割・現代の課題と改善の動きまでを、一連の論点として一つの長文見出し風にまとめ、読者が記事を開いた瞬間に何がどう違うのかを理解できるように意図した説明的な見出しです。
この見出しに続く本文では、救護法と生活保護法が同じ目的を持つ“生活の危機にある人を助ける制度”である点を認めつつ、時代背景・制度設計・実務運用の違いを丁寧に解説します。戦後すぐの混乱期には、生活に困窮する人々を支える仕組みがまだ定まっておらず、地方自治体が中心となって緊急的な支援を行っていました。これに対して1950年に制定された生活保護法は、国と自治体が協力して“最低限の生活を保障する基準”を設け、支援の対象や手続きの標準化を進める方向へと転換しました。
ここで重要なのは、救護法が終戦直後の特別な状況に対応する臨時的な枠組みであったのに対して、生活保護法は現代的な制度として、対象者の厳密な審査・給付の種類の整備・自立支援の仕組みを組み込んだ点です。制度の名前が違うだけでなく、運用の原理・財源の配分・社会全体の関係性も異なってきます。
以下の段落では、具体的な違いをわかりやすく整理します。まずは対象となる人の範囲、次に給付の種類、そして申請の流れや審査の基準、さらには自治体と国の関与の度合いについて見ていきます。最後に現代の課題と改善の動きにも触れ、読み手が生活現場での理解を深められるようにしています。長文の見出しで整理する具体的な違いと運用の実務
この章では、制度名の違いだけでなく、現場で直結するポイントを整理します。
まず、対象者の範囲について。救護法は戦後の急激な困窮を背景に、一定の条件を満たす人々を救済することを目的としましたが、生活保護法は世帯単位や個人単位での生活費、医療費、教育費、住宅費など、より広く具体的な支援を定めています。次に給付の種類。救護法では一般的には緊急対応的な支援が中心でしたが、生活保護法では生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助など、複数の必須給付が法に列挙され、日常生活の安定を長期的に支える仕組みが組み込まれています。
審査の流れも異なります。救護法では“必要かどうか”という判断基準が比較的柔軟で、自治体の裁量に任される部分が大きかったのに対し、生活保護法では“世帯の収入・資産・生活状況”を総合的に審査し、最低生活費を下回る場合に支給されるという厳密な枠組みが定められています。
制度運用の違いは、結果的に現場の窓口での対応にも表れます。救護法の時代には、窓口の担当者が個別の事情に応じて判断する場面が多く、自治体ごとのやり方に差が出ることがありました。生活保護法の下では、全国で標準化された要件と手続きが適用されることが多く、旅行費用や民間支援との連携など、横断的な支援制度を組み合わせるケースが増えています。
このように、名前の違いだけでなく、対象、給付、審査、運用の方法まで、制度の設計思想が変わっている点こそが最大の違いです。社会の安全網としての機能は共通していますが、実務的には現代の生活を支えるための仕組みが整えられている点を理解しておくと、教科書的な理解だけでなく日々の窓口での対応にも役立ちます。
最後に重要な結論を一言でまとめます。救護法は戦後の即時的な支援の歴史、生活保護法は現代の最低生活の安定と自立支援を目指す制度という大枠を押さえておくと、制度の違いが自然に理解でき、困っている人がどの制度を使えるかを判断する際にも役立ちます。
<table>
この表を見れば、制度の目的と運用の違いが一目で分かります。
総括すると、救護法は“迅速な救済のための仕組み”、生活保護法は“安定した生活の確保と自立を支える長期的な枠組み”という性格の違いが大きいのです。
生活保護法を深掘りするとき、私は“制度は人の生活を守るための道具”という視点を大切にします。救護法が戦後の危機に対応した臨時の仕組みだったのに対し、生活保護法は現代社会の多様な生活状況に対応するための恒常的な支援システムとして設計されていると感じます。自立支援の雰囲気を強く打ち出す制度設計は、困っている人がすぐに手を差し伸べられるだけでなく、長期的に社会全体の安定につながると私は考えています。読者の皆さんが、身近なケースで制度をどう使えるかを考えるきっかけになれば嬉しいです。
前の記事: « 社会権と自由権の違いをわかりやすく解説 中学生向けの基礎ガイド
次の記事: 児童憲章と子どもの権利条約の違いを徹底解説 »