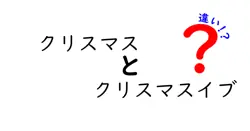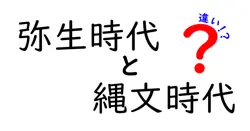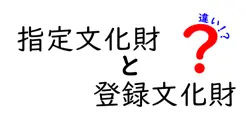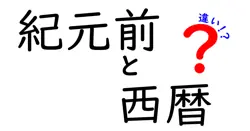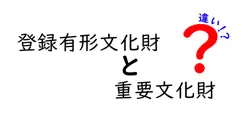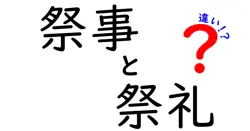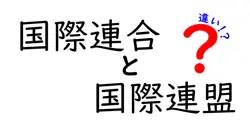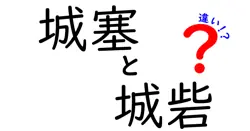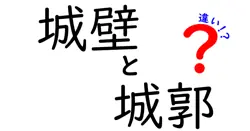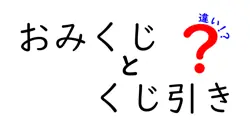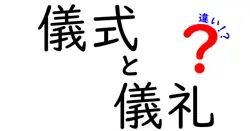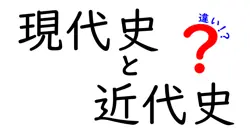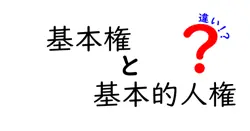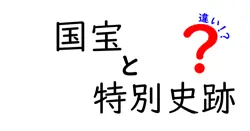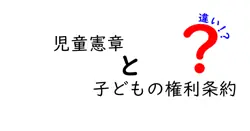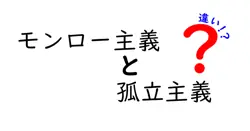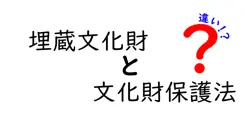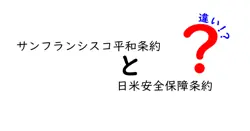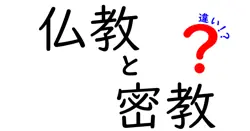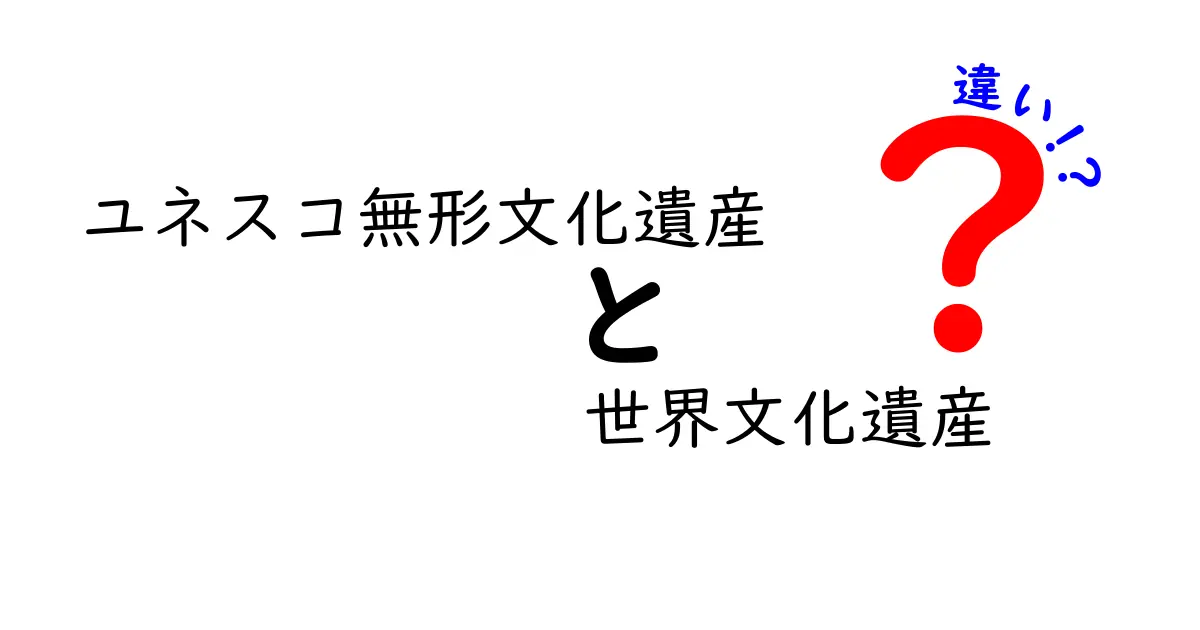

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
ユネスコ無形文化遺産と世界文化遺産の違いを徹底解説
日本の歴史や文化に興味がある中学生のみんなへ。ユネスコには無形の文化を守る遺産と、形のある建物や遺跡を守る遺産の2つの仕組みがあります。ここでは ユネスコ無形文化遺産 と 世界文化遺産 の違いを、日常の例えとともに分かりやすく紹介します。無形遺産は踊りや歌、語り継ぎの技や伝統の形そのものを未来へつないでいく仕組みです。一方世界遺産は建造物や街並み、自然景観など、現時点で残っている物理的な証拠を保護する仕組みです。両者とも人々の暮らしや歴史を次の世代へ伝える役割を担っていますが、見えるものと見えないものという大切な違いがあります。これからの話を読むときは、日常の中の小さなことにも目を向けてください。
たとえば校庭の旧校舎の窓ガラスが割れそうなほど年季が入っているとき、それが世界遺産には該当しなくても地元の記憶として大切にされていることがあります。そんな違いを理解することが、歴史を学ぶ第一歩になります。読書だけでなく、地域の祭りや伝統工芸の場にも出向くと、無形文化遺産の深さが感じられます。教育現場でもこの二つをセットで考えることで、学習が生きた体験になります。
最後に覚えておきたいのは、無形遺産と世界遺産は競争ではないということです。むしろ互いに補い合い、文化の多様性を守るための協力関係です。若い人たちがこの違いを知るほど、将来の国づくりや地域活性化に役立つ視点を身につけられます。
無形文化遺産とは何か
無形文化遺産は見えないけれど心と生活に深く根ざしています。踊り歌い方の技や口承伝統、手工芸の技法の口伝え、儀礼や祭りの型などが対象です。登録の基準は人々の生活に欠かせない性質を持ち、継承者と地域社会の協力で次の世代へ脈々と受け継がれること。世界中の文化がそれぞれの形で守られており、文化の多様性を尊重する考え方を学べます。ここを理解するには地域の人の話を聞くことが第一歩で、学校の授業で実演やワークショップが行われることがあります。
無形遺産は現地の暮らしの中で育つ知恵や技の伝承が中心であり、未来へ向けての教育的価値が高いです。子どもたちは伝統の意味を自分の生活と結びつけて考えることで、歴史の流れを体験的に感じられます。
また、地域の保存活動は継承者の存在なくしては成立しません。職人さんや踊り手、語り部といった人々の協力が欠かせず、学校や地域のイベントで彼らの話を直接聞くことができる機会を作ることが大切です。こうした取り組みは、文化を「学ぶもの」から「生きるもの」へと変える力を秘めています。
世界文化遺産とは何か
世界文化遺産は物理的な遺産として現存する建物や街並み、自然と人が作り上げた景観を守る仕組みです。対象は城郭や寺院の遺構、歴史的な町並み、自然の風景とその周辺環境などが挙げられます。登録されるには長い審査と現地調査があり、保全状況や周辺環境への影響、地域社会の参加程度が評価されます。世界遺産は観光資源としての機能も持つ一方で、観光の過度な人流が遺産に負担をかける問題もあります。そのため、適切な管理計画や持続可能な観光が不可欠です。現状を維持しながら新しい世代に伝えるためには、修復技術の研究や資金調達、地域住民の参画が重要です。世界遺産は私たちが歴史を実感する入口であり、過去の知恵を現代の暮らしと結びつける橋渡しの役割を果たします。
両者の違いをわかりやすく整理
要点を整理すると以下のようになります。
<table>
ここで大切なのは両方を同じ土俵で比べず、それぞれの役割を理解することです。見えるものと見えないもの、それぞれの保存方法が違い、私たちの学び方にも影響します。学校の授業や地域のイベントで、無形遺産の実演を観る機会があれば、ぜひ参加してみてください。
そして地域の歴史を知るためには現地の人の話を聞くことが大切です。昔の暮らしの知恵が今の生活にも活きていると気づくと、学ぶ楽しさが増します。
友だちAと B がカフェで雑談している。Aが「無形文化遺産って、ただの古い踊りとか伝統だけじゃないんだよ」と言うと、Bは眉をひそめつつも興味深そうに耳を傾けた。Aは続けて「無形遺産は、地域の人が日々作り上げる生活の知恵や技の伝承そのもので、口伝や技の継承者がいなくなると消える可能性もあるんだ」と話す。Bは「つまり、伝統を守るのは技術や習慣だけでなく、次の世代への関心と実践だね」と合点がいった様子。二人は次に世界文化遺産について議論する。Aは「世界遺産は形が残っている証拠だから、建物の保存状態や周辺環境の保護が重要。観光で傷つかないようにする工夫も必要だよ」と話す。Bは「でも観光が地域の活性化にもつながる。両方をうまく組み合わせるには、教育と地域の協力が不可欠だね」と締めくくる。彼らの会話は、歴史を学ぶ楽しさよりも、文化を守る責任を身近に感じさせてくれた。結局、無形遺産も世界遺産も、私たちの暮らしと未来をつなぐ大切な財産だという結論に落ち着く。