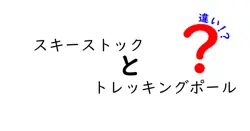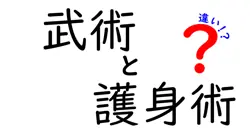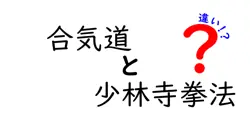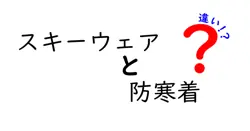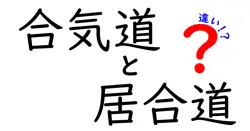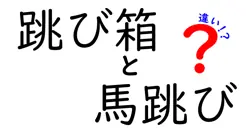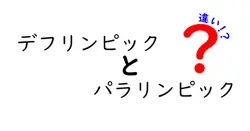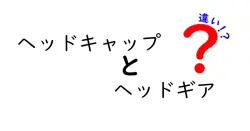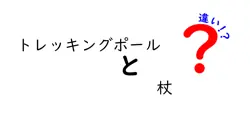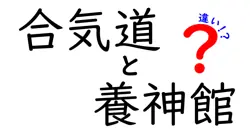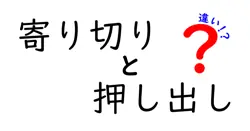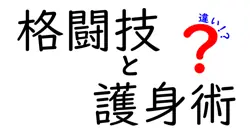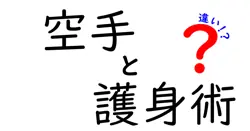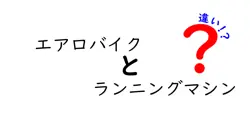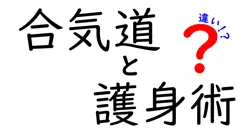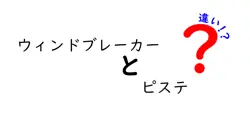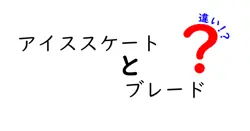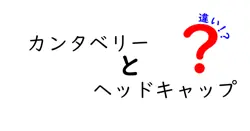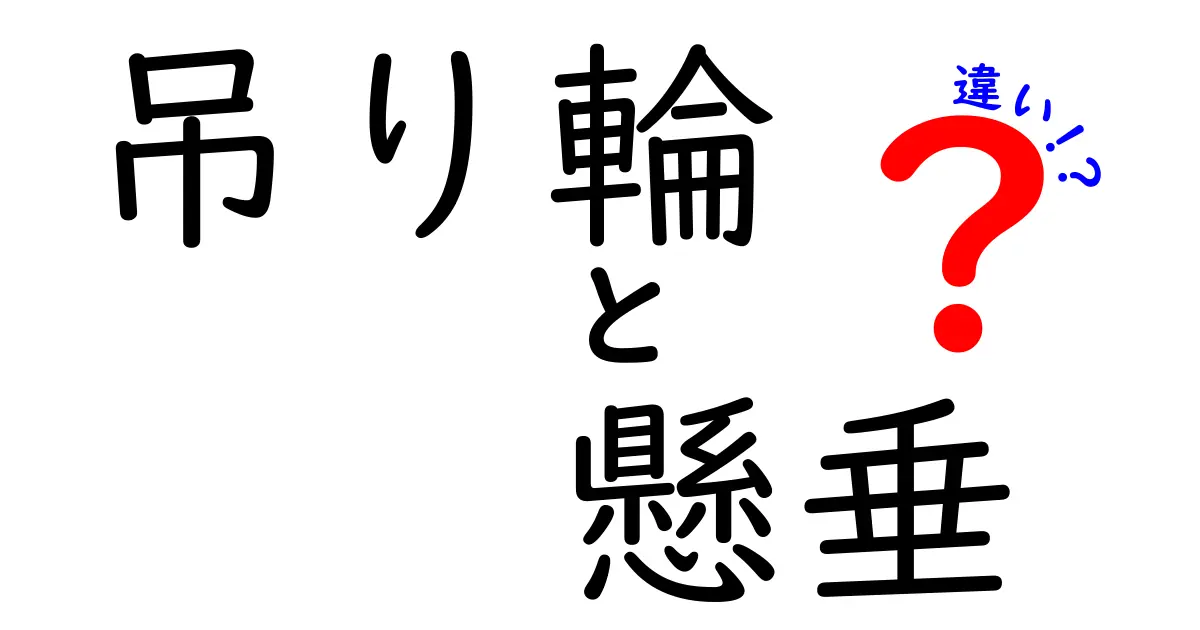

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに、吊り輪と懸垂の違いを理解する基本ガイド
この本文では、吊り輪と懸垂の違いを、初心者にも分かりやすく丁寧に説明します。吊り輪は天井やスタンドから吊るされた二つのリングを使い、体を移動させながら動作を行います。リングは不安定なため、体幹の安定性や肩のコントロールが特に重要になります。これに対して懸垂は一本の鉄棒を掴んで体を引き上げる動作で、主に背中と腕の筋力を直に鍛えます。動作の難易度や使われる筋群の組み合わせが異なるため、練習の組み方も変わってきます。
本章では基本的な違いを把握したうえで、どの順序で練習を進めればよいか、どんな注意点があるかを詳しく解説します。
これを読んだあとは、あなたの体力や目標に合わせて具体的な練習計画を立てられるようになります。健康的に、楽しく続けられるポイントを中心にまとめています。
吊り輪の特徴を詳しく見る
吊り輪の特徴
吊り輪の最大の特徴は不安定さを自分の体幹で支える力を養う点です。リングが揺れるほど体幹の安定性、肩甲骨の動き、胸と背中の連携が求められます。初めは低い高さから始め、リングの揺れに対する反応を身体で覚えることが大切です。練習を進めると、手首の角度、肘の角度、肩の開き方、背中の筋肉の使い方が自然と連動するようになります。
また、吊り輪は動作の幅を変えるだけで負荷の方向が大きく変わるため、同じ種目でも刺激を変えやすい利点があります。これを活かし、段階的に難易度を上げる訓練計画を立てると効率よく強くなれます。
吊り輪の練習の進め方
初級段階はリングの高さを低く設定し、握り方と肩の位置を安定させることから始めます。次に、体幹を硬くせずに動きを連動させる練習、そして腹筋と背筋を同時に使う意識を養います。段階的には、(1)小さな上げ下げ(体を少し持ち上げる程度)、(2)腕の角度を変えて負荷を調整、(3)両手で安定して支え、胸と肩の連携をさらに深める、という順序がおすすめです。練習の効果を感じるには、週に数回の継続と適切な休養が必要です。これらを守れば、リングの不安定さがむしろ体幹の強化につながります。
なお、補助具を使う場合は、補助具のセット位置を毎回同じにして、フォームの崩れを防ぐことが大切です。
懸垂の特徴を詳しく見る
懸垂の特徴
懸垂は背中と腕の筋肉を直線的に鍛える基本的な動作です。バーを握り、体を引き上げることで広背筋や上腕二頭筋が強く働き、フォームを正しく保つことが上達の鍵になります。懸垂の良い点は、体重を使って負荷をコントロールしやすい点と、道具がシンプルで場所を取らない点です。練習の初期には、自己の体重を活用した簡易な動作から始め、徐々に回数を増やしたり、手幅を変えたりして筋肉の使い方を多様化させます。
注意点としては、肩を上げすぎたり反り腰になったりしないよう、正しい軌道を意識することです。効率よく強くなるためには、負荷のかけ方とリカバリーの仕方をセットで考えることが大切です。
懸垂の練習の進め方
懸垂は初期にサポート付きの方法を取り入れると、上達の速度が上がりやすいです。膝を曲げた状態の懸垂、アシストバンドを使う方法、ネスティング段階を設けるなど、負荷を段階的に上げていくと良いでしょう。目標は「ゆっくりと安定して体を引き上げられること」ではなく、「体を使って地面から引き寄せ、顎がバーを越えるまで上げられること」です。これらをクリアするには、背中の筋肉を意識して使う練習が重要で、腕だけでなく肩甲骨の動きも大切です。
また、回復期間を設けることも忘れず、十分な睡眠と栄養をとることが、筋力の成長を支えます。
トレーニング効果と難易度の比較
筋力と体幹の使い方
吊り輪は不安定さを克服するために、体幹の安定性と肩の協調性を大きく鍛えます。体を固定し、腕だけでなく胸や背中の連携を使う場面が増え、上体のコントロール力が高まります。対して懸垂は、背中と腕の筋肉の発達に直接働きます。広背筋を広く使い、引く力を生む筋力が中心です。これらの違いを理解して目標を決めると、効率的な練習計画が立てやすくなります。
難易度と上達の目安
初めて取り組む場合、懸垂は補助を使いながらでも技術を覚えやすいことが多いです。一方、吊り輪は体幹と肩の協調性の獲得に時間がかかることがあります。しかし、リングの不安定さを克服する体幹の強さは、他の種目にも良い影響を与えます。上達の目安としては、懸垂は補助を外して連続回数を増やすこと、吊り輪は小さな上げ下ろしの回数を増やすことを段階的な目標にすると良いでしょう。
安全と準備運動
準備運動とフォーム
怪我を防ぐためには、練習前の準備運動とストレッチが欠かせません。肩回りの柔軟性、手首の動作、背中と胸の筋肉をほぐす運動を取り入れ、正しいフォームを体に覚えさせます。吊り輪では、リングを握る手首の角度を安定させ、肩甲骨を下げて胸を開く姿勢を作ります。懸垂では、体を引く際の軌道をまっすぐ保ち、顎がバーを越える位置まで引き上げることを意識します。これらのポイントを守ると、動作の安定性が高まり、怪我のリスクも減ります。
安全な使い方と怪我予防
器具の設置状態を必ず確認し、支点が安定しているか、リングが緩んでいないか、滑り止めが効いているかをチェックします。痛みのサインには敏感になり、痛みが出る前に休息をとることが大切です。特に肩の痛みは重症化しやすいので、痛みを感じたら練習を中断し、医療機関で診てもらう選択も考えましょう。安全のためには、適切な休憩・栄養・睡眠も欠かさず、毎回の練習を計画的に進めることが大切です。
これからのトレーニング計画
自分の目標を明確にし、週の練習回数を現実的に設定します。吊り輪と懸垂を組み合わせたプランを作ると、上半身の全体的なバランスがよくなります。例として、週2回の吊り輪練習と週1回の懸垂練習を組み合わせ、回数や難度を徐々に増やしていく方法があります。
加えて、休養日を取り、睡眠と栄養を整えることも忘れずに。体は使えば使うほど回復と成長をしますが、過度な負荷は逆効果になることもあるため注意が必要です。
部活の昼休みに友人と話していたときのことだ。吊り輪と懸垂、どちらから始めるべきかで意見が割れていた。私はまず吊り輪の不安定さの中で体幹を育てるのが良いと考え、友人は背中と腕の筋力を先に鍛える懸垂を勧めた。結局、二人で体を動かしてみて、段階的に練習計画を立てることにした。練習を重ねるうちに、体の使い方がはっきりと変わり、痛みも減っていった。今では、どちらから始めてもよいが、目標に合わせて順序を決め、無理なく進めることが大切だと実感している。