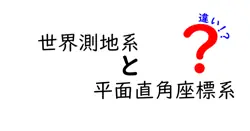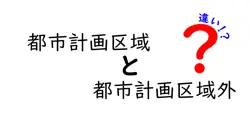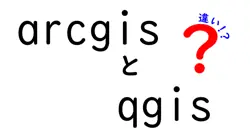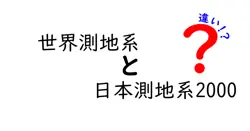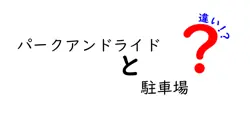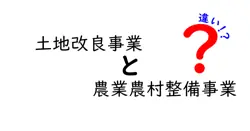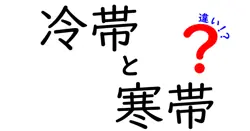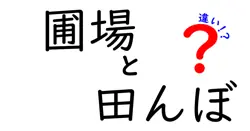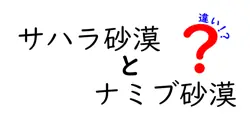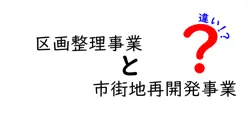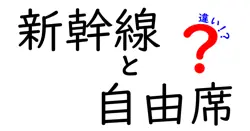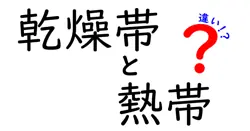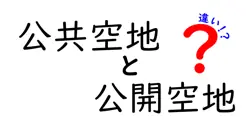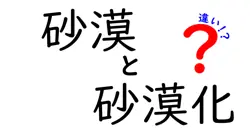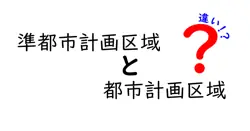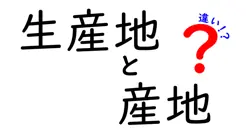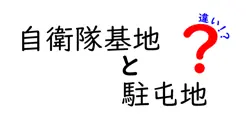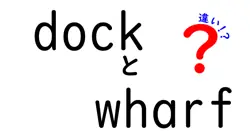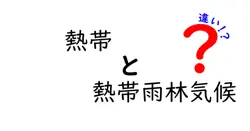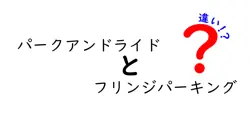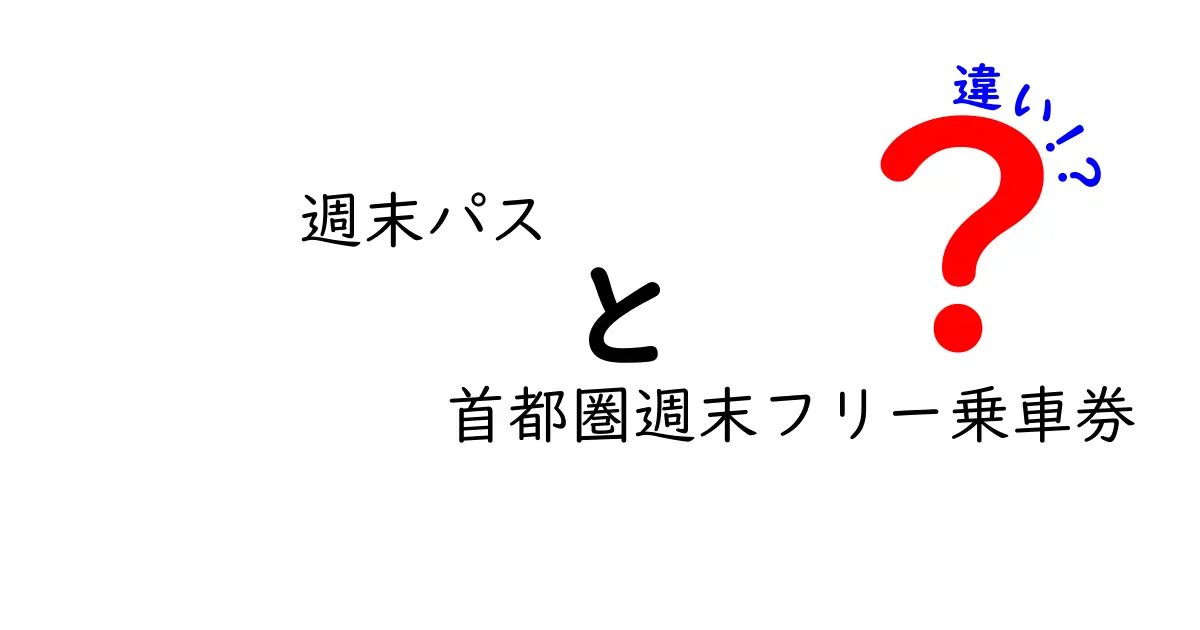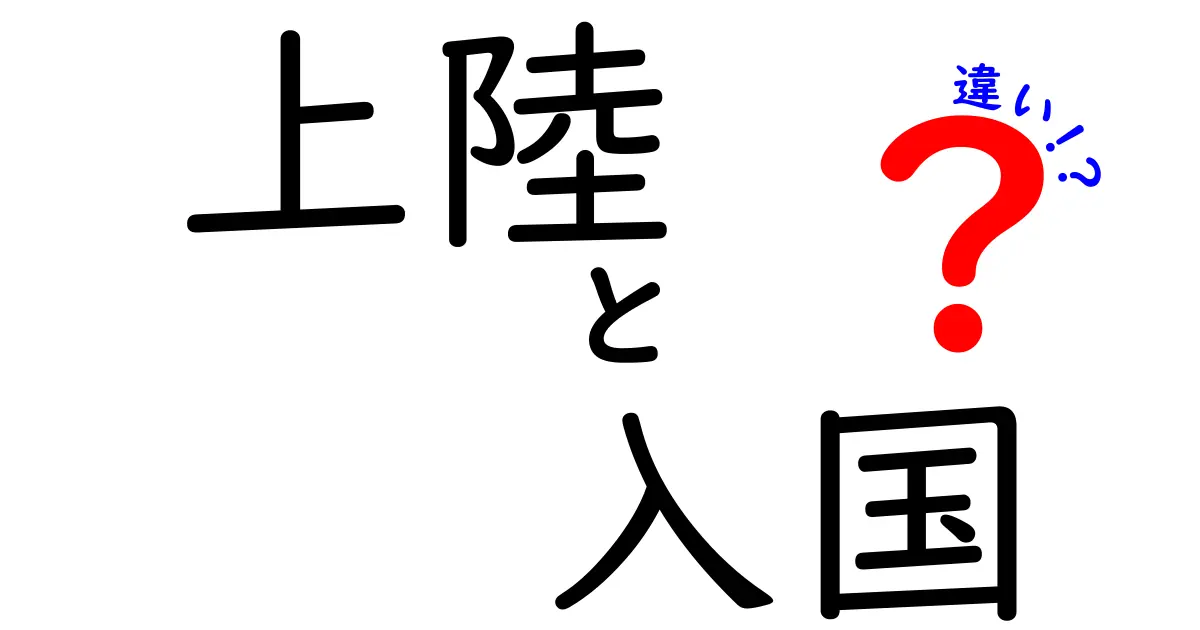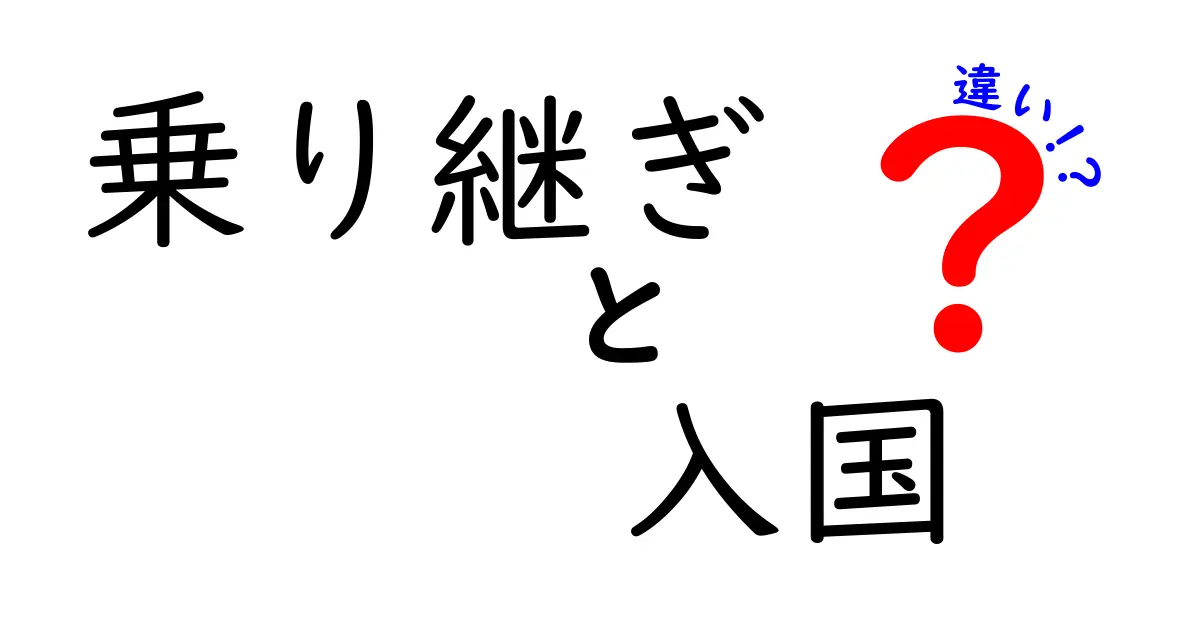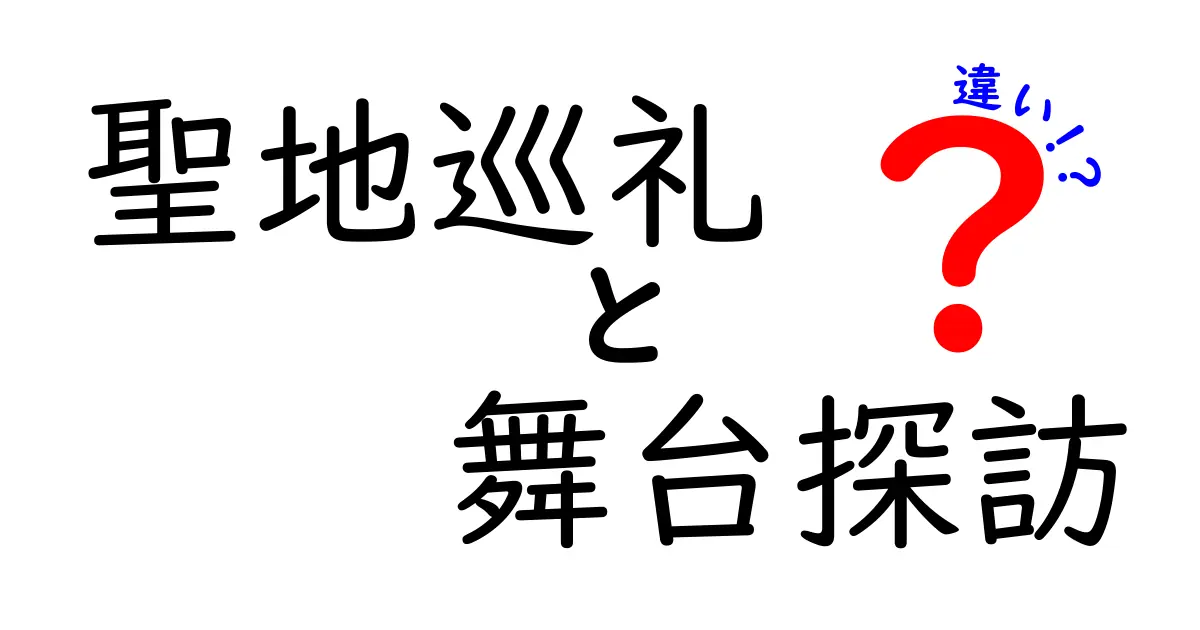

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
聖地巡礼と舞台探訪の違いを徹底的に整理する長文の見出し――目的の違い、現地での行動指針、選ぶ場所の基準、写真やSNSの使い方、そして地域社会への影響まで、初心者にも伝わりやすい具体例とともに解説します。この記事を読めば、何を見てどう感じ、何を守るべきかが自然にわかるようになり、中学生でも自分の興味に合わせて正しく楽しむコツを掴めます。また、同じ場所でも人によって意味が変わること、地元の人の生活と観光のバランス、撮影時のマナー、配慮のポイント、そして危険を避ける方法など、読者が今すぐ実践できる具体的な行動指針を盛り込みます。地元の人との距離感や、観光資源としての地域の魅力を保つための工夫、そして将来の時代に伝わるべき作品の記録としての責任感についても触れ、読者が自分なりの楽しみ方の設計図を描けるよう導きます。
聖地巡礼と舞台探訪は、似ているようで意味と目的が異なる活動です。
聖地巡礼は作品の「聖地」や伝統的背景を体感する行為で、敬意や祈りの要素が混じることもあります。
一方、舞台探訪は作品の舞台設定を現地で歩き、景色や町並みの雰囲気をじかに感じることを楽しみます。
この違いを理解することは、訪問先でのマナーを守り、地元の人に迷惑をかけず、良好な関係を築く第一歩です。
<table>
このような違いを理解すると、訪問の仕方が変わります。
例えば、写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)を撮るときには三脚を控えめに、混雑時間を避ける、住民の私生活の邪魔をしない、ゴミを必ず持ち帰るといった基本マナーを守ることが大切です。
また、地元の人に挨拶をする、至近距離での撮影を控える、商業目的の撮影には事前許可を求めるといった配慮も必要です。
それによって、次の世代のファンにも場所が大切にされ、地域の魅力が長く保たれます。
聖地巡礼と舞台探訪の違いを実生活でどう使い分けるか――具体的なケーススタディとおすすめの進め方
実際の場所を訪れる前に、公式情報をチェックする癖をつけましょう。
作品解説や制作側のコメント、地元観光協会の情報が、訪問の意味を深めてくれます。
一方で、現地に着いたら周囲の人の話をよく聴くこと。静かな朝の時間帯に歩くと風景の美しさが際立ちます。
このように計画と臨機応変さ、配慮と楽しさのバランスを取りながら楽しむのが、長期的に続く趣味への道です。
今日は聖地巡礼という言葉をクローズアップして、ただ場所を訪れるだけではなく、心の動きと社会的影響についても丁寧に雑談していこう。私は以前、ある場所で写真を撮っていたとき、周りの人が困っているのに気づかず、後で地元の方に声をかけられて反省した経験がある。
このキーワードを深掘りすると、ファンの熱量と地元の生活がどう共存できるか、撮影の許可と場所の選択、SNSへの発信の責任など、普段は見落としがちなポイントが出てくる。結局、良い意味の「つながり」を作るのは、マナーと共感だと感じる。だからこそ、私たちは現地の人と作品の世界観を結ぶ橋渡しを意識し、訪問前に調べ、訪問後に感謝の気持ちを伝える習慣を身につけるべきだ。
前の記事: « 民衆と農民の違いを徹底解説|歴史と現代をつなぐ分かりやすい視点