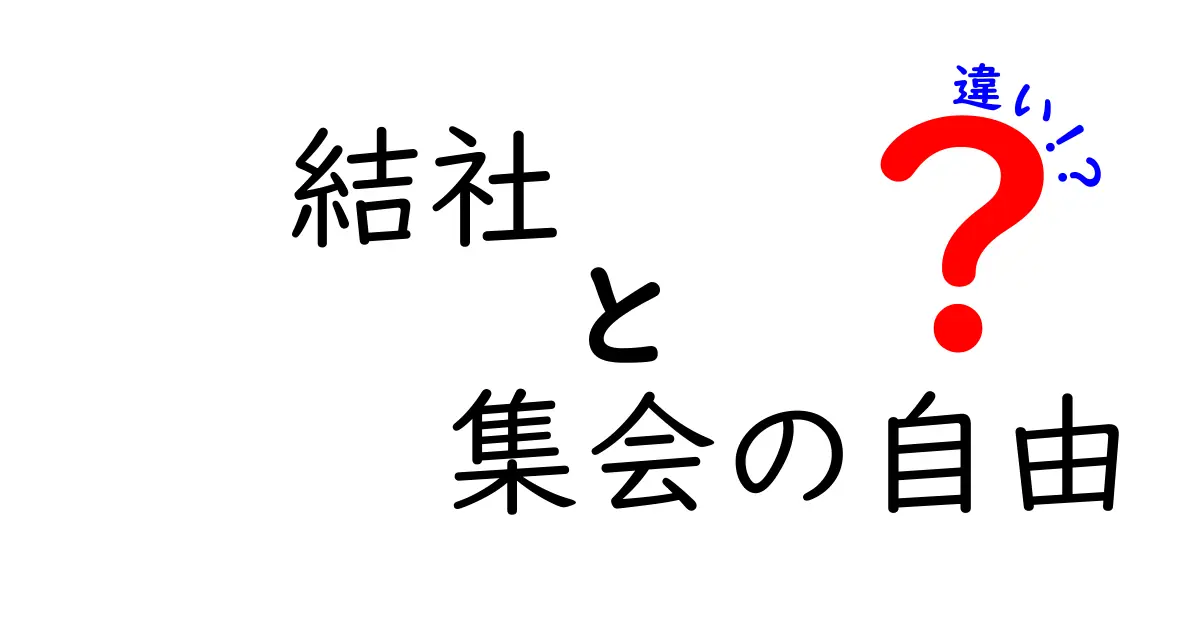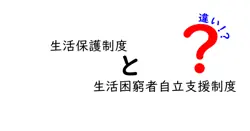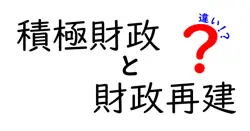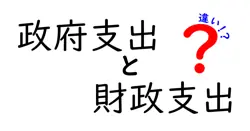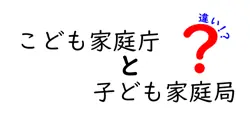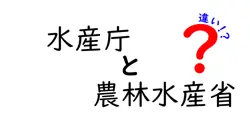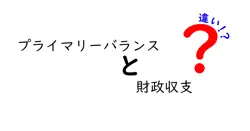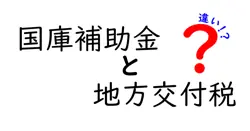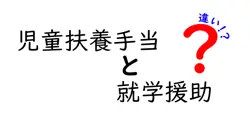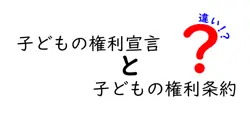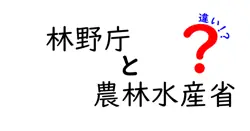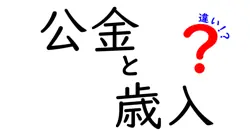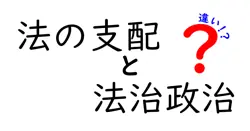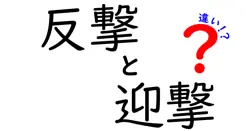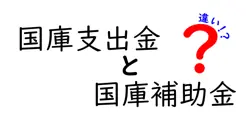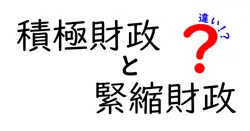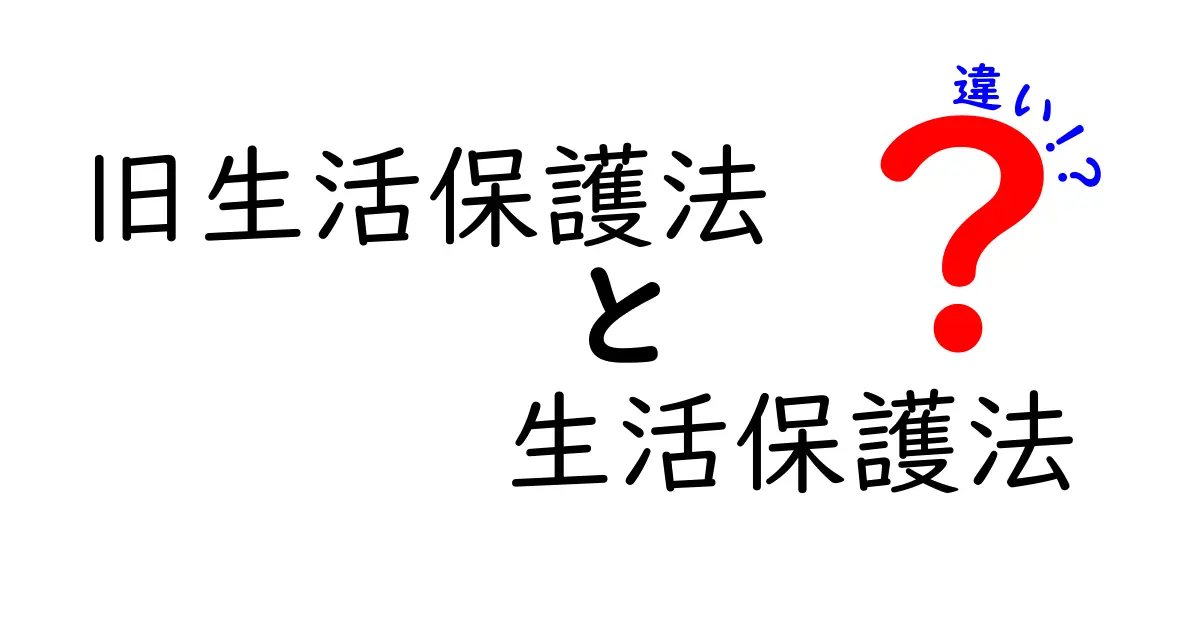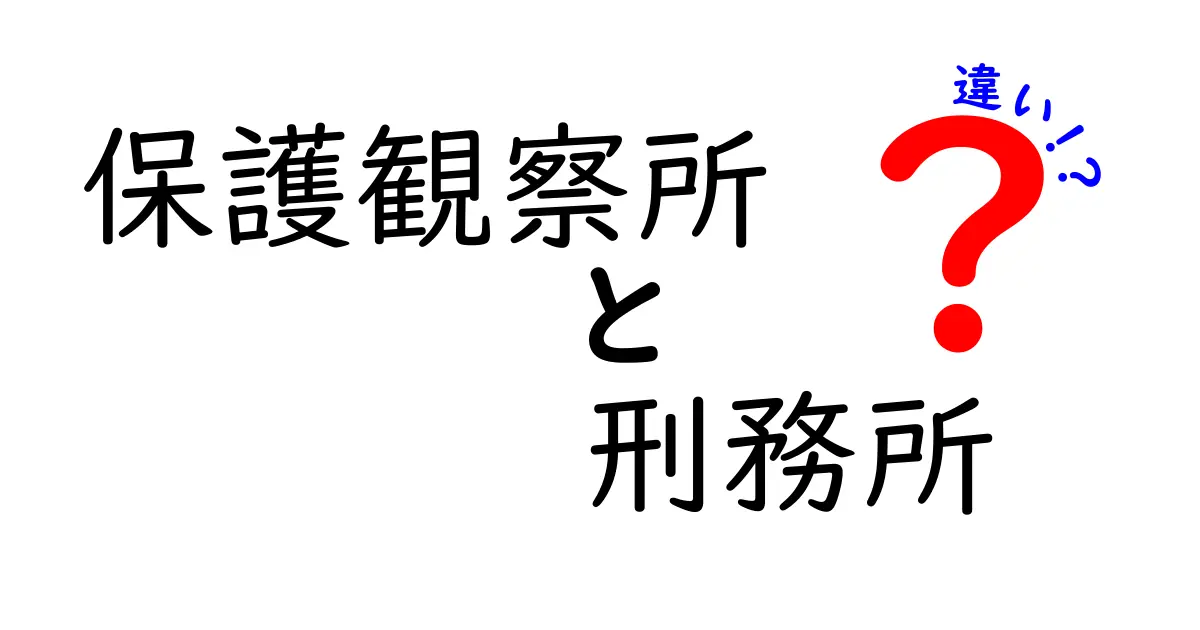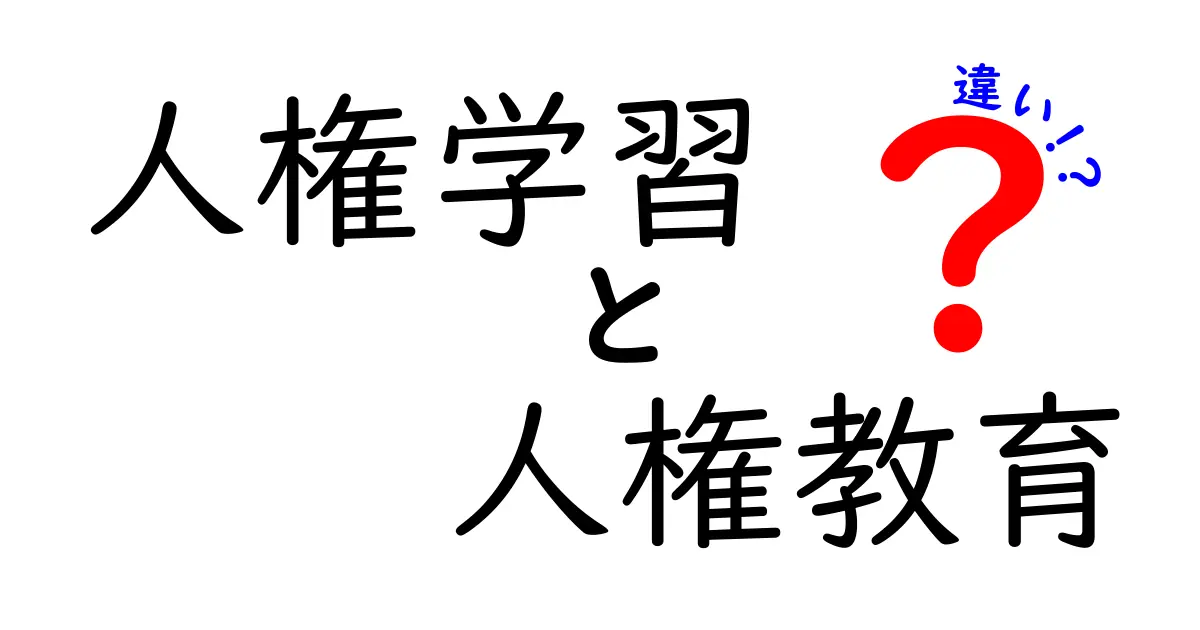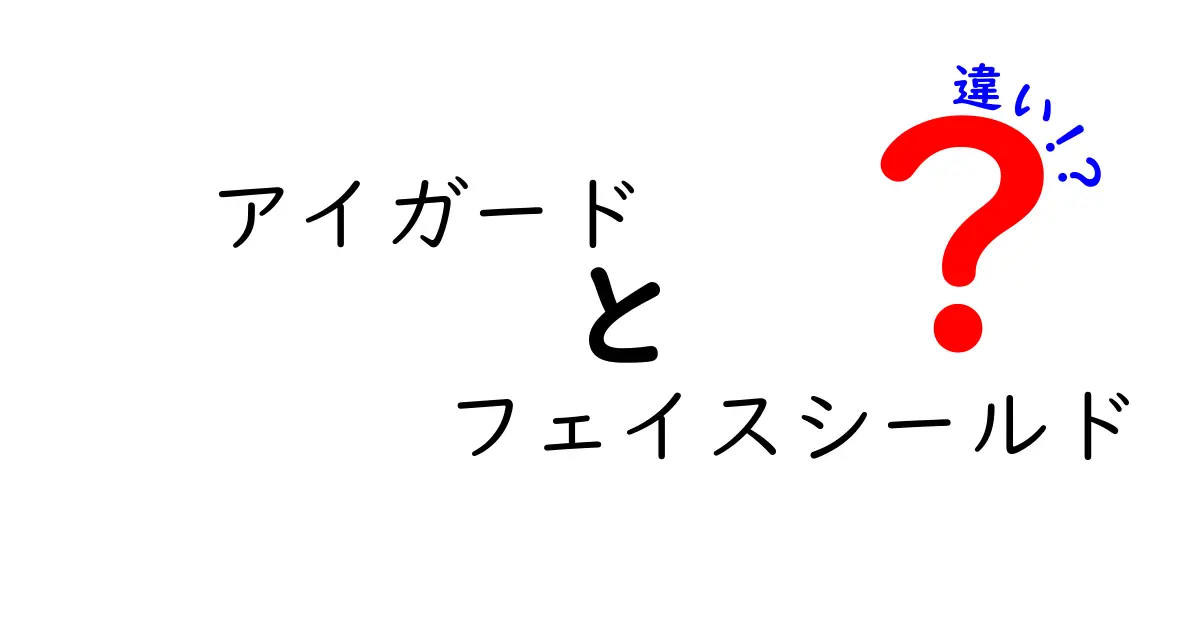

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに
「アイガード」と「フェイスシールド」は、顔を守る安全具として似た役割を持っていますが、実際には守る範囲、用途、使い勝手、手入れの方法などが大きく異なります。アイガードは目の周りの保護を中心に設計され、軽くて動作の妨げが少ないのが特徴です。一方でフェイスシールドは額から顎までを覆う大きな透明板とヘッドバンドで構成され、飛沫や液体の飛散を広い範囲でブロックします。学校の安全対策、職場の衛生管理、スポーツの練習など、場面ごとに適切な選択をすることが求められます。本記事では、基本的な違い、長所と短所、使い分けの実践ポイント、選び方の基準、日常的なメンテナンスについて、中学生にも分かりやすい言葉で整理します。
それぞれの道具がどんな場面で活躍するのか、どんな人に向いているのかを知ることで、事故や怪我を未然に防ぐ行動に繋がります。
違いのポイントを徹底比較
この章では、アイガードとフェイスシールドの大きな違いを、実際の場面を想定してわかりやすく整理します。まず第一に守る範囲が異なります。アイガードは主に目を中心に保護しますが、フェイスシールドは額から顎まで、さらには頬の一部までを覆います。これにより、飛沫がどこまで届くか、視界がどれだけ確保できるかが変わってきます。次に視界と作業のしやすさ。アイガードは軽量で視野が非常にクリアですが、頬や眉の近くの障害物があると作業の動作に影響が出ることがあります。フェイスシールドは広い視野を提供しますが、長時間の使用で曇り対策が必要になることがあります。
さらに適用される場面としては、アイガードは実験や工場の軽作業、スポーツの一部の場面で使われることが多いです。対してフェイスシールドは医療現場、研究機関、接近して作業をする場面、口や鼻を含む大きな防護が求められる環境で活躍します。コスト面では、アイガードは手頃な価格帯の製品が多く、予備を複数用意しやすいという利点があります。フェイスシールドは面板のサイズが大きく、素材によっては高価になることもありますが、丈夫で長く使えるモデルも存在します。
衛生面と清掃方法も異なります。アイガードはレンズのみを拭くことが多く、比較的手入れが簡単です。一方でフェイスシールドは広い面を清掃する必要があり、手袋やクリーナーの選択にも工夫が必要です。
結局のところ、最も大切なのは「場面に合わせて適切な防護具を選ぶこと」です。用途、予算、清掃の手間、着け心地を総合的に比較して決めるのが安全の近道です。
安全第一を心がけ、使う場面に応じた最適解を選ぶことが重要です。
総合すると、日常の学習や軽作業にはアイガードが使いやすく、飛沫や液体の飛散を広範囲に防ぎたい場面にはフェイスシールドが適しています。二つを使い分けることで、安全性を高めつつ作業効率を保つことができます。
ある日、友だちと科学実験室で実験の準備をしていたときのこと。私たちはアイガードとフェイスシールド、どっちを使うべきかで盛り上がりました。友だちは「フェイスシールドは視野が広くていいよ」と言う一方、私は「アイガードの方が軽くて動きやすい」と主張。結局、観察用の実験にはアイガードを使い、飛散の可能性が高い作業にはフェイスシールドを併用するという結論に。結論はシンプルで、状況に合わせて使い分けること。もし迷ったら、まずは自分の作業で何を守りたいのかを考え、次に予算と清掃のしやすさを考えるとよい。安全は道具だけで決まるものではなく、使い方と意識の高さが大きく影響します。
私たちはこの小さな選択から、安全への姿勢を学び、日々の授業や部活動で実践を心がけるようになりました。
次の記事: 子どもの権利に関する条約と子どもの権利条約の違いを徹底解説 »