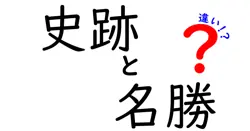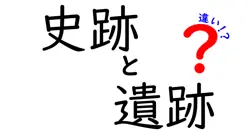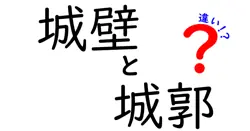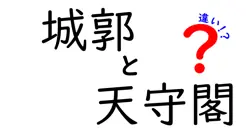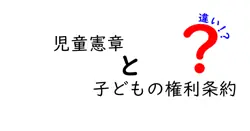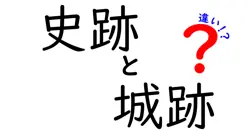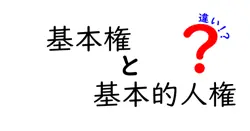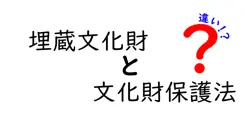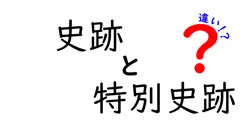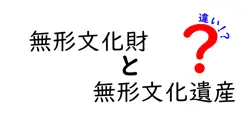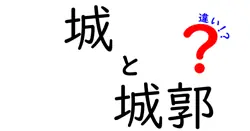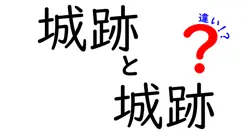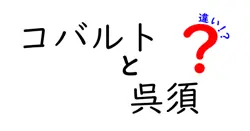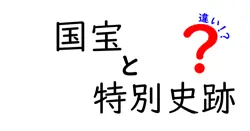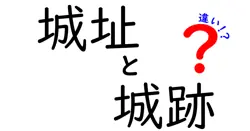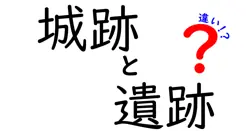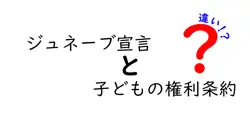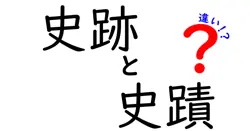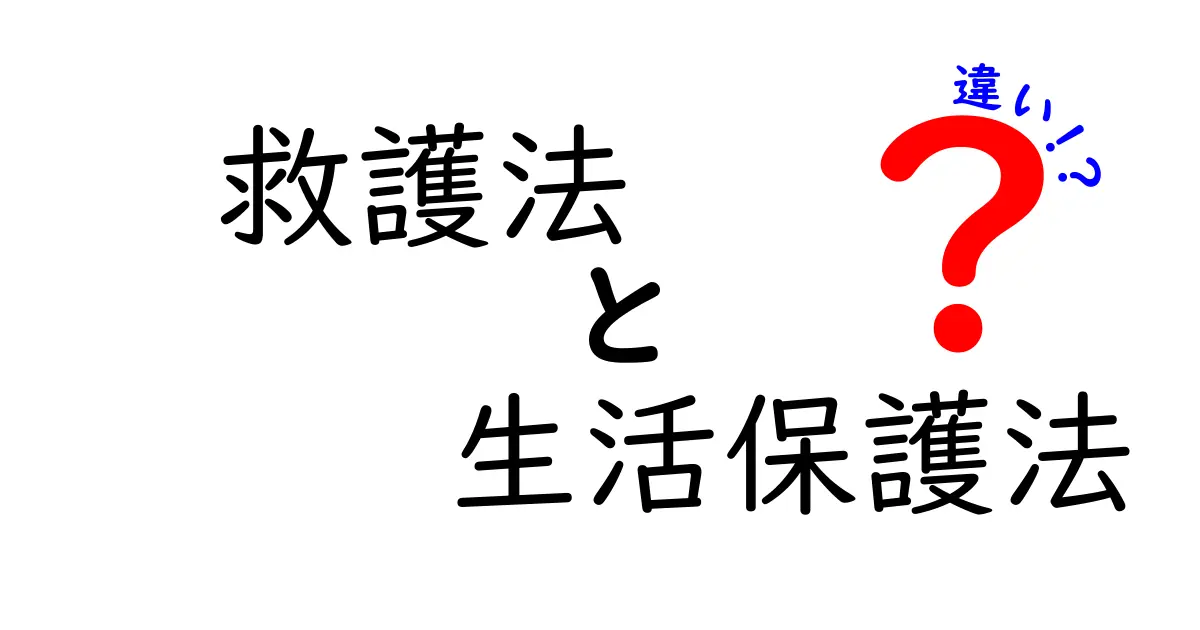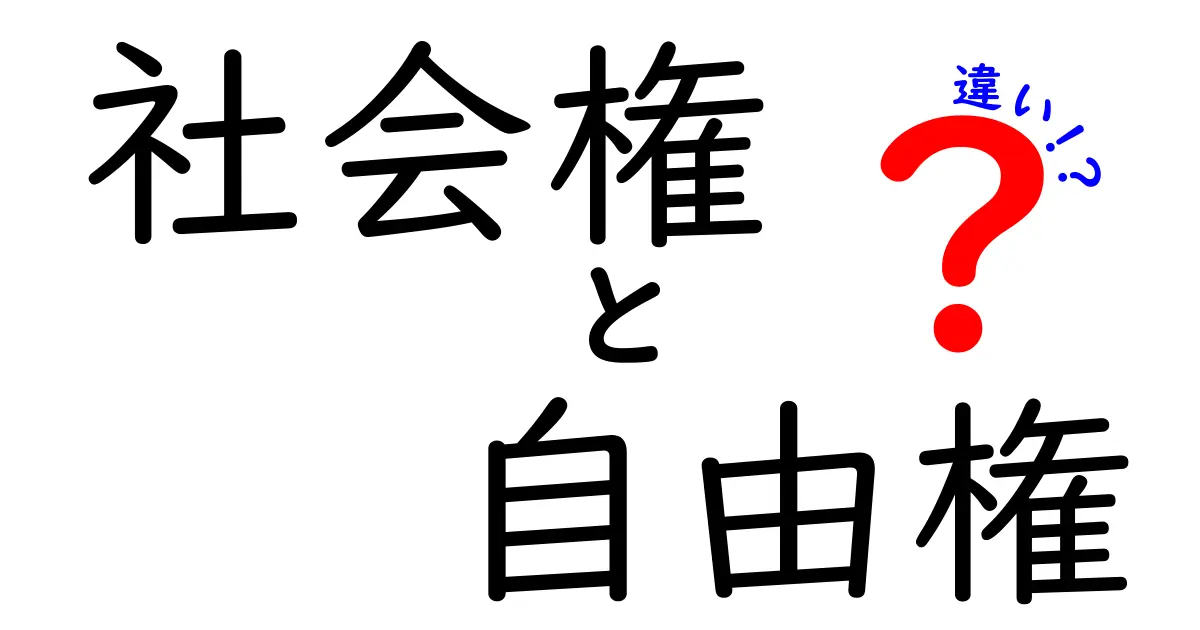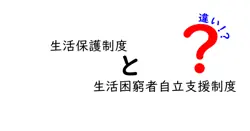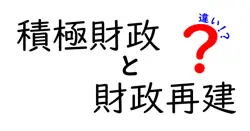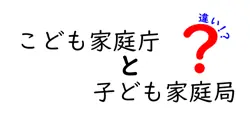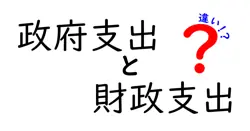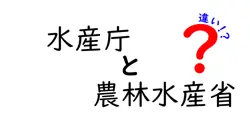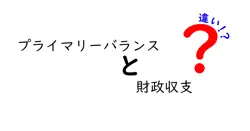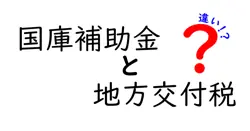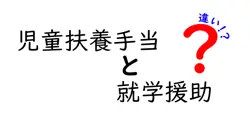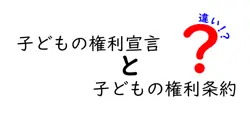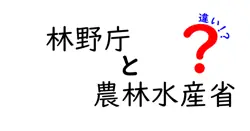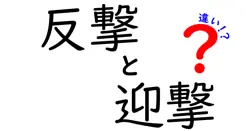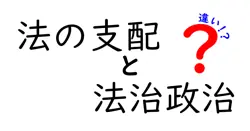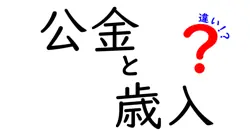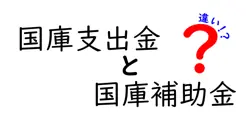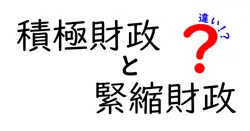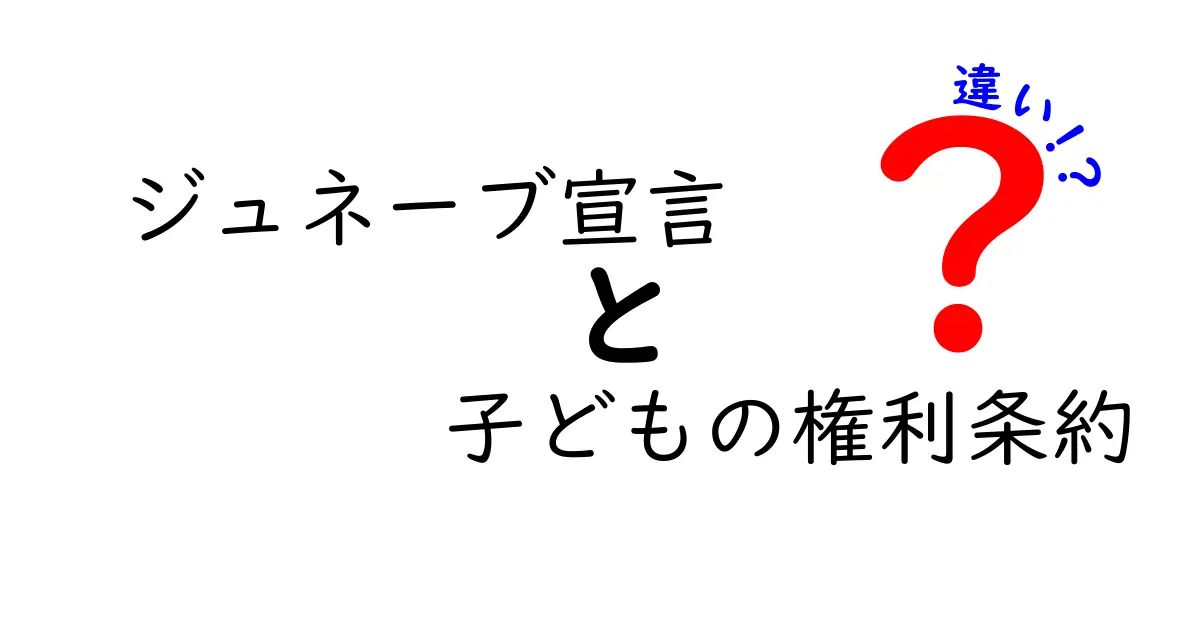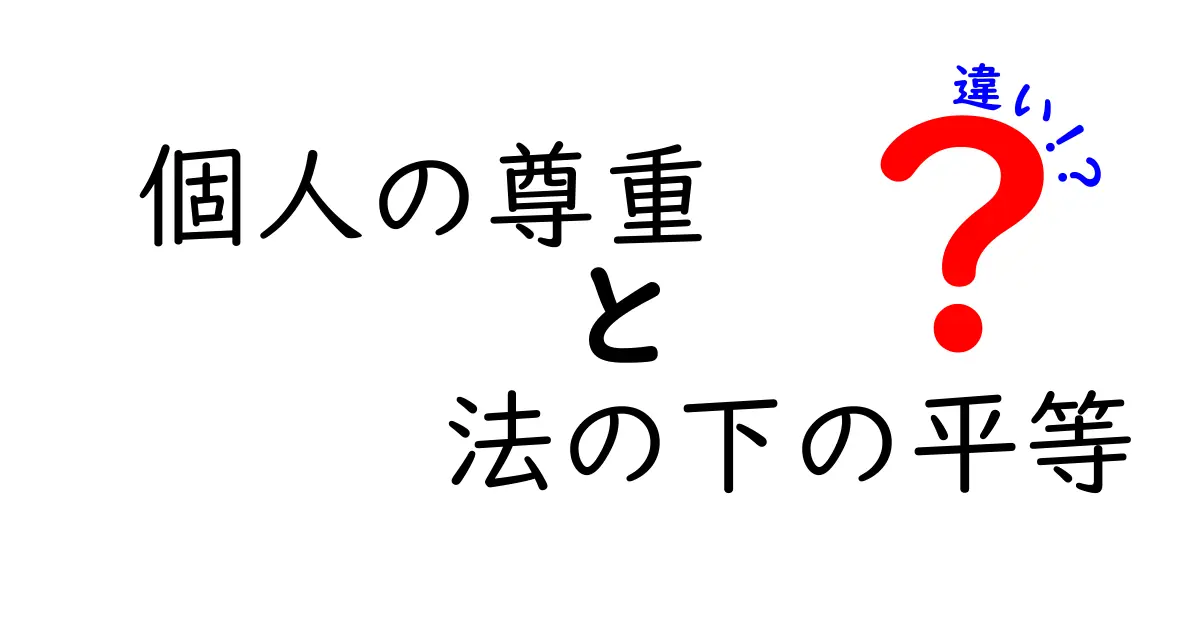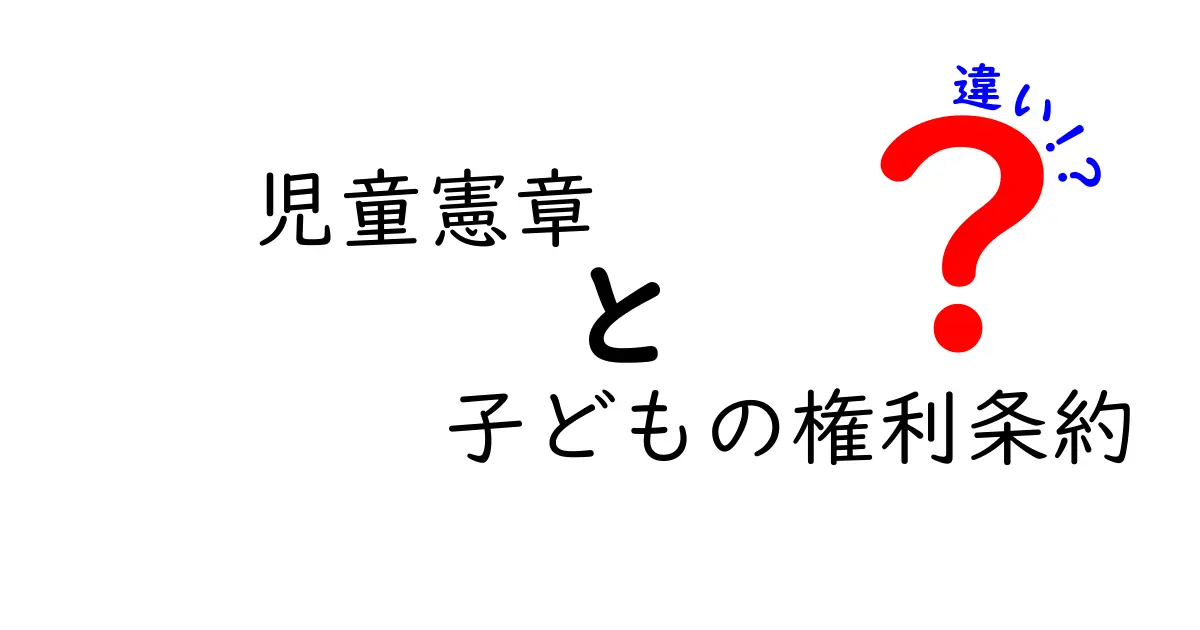

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
児童憲章と子どもの権利条約の違いを徹底解説
この文章では、児童憲章と子どもの権利条約がどう違うのか、どう関係しているのかを、中学生にも分かるように丁寧に説明します。まずはそれぞれの成り立ちと性質を整理し、次に具体的な例を挙げて比較します。児童憲章は日本の国内の宣言であり、CRCは国際法の条約です。これらの違いを知ることで、子どもの権利がどう守られているのか、そして私たち一人ひとりがどのような責任を持つのかを理解することができます。ここでは、法的拘束力、適用範囲、監督機関、教育現場での扱い、家庭での実践など、複数の視点から丁寧に解説します。
児童憲章とは何か
児童憲章は日本が戦後に定めた国の方針を示す国内の宣言です。これは法的拘束力を直接持つものではなく、社会全体の心構えや行動指針としての性格が強いです。学校や家庭、地域社会での子どもの育ちをどう守り、どう支えるかを示しています。児童憲章には子どもが「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」などの基本理念が含まれ、現場での実践としては人権教育の推進、いじめの未然防止、安心して学べる環境づくり、保護者と地域の連携といった具体的な取り組みが挙げられます。
子どもの権利条約(CRC)とは何か
子どもの権利条約は国連が採択した国際法の条約で、世界中の子どもが平等に人権を持つべきだと定めています。CRCは「生存」「成長」「保護」「参加」という四つの大きな分野で権利を列挙しており、国が批准すると国内法や教育、福祉、警察の対応などさまざまな制度にその義務を反映させる必要があります。条約は国にも人にも強制力を持ち、監視機関として人権委員会のような仕組みがあり、定期的な報告と改善が求められます。
違いの具体例
法的拘束力の有無が大きなポイントです。児童憲章は国内の宣言であり、法的拘束力を持たない場合が多いのに対して、CRCは批准国に対して法的拘束力を生じさせ、国内法の整備や予算配分、教育制度の変更など具体的な対応を求めます。
また、適用範囲の広さも違います。児童憲章は日本の子どもを対象にした理念的な指針であり、CRCは世界中のすべての子どもに適用されます。
監督機関や監査の方法も異なり、CRCには定期報告や独立委員会による監視が組み込まれています。
日本での適用と現状
日本はCRCを1994年ごろに批准し、それ以降国内法の整備が進みました。教育行政、福祉、保健分野などでCRCの精神を反映させる動きが続いています。しかし、現実には「条約の理念と日常の実践」の間にギャップもあり、学校現場でのいじめ対策、児童虐待の予防、障がいのある子の支援など、具体的な改善課題はまだ残っています。児童憲章とCRCの違いを理解することは、私たちがより良い社会を作る第一歩です。
比較表
<table>日本での適用と現状の深掘り
学校現場の実践としては、いじめ防止、子どもの安全、保護者と地域の協力など、日々の授業や生活の中で児童憲章の精神を体現する取り組みが進んでいます。一方、CRCは国際的な視点から日本の法制度を見直すきっかけを提供しており、学校や自治体がCRCの勧告を受けて施策を見直す事例も増えています。ここから学べるのは、単に条文を暗記することではなく、子どもの声をどう社会全体で尊重し守っていくのかという姿勢です。地域の子育て支援や学校内の相談体制を充実させることは、児童憲章とCRCの両方の精神を生かすために不可欠です。
ねえ CRC と児童憲章の話、難しく感じるかもしれないけれど、実は日常生活にも深く関係している話題なんだ。CRC は世界の子どもの権利を守る国際法で、日本が批准して国内の制度を変えるきっかけになる。児童憲章は日本の子どもたちの育ちを支えるための国内の宣言。つまりCRC は大きな仕組み、児童憲章は私たちが身近にどう生きるかのヒント。どちらも「子どもの声を聞く」ことが出発点だよ。