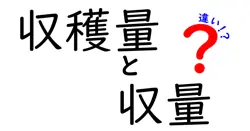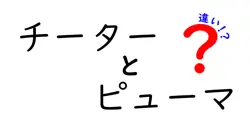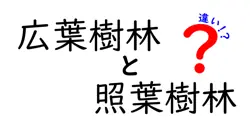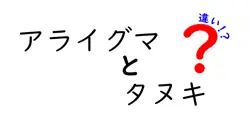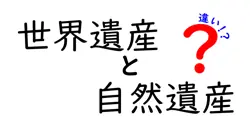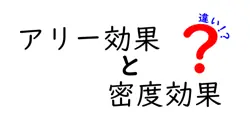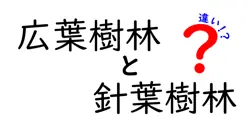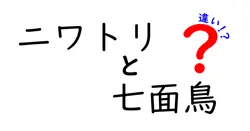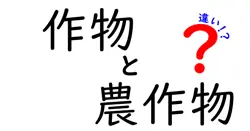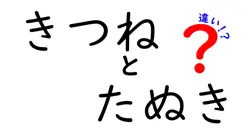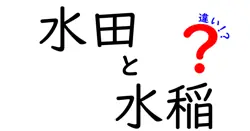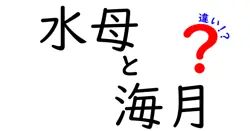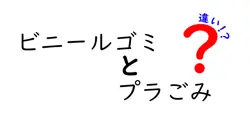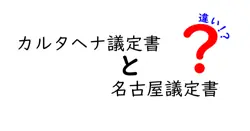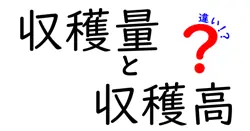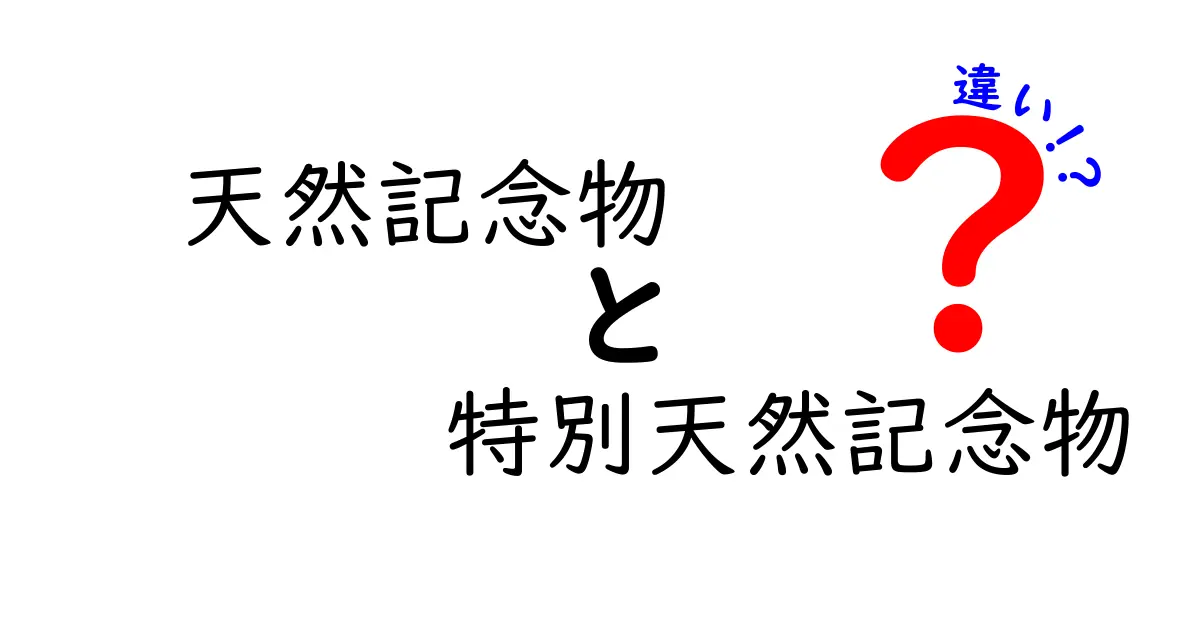

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
天然記念物と特別天然記念物の違いを理解するための基礎知識と制度の成り立ちを、中学生にも分かるようにできるだけ詳しく解説する長文見出しです。この見出しの役割は、なぜこの二つの用語が混同されがちなのか、どうして異なる保護の対象や権限が設けられているのか、どのようにして指定が進むのか、そして一般の人が守るべきルールは何かを、実例とともに順序立てて説明することです。
天然記念物と特別天然記念物は、私たちの暮らしの中では“自然の宝物”として扱われますが、正式には法的な制度の中で守られている制度用語です。まず大切な点は、これらの言葉はどちらも「保存の対象となる自然の物事」を指すということです。
ただし、守るべき強さや対象の大きさ、そして関与する機関が異なるため、実際の運用や日常生活への影響が変わってきます。次の節からは、具体的な違いを分かりやすく整理していきます。
この解説を読めば、学校の資料やニュースで出てくる名称が出てきたときにも、すぐに「どちらの制度の話か」「どんな保護がされているのか」が筋道立てて理解できるようになります。
天然記念物と特別天然記念物の定義・指定手続き・保護の実務を整理する長い見出しです
まず定義から整理します。天然記念物は、自然界にある動植物・地形・地質現象など、全国的または地域的に貴重で保存の価値が高いものを指します。特別天然記念物は、その中でも特に重要度が高いものとして、国の指定を受ける厳格なカテゴリです。つまり、すべての特別天然記念物は天然記念物ですが、すべての天然記念物が特別天然記念物というわけではありません。
指定の流れとしては、まず専門家の調査・評価を経て、関係機関(国や都道府県の教育委員会など)により「保存の重要性が高いかどうか」が判断されます。
国が指定する場合、法的な根拠は文化財保護法などの枠組みの中で位置づけられ、保護の範囲や規制内容が明確に定められます。地域の自然であれば、都道府県レベルの独自指定が行われることもありますが、特別天然記念物の指定は原則として国の手続きで進行します。ここで重要なのは、指定が進むほど保護の強度が高まり、一般の人の立入りや開放の条件、研究・教育利用のルールが厳しくなる場合が多い、という点です。
現場の運用は多様で、保護対象の周囲には立入制限や採取・撮影の制限、研究機関による追加の運用ルールが設定されることがあります。これらは保護対象を守るための現実的な対応であり、観光や学習の機会を損なわないよう、バランスを取りながら運用されます。
<table>
次に、実際の活用例を見てみましょう。天然記念物に指定されている場所は、地域の教育資源として授業の題材となり得ますし、自然観察会や環境教育プログラムの場としても活用されます。しかし、特別天然記念物は公的な保護が強化される代わりに、開放と利用にも厳格な条件が課されることが多いため、研究者と一般の人とのバランスをとりながら運用されるのが特徴です。
なぜこの二つの制度が並存するのか――制度の背景と現場の工夫
日本には豊かな自然や歴史的な地形が多く、それらを守るための制度が複数あります。天然記念物は地域の宝を広く守る基盤として機能します。一方で、特別天然記念物は国としての最重要資産を厳格に守る「最高峰の保護対象」として位置づけられています。現場では、観光地としての訪問者数、研究者のアクセス、地域住民の生活への影響などを総合的に考慮し、適切な制限と緩和を組み合わせています。
このような仕組みは、自然の美しさを維持しつつ、教育・研究・地方創生の機会を損なわないよう工夫されています。
現場のポイントを押さえる要点リスト
・天然記念物と特別天然記念物の違いを知るときは「指定者と指定基準」を最初に確認することが大事です。
・特別天然記念物は国の指定であり、保護の強度が高く、研究・教育利用の条件も厳しくなることが多いです。
・表のような比較表を使うと、イメージがつかみやすくなります。
・現場でのルールは、看板やパンフレット、観光案内所で詳しく案内されているので、訪問時には事前に確認しましょう。
まとめとして、天然記念物と特別天然記念物は似て非なる制度です。違いを正しく理解しておくと、自然や場所を訪れるときに「何ができて、何ができないのか」をすぐに判断でき、地域の守るべき宝を尊重した見学・研究・教育が実現できます。
友達と放課後に自然公園を歩きながら、天然記念物と特別天然記念物の違いについて雑談してみたことがあります。僕らの学校の授業では、どちらも“守るべき自然の宝物”と教わりますが、特別天然記念物は国の最重要資産として扱われる点が特に印象的でした。
その結果、見学ルールや撮影の配慮、研究のための申請手続きなどが、普段の生活とどう結びつくのかを実感として感じることができました。
結局は、自然を大切にしながら人が学び、楽しむバランスをどう保つかという話に戻ります。だからこそ、私たちにも公園のルールを守る意識が必要だと感じます。
次の記事: 特別天然記念物と絶滅危惧種の違いを徹底解説|何がどう違うの? »