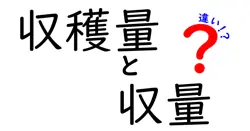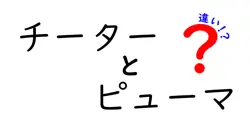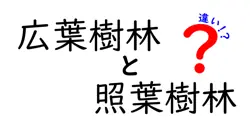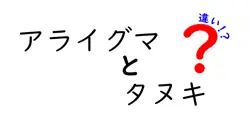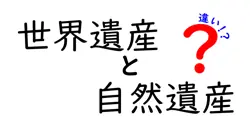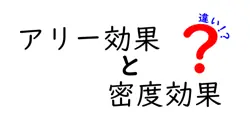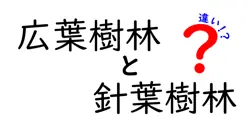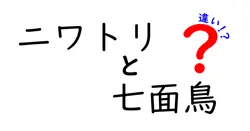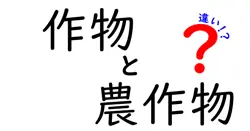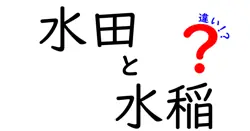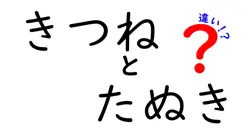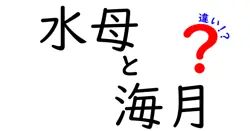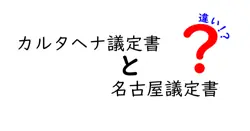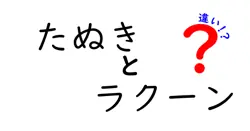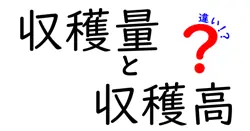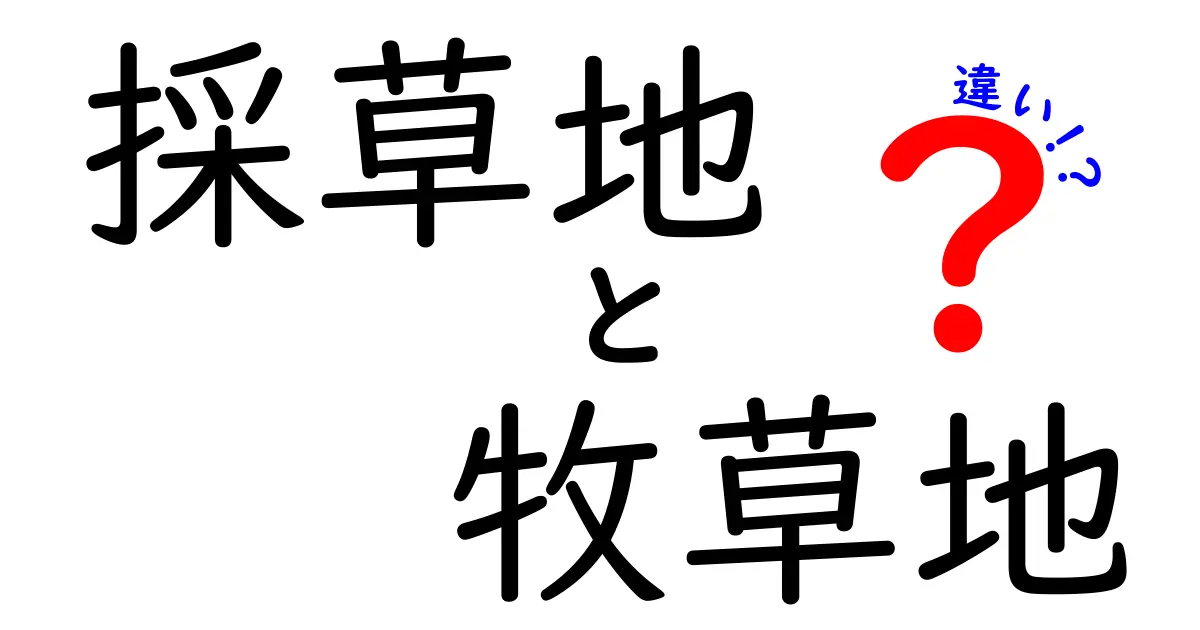

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
採草地と牧草地の違いを学ぶための基礎知識
畜産の現場では日常的に耳にする言葉が2つあります。採草地と牧草地です。両者は似ているようで用途や管理の目的が大きく異なります。採草地は草を刈ってから乾燥させ、飼料として保存することを前提に設計された土地です。冬場に不足しがちなエネルギー源を確保するため、刈り取りのタイミングや乾燥方法、保存の仕方が重要になります。
一方の牧草地は生草を直接家畜に与える場所で、季節ごとに草の生育状況や草種の組み合わせを調整します。牧草地では草の柔らかさや青草の風味、齧りやすさが大事な要素となり、草丈・葉量・茎の硬さを管理して、安定した給餌を目指します。これらの差は土地の設計図にも表れ、刈り取りの頻度、草種の選択、灌水・排水の設計、さらには牧場の経営計画にも深く関わってきます。
以下の章では具体的な違いを「用途」「管理」「経済」「現場の実例」という観点から詳しく見ていきます。
まず前提として覚えておきたいのは、採草地と牧草地は同じ草地でも「目的が違えば設計や運用も大きく変わる」という点です。この差を理解することで、土地の価値を最大化しやすくなります。
1)目的と用途の違いを深掘り
採草地と牧草地の最も大きな違いは「草の用途」です。採草地は草を刈って乾燥・貯蔵して冬期の飼料を確保する目的、いわば保存食の生産ラインの役割を果たします。刈り取り時期は草の乾燥適性と品質を最重視し、乾燥後の風味・栄養価・水分量を安定させる工夫が必要です。
対して牧草地は生草をそのまま家畜に提供する目的で、草の長さ・柔らかさ・咀嚼感・風味を調整します。牧草地は季節ごとに草の生育サイクルに合わせて刈り取りの回数・草種の組み合わせを変え、草が過剰に伸びて茎が硬くなるのを避ける管理が求められます。こうした目的の違いは、草の育成計画や収穫・給餌のタイミングに直結します。
この点を理解しておくと、現場の作業計画を立てるときに「何の草を、いつ、どれくらい採るべきか」が見えやすくなります。
また、使用目的が決まれば草種の選択肢も変わります。採草地では乾燥に強く、保存性の高い品種を選ぶケースが多く、牧草地では生草の柔らかさを重視しておおむね若い草や葉の多い品種を組み合わせることが一般的です。草種の違いは病害や天候にも影響を受けるため、地域性や季節性を考慮した作付け計画が必要です。
2)管理方法と季節の変化を詳しく解説
管理方法は土地の目的によって大きく異なります。採草地では年に数回の刈り取りが中心となり、刈り取り間隔は乾燥具合・草の品質・貯蔵計画に合わせて設定します。乾燥過程では風通しの良い場所を選び、畜産の需要に合わせて加圧・巻き取り・乾燥の速さをコントロールします。
一方の牧草地は生草を継続的に提供するため、草丈・葉量・葉柄の柔らかさを常時モニタリングします。季節が進むにつれて草の勢いが増減するため、草丈の目標値や草種の混合比を季節ごとに調整します。夏場は高温多湿になる地域で病害が出やすいため、薬剤の使用と放牧の回転を組み合わせ、草地の回復を促します。秋には草の再生を促すための肥料投入や、冬場の保護のための覆土・マルチの活用を検討します。
3)現場の実例と表で見る比較
実際の農場では、採草地と牧草地を組み合わせて運用しているケースが多く見られます。以下の表は、典型的な違いを「用途」「作業頻度」「草種の例」「収穫タイミング」「経済的な特徴」の観点から整理したものです。表を参考に自分の地域・規模に合わせて設計を見直すと良いでしょう。
<table>この表を見ると、同じ「草地」でも用途が違えば管理の焦点が全く異なることがわかります。現場では天候、土壌、水資源、飼育方針を総合的に考慮して、どの割合で採草地と牧草地を組み合わせるかを決定します。
重要なのは、地域の条件と家畜のニーズを結びつけた現実的な計画を立てることです。そのためには、継続的な観察とデータの蓄積が不可欠です。
友人と農場を見学していると、採草地と牧草地の違いがすぐに腹落ちします。友人が「採草地っていうのは、草を刈って干草にする工場のような場所だよね」と言いました。私は「そう、つまり冬の飼料を確保するための貯蔵計画が前提なんだ」と返しました。話は続き、牧草地は“今この瞬間のごはん”を用意する場所だと理解。草の柔らかさが重要なので、種の組み合わせも工夫します。見学中、黒板に描いた図には土壌の排水と風通しの良さが大きく影響するとあり、それを体感すると、草の高さだけでなく全体の環境が飼料の品質に直結することがよくわかります。自然のリズムと人の知恵が重なる現場こそが、良い飼料を作る鍵なんだと改めて感じました。
次の記事: 牛乳の脂肪分の違いを徹底解説|味・カロリー・用途別の選び方 »