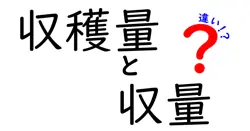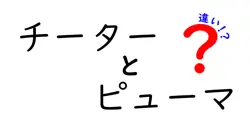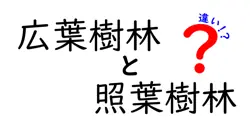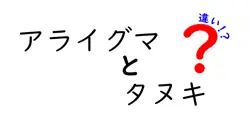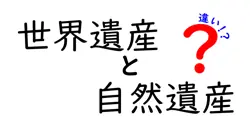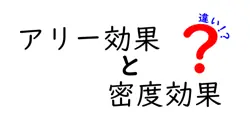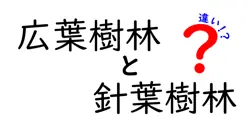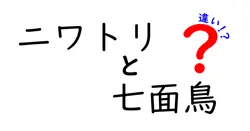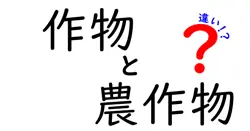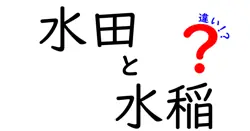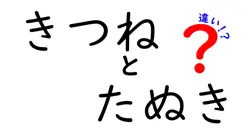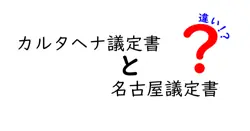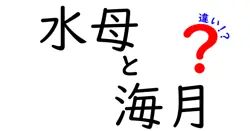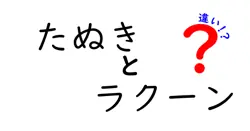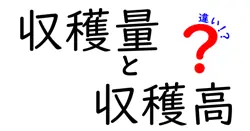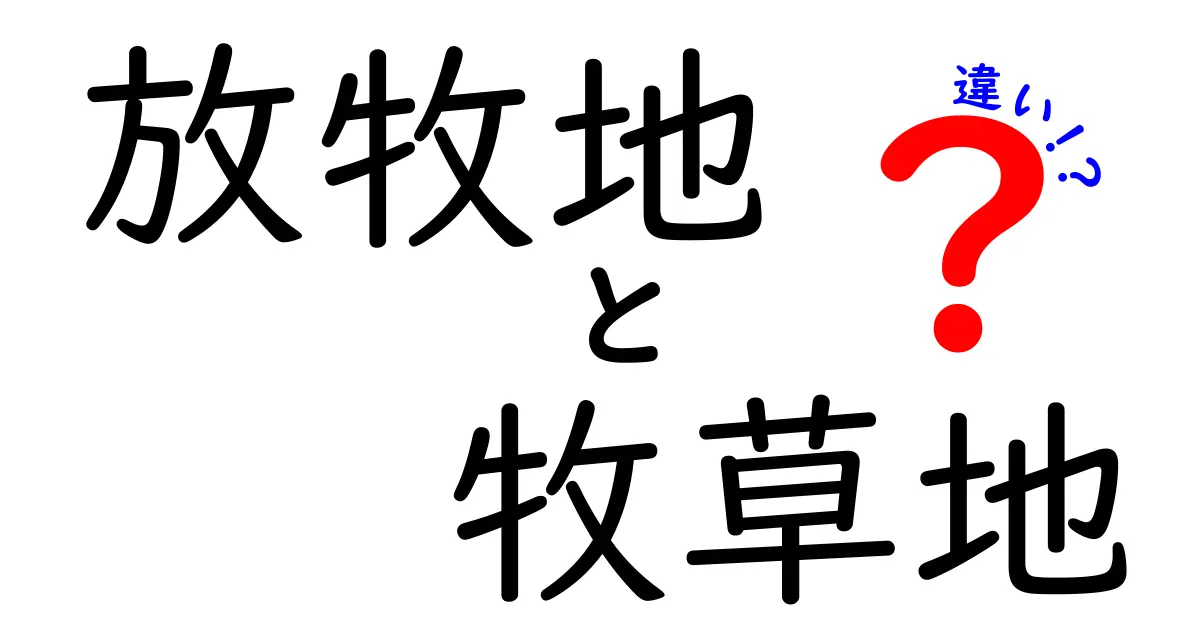

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
放牧地と牧草地の違いを理解する基礎
畜産の世界には「放牧地」と「牧草地」という言葉があります。どちらも畜産の場で草を食べる場所ですが、目的や作り方、動物の生活に与える影響が大きく異なります。この記事では、中学生にも分かるように、放牧地と牧草地の違いを分かりやすく説明します。まず押さえるべきポイントは次の3つです。1つ目は「草を育てる人の手の有無」、2つ目は「動物の自由度と管理の度合い」、3つ目は「環境への影響と持続可能性」です。放牧地は、自然の草が生えたままの地面を活かして、動物が自由に歩き回り草を食べる場所です。草は季節や天候で変化します。牧草地は、人が草を育て、刈り取り・乾燥・保存まで計画的に行う飼料作りの場所です。
この違いは、実際の畜産の現場でもとても大きな意味を持ちます。放牧地では動物の運動量が増え、草地の踏み固めや排水、土壌の微生物の働きが変わりやすい一方で、天候に左右されるリスクも大きくなります。牧草地では草の高さを一定に保つための刈り取りや施肥、草種の組み合わせといった管理作業が中心となり、飼料の安定供給を確保しやすい反面、費用や労力がかさむこともあります。
ここからは、具体的な使い分けのコツや、現場でよくある質問にも答えていきます。
放牧地と牧草地の実際の使い分けと影響
現場の運用イメージとして、放牧地と牧草地をどう組み合わせるかが成績に直結します。動物に自由を与えつつも、飼料の安定性を確保するために「回転放牧」という手法がよく使われます。回転放牧では、動物を複数の区画に分け、一定期間ごとに移動させることで草が再生する時間を作ります。これにより草地の疲弊を防ぎ、土壌の水はけと微生物の活動を活発にします。
同時に、牧草地は品種の選択と栽培管理が鍵です。嗜好性の高い草、栄養価の高い草、乾燥耐性のある草を組み合わせることで、動物の成長スピードを安定させ、飼料費を抑える効果が期待できます。
このような現場の取り組みは、子どもでも理解できる“自然と人の協力”の良い例です。放牧地で動物の体力を使い、牧草地で草の育ちをコントロールする、そんな二刀流の運用が畜産の現場では普通になってきました。 環境保全と経済性の両立を目指すとき、放牧地と牧草地の使い分けは欠かせない設計図となります。
放牧地の話をしていたら、友達のカエルさんが“放牧地と牧草地、どっちが楽なの?”と尋ねてきた。僕は答えたんだ。放牧地は動物が自由に歩き回り草を食べる分、体を使って育つ喜びがある反面、天候に左右されて餌が足りなくなることもある。牧草地は草を育てて飼料として保存するので安定しやすいけど、手間と費用がかかる。結局は二つを組み合わせて、自然の力と人の管理を両立させるのが賢い選択だと思う。現場の工夫次第で、動物の健康も環境も守れるって、僕は信じています。話をしていたら先生が「自然と人の知恵のコラボレーションだね」と言ってくれた。僕もそう感じました。
前の記事: « サラダ油と食用油の違いを徹底解説!使い分けのコツと選び方ガイド
次の記事: K2とビタミンKの違いは何?中学生にもわかる徹底解説 »