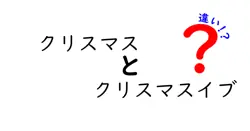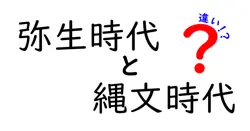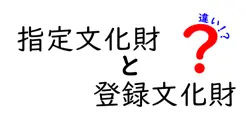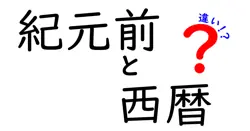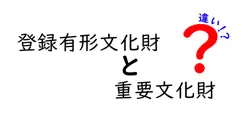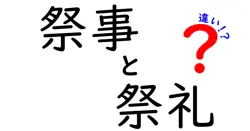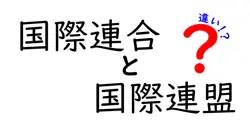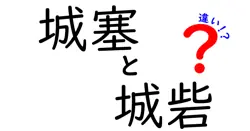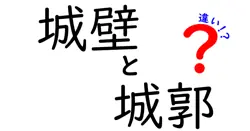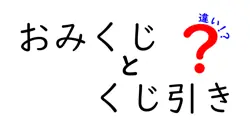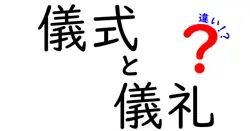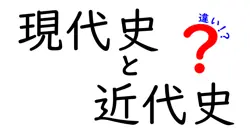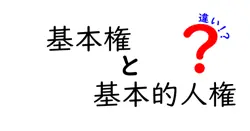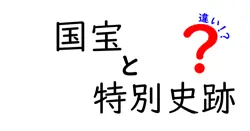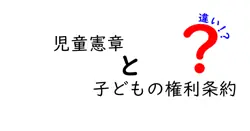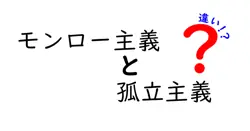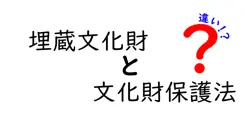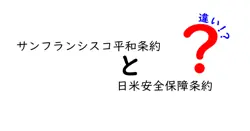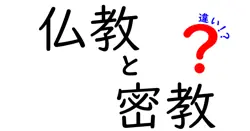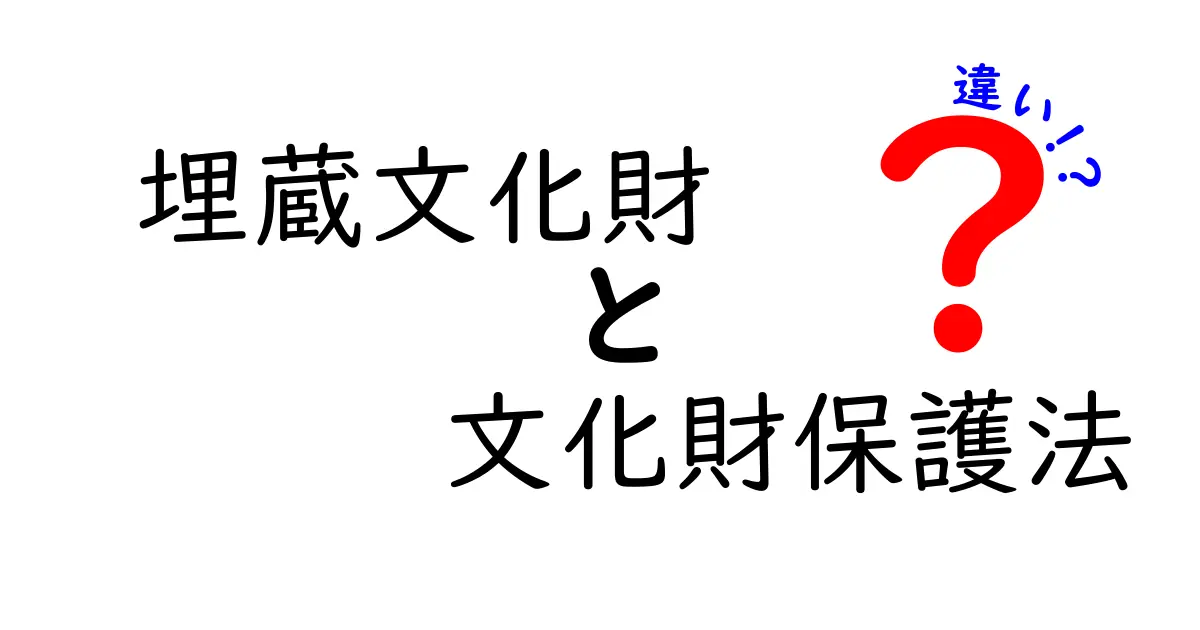

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:埋蔵文化財と文化財保護法の違いをざっくり把握する
この3つの言葉は、歴史の授業や現場の作業現場で耳にする機会が多いものの、実際には別々の意味と役割を持っています。まず「埋蔵文化財」は地中に眠っている遺物の総称で、土器・石器・建物の基礎の痕跡など、過去の人々が使ったものが長い時間の中で地面の下に残っている状態を指します。これらは場所や時代によって意味が大きく異なり、ただの「石や土の塊」ではなく、文化や歴史を理解する手掛かりになる貴重な資産です。次に「文化財保護法」は国が文化財を保護・活用するための枠組みを定めた制度で、どのようなものを文化財とみなすのか、保存・修復・展示・教育利用をどう進めるのか、どの機関が監督するのかといった点を決めています。さらに「違い」という観点から見ると、埋蔵文化財は眠っている物そのものを指す名詞的な概念であり、文化財保護法はそれを含む対象をどう扱い、どう管理するかという制度の設計です。ゆえに、現場の調査や学校の学習、地域の歴史教育の際には、この二つを混同せず、別々の役割を意識することが大切です。
埋蔵文化財とは何かと文化財保護法の役割の違い
埋蔵文化財は、古代の遺物が地下に埋まって長い時を超えて保存されている状態を指す語です。地震・地盤の動き・人の活動によって地層が動くと、掘り出される可能性があります。地域の遺跡が埋蔵されている場合、その場所を壊さずに保護するルールが必要です。こうした物を見つけた場合、勝手に処理してしまうと史料価値を台無しにしてしまいます。そこで法の力が働きます。文化財保護法は、国が文化財として扱うべき対象を列挙し、後の保存・調査・教育・公開の方法を決めます。埋蔵文化財が対象となる場合もあり得ますが、法は対象の選定だけでなく、保存の手順、修復の基準、展示の条件、教育機関での使用のさせ方、盗掘や損壊に対する罰則などを網羅しています。
埋蔵文化財とは何か
埋蔵文化財とは何かを具体的に見ていくと、まず「眠っている遺物」という理解が基本です。陶磁器のかけら、石器の刃、家屋の柱跡、井戸の跡など、地層の中に混じって今日まで残っているものを総称します。産業や生活の痕跡を示すことが多く、埋蔵状況により発見のタイミングも様々です。発掘の現場では、金属探査機や地中レーダーを用いながら、遺物を傷つけないよう慎重に検討します。埋蔵文化財は地域の歴史、風土、生活の知恵を理解するうえで欠かせない資料です。見学や研究の際には、現場の決まりを守り、記録を丁寧につけることが重要です。
文化財保護法とは何か
文化財保護法は、どんな物をどのように守るべきかを定義する“大きな設計図”のようなものです。国宝、重要文化財、重要美術品といった分類や、それぞれの保存・修復・展示の基準を定めます。法律の下では、地方自治体も協力して調査や保存活動を進め、教育目的の展示や市民の学習機会を確保します。埋蔵文化財が見つかった場合には、法に基づく手続きに沿って、遺物の取り扱い・記録・保護の措置が講じられます。さらに、文化財の適切な利用を推進するためのルール、損傷の防止、盗掘の防止、保存技術の普及など、長期的な視点で制度設計がされています。
現場での違いと具体例
現場で接する場面は、教室の話と違い実践的です。たとえば、建設現場で埋蔵文化財の可能性があると判断された場合、埋蔵文化財の保護に関する法律に基づき作業を一時停止し、関係機関へ通報します。このときの対応は迅速さと正確さが求められ、現場の責任者は誰が連絡するか、どの資料を保存するかを事前に決めておく必要があります。対して文化財保護法の適用が絡む場面は、学校の博物館展示や市民講座のような公共的利用をするときの許認可、保護対象の管理方法、修復時の専門家の配置など、制度的な側面が中心になります。つまり、埋蔵文化財は“現場の遺物”を守るための即時対応、文化財保護法は“保護の仕組み全体”を整える役割を果たしているのです。具体例として、ある住宅建設プロジェクトで土の中から土器の破片が出てきた場合の手順、駅前の発掘調査で史跡の候補が見つかった場合の手続き、学校の展示などで史料を公開する際の条件など、日常の学習から社会の仕組みまで、幅広く関係します。
ある日、校外学習の現場で地面の下に眠っているものが突然話題になりました。私は友達と地層の話をしていて、先生が『埋蔵文化財は宝物ではなく、歴史を語る教科書だ』と言ったのを今でも覚えています。実際、埋蔵文化財を見つけたときの正しい対応は現場を止めて専門機関に連絡することです。私たちが勝手に掘ってしまえば、遺物を傷つけるだけでなく、貴重な歴史の断片を失うことにもつながります。だからこそ、授業で学んだ「守るべきルール」を現場で生かす訓練が必要になるのです。埋蔵文化財という言葉は、地下に眠る過去の記憶を未来の人に伝える鍵になる、そんな気がします。