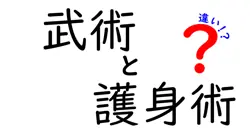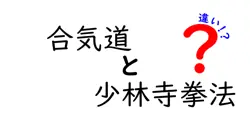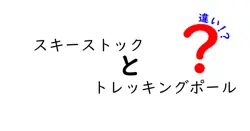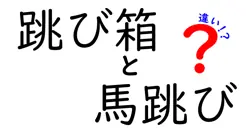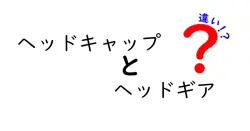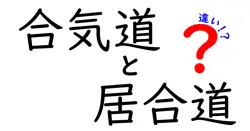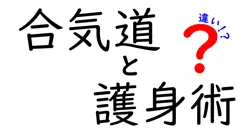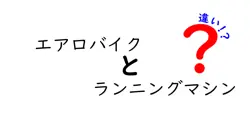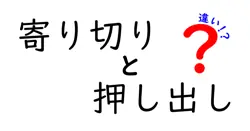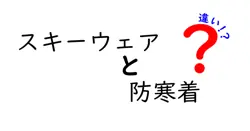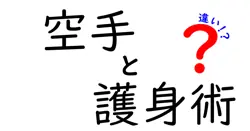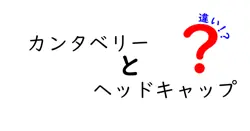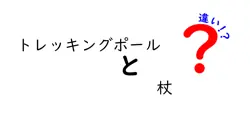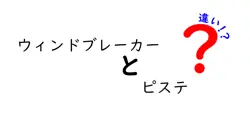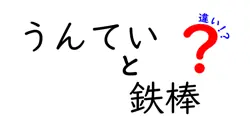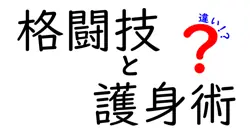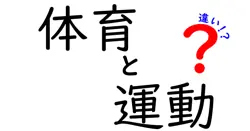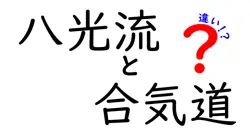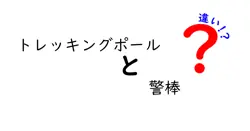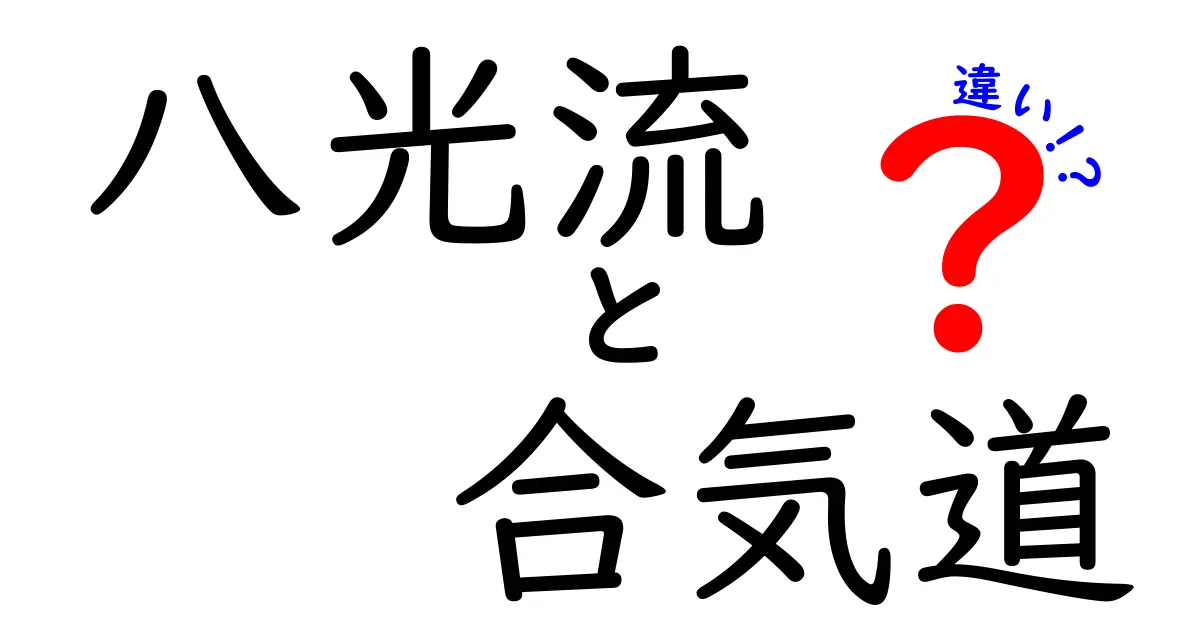

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに: 八光流と合気道の違いを知る基本
現代の武道にはさまざまな流派があり、人によっては混同しやすいものもあります。とくに 八光流と 合気道 は名前が似ているため混同しがちですが、それぞれには独自の歴史と特徴があります。本ブログでは初心者にも分かりやすく、どんな点が違うのかを丁寧に解説します。まずは大きな違いを三つに絞って紹介します。第一に起源と伝統の形態、第二に技術の組み方と考え方、第三に現代の稽古の形です。これらを押さえると、八光流と合気道の"何が違うのか"がはっきり見えてきます。
また、練習を始める前の心構えや、道場での基本マナーについても触れていきます。
要点のまとめを冒頭と末尾に置くことで、どの場面でもすぐに理解できるようにしています。
起源と歴史の違い
八光流は古い流派として日本の戦闘技術の伝統の中に位置づけられます。名称の由来には地域や師範の系統による違いがあり、各道場で世代ごとに技の名称や稽古の順序が少しずつ異なる点が特徴です。伝承性が高く、師から弟子へ技術と精神が受け継がれる形をとることが多いです。
対して合気道は近代の日本で体系化された武術で、創始者は植芝盛平です。19世紀末から20世紀初頭にかけて技術が整理・普及され、現代社会に合わせて道場運営や教育方針が整えられました。思想としては相手の力を利用して自分を守るという「合気」の考え方が中心で、技術だけでなく心の成長を重視します。
この歴史の違いが、現在の練習内容や道場の雰囲気に大きく影響しています。
技術の特徴と実践の違い
八光流は関節技・投げ技・締め技など、相手の動きに対して力を少なく使い、相手の重心移動を利用して制する技術が中心です。武器術の稽古も含まれることがあり、技の名称や動きの意味を理解することが重視されます。
一方、合気道は呼吸法・体捌き・軸といった基礎を重視し、相手の力を受け流す動作が中心です。技の完成形は投げや崩し、固め技へとつながりますが、最も大切なのは相手の力を利用する「受けの心」と、急激な力のかかり方を避ける「回避と迎え入れる動作」です。実際の稽古では、相手を崩す前の予備動作や身体の使い方を丁寧に確認する時間が多く設けられます。
この違いは、技の見た目だけでなく、稽古の進め方や安全性にも現れます。
教え方・稽古の進め方の違い
八光流の教え方は師から弟子へ技の技術と意味を厳格に伝える伝承形が多いです。基本の型(形)や段位の習得を重視する場面もあり、元の流派の歴史・礼儀作法の学習も組み込まれることがあります。道場ごとに伝統の継承を大切にする雰囲気が強いことが多く、個々の理解度に合わせた長い稽古時間が必要とされることもあります。
合気道は師範の思想を受けつつ、現代の道場ではより実践的な組み手・乱取り・呼吸法・身体の節度の訓練を取り入れ、初心者にも段階的なプログラムが提供されることが多いです。技術と心の成長を同時に目指す傾向が強く、練習の中で安全性と協調性を重視します。どちらにも礼儀・謙虚さ・継続が重要な要素として共通しています。
現代の位置づけと利用の場
現在、八光流は主に伝統的な流派として道場が存続しており、演武会や伝承活動を通じて技の保存が行われています。地域の伝統行事や武道イベントでの演武も見ることができます。現代の子どもや大人の礼儀作法や体力づくりの一部として興味を持つ人もいます。
合気道は全国に道場が広がり、学生・社会人を問わず多くの人が学んでいます。学校の部活動にも取り入れられることがあり、護身術や心身の鍛錬としての実用性が評価されています。現代社会においては「武術としての美しさ」と「心身の健康」を両立する道として選ばれることが多いです。
友人とカフェでの会話の続きを想像してみましょう。私が八光流と合気道の違いを質問すると友人はこう答えます。「八光流は昔の技術を大事にして、技の形をきちんと覚えることが多いんだ。鍛え方も地味に見えることが多いけど、体の使い方がしっかりしている。対して合気道は、力をぶつけずに相手の動きを活かす練習が多い。流れと呼吸を合わせる感覚を大切にするから、技を掛ける瞬間に“間”が生まれるんだ。」と。私はなるほどと頷きつつ、「どちらも人を傷つけずに自分を守る術を学ぶものだよね」と加えます。さらに友人は「結局は心の成長が一番の目的だと思う」と続けました。私たちは学ぶときの心構えとして、礼儀・安全・継続を第一に置くべきだと再確認しました。八光流の伝承と合気道の現代性、その両方を理解することで、自分に合った学び方が見つかると実感した日でした。