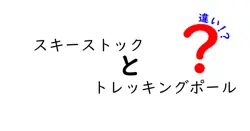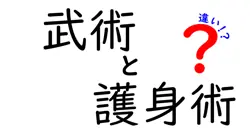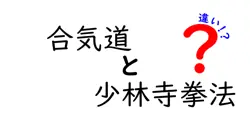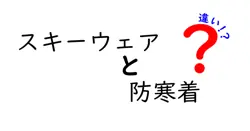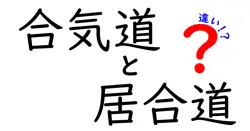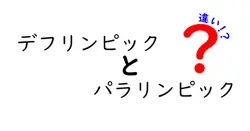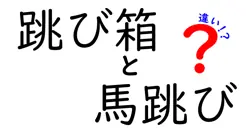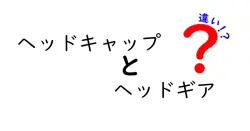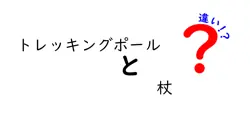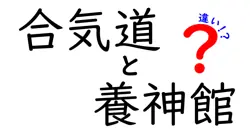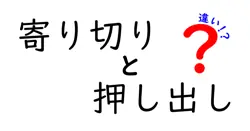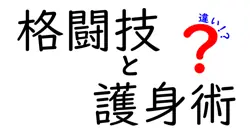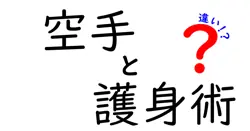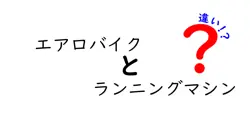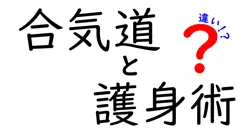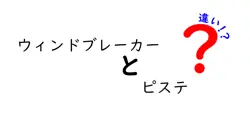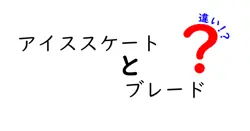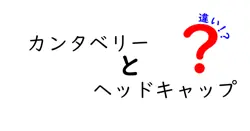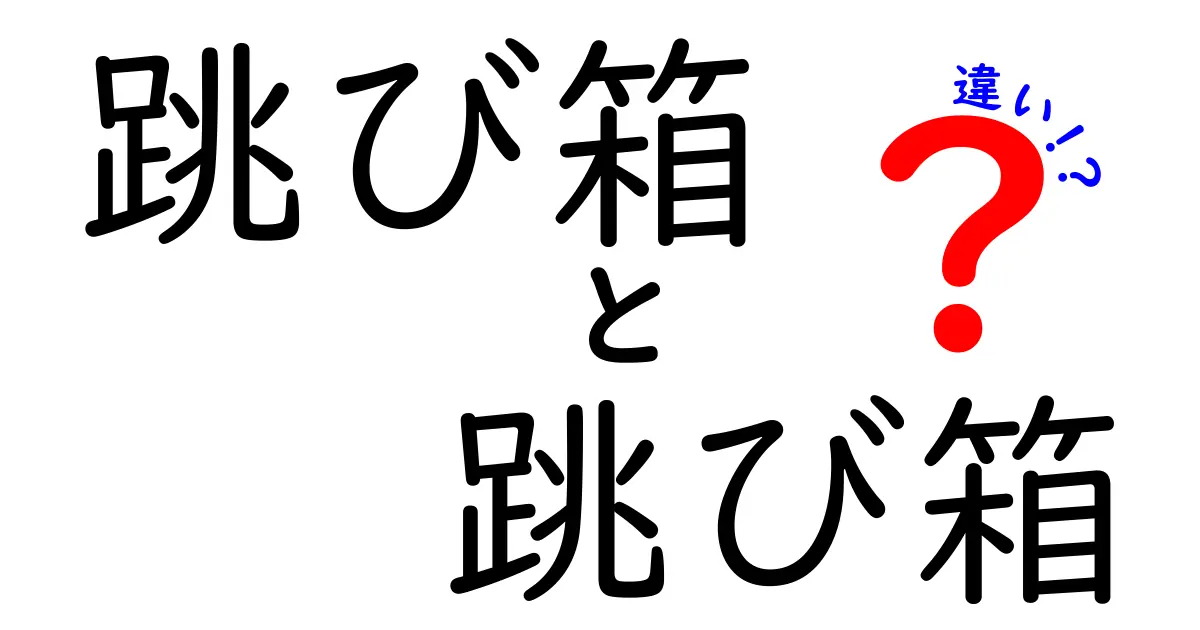

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
跳び箱と跳び箱の違いを理解するための基礎知識
跳び箱とは日本の体育でおなじみの器具です。一般に「跳び箱」とは、複数の板や箱を積み重ねた高い台のことを指し、走って助走をつけて前方へジャンプして上段へ乗る技術を練習します。この道具は学校の体育で使われることが最も多いですが、部活動や競技の練習でも使われます。同じ「跳び箱」という言葉を耳にしても、場所や目的によって意味が少し変わることがあります。例えば、学校の授業では安全性と基本動作の習得が第一で、段数を少なくして練習します。一方競技練習では高度な跳躍や技の難度を追求することが多いです。このような違いを知っておくと、初めて見る人でも「どうしてこんなに高さが違うのか」「どういう場面で使い分けるのか」が理解しやすくなります。
このような知識は、観察するだけの人にも、実際に練習する人にも役に立ちます。跳び箱の種類を理解することは、怪我のリスクを減らし、適切な段階へと安全に進むための第一歩です。
構造と高さの違いを理解する
跳び箱の構造は「箱の高さを作る段」と呼ばれる板を積み重ねる形で基本が作られています。一般的な学校用の跳び箱は3段から5段のものが多く、目安として高さはおおよそ0.6メートルから1.2メートル程度に設定されます。段数が増えると難易度が上がり、踏み切りの助走距離や着地の安定感も変わってきます。
ここで重要なのは「高さだけで難易度が決まるのではない」という点です。実際には段の配置、台の幅、板の反発、床のクッション性など、複合的な要素が生徒の跳躍を左右します。競技用の跳び箱や練習用の特別な箱では、最大で1.5メートル以上の高さを設定できることもあり、そこで扱われる技の難易度は学校の授業時より大きくなります。
このような違いを知ると、授業での練習計画を立てやすくなり、個々の目標に合わせた適切な高さを選べます。
表で見るポイント
| 項目 | 学校用の跳び箱 | 競技用・練習用跳び箱 |
|---|---|---|
| 高さの目安 | 0.6m程度から1.2m程度 | 1.4m以上も設定可能 |
| 段数の目安 | 3段〜5段が多い | 6段以上もあり得る |
| 材質と表面 | 布張りの表面、衝撃吸収は一般的 | 表面が硬めで反発が高い場合がある |
用途と練習の違い
学校の授業では、跳び箱は「基本的な跳躍動作の習得と安全な着地」の訓練として位置づけられます。
先生は生徒の技量に合わせて段数を決め、助走の長さ、踏み切りの高さ、着地の姿勢を段階的に指導します。初めて跳び箱に触れる子どもには、段を低くして「前転や着地の安定感」を身につけさせることが多いです。対して部活動や競技練習では、より高度な技へ挑戦します。例えば「二段跳び」や「三段跳び」のコンビネーション、空中での体のひねりや着地の正確さを求める訓練など、難度が上がります。ここで大切なのは「安全な準備運動と段階的な難易度設定」です。
また道具の設定を変えることで、同じ練習でも新しい課題を作り出せます。例えば高さを上げると踏み切りのスピードが重要になり、連携する体幹の強さも問われます。
このように同じ跳び箱でも、使う目的によって練習の内容と指導のポイントが大きく変わる点が特徴です。
練習の具体例
- 低い段から順に、助走の長さと着地の安定を確かめる
- 段数を増やして、介助者のサポートを受けながらリスクを減らす
- 高度な技の導入時は、ビデオで自分の動きを確認する
安全性と準備の違い
跳び箱の安全を確保するには、準備運動と適切なマットの配置が前提です。
靴は室内用の運動靴を選び、床は滑りにくい状態にします。マットは跳び箱の周りを広く囲み、落下時の衝撃を和らげる役割を果たします。教室では教師の見守りのもと、生徒同士の声掛けやサポートを取り入れることで事故を防ぎます。
保護者や指導者は、跳び箱の高さを一気に上げず、段階的に難易度を上げる「漸進的なアプローチ」を重視します。安全第一 の精神を全員が共有することが大切です。謎の動作を無理に真似するのではなく、正しいフォームと着地の練習を繰り返すことが怪我の予防につながります。
また、天候や床の状態に応じて練習内容を柔軟に変更する柔軟性も大切です。
表で見る安全ポイント
| 観点 | 学校 | 部活動 |
|---|---|---|
| 安全対策 | マットとサポート要員を配置 | 補助者の配置と映像による振り返り |
| 準備運動 | 股関節と足首の柔軟性を中心に | 体幹と下半身の強化運動を追加 |
| 難易度の調整 | 段数を段階的に増やす | 高度な技の導入で個別対応 |
結論として、跳び箱は同じ名前でも使う場面で意味が異なり、実践する人の目的に合わせて練習方法と安全対策が変わります。学校の授業は基本を固め、部活動は高度な技へ橋渡しをする役割を担います。だからこそ、教える側と学ぶ側の双方が、段階的な目標設定と安全な進行を心掛けることが大切です。
今日は跳び箱の話を雑談風に深掘りしてみます。友達と学校の体育館を歩き回りながら、跳び箱の高さが違う理由についてつい話し込んでしまうこと、ありませんか。実はその場の雰囲気や目標によって、跳び箱の使い方はかなり変わってくるんです。例えば、友だちに「今日は高さを2段にして挑戦してみよう」と提案すると、自然と会話のテンポが上がり、みんなで安全チェックを共有します。跳び箱は単なる道具ではなく、練習の過程を通じて協力する意識や自分の体の感覚を高める道具でもあります。私たちが日々感じる微妙な難易度の差は、実は「段数と高さの組み合わせ」によって生まれる微妙なニュアンスです。だからこそ、練習を始める前には「どの高さで何を目指すのか」をみんなで話し合い、段階的に進めることが大切です。次の体育の時間には、友だちと一緒に低い段から丁寧に積み上げ、成功体験を共有するところから始めてみてください。跳び箱は、ちょっとした対話と協力が大きな成長につながる、そんな体育の相棒なのです。>
前の記事: « 母と母親の違いを徹底解説!中学生にもわかる使い分けガイド