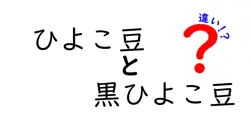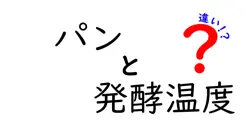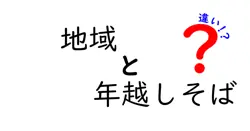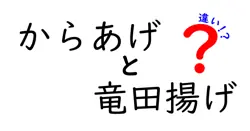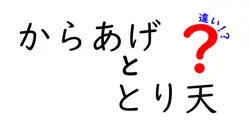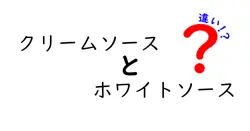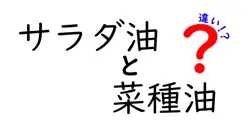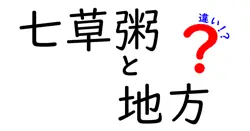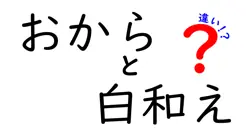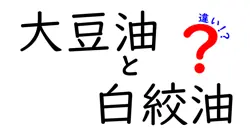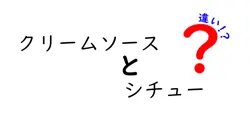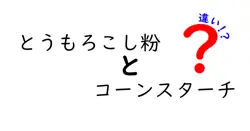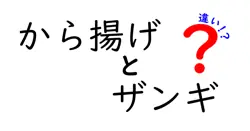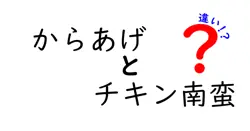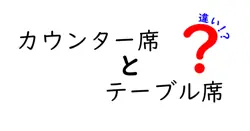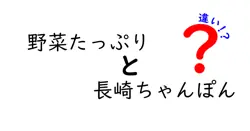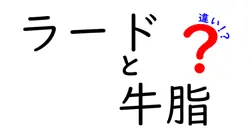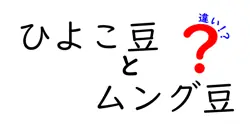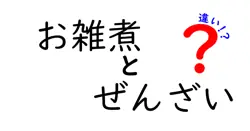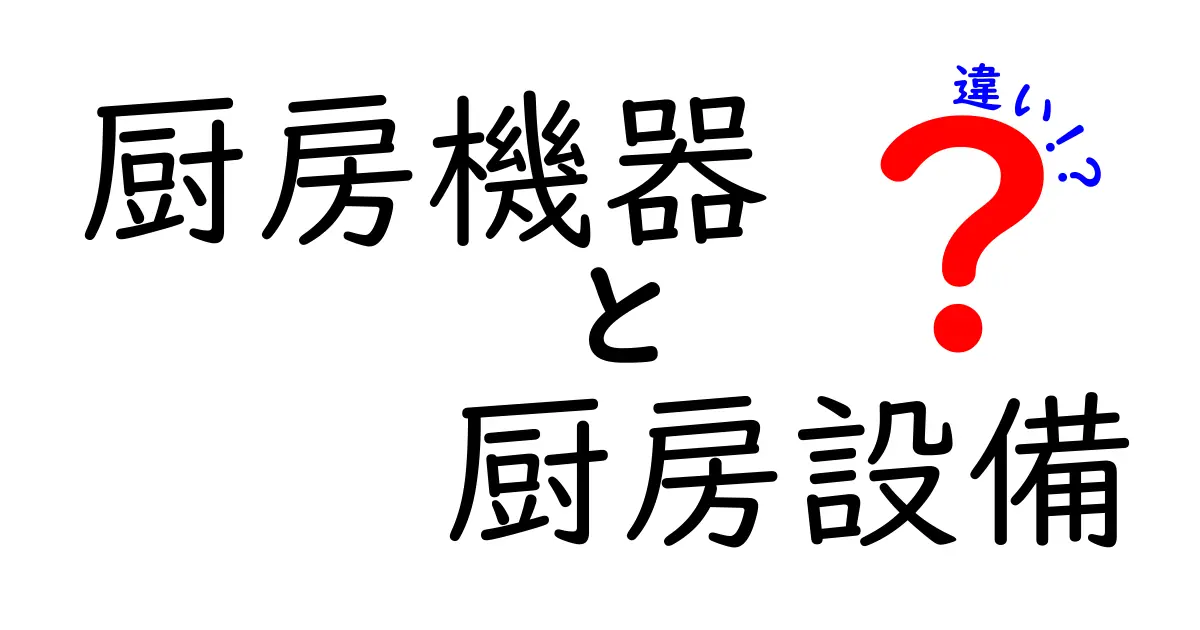

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
厨房機器と厨房設備の基本的な違いを理解するための基本の考え方
厨房機器と厨房設備は、言い換えると「何を使って料理を作るか」という視点と「その料理が安全・衛生・安定に作られるための基盤」という視点の違いです。厨房機器とは、料理を作るために直接「火を使う・加熱する・加工する」機能を果たす道具のことを指します。包丁、まな板、オーブン、ガスレンジ、IHクッキングヒーター、フライヤー、ミキサー、製氷機などがこれにあたります。これらは日々の現場で動く具体的な器具で、作業者が手動または自動で操作して料理を作る最前線の武器です。対して厨房設備は、これらの機器が安定して、安全に動くための土台となる“仕組み”や“空間の構成”を指します。換気システム、排水設備、給排水配管、電源盤、ガス配管、消火設備、床の材質と衛生管理、照明と作業動線などが該当します。
例えば、厨房機器の選定は「どの機器をどの程度の出力で使うか」「年間の稼働時間に対して耐久性はどうか」といった点に焦点が当たります。一方で厨房設備は「この厨房で安全に運用できるか」を左右します。換気の容量、排水の勾配・トラップ、給排水の配管径、電力の容量分配、ガスの圧力・安全対策、火災報知と消火設備、衛生管理のための素材選びなどが重要です。
このように、機器と設備は互いに補完関係にあり、一方だけを見ても全体像は見えません。現場の声としては、機器の使い勝手と設備の安全性・衛生性の両輪が揃って初めて「実務で役立つ厨房」が生まれる、という理解が最も現実的です。
厨房機器と厨房設備の具体例を並べて比較する
現場では、何が機器で何が設備かを混同しがちです。以下の表は、代表的な例を挙げて整理したものです。装置の呼称は企業ごとに異なることもあり、現場ルールに合わせて使い分けるのが実務的です。
機器と設備の境界をはっきりさせると、導入計画・保守計画・教育計画が立てやすくなります。
この表を見れば、機器は「その場で料理を作るための道具」、設備は「それを動かすための土台・環境整備」という大きな役割の違いをつかみやすくなります。現場の実務では、機器の性能だけでなく、設置場所の広さ、天井高、排気の風量、床の清掃性、引火性のリスク、メンテナンス費用なども含めて総合的に判断します。
したがって、導入時には「機器と設備の両方を同時に検討する」ことが肝心です。
購買・運用の現場でのポイント
導入計画を立てるとき、単純な初期費用だけで判断しがちですが、現場運用での総費用(TCO)を意識することが大切です。短期の節約より長期の安定性を優先すると、後々の修理頻度や部品供給の確保といった不安が減ります。以下の観点を軸に検討します。
第一に機器の耐久性と清掃性、部品の供給状況。第二に設備の法令適合・点検スケジュール・設置後の運用マニュアル。第三にエネルギー効率と ランニングコスト。第四に保守サービスの品質とレスポンスの速さ。これらを総合して判断することで、現場の作業効率と安全性が高まります。
また、教育・訓練の観点も重要です。新しい機器を導入すると、操作方法や日々の清掃・点検手順が変わる場合があります。従業員に対しては、機器の扱い方だけでなく、設備の点検・清掃・故障時の対応手順をセットで教育することが、トラブルを未然に防ぐコツです。現場の声を反映した導入計画を作るためには、現場責任者・サービス技術者・衛生管理者が同席する会議を定期的に開くのが効果的です。
結論として、厨房機器と厨房設備は補完関係にあり、それぞれの役割を正しく理解して初めて、安全・衛生・効率の三拍子が揃います。
厨房機器という言葉を話すとき、私たちはつい機械そのものの話をします。でも、実際の現場では「機器と設備の役割を分けて考える」ことが導入ミスを減らすコツです。例えば新しくオーブンを導入する際、機器の出力だけを見て決めると、後で電源容量が足りず動かせないことがあります。そこでまず設備側の容量・配線・換気・給排水の容量を確認します。次に機器の使い勝手・清掃性・部品供給の安定性を評価します。結局、機器は料理を作る“道具”、設備はそれを安全・衛生・効率的に使うための“仕組み”です。こうした視点で話すと、現場の新人にもわかりやすく、導入後の運用もスムーズになります。雑談の形でこの違いを共有すると、実務の場ですぐに役立つ判断材料が増え、チームの連携も良くなるのです。