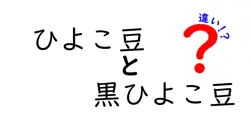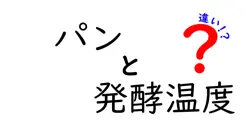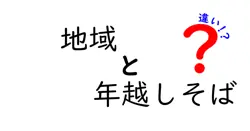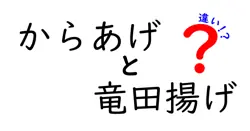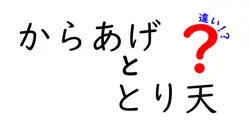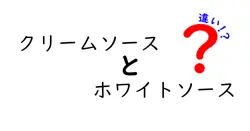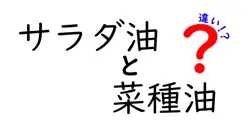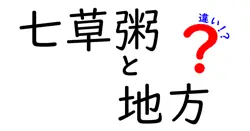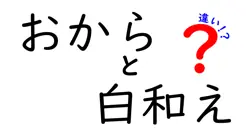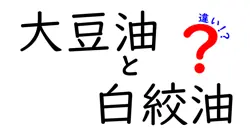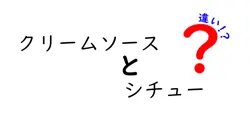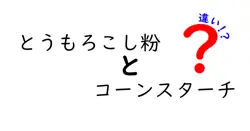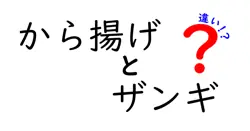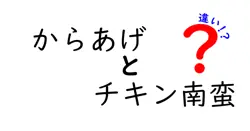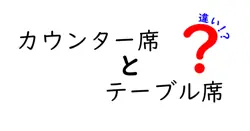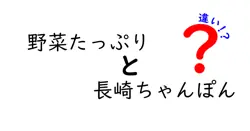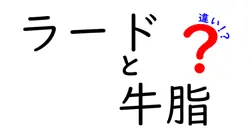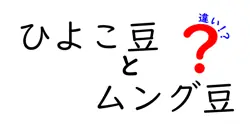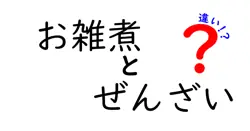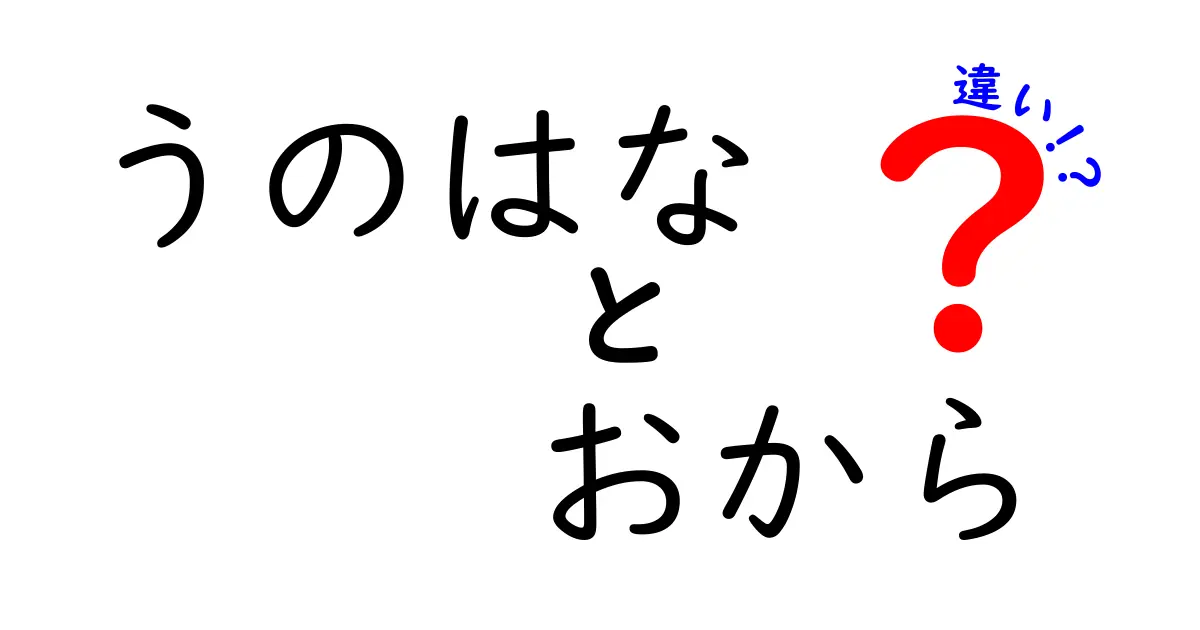

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
うの花とおからの違いを徹底解説
この解説では、日本の豆を使った代表的な食材・料理である「うの花」と「おから」の違いを、名前の意味・作り方・栄養・地域文化という四つの視点から丁寧に整理します。日常の台所で混同されがちなこのふたつは、名前だけでなく実際の用途や調理のアプローチにも違いがあり、理解を深めるとレシピ選びや食卓作りがスムーズになります。まずは基本となる言葉の成り立ちを押さえ、次に実際の料理としての取り扱い方、そして地域ごとの呼び方の違いと文化的背景へと話を広げます。
読み進めるほど、材料としてのおからと完成品としてのうの花の関係性が見えてきます。
名称の成り立ちと意味の違い
「おから」は豆乳を絞るときに副産物として生まれる材料の名で、江戸時代頃から家庭料理の基本素材として広く使われてきました。材料としてのおからが基本単位であり、塩味・味付け・混ぜる具材によってさまざまな料理へと姿を変えます。これに対して「うの花」は関西圏を中心に使われる呼称で、おからを使った煮物・炒め物・和え物などの完成品の名称として用いられることが多いです。つまり、おからが材料名、うの花が料理名として機能するケースが多いという違いが基本です。地域差を除けば、言葉のニュアンスとして「おから=素材」「うの花=仕上がりの料理」という二つの枠組みが一般的です。
この区分を意識すると、レシピ検索時の混乱が減り、同じ材料でも異なる料理名で記載されている場合の意味を読み解きやすくなります。名称の違いを知ることは、初めての料理挑戦のハードルを下げる第一歩です。
言葉の意味をはっきりさせておくと、買い物リストを作るときにも役立ちます。
作り方と使い方の違い
次に重要なのは、作り方と使い方の違いです。おからは調理の基礎素材として、炒める・煮る・焼く・和えるなど多様な技法で直感的に使えます。基本的には水分量を調整し、油分・塩分・糖分のバランスを整えることがポイントです。おからは原材料そのものなので、野菜やきのこ、肉・魚介との相性も幅広く、家庭ごとに独自のレシピが育まれてきました。
一方、うの花はおからを使った完成品を指すため、レシピは「具材の組み合わせ」「煮込みの時間」「仕上げの味付け」といった料理作りの工程に焦点が当たります。典型的には煮物系や卵とじ、油で香ばしく炒める系など、材料の組み合わせと火加減が味の決め手になります。つまり、おからは素材、うの花は完成品としての料理という役割分担がはっきりしており、作り方の設計もこれに沿って変わります。
また、家庭ごとに異なる味付けの工夫にも注目です。おからの基本はシンプルで、出汁・醤油・みりん・ごま油などをベースに、野菜の旨味を加えることで体に優しい一皿となります。うの花になると、味付けの方向性がもう少し複雑になり、野菜の種類・油の使い方・砂糖の量などを調整して、甘辛い煮物風や、より和風の煮しめ風に仕上げることが多いです。
作り方の違いを意識することで、同じおからでも違う味わいを楽しむことができます。
栄養と健康の違い
栄養面でも違いは見られます。おからそのものは食物繊維が豊富で腸内環境を整える効果が期待できます。また、良質なたんぱく質も多く含み、低カロリーで満腹感を得やすいのが特徴です。ただし、油を多く使う調理法や砂糖の多い味付けをするとカロリーが増える点には注意が必要です。うの花という完成品になると、調味料の量や油分の使い方が総カロリーや糖質に影響します。
したがって健康を意識する場面では、材料としてのおからの取り方だけでなく、うの花のレシピ設計自体も見直すことが大切です。繊維を多く含む食事を取りつつ、油分を控えめにする工夫を日常の献立に取り入れると、体への負担を減らせます。
地域性と地域文化の違い
地域性はこのテーマの大きなポイントです。関西では「うの花」という呼称が昔から定着しており、家庭料理としての伝統的な位置づけが強いです。この地域でのおからの利用は、煮物や和え物などの形で現れ、味付けは薄口醤油系や出汁を使った上品なスタイルが多い傾向にあります。逆に東日本では「おから」と呼ぶ場面が多く、市販の製品や惣菜にもこの表現が使われています。味付けにも地域ごとの好みが色濃く出るため、同じ材料でも食卓の印象が大きく異なることがあります。地域文化としては、季節行事や家庭の伝統レシピにうの花の名が登場する場面があり、旅先で現地ならではの味に出合う楽しみがあります。
地域ごとの呼称と味の違いを知ると、旅行先の食事がより一点の魅力として増します。
表で比較してみよう
| 項目 | うの花 | おから |
|---|---|---|
| 意味・呼称 | 完成品の名称・地域名として使われることが多い | 材料名として用いられることが一般的 |
| 主な材料 | おから+野菜・油揚げ・豆腐などを組み合わせる | おからそのものを主材料として使うことが多い |
| 主な調理法 | 煮物・炒め物・卵とじ・和え物など多彩 | 焼く・煮る・和えるなど基本的な技法で活用 |
| 地域差 | 関西でうの花の呼称が主流 | 全国的におからと呼ばれることが多い |
| 栄養ポイント | 繊維質が豊富だが、調理法次第で変動 | |
| よく作る場面 | 家庭の定番おかず・季節の煮物に適す |
まとめ
要点をもう一度整理します。おからは豆乳を絞った副産物の材料名であり、うの花はそのおからを使った完成品の名称・料理名という基本的な違いがあります。料理の場面では材料名と料理名を正しく分けて理解することが、レシピを正しく読む力と作業の効率を高めます。また、地域性を理解しておくと、同じ材料でも異なる味わいに出会える楽しみが広がります。今後はこの違いを意識して、日常の献立づくりや食卓提案に活かしてみてください。
うの花の話題を友達と雑談風に深掘りする小ネタ。友達Aが『うの花ってお菓子みたいな名前だね』と半笑いで言い、友達Bが『実はおからを使った煮物の名前なんだ。地域によって呼び方が違うから、同じ材料でも家庭ごとに味が違うんだよ』と返します。二人はスーパーの惣菜コーナーを歩きながら、うの花として売られている料理の実際の作り方や、家で作るときの工夫点、油分や砂糖の量の調整、食物繊維の摂取の話題へと話題を広げ、最後には「日常の料理は名称よりも味と健康をどう保つかが大事」という結論に落ち着く、そんな雑談の中身を描写します。